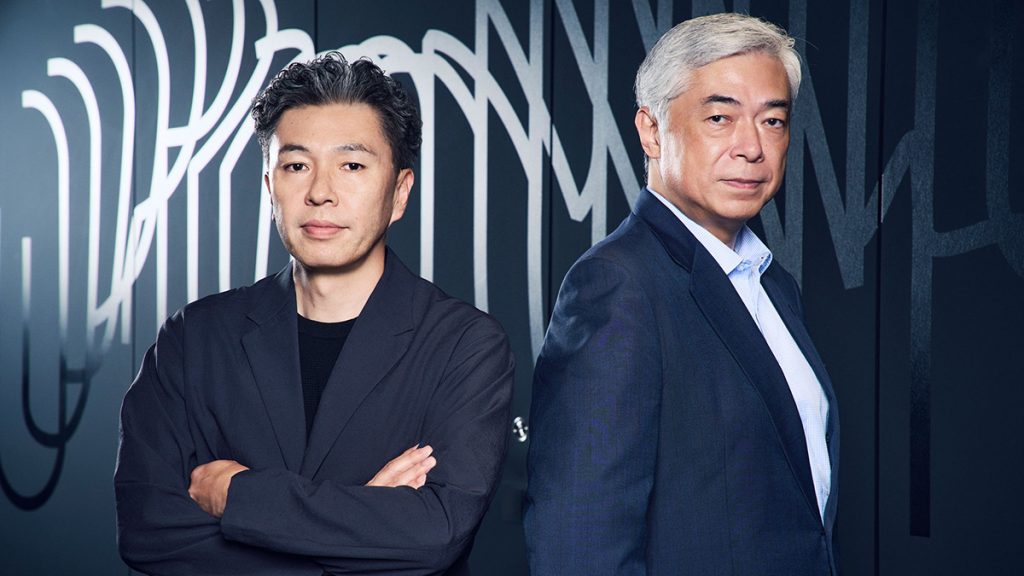
2025.09.5(Fri)
日本発の共創が世界を変える時代へ——産官学連携とスタートアップ主導で描く新たな共創の可能性
会員登録をすると
記事をマイページに
保存することができます。

OPEN HUB
THEME

OPEN HUB
THEME

Co-Create the Future
組織や分野を超えたコラボレーションは、今や当たり前の時代。では、未来をつくるための共創のありかたとは? OPEN HUBでの取り組みや国内外の事例とともに考えます。
共創プロジェクトの“いま”を発信。実装済の事例のほか、
共創パートナーの募集や、進行中のプロジェクトの様子も随時アップデート。

#82
PARTNER
会員登録をすると
記事をマイページに
保存することができます。

#81
PARTNER
会員登録をすると
記事をマイページに
保存することができます。

#79
PARTNER
会員登録をすると
記事をマイページに
保存することができます。

#75
PARTNER
会員登録をすると
記事をマイページに
保存することができます。

#73
PARTNER
会員登録をすると
記事をマイページに
保存することができます。
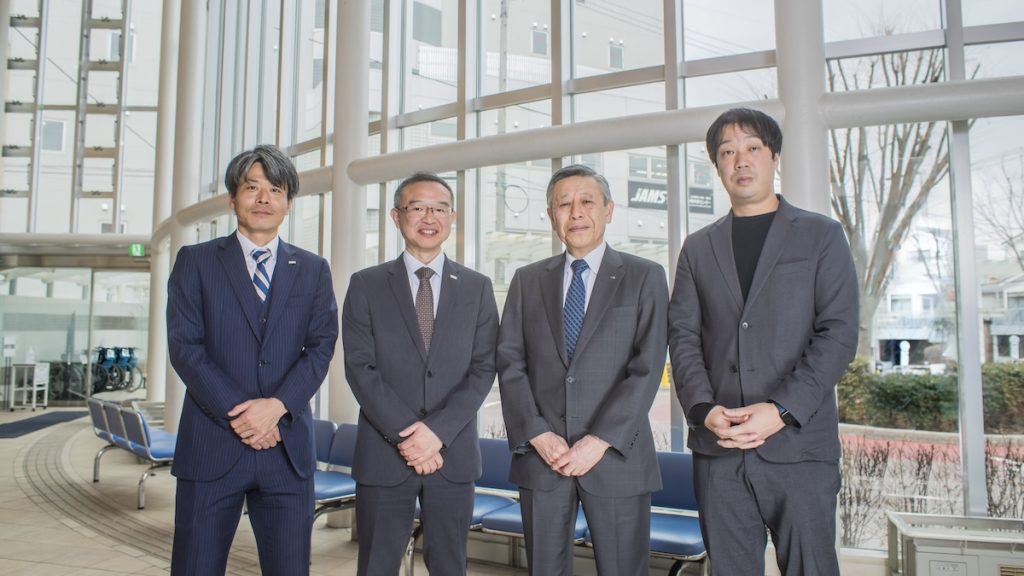
#70
PARTNER
会員登録をすると
記事をマイページに
保存することができます。

#68
PARTNER
会員登録をすると
記事をマイページに
保存することができます。

#67
PARTNER
会員登録をすると
記事をマイページに
保存することができます。

#66
PARTNER
会員登録をすると
記事をマイページに
保存することができます。

#55
PARTNER
会員登録をすると
記事をマイページに
保存することができます。

#53
PARTNER
会員登録をすると
記事をマイページに
保存することができます。

#47
PARTNER
会員登録をすると
記事をマイページに
保存することができます。
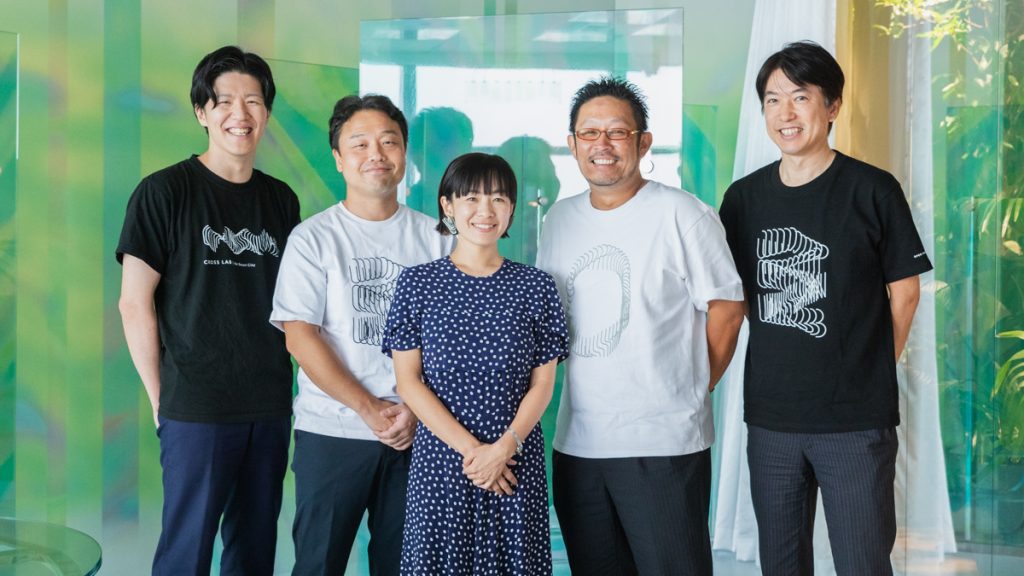
#39
PARTNER
会員登録をすると
記事をマイページに
保存することができます。

#33
PARTNER
会員登録をすると
記事をマイページに
保存することができます。

#29
PARTNER
会員登録をすると
記事をマイページに
保存することができます。

#28
PARTNER
会員登録をすると
記事をマイページに
保存することができます。

#27
PARTNER
会員登録をすると
記事をマイページに
保存することができます。

#23
PARTNER
会員登録をすると
記事をマイページに
保存することができます。

#22
PARTNER
会員登録をすると
記事をマイページに
保存することができます。

#18
PARTNER
会員登録をすると
記事をマイページに
保存することができます。

#2
PARTNER
会員登録をすると
記事をマイページに
保存することができます。
社会課題を起点に特集を発信。記事、イベント、実証実験のプロジェクトなど、多角的な視点から、新たなインサイトをお届けします。