
01
2025.07.18(Fri)
この記事の要約
ビジネスアイデアの磨き方を探るイベントが開催され、有識者が「筋の良いビジネス」とは何かを議論。
山口氏は「アジェンダが少数派」であることの重要性を強調し、樋口氏は時間軸の意識が必要と述べた。
水野氏は法務との共犯関係の重要性を語り、アイデアをオープンにする戦略を提案。また、仮想敵やオープンソース化、仲間の存在がアイデア形成に重要であることが指摘された。
第2部では、会員がビジネスアイデアをプレゼンし、有識者からフィードバックを受けた。
最後に、ネットワーキングが行われ、ビジネスアイデアの共創が促進された。
※この要約はChatGPTで作成しました。
目次
戸松正剛(以下、戸松):新しいビジネスアイデアを聞いて、「筋は通っているように聞こえるがワクワクしない」「理路整然としているけれどあまり儲かる気がしない」と直感的に思った経験を持つビジネスパーソンは少なくないのではないでしょうか。お三方から見た「筋の良いビジネスアイデア」とはどういうものなのか、まずはそれぞれのご経験や専門分野の観点からお話しいただけますか。
山口周氏(以下、山口氏):僕が思う「筋の良いビジネスアイデア」の条件は、「アジェンダが少数派」ということです。多数派のコンセンサスがとれているアジェンダはすでに先行する多くの企業が取り組んでいるため、レッドオーシャンに後発参入することになります。
例えば、日本の企業が「電気自動車は時期尚早」といっていた2000年代、そこに打って出たTeslaの時価総額は、2020年に自動車メーカー世界1位になりました。こうしたケースからわかる通り、まだ社会的なコンセンサスはとれていないけれど、「Surprising yet Right(意外だけど言われてみれば納得感がある)」というアジェンダを掲げることが重要な条件だと思っています。

戸松:アジェンダが少数派のビジネスとニッチビジネスとは何が違うのでしょうか。
山口氏:ニッチというのはすでに市場が存在していますよね。一方で、コンセンサスがとれていないアジェンダが少数派のビジネスというのは、まだ市場が存在しないということ。SDGsには17の目標が設定されていますが、18番目の目標は何だと思いますか?という話です。
戸松:なるほど。ビジネスとしての既視感というか、既成のスキームによるパターン思考にとらわれないという意味でも、「新しいアジェンダを掲げる」のはおっしゃる通り重要ですね。SF作家として、さらにはコンサルタントとしても活動されている樋口さんはいかがでしょうか。
樋口恭介氏(以下、樋口氏):私からは、新規ビジネスを進める際に「時間軸が意識されているか」というポイントを挙げたいと思います。50年後の未来においても、そのビジネスアイデアにはまだ価値があるのかどうか。また、未来だけでなく過去にも目を向けること。企業によっては100年以上の歴史があったりもすると思いますが、そうした歴史の中で紡がれてきた企業理念やパーパスをしっかり受け継ぐようなアイデアになっているのかどうかも重要です。
よりパーソナルな時間軸でいえば、例えばイーロン・マスクやスティーブ・ジョブズには自分が描くストーリーがあって、ゴールに向かってやり切るという点で一貫しています。どんなに失敗してもありえないようなことをしても、それは成功に至るまでの過程に過ぎないという時間軸を彼らは持っている。自分も周りも騙し切って描いたストーリーを突き進むというか、人生の大半をそこに投下する覚悟がなければ、ビジネスアイデアが育っていくのは難しい気がします。
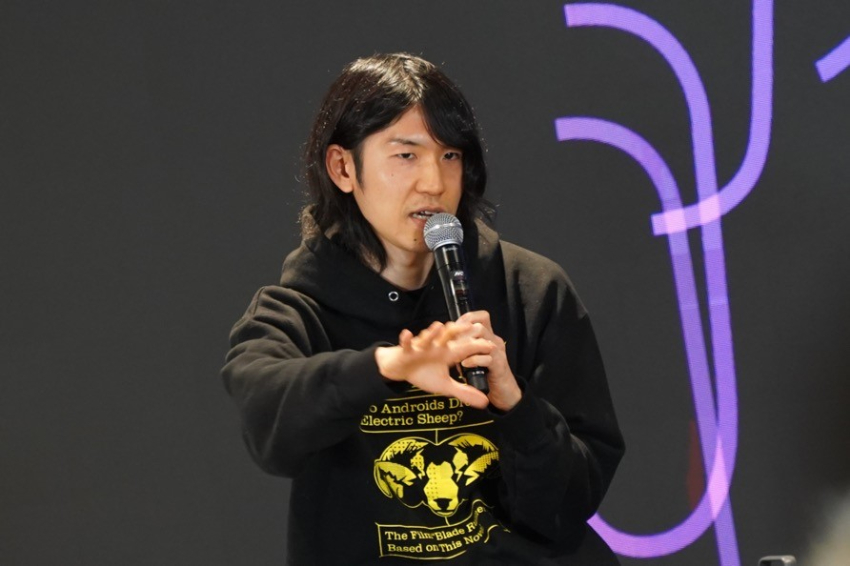
戸松:確かに、イノベーションは“火花が散るようなひらめき”と思われがちですが、実際は歴史のコンテクストを引き受ける中で顕在化するケースが多いのも、樋口さんのおっしゃる時間軸から覚悟を引き出せているからですよね。法律家で弁護士の水野祐さんはいかがですか?
水野祐氏(以下、水野氏):私は日ごろ、スタートアップから大企業までさまざまな企業の法務をサポートしているのですが、その中で筋が良いと感じられるビジネスアイデアは、必ず「世の中に新しい価値を提供できる」ものになっていると思います。そうしたアイデアに仕上げるためには、まだ競争が激化していない場所にビジネスチャンスを見出すことが重要です。
また、新たな価値というのは、既存の法やルールが古くなったり、ドラスティックに変わったりしそうなところに生まれやすいのですが、日本人は「ルールは守るもの。変えちゃいけないもの」と考えがちで、法が遅れているところを避けて通りたがります。でも本当はローラグ(法の遅れ)のあるところこそ社会課題が一番詰まっている場所だと捉えてチャレンジするマインドセットが大事だと思っています。
戸松:日本の企業は「社会における“ルールメーカー”としての機能が弱い」とよくいわれたりしますが、ルールといっても変えられるものはあるし、チャレンジする価値はある、ということですね。
水野氏:そうです。具体的な手法としては、アイデアの企画段階から法務に関わってもらう、というやり方があります。法務と一緒にそのビジネスアイデアのポテンシャルを見極めつつ「法的にはこの範囲までならできる/できない」という議論を早い段階からしておくのです。法務の立場からすると、アイデアが固めきられた最後に相談されても、時間などの余裕がなくてノーと言わざるを得ないケースが多いのですが、法務との“共犯関係”ができていれば、ビジネスとして実現する可能性がより見えてくると思います。

樋口氏:ステークホルダーと共犯関係を結んで一緒にビジネスをつくっていくと、予想していなかったリスクが顕現しても、チームとしての柔軟性を育めているので「何とかして頑張ろう」という気持ちが生まれやすいのですよね。レジリエンスという意味でも、法務を戦略的に使うのはすぐにやったほうがいいTipsだと思います。
戸松:市場における「新しいアジェンダ」という“空間”認知の視点、ビジネスの時間軸の重要性、そして法務の観点からポテンシャルの大きなビジネスチャンスを見出す方法論について、三者三様のコメントをもらえたところで、続いては「ビジネスアイデアへのフィードバック」についてお聞きしたいと思います。提示されたビジネスアイデアに対して皆さんはどんな返し方をしているのか、山口さんはいかがでしょうか。

山口氏:筋の良いビジネスを見抜くというのは、そもそも不可能といえるほどに難しいことなのです。過去の事例を振り返ってみても、Googleは最初の資金調達をするまでに350回、Airbnbは250回断られていますが、いずれも世界的な企業へと成長しています。
一方で筋の悪いビジネスというのは割とはっきりしていて、流行のアジェンダは大体筋が悪いですね。実際、「このビジネスに取り組んでいる人は世界で何百万人もいるけれど、あなたがやらなくちゃいけない理由は何ですか?」と返すことがよくあります。そこで、「従来のものより安いです、早いです」といった回答しか出てこないようだと、投資対象としての魅力は感じられないですね。
戸松:誰もが考えつくような競争優位性以外の部分が重要である、ということですね。樋口さんはいかがでしょうか。
樋口氏:難しい質問ですが、僕の場合は「誰に何を言われてもそこに自分の労力を投資できる」という情熱や覚悟みたいなものが発案者にあるかないか、それだけは確認しますね。
戸松:樋口さんご自身はSF小説を執筆されていますが、「こういう世界になってほしい」という情熱をベースに未来を描くことの是非についてはいかがお考えですか。
樋口氏:それはもう是でしょうね。自分が幻視したものを書くことがSF作家の情熱だと思います。1950年代や60年代はアメリカのSF黄金期といわれていて、そのころの作品を読んでいると「絶対こんな未来になる」と作家自身が信じ切っている迫力があるのですよ。当たろうが外れようが、自分にはその未来が見えるという思いがすごくて。書きながら解像度を上げているのでしょうね。「もっと見たい、詳しく見てみたい」って思いながら執筆していたのだと思います。ビジネスアイデアについても同じことがいえるのではないでしょうか。
戸松:まさにバックキャスティング思考ですね、興味深いお話です。水野さんもビジネスアイデアの相談を受けることは多いと思いますが、どんな観点で人のアイデアを見ていますか。
水野氏:シンプルに面白いアイデアか、面白い人かどうかですね。私は見たことのないプロダクトやサービスを見てみたいという好奇心が強いので、自分のアイデアを信じて形にして誰かに見せたいと心から思っている人かどうか。そういう人であればサポートしたい、ただそれだけなのですよね。
山口氏:水野さんのおっしゃる通りだと思います。自分のアイデアを本当に実現したい人は、「このアイデア、いけると思いますか?」って人に聞く前に、もうやり始めているというか。
水野氏:それだけの狂気があるかどうか、ということかもしれませんね。先ほどの法やルールを変えていこうというような話をすると面倒くさいと思ってしまう方が多いのですが、本当に情熱や狂気がある人はむしろそこにワクワクして、じゃあどうやったらいいだろうかとプロセスを考え始めるのです。そこに本人の覚悟が見えますし、応援したくなりますね。

戸松:一方で、コンプライアンスの厳しい時代にそこまでやり切れる人がどこまでいるのかは気になるところです。
水野氏:実際は少ないでしょうね。ただしこれは皆さんにぜひ持ち帰っていただきたいのですが、コンプライアンスの意味を英英辞典で調べると、「Wish(意志)またはCommand(命令)に従って行動すること」と書かれています。日本語では法令順守と訳されますが、これだとCommandだけでWishがないのですよね。本来は「どうしたいか」が前提にあるべきなのに、ただ単にルールに従うという意味になっている。これは大いに考える余地があると思っています。
戸松:ここからは少し視点を変えて、「人を惹きつけるアイデア」とはどんなものなのかを考えていきたいと思います。山口さんからお願いできますか。
山口氏:少し質問からずれるかもしれませんが、同じ敵がいる人同士って仲間になれますよね。そこはポイントになるのかなと思っています。
戸松:先ほどの水野さんの共犯関係のお話にもつながりそうですね。
山口氏:ある仮想敵みたいなものがいて、それを出し抜こうとかやっつけてやろうという気持ちは、人をつなげる力がとても強いです。Appleが最初につくった「1984」というテレビCMは、同名のSF小説で描かれた全体主義の社会が打ち壊されるという内容なのですが、驚くべきことに製品の特長や機能にはまったく触れておらず、ただただ「私たちは1984のような世界にはさせない」という宣戦布告のマニフェストになっています。
「我々の敵は誰なのか。もし同じものを敵だと思うならあなたは私の仲間だ」といっているこのCMは史上最高のCMとの呼び声が高く、非常に示唆に富んだ内容になっています。
戸松:多くの人がそのアイデアに乗っかるためには、仮想敵はひとつのカギになりそうですね。水野さんは、作者が著作権を保持したまま第三者がその作品を条件の範囲内で利用できる「クリエイティブ・コモンズ・ライセンス」に取り組まれていますが、ビジネスアイデアを自社で囲わずにシェアすることについてどのようにお考えでしょうか。
水野氏:企業が持つ情報や技術をオープンソース化するといってもさまざまなレイヤーがありますが、自社だけではアイデアが出ないところを一部オープンにして、いろいろな人に触ってもらいながら可能性を広げていくオープンクローズ戦略はひとつの手法であり、この10年くらいで一気にメジャーになった感じがします。
先ほどのTeslaも、自社の特許権を防御目的でしか使わないと「特許解放」を宣言することで、EV市場自体を広げることに大きく貢献しました。ただしこれはチャリティーではなく、大いなる野望のもとでの戦略的なオープンソース化です。日本では慈善と捉えられがちですが、オープンソース化は「仲間を増やす」「技術の可能性を救い出す」「市場規模を拡大する」ための戦略として十分に活用可能な選択肢だと考えています。

戸松:なるほど。仲間を増やすという観点では、先ほど樋口さんが述べられたSF思考にも、「物語の共有」という同じような効果がありますよね。
樋口氏:SF思考で描いた物語を共有する、というと、とかく未来にばかり目が向きがちですが、バックキャスティングでビジネスアイデアを考えるということは、チームとして物語を構成し直し、“歴史を捏造する”ということでもあるのです。自分たちがどんな物語を生きてどこに向かっていくのか、それを共有して一緒につくりあげることは、ビジネスアイデアを磨く上で大事なことだと思います。
戸松:自分とは意見の異なる他者の中にこそ新しい視座がある、とレヴィ=ストロースも論じていますが、他者とビジネスを構築したり、こうして皆さんの知見に触れたりする意義が改めて感じられたところで、第1部はここまでにしたいと思います。貴重なお話をありがとうございました。
続いて第2部では、3名のOPEN HUB Base会員によるビジネスアイデアのプレゼンテーションが行われました。発表されたビジネスアイデアについて、山口氏、樋口氏、水野氏の有識者3名はどのような評価をし、フィードバックを行ったのか。プレゼンターと有識者との間に、どのようなアイデアを深める対話があったのか。ぜひ当日の模様を収録した動画をご覧ください。
「仮)日本映画再興計画」
株式会社電通 2BX局 鈴木 涼真
映画製作の現場で資金難に困っている有望なクリエイターを、映画製作に意欲を持つ富裕層とマッチング。邦画製作を活性化させ、邦画の世界的プレゼンスを高めることを目的としたサービス
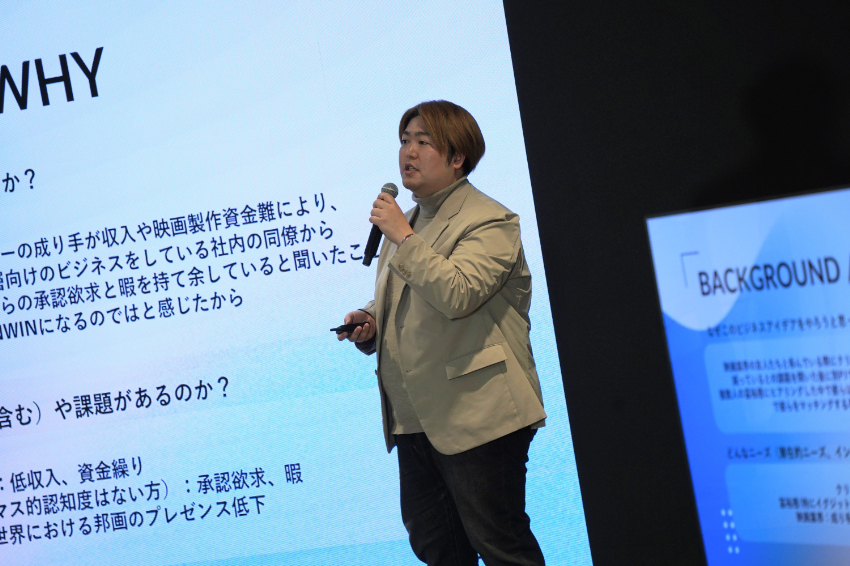
「社内図書館×Web3」
日本郵船株式会社 イノベーション推進グループ 原 文也/DX推進グループ 横山 真由
社内各所にある図書管理を、従来の紙方式からデジタル化することで管理効率+知的生産性を向上。Web3のブロックチェーン技術を活用した新たなコミュニケーションツールも提供し、社員の知性と独創性を刺激する環境を構築

「セカンドメディカルアドバイザー」
株式会社パソナグループ メタバース本部 内藤 駿貴
“紹介状を必要としない”セカンドオピニオンプラットフォーム。自分自身の健康情報(PHR)の所有を前提とした、最適な専門医の推薦とパーソナライズされた治療オプションの比較支援を提供

オンデマンド配信はこちら(視聴には会員登録が必要です)
本イベントの最後には、会場であるOPEN HUB Parkに観覧参加した会員とプレゼンター、有識者の方々を交えたネットワーキングを開催。第1部のトークセッション、第2部のプレゼンテーションなどについてさらに議論を深めていきました。OPEN HUBでは、今後もさまざまなビジネスインサイトの提供や、ビジネスアイデアを磨いた先の新規ビジネス共創を目指して活動展開していきます。


OPEN HUB
THEME
Co-Create the Future
#共創