
01
2025.07.18(Fri)
この記事の要約
元シャープ社長の片山幹雄氏は、日本企業が直面する課題と共創の重要性について語っています。
日本の大企業はヒト・モノ・カネの固定化により時代の変化に対応しづらく、グローバル市場での競争力低下を招いています。その主因は販売網の不足など偏重した経営戦略にあるといいます。
また、片山氏は共創こそが企業間再編を促し不足要素を補完する有効手段であると説明します。成功するリーダーには情熱とスピード、「やってみなはれ」の精神が重要で、クロストレプレナーには収益を生む仕組みづくりと競争力が求められます。
日本の変革には、能力ある人材の登用と資本の集中が不可欠です。片山氏は現在を日本企業の成長チャンスと捉え、積極的な共創を通じたイノベーションの重要性を強調しています。
※この要約は生成AIをもとに作成しました
目次
――「共創」をキーワードに考えたとき、現在の日本企業はどのような課題を抱えていると言えそうでしょうか。片山さんのお考えをお聞かせください。
片山幹雄氏(以下、片山氏):日本の大企業では、創業から年月がたっているが故にヒト・モノ・カネが固定化し、流動性がなくなっているケースが散見されます。そのため、時代の変化に対して鈍くなってしまっている。資本も人も動かなくなってしまっているから、成長産業と呼ばれる分野で新規事業をスタートしたいと思いながらも「資金が足りない」「人が足りない」とボヤくだけで終わってしまうのです。
総合電機メーカーが象徴するように、大企業は小さな事業ユニットの集合体になっています。多角化経営においては、人材や資本が企業内で分散し、成長分野を伸ばそうと思っても集中投資がしにくくなってしまうのです。海外に目を向けると、単一事業のベンチャー企業が立ち上がり、そこに資本と人材が集中投下されています。ヒト・モノ・カネが成長分野に流動していく。だから、グンと数字が伸びる。日本は大企業の中でヒト・モノ・カネが分散し、流動性が失われ、各事業が中途半端になってしまっています。これがグローバルでの競争力が足りないといわれる理由の1つにもなっていると思います。

――片山さんは、かつてシャープで液晶事業本部長や同事業部の取締役を歴任され、同社の代表取締役を務められました。イノベーションの波を最前線で見つめ、世界で戦ってきたご経験もお持ちです。その中で得た教訓として、若い世代に伝えたいことはなんですか?
片山氏:世界に通用するためには、開発力ももちろん重要ですが、同時にグローバルに営業体制を敷かなければなりません。液晶事業を通じて自分が見てきたことをお話しすると、1990年代後半から2000年代初頭にかけて、当時のシャープは「AQUOS(アクオス)」が象徴するように日本国内での液晶テレビのシェアは60%以上を誇っていました。
その一方で、欧米や中国といった国外での営業体制はつくれていなかったわけです。韓国のサムスンに追い抜かれてしまった大きな要因は、デリバリーで負けたことでした。私が2007年にシャープの社長になったころ、韓国に比べてグローバルでの販売網が不足していた。一方、サムスンは欧州市場に年間1兆円規模の巨額の販促費を使っていました。そして、ロシアと契約して私たちより先にシベリア鉄道を押さえていたのです。
つまり、グローバルの販売網を確立できないまま国内に巨大な生産体制をつくってしまっていた。そして、韓国に販売網で負けていると分析できていたにもかかわらず、資本力や人材力に限界があり、手の打ちようがなかった。なんとしてでも資金をかき集めて営業部隊を増やすとか、あるいは海外に販売網を持つ他社とM&Aを行うなどできればグローバルでも勝てたかもしれませんが、当時はそういう戦略を立てる企業はありませんでした。
なぜ韓国はグローバルの販売網に巨額の投資ができたかというと、企業統合を行っていたから国内で競争しなくても利益が出せる体制をつくれていたのです。一方、当時の日本は液晶やパソコンの事業を持つ企業が乱立してしまっていた。国内に資本が分散し、シャープのみならず、日本国内のどの企業もグローバルでの競争に勝つための体制づくりができていなかったのです。
この教訓から言えることは、まず、企業はしっかりと自社の分析をしなければいけません。企業の中のサプライチェーンを考えたときに、開発、生産、営業、管理などどこかに偏重しているケースが多く、すべてが均一にきれいなパイプで運用されていることはめったにありません。今申し上げた液晶事業の事例で言うと、生産に偏重していて、海外の営業力が不足していた。その結果として事業は伸び悩み、グローバルでの競争でも負けてしまった。だからこそ、自社には何が足りていて、何が足りていないのかを冷静に分析することが重要なのです。
とはいえ、事業体によって偏重が生まれてしまうのは仕方がないことでもあります。大事なことは、自社に不足している要素をどこから、どのように補うか、タイムリーに戦略を立てることなのです。本来は経営企画室や企画管理部といった部署がその分析を行うべきですが、現在の日本企業の多くは決算処理に追われ、分析が後回しになっているように見受けられます。
――近年、企業間で共創してイノベーションを起こそうとする流れができてきています。今回の「Xtrepreneur AWARD」も、こうした取り組みに光を当てることを目的としたアワードです。共創の意義について片山さんはどのようにお考えですか。
片山氏:企業がこういうかたちでクロスしていくという動きは、硬直化した日本企業にとって大きなチャンスだと私は思っています。事業を切り出し、技術を持ち寄ることによって、ヒト・モノ・カネに流動性が生まれる。さらに自社には足りていないものを、他社との共創により補い合うことができる。非常にいい動きが出てきているなと思います。
同時に、日本は今、産業の大きな変わり目を迎えています。グローバル視点で考えたとき、ビジネスの世界では「日本のインフラはやっぱりすごい」と再び注目を集め、日本に資本が集まり始めています。円安の影響はもとより、日本の成長性にも期待が高まっているのです。

では、私たちは今何をすべきなのか。期せずして、今年7月から新紙幣に渋沢栄一の肖像が採用されましたが、彼は、お金を集め、人材を確保し、銀行、鉄道、ガス、製紙業とどんどん新しい事業を築き、新しい産業の構造をつくっていきました。そこに「共創」のヒントがある。歴史は繰り返すものですし、何かをつくるということは、中身が変わっても一緒です。私たちは、渋沢栄一に学ぶべきものがたくさんあると思います。
――では、共創によりイノベーションを起こしていく上で、まず重要なことはどのようなことでしょうか。
片山氏:まずは能力のある人をリーダーにすることです。渋沢栄一が中心になって産業の構造を変えていったように、ヒト・モノ・カネを集め、動かせる人をリーダーにしなければいけない。日本企業の多くは年齢や社歴で責任のある役職に人を立てがちですが、その人たちに、新規事業に適した能力があるとは限らない。これからはちゃんと人を見てリーダーを任せなければいけないのです。
そして、リーダーに必要な資質は何かというと、情熱とスピードです。優れたリーダーは皆、ビジネスの情熱が強すぎるが故に突っ走ってしまうことがある。私もこれまでに何人もの経営者とお会いしてきましたが、アポイントもなしに会社に乗り込んできた経営者もいたし、世間的には「変わっている」と思われるような一面を持ち合わせている人が本当に多かった。でも、そういう人こそ、日本の産業史に残るような実績を残しています。
彼らはなぜ突っ走るのか。ビジネスの成功にはスピードが不可欠だからです。成功するリーダーというのは、情熱で走り回るのです。今の共創の動きを見ていても思うのは、とにかく産業の変わり目を迎えている今を絶好のチャンスと捉えて、1年、2年というスパンでスピーディーに事業を展開していくべきです。3年、5年と時間をかけていたら、国内外のどこかで必ず先を越されますから。

それから、マネジメント上心得ておくべきは、サントリー創業者・鳥井信治郎や、「経営の神様」とも呼ばれたパナソニック創業者・松下幸之助のような「やってみなはれ」の精神です。5億円なり、10億円なり、事業に必要なお金を出して、あとは成功を見届ける。お金を出す代わりに決算書を随時提出させているようでしたら、数字に追われて本当に必要な開発や営業に割くべき時間や人が削られてしまいますから。利益余剰金など、大企業にはいろいろな意味で資本が残っていますよね。そういうお金を、イノベーションを起こそうとする人たちに移していかないと、今日本が迎えている大きなビジネスの波に乗ることはできません。
――ビジネスモデルを維持・発展させやすい事業体制を構築するためのアドバイスはありますか。
片山氏:人が仕事をする、ということを忘れてはなりません。アップル創業者のスティーブ・ジョブズの伝記を私は何回も読み直しましたが、彼が日々何を考えていたかというと、今日は誰に会うか、誰と組むか、誰に何をしてもらうか、ということばかり。どんなアイデアが浮かんだとか、何をどう頑張ったかは、ほとんど意識していないのです。
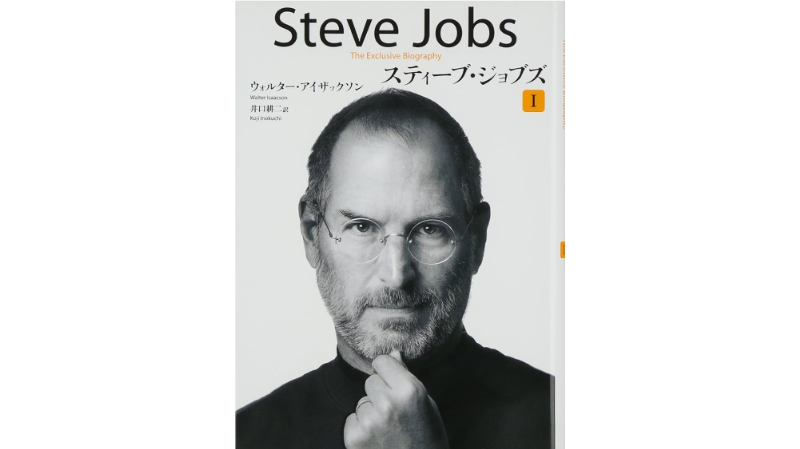
ビジネスを維持・発展させるために一番大事なのは「人」です。先ほど誰をリーダーにするのか、という話をしたときにも触れましたが、日本は能力や技術よりも、社歴や年齢で人を見がちです。でも、ビジネスを成長させる上で本当に大事なのは、その事業に必要な能力を持つ人を集めること。スティーブ・ジョブズが日夜人集めに奔走したように、開発、製造、営業、管理とそれぞれに敵した人を探してこなければいけない。社内にいなければ、社外からスカウトしてこなければいけない。共創するときには、どこと組むか誰と組むかが重要になります。
――今回の「Xtrepreneur AWARD」の選考会を経て、あらためてクロストレプレナーにはどのような能力が必要だとお感じになりましたか。
片山氏:大きく分けて2つあります。1つめは、お金が回る仕組みをつくる能力。お金の話ばかりするといやらしく聞こえるかもしれませんが、これはビジネスですから。事業を軌道に乗せ、さらに拡大しようとするときには、必ず巨額の投資が必要になる。ビジネスの継続と発展にはもうかる仕組みが不可欠です。
今回の選考会でもさまざまなエントリーがありましたが、残念ながらアイデアが良くてもお金が集まる仕組みをつくれていないプロジェクトもありました。どんなに素晴らしいアイデアでも、マネタイズのプランがなければ継続・発展は見込めません。
2つめは競争力です。今回のエントリーの中には、日本では新しいビジネスに見えても、世界ですでに先行事例が出ているプロジェクトもありました。つまり、新規事業を始めるにあたってリサーチが足りていないのです。新しい事業をグローバルで拡大をするときには、世界に通用する視点を持ち、情報を収集・分析していかなくてはなりません。
どんなビジネスも、必ず競争相手がいます。これは、絶対です。日本の中で優位だからといって、世界でも勝てるとは限らない。勝てない相手に立ち向かうときには、戦略を立てなければいけない。そこでも「共創」は大きな力を発揮します。足りない力を補うきっかけになるからです。世界で戦おうとするとき、今のチームに何が足りていないのかを分析する。そして、自分たちが必要とするものを持つ他社と手を組んで、勝てるシナリオをつくっていけばいいのです。
――最後に、「共創」をミッションに掲げている皆さまに向けてメッセージをお願いします。
片山:今、日本は本当に大きな時代の変わり目を迎えています。そして、AIからもたらされる新たなイノベーションの波も起きている。日本には優秀な人材も技術も揃っているわけですから、世界に通用するような事業がこれからどんどん生まれていく可能性があるのです。だからこそ、小さくまとまっていたら駄目なのです。今のように大企業が組織と経営が固定化したままでは、グローバルでの戦いでまた負けてしまう。能力のある人を集め、資本をかき集めて、世界に対抗できるような軸をつくっていくことがとにかく重要なのです。「共創」こそが、日本に変革を起こすと期待しています。
<関連イベントのご案内>
OPEN HUBとForbes JAPANは、社会課題に挑む事業共創アワード「Xtrepreneur AWARD 2024」の受賞プロジェクトを中心にした特別イベントを開催いたします。
本イベントでは、作家・池井戸潤氏も注目した福井経編興業・帝人・大阪医科薬科大学の共創プロジェクトの「シンフォリウム」や、日本初の「ゼロ・ウェイスト宣言」を行った徳島県上勝町と三菱地所・スペックによる都市部での資源循環プロジェクトなど、受賞事例をご紹介。
トークセッションやピッチプレゼンテーション、ネットワーキングの場を通じて、未来をつくる共創の可能性を広げます。
申込はこちらから


OPEN HUB
THEME
Co-Create the Future
#共創