
01
2025.07.18(Fri)
この記事の要約
「クロストレプレナーアワード2024」のグランプリは、大阪医科薬科大学、福井経編興業、帝人が共同開発した「心・血管修復パッチ『シンフォリウム』」が受賞しました。審査員の石川俊祐氏と川村真司氏は、このプロジェクトの長期的な取り組みと熱意に感銘を受けたと評価しています。特に注目されたのは、10年以上にわたるプロジェクトを完遂した点です。
プロジェクトの継続には初期の成功体験が重要であり、これがチームのモチベーション維持に大きく貢献するといいます。また、共創プロジェクトを成功に導くためには、熱意あるリーダーシップと、人々を巻き込む力が不可欠であると強調されています。
このグランプリ受賞は、医療分野における長期的な研究開発の重要性と、異分野間の協力の価値を示しています。「シンフォリウム」の開発は、粘り強い取り組みと効果的な共創が、革新的な医療ソリューションを生み出す可能性を示す好例となりました。
目次
——「クロストレプレナーアワード2024」を振り返って、審査の感想をお聞かせください。
石川俊祐氏(以下、石川氏):なんといってもインパクトがあったのは、グランプリに選出された「心・血管修復パッチ『シンフォリウム』の共同開発」(大阪医科薬科大学、福井経編興業、帝人)ですよね。医工/産学官の連携で心疾患の子どもたちを救う技術を生み出したプロジェクトの発想や開発力はもとより、10年以上という長い期間をかけて取り組み続けたことが素晴らしい。近年、企業間の共創や協働のプロジェクトが増えていますが、2年、3年で中断してしまうケースが本当に多いです。だからこそ、このプロジェクトはそもそもなぜ諦めずに10年も継続できたのか、短期間での結果を求めがちな企業にとっても、大きなヒントが秘められていると感じました。

川村真司氏(以下、川村氏):数年で頓挫してしまったプロジェクトを、私もこれまでに数えきれないほど見てきました。プロトタイプの発表まで進んだのに、完遂できないものが多い。その理由としては資金繰りだけでなく、技術やアイデア、熱量などプロジェクトを持続させるための要素が欠けてしまっていることが考えられますが、この心・血管修復パッチのプロジェクトは、とにかく中心人物たちの「完成させなければならない」という強い熱量を感じました。
——デザインやクリエイティブを専門とするお2人は、このプロジェクトが実を結んだ理由をどのように読み解きますか?
石川氏:まずビジョンを設定する段階で、課題を解決した先の幸せな未来まで描けていたことですよね。単純に「一緒に課題を解決しましょう」と言うだけでは、なかなか人はついてきてくれません。例えば、サーフィンが大好きで一生続けていきたいから、そのために海洋保護に取り組む、でもいい。美しい自然を守りたい、それがどんな未来につながっていくのかをブレずに描ききることが大切ですよね。

今回のグランプリに選ばれた心・血管修復パッチは、先天性心疾患の子どもを救うことが目的で、子どももその家族も、そして手術を行う医師もみんなが幸せになる未来がすぐに想像できる。「生まれてすぐに手術した後、従来は成長に合わせて再手術が必要だったけど、子どもと一緒に成長していくパッチを開発すればもう手術しなくてよくなる。だから、どうしても開発したい」と言われると、その熱量はすごく伝わってくるし、共感しやすいですよね。人の巻き込み方が上手なプロジェクトです。
川村氏:プロジェクトをスタートさせたら、次はどう継続させるかがポイントになってきますが、そこで必要なのが「成功体験」だと私は思っています。このプロジェクトでも、研究、実験を重ねるなかで、メンバーが「いける!」と確信した瞬間があったと思うのです。その成功体験の積み重ねが、プロジェクトを持続させる燃料になる。だからこそ、壮大なビジョンを描いてスタートするプロジェクトであっても、小さい成功体験をどれだけ早くつくるかがカギになります。

——プロジェクトデザインやチーム設計のために重要なことは何でしょうか?
川村氏:プロジェクトにおいて大事なのは、人を集めること。そして、集まった人が成功を紡いでいくことです。そういう意味で、この「クロストレプレナーアワード」が核心をついているのは、「クロストレプレナー」、つまり人に焦点を当てていることだと思います。組織づくりにおいては、イノベーションを起こそうとしている人を応援する、つまり「自由に動いていいよ」と許容してあげるカルチャー醸成が重要だと思うのです。

石川氏:まさに私も同じことを思っていました。新規プロジェクトをスタートさせるとき、チームや部署、あるいは新会社を新設させることもあります。いずれのケースにおいても、少しでも早くプロジェクトを成功させるためには、意思決定の権限委譲をすることがポイントになります。
実は最近、「意思決定のデザイン」というテーマで思索を深めていました。世の中の課題が複雑化する中で、企業にとっても「自分たちらしさ」という視点は重要です。自分たちならではの意思に基づいて、誰のためにどんな価値を追い求めるべきなのか、といった意思決定の基準を決めておく必要があります。その答えが、企業としてのユニークさやブランドを形成しますし、ときには「自分たちらしくないからやらない」と決断する勇気も必要になるでしょう。
「共創」というテーマに当てはめるなら、現場を熟知しているプロジェクトの中心人物に意思決定の権限がなければ、モチベーションを維持できないだけでなく、ゴールに辿り着くまでに時間がかかり、もっと言うと、世界中のどこかで別の誰かが先に同じ内容のプロジェクトを成功させてしまうかもしれません。単なる前例踏襲ではなく、日本発の共創ビジネスをつくっていくためには、プロジェクトを前へ前へと推進する彼らに意思決定の権限を委譲することが本当に大切なのです。
——お2人はこれまでに大企業や行政など、さまざまなステークホルダーとのプロジェクトを手掛けていらっしゃいます。そのなかで大切にしてきたことはどんなことでしたか?
川村氏:誰もが共感できるアイデアをいかに端的に伝えられるかを大切にしています。人の心を動かすアイデアって、実はとてもシンプルです。説明に時間がかかるものは、アイデアとしてうまく伝わりません。人として共感できる、思わず笑顔になれる。そんなヒューマンインサイトに近いアイデアが結局は一番強いし、いいアイデアだと思います。

それから、どんな規模のプロジェクトであれ、あきらめずに声を上げ続けること。私が過去に事業開発で手がけた「minute mint(ミニット ミント)」は時間を計れるミントタブレットで、3分もしくは1分半で溶けるようにつくってあるのですが、なかなか共同開発してくれるパートナーが見つからず、開発までに10年以上かかりました。
グランプリを受賞した大阪医科薬科大学病院の小児心臓外科医・根本慎太郎さんも、体内で細胞と一緒に伸張するパッチのアイデアを約10社の医療機器メーカーに伝え続けてきたけれど、はじめは見向きもされなかったそうです。それでも諦めずに、福井経編興業に声をかけ、プロジェクトを進めていくなかで足りないものが見えてくると、大手メーカーの帝人に働きかけて、どんどん共創の輪を広げていった。そして今は、世界進出を目指してさらに輪を大きくしようとしています。大切なのは、人の心を動かすアイデアと、それを伝え続けるパッションなのだろうと思います。
——カルチャーの異なる人たちが互いに理解し、協力しあえるかどうかも共創の成否を分けるポイントになってくると思います。石川さんから、何かアドバイスはありますか。
石川氏:人が大勢集まって何かを成し遂げようとするとき、全員が同じ熱量を持つのは難しいものです。「このやり方だとうまくいく」という正攻法はありません。そのなかで大事なのは、「のりしろ」をつくっておくこと。アルファベットのTの字のように、自分の専門スキル(縦線)をしっかりと築いておき、好奇心や興味の幅(横線)を広げる。こののりしろがくっついてコラボレーションが生まれたり、カルチャーの違う相手であっても対話から協力へと発展するきっかけになります。のりしろをデザインしていくことに、共創のヒントもあるはずです。
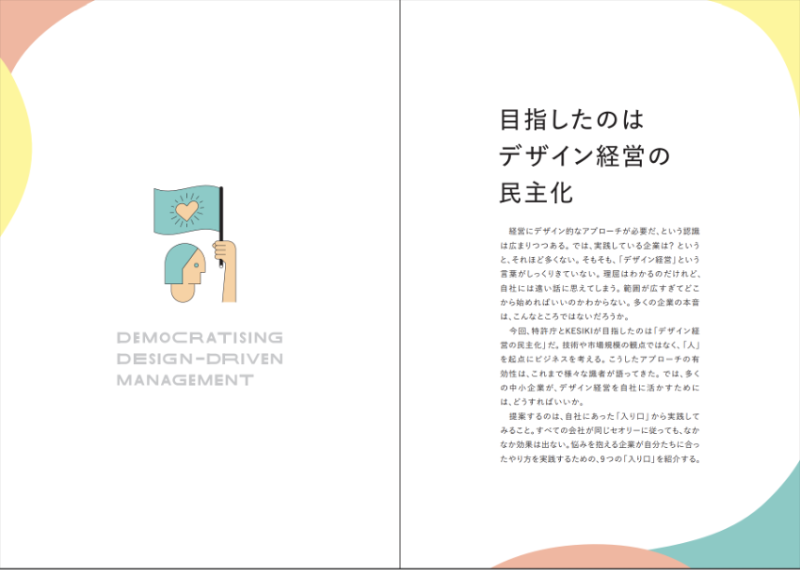
——「共創」という言葉に関心を持ったり、実際に動き出したりする企業も増えてきました。この気運をさらに高めていくためには、どのようなことが必要だと思いますか?
石川氏:マネージャー層の方々に向けては先ほど権限委譲の話をしたので、現場に立つプレーヤー層の方々には、自分でアクションを制限していないか、振り返ってみてほしいです。「許可されないだろう」「組織の枠を越えられない」と、自分でブレーキを踏んでいるケースもあるのではないでしょうか。でも、実はそれが思い込みで、上層部の人たちは「もっと自由に動いていい」と思っているときもあるかもしれません。
川村氏:そうですね。よりカジュアルに共創が生まれるようになっていくといいですよね。今はまだ少し、共創が特別視されているように感じます。「最初は失敗しても仕方ない」くらいの気持ちでプロトタイプを積み重ねていけたらいいのではないでしょうか。その心理的安全性を組織として担保してあげることも不可欠です。
それから、繰り返しになりますが諦めないこと。2年、3年続けてやっと芽が出てきて、そこからさらに育てていかなくてはいけない。共創とは、そういうものです。マネージャー層の見守る覚悟、そして何よりもプレーヤー層の成し遂げる覚悟が大事だと思っています。
<関連イベントのご案内>
OPEN HUBとForbes JAPANは、社会課題に挑む事業共創アワード「Xtrepreneur AWARD 2024」の受賞プロジェクトを中心にした特別イベントを開催いたします。
本イベントでは、作家・池井戸潤氏も注目した福井経編興業・帝人・大阪医科薬科大学の共創プロジェクトの「シンフォリウム」や、日本初の「ゼロ・ウェイスト宣言」を行った徳島県上勝町と三菱地所・スペックによる都市部での資源循環プロジェクトなど、受賞事例をご紹介。
トークセッションやピッチプレゼンテーション、ネットワーキングの場を通じて、未来をつくる共創の可能性を広げます。
≪出演者≫
中野貴之 氏(帝人ミッション・エグゼクティブ再生医療・埋込医療機器部門長 医学博士/経営管理修士
髙木義秀 氏(福井経編興業 代表取締役社長)
根本慎太郎 氏(大阪医科薬科大学 医学部 外科学講座胸部外科学教室 教授 小児心臓血管外科診療科長)
上田寛 氏(三菱地所 TOKYO TORCH事業部長)
田中達也 氏(スペック 代表取締役)
花本靖 氏(上勝町 町長)
申込はこちらから


OPEN HUB
THEME
Co-Create the Future
#共創