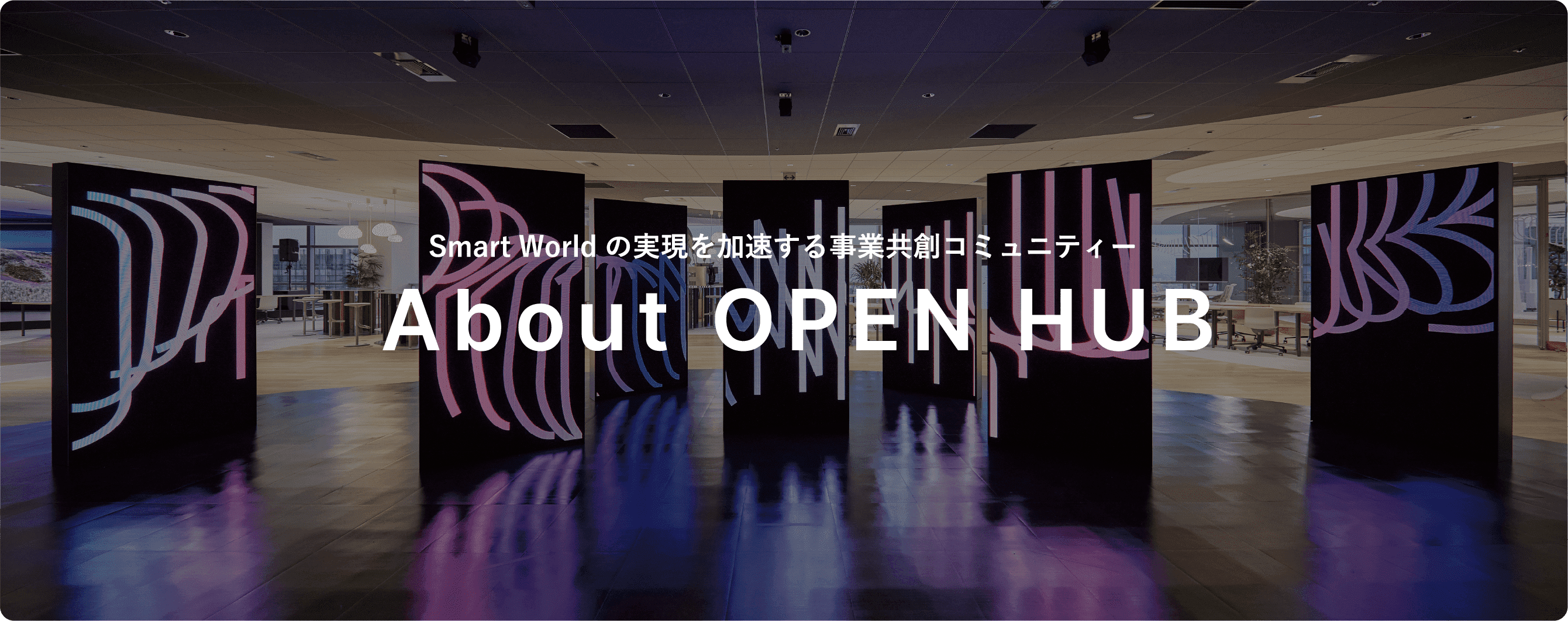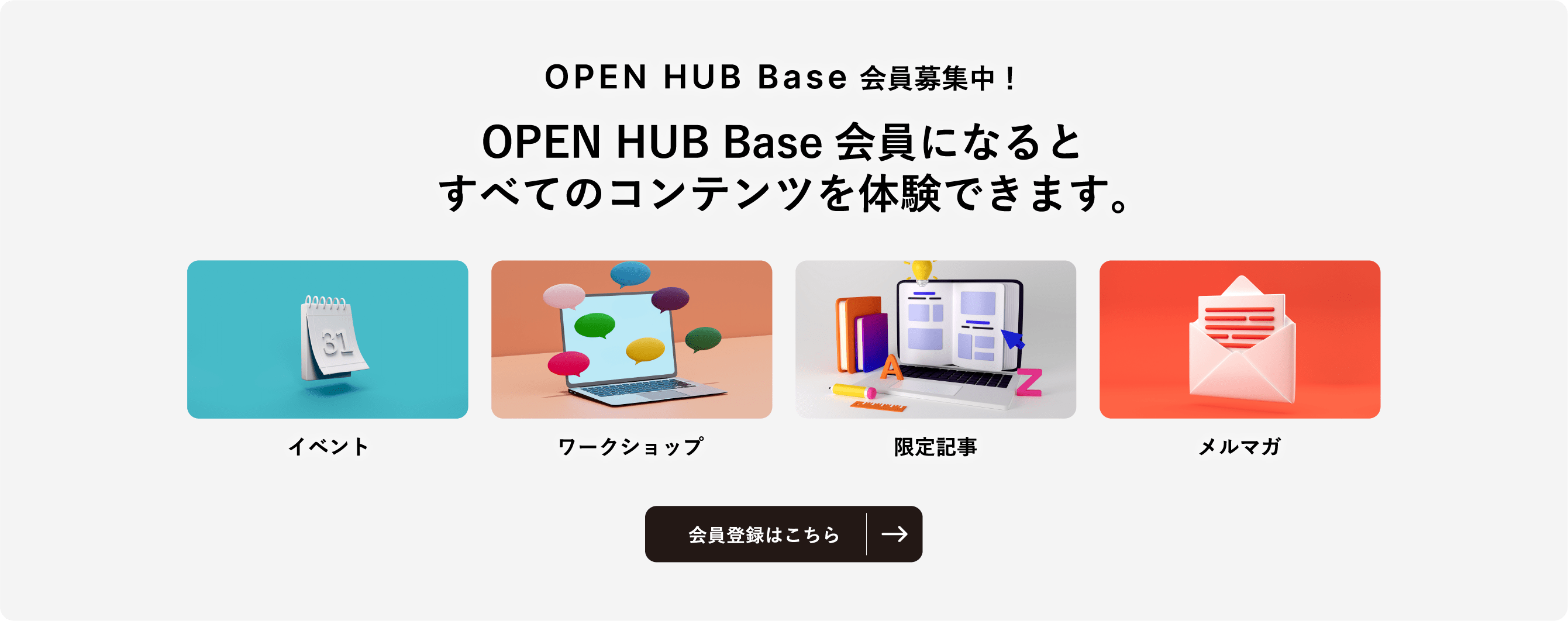目次
スマートシティの基礎知識
まずはスマートシティの基礎知識をお伝えします。スマートシティの意味や、似ている用語との違い、必要性が高まっている理由などを解説します。
●スマートシティの意味
スマートシティとは、まちづくりにAIやIoTなどの先端的なICT(情報通信技術)を活用して、都市機能やサービスの高度化・効率化を目指す取り組みのことです。国土交通省都市局は、スマートシティを以下のように定義しています。
“都市の抱える諸課題に対して、ICT等の新技術を活用しつつ、マネジメント(計画、整備、管理・運営等)が行われ、全体最適化が図られる持続可能な都市または地区”
出典:「都市交通調査・都市計画調査」(国土交通省)
スマートシティという言葉が広まった当初は、エネルギー問題や環境問題などの個別分野に関する取り組みが中心でした。それに対して近年では、住民のウェルビーイングの向上が重視されるようになっています。ウェルビーイングとは、精神的・身体的・社会的に満たされている状態を指します。現在は、こうした複数分野の課題を横断的に解決するまちづくりが、官民連携で進められている状況です。
●スーパーシティとスマートシティの違い
スーパーシティとは、先端技術の活用により住民生活全体の利便性向上を目指している都市や地区のことです。内閣府地方創生推進事務局のスーパーシティ構想においては「住民が参画し、住民⽬線で、2030年頃に実現される未来社会を先行実現することを目指す」と強調されています。スマートシティは技術の活用を重視した考え方である一方、スーパーシティはより住民目線で課題解決に必要な技術を用いるという点が、両者の違いといえるでしょう。
出典:『「スーパーシティ」構想について』(内閣府地方創生推進事務局 令和3年8月)
●スマートシティとスマートビルディングの違い
スマートビルディングとは、先端技術の活用によって効率的な管理を実現した建物のことです。主に企業のオフィスビルや大規模な商業施設などへの導入が進んでいます。スマートシティとスマートビルディングは、どちらも先端技術を活用して利便性を向上させるという点が共通しています。ただし、スマートシティでは街全体が対象となり、スマートビルディングでは建物が対象となるところが大きな違いです。
●スマートシティの必要性が高まっている理由
日本をはじめとした世界各国では、都市部への人口の集中が進んでいます。このように都市部に人口が集中すると、さまざまな社会課題が引き起こされることが懸念されており、具体的には、環境問題、エネルギー問題、交通問題、地方経済の停滞などが挙げられます。日本ではこれらに加えて、インフラ設備の老朽化や高齢化社会への対応、自然災害への対策なども課題となっています。こうした背景から、まちづくりに先端技術を活用して、複雑化する社会課題の解決が期待できるスマートシティに注目が集まっているのです。
スマートシティの実現によるメリットと想定される課題
スマートシティを実現すると、どのようなメリットが期待できるのでしょうか。現状の課題と併せて解説します。
●メリット
・持続可能な都市を実現できる
スマートシティ化によって将来の世代にとって暮らしやすい都市を実現できます。というのも、ICTの活用を通してさまざまな社会課題が解決され、生活の質の向上につながるためです。具体的には交通渋滞、高齢者ケア、エネルギー不足などの課題を解決へと導き、さらにはSDGs(持続可能な開発目標)の達成にも貢献します。
・防災や減災に役立てられる
自然災害のリスクがある地域では、スマートシティ化による防災や減災が期待できます。たとえば、地域の特定の箇所にIoTのセンサーやカメラを設置することで、河川の氾濫や土砂崩れなどの危険性を早期にキャッチし、住人への的確な避難の促進が可能に。ほかにも、被災状況の把握や住民への情報共有など、先端技術を幅広く役立てることができます。
・ビジネスチャンスの創出を期待できる
スマートシティ化により自治体や教育機関、そして民間企業の連携が進み、新たなビジネスが生まれる可能性が期待されています。官民連携により住民の利便性が向上するだけでなく、地元企業のビジネスチャンス創出にもつながるでしょう。
●想定される課題
・トラブルによる都市機能停止のリスクがある
スマートシティでは、システムトラブルやサイバー攻撃を受けた際に、都市機能そのものが停止してしまうおそれがあります。住民生活への影響や情報の流出などが懸念されるのが課題です。都市機能の維持に必要なデータやシステムの分散管理、ICTに依存しすぎないまちづくりなどが必要となります。
・プライバシーの確保が必要になる
スマートシティでは幅広いデータを活用することで街の利便性が高まる反面、住民のプライバシーへの配慮も欠かせません。人によっては、知られたくないと感じる情報が収集されることに不安を感じる場合もあるでしょう。住民のプライバシーの確保は不可欠です。
・住民自身の参画が求められる
スマートシティ化を推進するには、地域住民からの賛同を得る必要があります。施策では住民の協力が求められる場面も数多く存在するため、先端技術に親しみやすい若年層だけでなく、高齢者層の住民も広く参画できるように工夫することが重要です。
スマートシティの取り組み事例
日本国内では各地でスマートシティ化が進んでいます。最後に、スマートシティの具体的な取り組み事例をご紹介します。
●福島県会津若松市
福島県会津若松市は、急激な人口減少の進行という課題を受けて、将来も住み続けられる街を作るために「スマートシティ会津若松」に取り組んでいます。スマートシティ化へ向けて、母子健康手帳の電子化や、通院の負担を軽減するオンライン診療などを実現。幅広い世代の住民が恩恵を受けられるようになりました。また、ICTを農業の分野に活用する「スマートアグリ」など、農業振興にも力を入れています。
●北海道札幌市
北海道札幌市では、健康寿命の延伸やイノベーション創出などを目指して、ICTを活用したスマートシティ化を進めています。代表的な事例として挙げられるのは「健康ポイント事業の実施」です。住民が専用アプリから街歩きに参加することで、収集されたデータがまちづくりや新サービスの開発などに活用されます。市民の行動変容を促進し、健康寿命を延ばすことが施策の目的となっています。
●富山県富山市
富山県富山市のスマートシティ事業では、市内に設置されたIoTセンサーから情報を収集し、住民への情報共有に役立てられています。市民向けの情報公開サイトでは、行政窓口の混雑具合や、道路工事・除雪の状況など生活に必要な情報をリアルタイムで把握できます。さらに、今後は被災状況の把握や迅速な復旧作業に役立てられるよう、災害発生時に備えてプラットフォームの整備が進められている状況です。
合わせて読みたい:
「「都市開発✕デジタル」に必要なSmart Cityの発想と乗り越えるべき課題」
スマートシティの実現へ向けて企業ができること
ここまで、スマートシティの基礎知識から、メリットや現状の課題、自治体での取り組み事例までご紹介しました。このほかにも、企業が提供するソリューションを上手に活用することスマートシティの実現に貢献できる場合もあります。NTTコミュニケーションズ(以下、NTT Com)では「Smart City推進室」を設置し、ICTの活用によって、都市に関する社会課題の解決に取り組んでいます。安心安全で住みやすいまちづくりに貢献するNTT Comの取り組みやソリューションについて、ぜひ一度ご確認ください。
合わせて読みたい:
「Smart City 街づくりDXソリューション」
「CROSS LAB for Smart City」
さらに詳しく知るために、合わせて読みたい関連記事



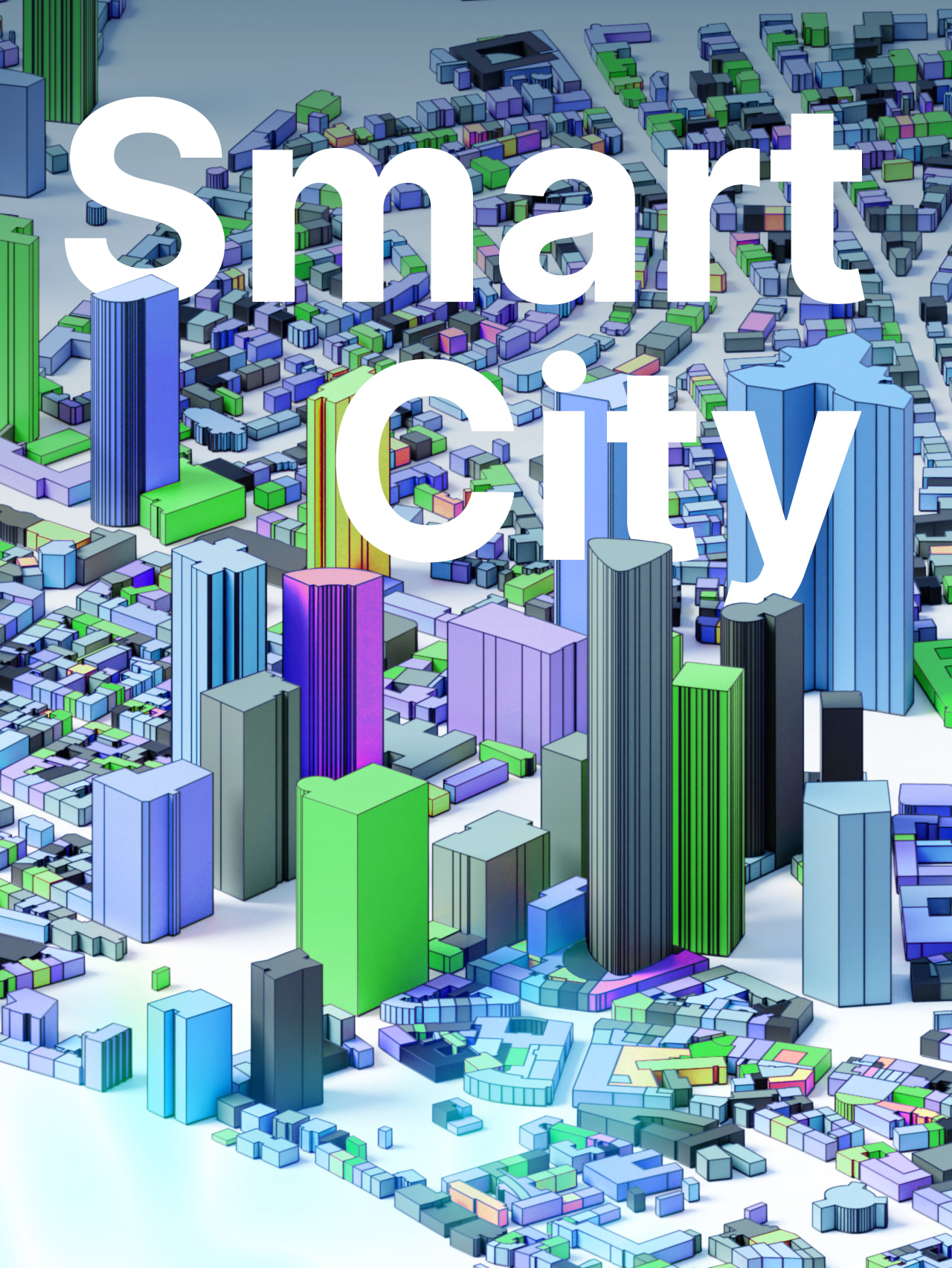
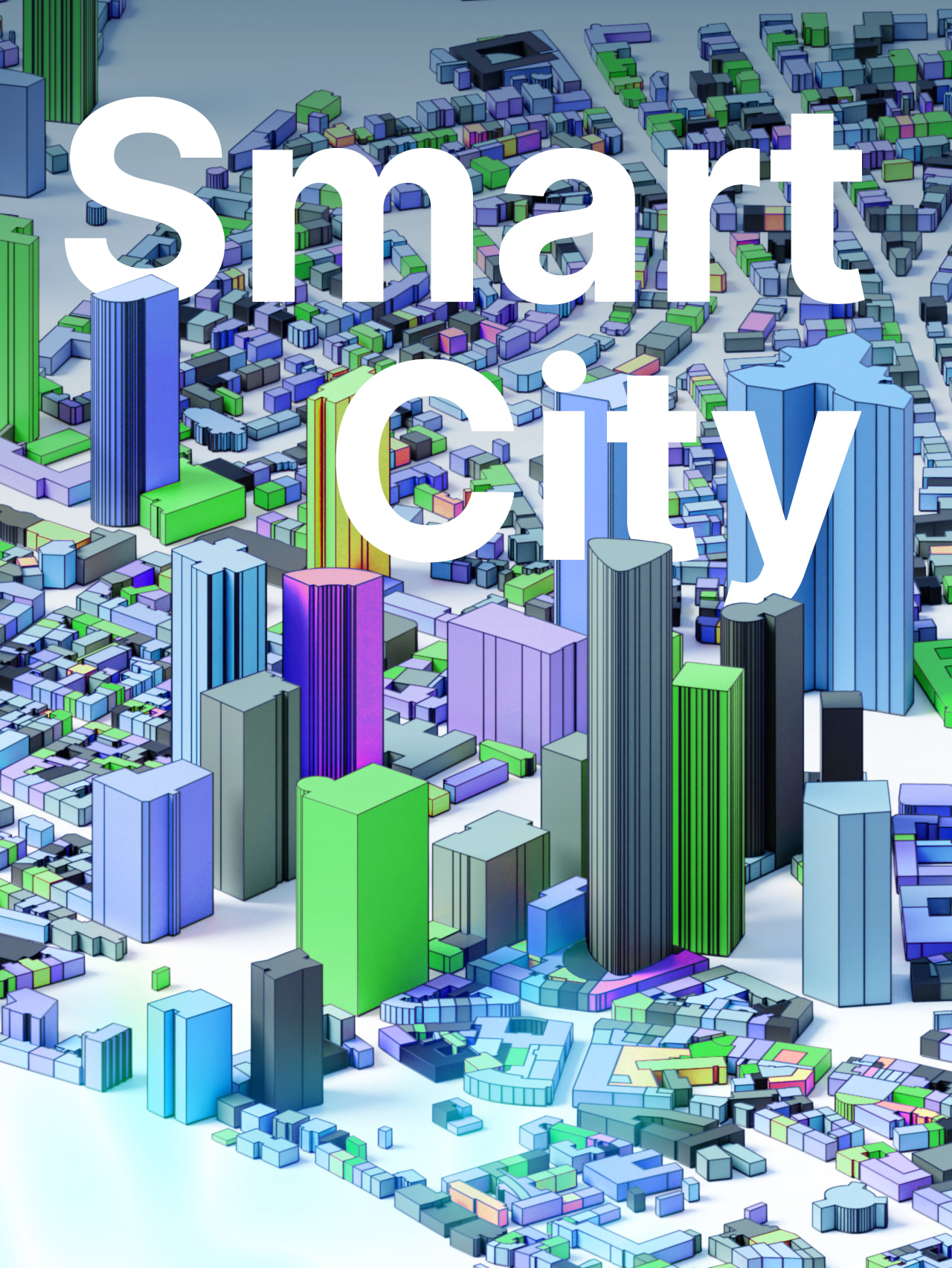
OPEN HUB
THEME
Smart City
#スマートシティ