
01
2025.07.18(Fri)
目次
ゼロカーボンとは「カーボンニュートラル」とも呼ばれ、温室効果ガス(二酸化炭素など)の実質的な排出量をゼロにすることです。温室効果ガスの排出を完全に止めるのは難しいものの、森林による吸収やCO2を回収・貯留する技術などを活用し、排出量と吸収量が釣り合うことをめざします。
ゼロカーボンに向けての取り組みは、地球温暖化対策のためにも重要とされます。以下では、ゼロカーボンが必要とされる理由や、地球温暖化の進行による主な影響をご紹介します。
●ゼロカーボンが必要な理由
ゼロカーボンの実現は、地球温暖化の影響を抑制し、持続可能な社会を構築するために必要です。地球温暖化が進行すると、気候変動による異常気象、海面上昇、生態系への影響など、さまざまな問題が引き起こされます。未来の世代に安全な環境を残すためにも、社会全体でゼロカーボンに向けた取り組みを行うことが重要です。
●地球温暖化が進んだ場合の環境への影響
地球温暖化とは、温室効果ガスの増加によって地球の気温が上昇する現象です。温室効果ガスの排出量は、森林伐採、工場の生産活動、自動車の運転など、さまざまな要因で増えています。
地球温暖化が進行すると、猛暑や豪雨といった異常気象の増加による「農作物の生産量減少」や、海面上昇による「沿岸部の居住地域の減少」などの新たな問題も招きます。こうしたリスクを回避するためにも、ゼロカーボンへの取り組みが急務といえます。
ゼロカーボンの取り組みが世界的に広がる中、日本においても政府や自治体が具体的な行動を進めています。ここでは、2050年ゼロカーボンやゼロカーボンシティについて解説します。
●2050年ゼロカーボンとは
2020年10月、日本政府は2050年までにゼロカーボンをめざすことを宣言しました。この宣言は、2015年に採択された「パリ協定」を受けて行われたものです。パリ協定は国際的な気候変動対策の枠組みであり、世界の平均気温上昇を産業革命前と比べて2℃未満(努力目標時は1.5℃以下)に抑えることを目標としています。
●ゼロカーボンシティとは
ゼロカーボンシティとは、2050年までに温室効果ガスの排出量を実質ゼロにすることを目標とする地方自治体です。自治体がゼロカーボンシティへの取り組みを公式に表明することを「ゼロカーボンシティ宣言」といいます。
2024年12月27日時点で、東京都や京都市、横浜市などをはじめとする1,127自治体がゼロカーボンシティ宣言を行っています。2019年9月時点では4自治体のみが表明している状態でしたが、約4年で大幅に増加しました。ゼロカーボンの取り組みが全国的に広まっている状況が伺えます。
【出典】環境省「地方公共団体における2050年二酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」
ゼロカーボンへの取り組みは、企業にとってさまざまなメリットをもたらします。ただし、導入コストや地域住民との合意形成など、課題となり得る部分もあるため気をつけましょう。ここでは、ゼロカーボンに取り組むメリットや注意点を解説します。
●ゼロカーボンに取り組むメリット
・企業イメージの向上が期待できる
ゼロカーボンに取り組むことで、企業の環境意識の高さを示せます。近年は環境問題への関心が高まっており、エコフレンドリーな企業への支持が広がっています。ゼロカーボンに貢献する姿勢を明確に表すことで、消費者や取引先、株主などからの評価向上が期待できるでしょう。
・再生可能エネルギーの導入によって電気代などを節約できる
太陽光や風力などを利用した再生可能エネルギーを自社施設に導入すれば、電気代の節約になります。余剰電力が生じた場合は売電することも可能です。また、災害などの非常時に使える電源としても有効なため、防災目的で設置するのもおすすめです。
・機関投資家からの評価が上がり資金調達しやすくなる
投資先を選定するにあたって「環境・社会・ガバナンス(ESG)」を重視する投資家が少なくありません。ESGの3要素の評価が低ければ、魅力的な投資対象とみなされない可能性があります。
環境負荷の低減に努める企業は、SDGsやサステナビリティを重視する投資家からの資金を集めやすくなると期待できます。企業成長の観点からもゼロカーボンへの取り組みが重要です。
・新たなサービス開発によるビジネス創出
ゼロカーボンに関する技術開発やサービス提供は、新たなビジネスチャンスを生み出す可能性もあります。たとえば、脱炭素に貢献できる製品やリサイクル技術の開発、環境コンサルティング事業の展開などが挙げられます。また、欧州を中心に環境規制が厳しくなる中でゼロカーボン対応を進めることは、ビジネス機会の損失回避につながるでしょう。
・地球温暖化の防止につながる
ゼロカーボンの推進は、地球温暖化防止のためにも不可欠となります。温室効果ガスの排出を削減して気温上昇を抑えると、異常気象や自然災害などのリスクを軽減できます。企業や自治体が率先してゼロカーボンに取り組むことで、より持続可能な社会の実現に貢献できるでしょう。
・有限な資源の使用量を減らして枯渇を防ぐ
化石燃料などの有限な資源を大量に消費し続けると、いずれ枯渇してしまいます。ゼロカーボンへの取り組みを実践して、再生可能エネルギーの活用が促進されると、資源の消費を抑えられるでしょう。可能な限り燃料の輸入に頼らずに済む仕組みを整えることで、エネルギーの安定供給を確保し、経済的なリスク低減にもつなげられます。
●ゼロカーボンに取り組む際の注意点
・産業によってはコストがかかる
ゼロカーボンの実現には、新たな技術の導入や設備投資が必要になります。特に二酸化炭素を多く排出する産業ではコスト負担が大きくなるでしょう。たとえば、鉄鋼や化学産業などの場合は、製造過程で多量のCO2が排出されます。こうした産業においてゼロカーボンを達成するためには、革新的な技術開発が不可欠です。
・再エネ導入などで地域住民に理解を得られないおそれがある
太陽光発電や風力発電、水力発電などの再生可能エネルギーの導入時には、設備の設置による景観の変化や騒音などが懸念されます。地域住民の反発によって、再エネ導入がスムーズに進まないケースもあるでしょう。事前に住民との十分な対話を行い、地域にもたらすメリットをしっかりと伝える必要があります。
個人や企業がゼロカーボンを実現させる活動の例として、環境省が発表した「ゼロカーボンアクション30」があります。加えて、脱炭素に取り組む国民運動「デコ活」も展開されています。ゼロカーボンの実現に向けての計画を策定する際は、上記のような活動を参考にしてみましょう。以下では、環境省の「ゼロカーボンアクション30」をもとに、企業や個人でも取り組める対策の具体例をご紹介します。
●エネルギーを節約する・転換する
企業がゼロカーボンを実現するためには、エネルギーの消費を抑えつつ、再生可能エネルギーへの転換を進めることが重要です。再エネ電力への切り替えや省エネ設備の導入などを検討しましょう。また、クールビズ・ウォームビズの推進や宅配サービスの一括受取など、日常業務でのエネルギー削減策も有効です。企業全体での意識改革が、持続可能な脱炭素経営につながります。
●太陽光パネル付き・省エネ住宅に住む
オフィスビルや自社施設などに太陽光パネルを設置することで、自家発電によるエネルギーの活用が可能になります。断熱性能の向上や高効率な空調設備の導入により、エネルギー消費を抑えられるでしょう。経済産業省の「需要家主導型太陽光発電導入促進支援事業」のように、企業が利用できる補助金もあります。
●CO2排出量の少ない交通手段を選ぶ
企業活動におけるCO2排出を削減するには、公共交通機関の活用を推進する対策がおすすめです。テレワークやオンライン会議などを導入して、通勤や移動自体を減らす対策も効果があるでしょう。
また、社用車をEV(電気自動車)やFCV(燃料電池自動車)に買い替えることでも、交通分野の脱炭素化を進められます。経済産業省の実施する「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」を活用できるケースもあるため確認してみましょう。
●食品ロスをなくす
食品製造や小売、飲食業者においては、特にフードロスが深刻な問題となっています。過剰生産の抑制や仕入れの最適化、消費期限管理の徹底を行うことで、廃棄物の削減につながるでしょう。廃棄されるはずだった食品を有効活用するなら、フードバンクに寄付する方法がおすすめです。
●環境保全活動に積極的に参加する
CSR(企業の社会的責任)を果たすためにも、環境保全活動に力を入れることが重要だといえます。ビーチクリーンのように社員参加型のプログラムを設けるほか、製造工程の脱炭素化や環境に配慮した物流の推進、店舗設備の省エネ化など、組織全体で取り組める活動もあります。
●CO2の少ない製品・サービスを選ぶ
脱炭素型の製品開発やサプライチェーンの構築などもゼロカーボンの実現につながります。たとえば、商品容器を製造する際は、環境に配慮した素材を利用することで二酸化炭素排出量を減らせます。条件を満たして「エコマーク」などの環境ラベルを取得できれば、商品イメージの向上にもつながるでしょう。
●3R(リデュース、リユース、リサイクル)に取り組む
3R(リデュース、リユース、リサイクル)は、廃棄物削減の基本となる考え方です。資源の効率的な利用やリサイクル技術の導入などにより、企業活動における廃棄物を減らせるでしょう。オフィスではペーパーレス化を進める、ゴミの分別処理に努めるなど、まずはできることから始めるのが大切です。
●サステナブルなファッションを取り入れる
リサイクル可能な衣料品を開発する、エコ素材を採用した制服を導入するといった方法でも、ゼロカーボンに貢献できます。サステナブルな衣類を選ぶことで資源の無駄遣いを減らし、製造過程でのCO2排出量を抑えられるでしょう。
現在では、多くの事業者や自治体などがゼロカーボンの達成に向けた活動を行っています。以下では、ゼロカーボンに関する主なプロジェクトの事例をご紹介します。
●NTTコミュニケーションズ
NTTグループは、ゼロカーボンを推進するために「NTT Green Innovation toward 2040」という環境エネルギービジョンを掲げています。2030年度までの間に、温室効果ガス排出量を80%削減(2013年度比)することが目標です。また、2040年度にはグループにおけるゼロカーボンの達成をめざしています。
具体的な取り組みとして、NTTコミュニケーションズでは、リモートワーク環境を整備する「フレキシブル・ハイブリッドワーク」を推進し、業務の効率化とともにオフィスのCO2排出量削減に取り組んでいます。また、自社の排出量を可視化する「GHG排出可視化PoC」を活用し、温室効果ガスの管理を強化。さらに、データセンターの省エネ化や再生可能エネルギーの活用を進める「データセンターのグリーン化」にも力を入れています。
参考:「カーボンニュートラルとは?気候変動に対する国や企業の取り組み事例」
●長野県松本市
松本市は全国に先駆けてゼロカーボンの実現に取り組んできました。その背景には、長野県の気温上昇幅が全国平均を上回ることや、豊富な水資源を活かした再生可能エネルギーの活用が根づいていたことなどがあります。特に、2020年に政府が公表した「2050年ゼロカーボン宣言」を受け、松本市は積極的に挑戦する姿勢を強めました。
松本市の行ってきた施策には、太陽光パネルの設置推進や条例整備などがあります。乗鞍高原では、小水力発電や薪ストーブの活用を通じてエネルギーの地産地消を実現。環境省の「ゼロカーボンパーク」第1号として選定されました。また、環境・暮らし・観光の3つの要素をもとにした「のりくら高原ミライズ」構想を策定しています。
さらに、2022年には信州大学と連携し「松本平ゼロカーボン・コンソーシアム」を設立しました。多くの企業や自治体、研究機関が協力し、脱炭素社会の実現に向けた技術開発や事業創出を進めています。
参考:「目指すは“エネルギーの地産地消”垣根を越えた連携「松本平ゼロカーボン・コンソーシアム」が果たす役割とは」
●CHOOOSE
ノルウェー・オスロに本社を構えるCHOOOSEは、気候変動対策プロジェクトの情報を集約し、企業や個人向けにカーボン・オフセットの導入を支援するプラットフォームを提供しています。カーボン・オフセットとは、日常生活や経済活動の中でやむを得ずに排出される温室効果ガスを、別の場所での削減によって埋め合わせることです。
同社の共同創業者であるマーティン・クベイム氏は、温室効果ガス排出の規制強化やユーザーの関心の高まりにより、個人のカーボン・オフセット市場が成長すると予測。CHOOOSEのウェブサイトでは、オフセット活動を可視化するダッシュボードを提供し、参加者のモチベーション向上を図っています。また、イギリスのヒースロー空港にて、旅行プランに合わせてオフセットを提案し、利用者が任意で選択できる仕組みを導入しました。現在、日本の大手旅行代理店を含む企業とのパートナーシップを拡大し、グローバル展開を進めています。
参考:「シリコンバレーから見る、カーボンオフセットビジネス最前線 前編」
ゼロカーボンを実現するためには、個人や企業、自治体など、多くの人が協力し合って温室効果ガスの削減に取り組む必要があります。企業の場合、ゼロカーボンに向けてのアプローチを実行することで、イメージの向上や新規ビジネスの創出などにつなげられる点は魅力です。費用負担が大きくなる懸念もありますが、長期的な目線で見るとエネルギーコストの削減や新たなビジネスチャンスにつなげられると期待できます。ゼロカーボンの達成に向けて、再生エネルギーの活用や環境負荷の少ない技術の導入を進めていきましょう。
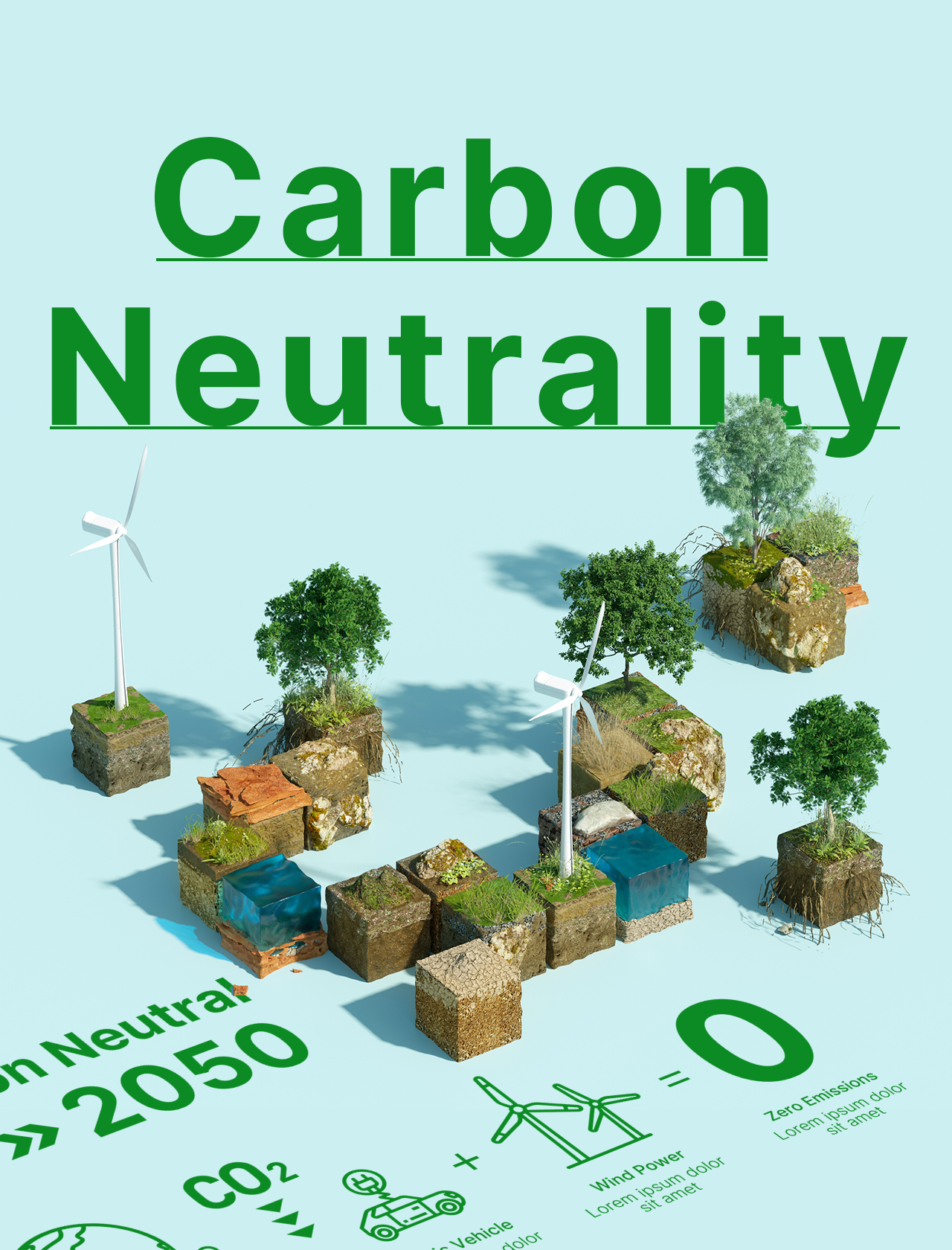
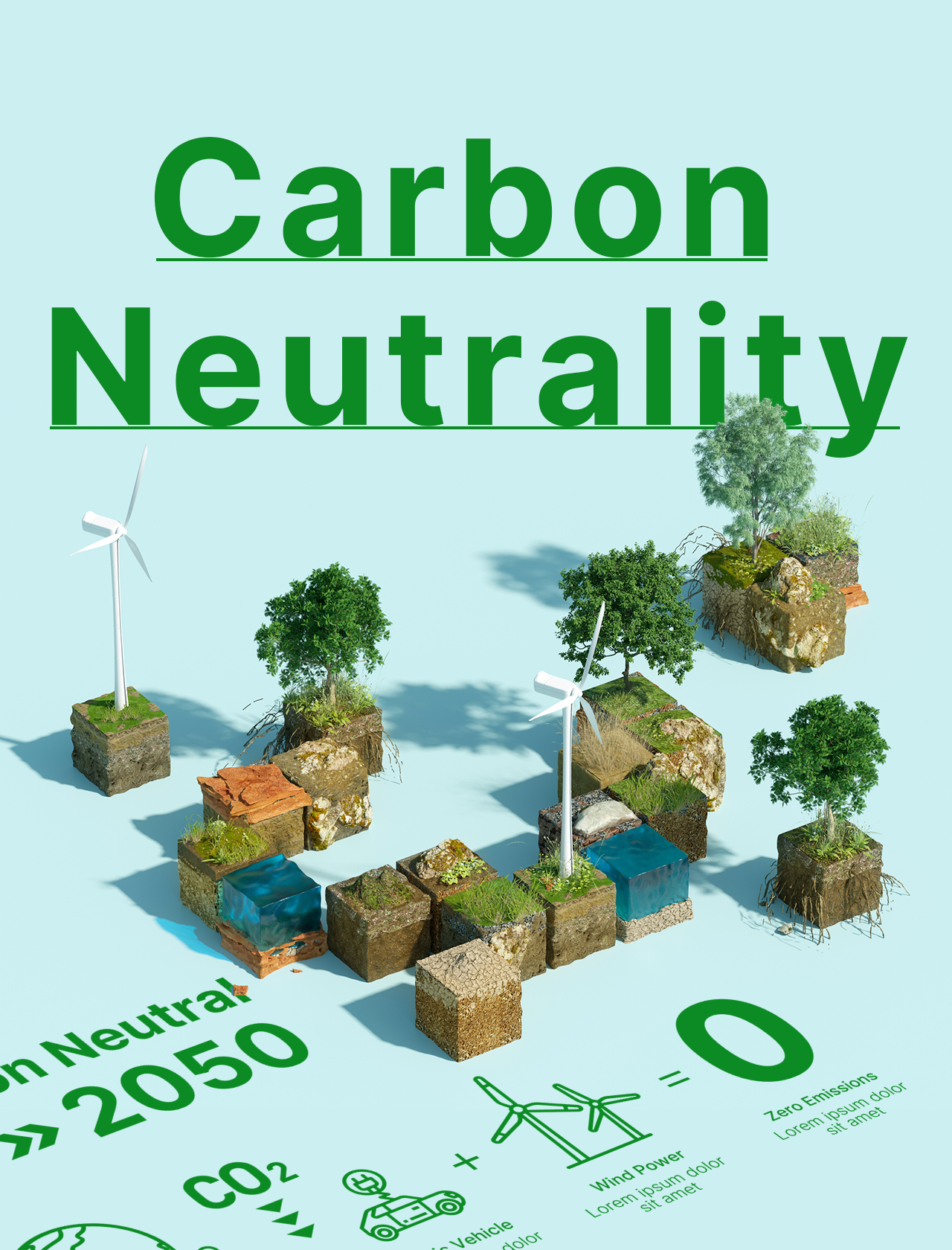
OPEN HUB
THEME
Carbon Neutrality
#脱炭素