
01
2025.07.18(Fri)
目次
——ここ数年で「GX(グリーン・トランスフォーメーション)」という言葉をよく聞くようになりました。改めて、「GX」が注目されている背景を教えてください。
夫馬賢治氏(以下、夫馬):「GX」という言葉は、実は日本で生まれたものです。海外では「グリーントランジション」と言うことが多いですね。GXが注目されている背景には地球規模での気候変動問題への関心の高まりがあり、「カーボンニュートラル」や「脱炭素」といったキーワードと連動しています。
大きな転換点となったのは、2015年のパリ協定ですが、日本では、2020年に当時の菅総理が「2050年カーボンニュートラル宣言」を出したことで、気候変動問題への関心が一気に高まりました。今年に入りこの動きから米国が離脱しましたが、世界で約140カ国が同様の政策を堅持しており、これは世界のGDPの約8割を占める国々が同じ方向を向いていることを意味します。
しかし、カーボンニュートラルの実現は並大抵のことではありません。経済活動の中で排出される温室効果ガスを劇的に減らすためには、既存の取り組みの延長線上では全く不可能で、大きなイノベーションを起こさなければなりません。
この「気候変動対策としてのイノベーション」というメガトレンドを、日本政府がより多くの企業にビジネスチャンスであることを伝えるために、日本ですでに浸透していた「DX」に倣って名付けたのが「GX」です。そして、そのイノベーションを具体的にどう加速させていくかという道筋を示す新たな指針として、政府は2024年12月に「GX2040ビジョン」を発表しました。
これは、2050年のカーボンニュートラル達成に向けた道筋の中で、特に2030年以降の取り組みを具体化し、イノベーションをさらに加速させる内容となっています。2030年までの目標が、現時点である程度見えている技術をベースに策定された手堅い目標であるのに対し、「GX2040ビジョン」ではまだ確立されていない新しい技術、つまりイノベーションがより強く求められるのです。
こうした中、多くの企業が危機感を持ち、新たなビジネスチャンスを探る動きを本格化させています。

——GXは、従来のCSRのような「やらなければならない」という守りのイメージとは異なるのですね。
夫馬:まさにその通りです。2020年の菅総理の宣言当初は、まだ大手企業の上層部で「カーボンニュートラルを目指すべきか、否か」といった議論がされている段階でした。
しかし、今は状況が大きく変わり、特にここ1年で爆発的にレベルが上がったと感じています。「やるかやらないか」ではなく、「どうやるか」という具体的な実行フェーズへと明らかにギアが一段上がりました。なぜかというと、「GX2040ビジョン」を実現するためには、2030年までに技術開発やイノベーションの目処をつけなければならないからです。米国のパリ協定脱退宣言以降も、日本企業からは技術開発、技術実証、企業間連携、官民共創等の発表が増え続けています。
こうした危機感の高まりとイノベーション重視の流れを受けて、企業内での取り組み体制も大きく変わってきています。GXはもはや企業の環境部門だけの仕事ではなく、事業開発部門や投資部門こそが主役となるべき分野になりました。DXがそうであったように、新しい事業や働き方、製品サービスが生まれるという「事業開発モード」で、多くのプレイヤーが動き出しているのです。
——GXへの意識が高まる中で、具体的にどのような産業構造の変化が予測され、企業はどのような対応を迫られるのでしょうか。
夫馬:GXが本格化することでエネルギー業界を筆頭に、製造、運輸、建設・不動産、食品・農林水産業に至るまで、あらゆる産業が根底から変わる可能性があります。
特に「GX2040ビジョン」では、革新技術を活かした新たなGX事業の創出や、素材から製品に至るサプライチェーン全体での脱炭素エネルギー利用・DXによる高度化がうたわれています。これはつまり、「ものづくりのプロセスそのものから見直す必要がある」ということ。たとえば、製品の素材が変わる、製造過程で使うエネルギーを転換する、建物の建て方や構造そのものが変わるといった大きな変化が起こるのです。
当然、1つの企業だけで対応できる範囲は限られているため、サプライチェーン全体での取り組みに加え、業界の垣根を越えた連携やオープンイノベーションが一層重要になります。まさに、NTTドコモビジネスが推進している「OPEN HUB」のような、共創を生み出すプラットフォームの価値が高まっていくでしょう。

——一方で、「非ものづくり企業」であるIT・デジタル企業にはどのような役割が期待されているのでしょうか。
夫馬:各業界の変革を横断的に支えるためには、テクノロジーの力が必要です。センサーで収集したさまざまなデータをAIで解析してエネルギー効率を最適化したり、サプライチェーン全体で排出量を管理したりと、GXの推進においてデータマネジメントは不可欠な要素となります。
こうした中でIT・デジタル企業には、「イネーブラー(実現を可能にする者)」としての役割が期待されています。具体的には2つの側面での貢献が求められます。
1つ目は、「業務効率化によるコスト削減」です。たとえば、工場やビルのエネルギー消費量をリアルタイムで可視化し、無駄なエネルギー消費を特定して削減する。あるいは、サプライチェーン全体でモノの動きやCO2排出量をデータで可視化し、ボトルネックとなっている部分を改善していく。こうしたきめ細かいデータマネジメントによって無駄を排除し、効率を上げていくことがGXの第一歩となります 。
【関連記事】競合とのデータ連携を実現。日用品業界GX革命にみる、データスペースの可能性
2つ目は、「イノベーションの加速」です。新しい技術や手法を開発する際、従来は膨大な時間とコストを要する試行錯誤が伴いました。しかし、AIによるシミュレーションやデジタルツインなどの技術を活用することで、開発のリードタイムを大幅に短縮したり、これまで不可能だった複雑な条件下での実験を仮想空間で行ったりすることが可能になります。これは、まさにGXが求める「非連続なイノベーション」を創出するうえで非常に強力な武器となります。
——あらゆる産業でデータ活用の重要性が高まる中、現在は業界ごとに個別のデータプラットフォームが存在している状態です。今後これらのプラットフォームはどのような方向に向かうべきでしょうか。
夫馬:GXの効果を最大化するためには、各業界、企業のデータプラットフォームがバラバラに存在するのではなく、相互に接続され、連携できることが重要になります。
プラットフォームの提供企業が必ずしも統一される必要はありませんが、共通のプロトコルを整備し、異なるシステム間でもデータのやり取りをスムーズに行えることが望ましいです。すでに自動車業界や電力業界ではプロトコルの標準化に向けた動きが出てきています。
重要なのは、データの世界では「早く始めて早く仕掛けた人たちがルールをつくり、市場の強いポジションを築く」という競争原理が働くこと。この領域でいかに主導権を握れるかが、GXにおける競争力を左右する重要な要素になるでしょう。

——国際競争という観点では、現時点で日本のGXはどのような状況にあるのでしょうか。日本企業が強みを発揮できる分野はあるのでしょうか。
夫馬:これは時間軸によって状況が大きく異なります。
2030年までの競争環境では、既存の技術をベースにした取り組みが中心となるため、正直なところ日本は出遅れている分野が多くあります。たとえば、再生可能エネルギーの設備については、日本企業のシェアは決して高くありません。
しかし、2030年以降はまったく異なる風景が広がります。ここからは「まだ見ぬ技術」の領域に入るため、世界中の企業が「ほぼ横一線」の状況にあるのです。現時点で特定の国や企業が圧倒的に有利ということはなく、これから5年間の取り組み方次第で勝負が決まる段階です。つまり、日本企業にも世界をリードする存在になるチャンスがあるのです。もちろん、横一線だからこそ、出遅れれば、新興国や途上国の企業からも突き上げを受けることにもなります。
重要なのは、現在の技術の延長線上で考えるのではなく、GXが求める「非連続なイノベーション」、つまり、産業構造を変えうるゲームチェンジが求められていると認識すること。GXへの対応次第で、既存の産業構造や競争優位性が大きく変わる可能性があるのです。 そのため「新しい産業革命」という用語が使われるようになりました。
こうした中で日本企業が持つ大きなアドバンテージの1つが、サプライチェーン全体での連携力です。
自動車業界や建設業界などでは、すでに大手企業だけでなく中小企業まで含めた緊密な連携体制が構築されており、GXのような複雑で大規模な変革を進めるうえで非常に大きな強みとなります。実際、中小企業まで巻き込んだGXへの取り組みの早さという点では、日本は世界的にも進んでいます。

——GXを日本経済の再興につなげていくために、企業やビジネスパーソンは今後どのように向き合っていくべきでしょうか。
夫馬:GXは2030年以降に本格的な成果が期待される非常に息の長い取り組みです。企業経営者には短期的な成果に一喜一憂することなく、長期的な視点でGXにコミットし、必要な投資を継続していく覚悟が求められます。
幸い、日本の経営層のGXに対するコミットメントは近年非常に高まってきています。このことは、日本企業の経営の時間軸が、今後2〜3年といった短期目線から、今後10〜20年といった長期目線にシフトしてきたこととも関係しています。課題はむしろ、長期思考になった取締役会や経営陣の熱意をいかに事業開発の現場にまで浸透させ、具体的なアクションにつなげていくかという点にあります。
あとは業界の垣根を越えた連携やオープンイノベーションを通じて共創パートナーを見つけ、大手企業だけでなく中小企業まで巻き込んだサプライチェーン全体での取り組みをどれだけ加速させていくかが勝負の分かれ目になっていくと思います。
——一方で、GXに取り組むうえでの注意点はありますか。
夫馬:よく陥りがちなのが、「コストアップを価格転嫁で解決しようとする発想」です。「新たに環境に優しい製品をつくりました。コストは上がりましたが、環境意識の高い消費者の方に買ってもらいたい」という提案では、まず成功しません。そのコストアップは消費者にとっての直接的な価値につながらないからです。
GXを本当に成功させたいなら、環境を重視した製品をつくったうえで、コストを下げるというコストイノベーションまでやりきる必要があります。そのためにも、省エネや生産効率を上げるためのデータマネジメントも重要な役割を果たします。
——「GXに出遅れた」と考えている企業も少なくないと思います。今から本格的に取り組む企業にとってのメッセージをお願いします。
夫馬:まず伝えたいのは、「今からでも決して遅くない」ということです。2030年以降の技術領域では「ほぼ横一線」の状況にあるため、これから本格的に取り組んでも十分にチャンスがあります。
GXは日本が直面する大きな課題であると同時に、新たな成長と国際競争力回復を実現するための千載一遇のチャンスでもあります。この変革の波を捉え、日本の強みを活かし、官民一体となったイノベーションを創出できるか。今まさに、日本企業、そして私たち一人ひとりの本気度が問われているのです。
■Sustainable Smart City Partner Program概要はこちら
https://digital-is-green.jp/program/forum04.html
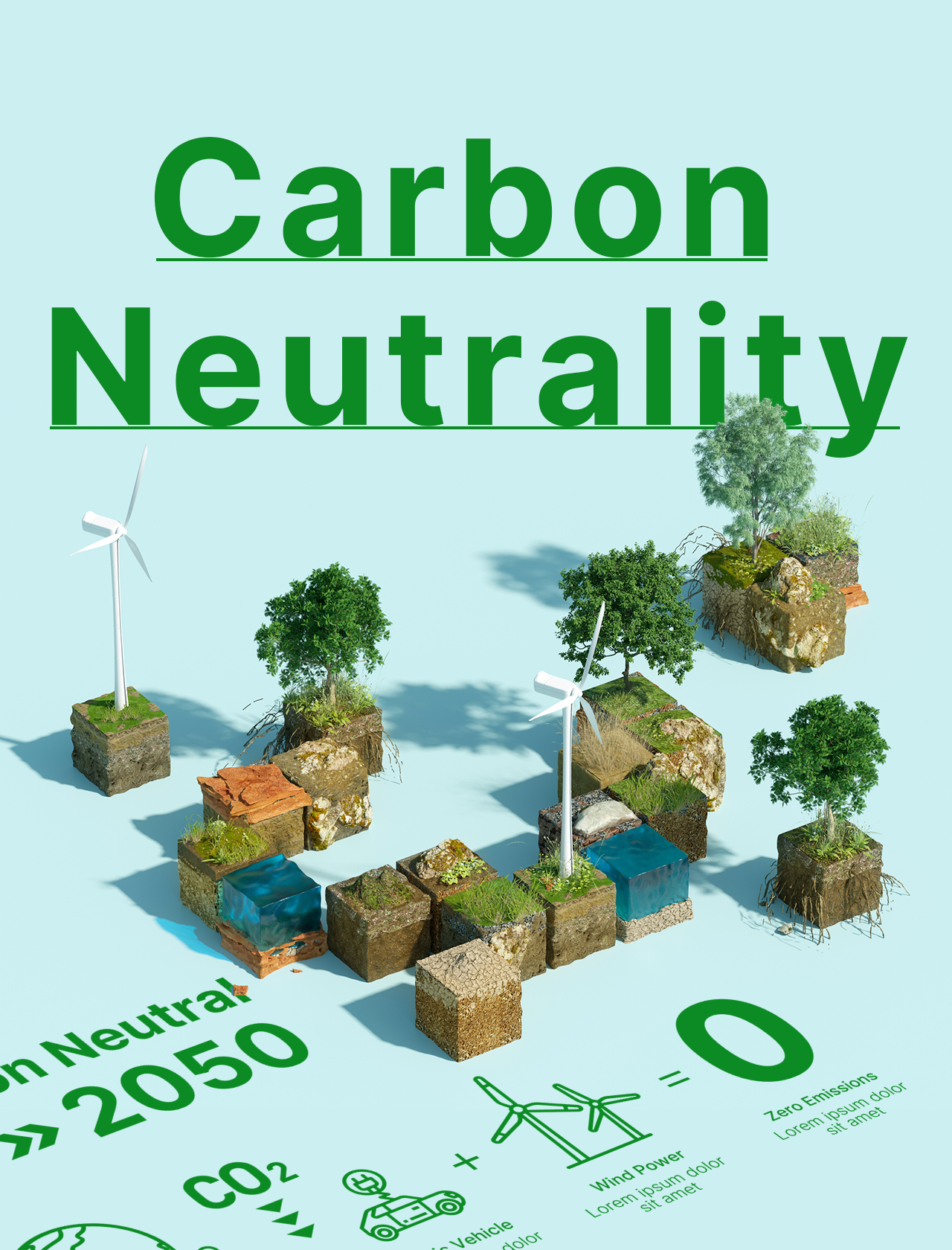
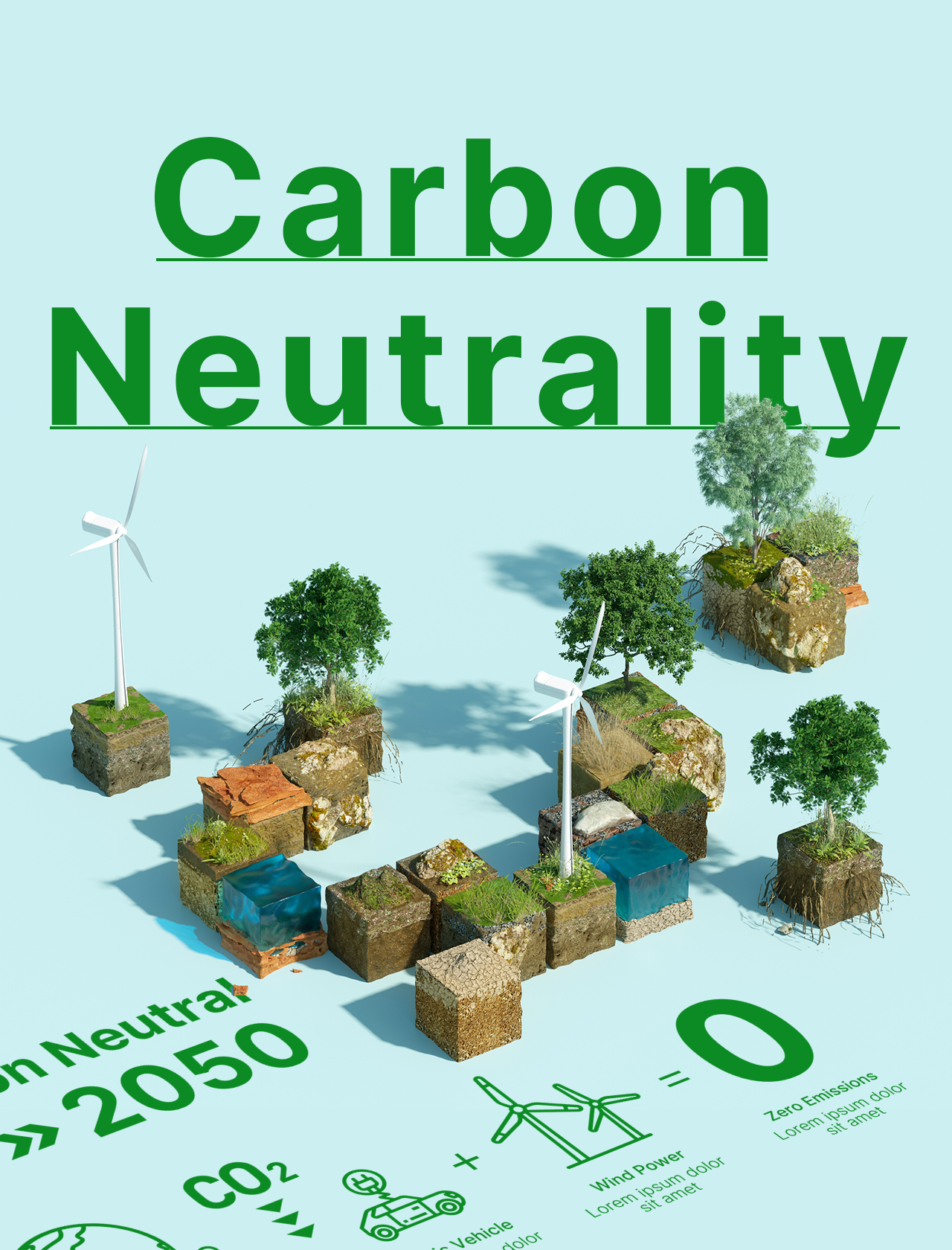
OPEN HUB
THEME
Carbon Neutrality
#脱炭素