
01
2025.07.09(Wed)
#62

この記事の要約
宿毛市は「デジタル田園都市国家構想交付金」を活用し、「SUKUMO マイナンバーカード市民カード化『宿毛ID』構想」を実施。マイナンバーカードの普及と行政サービスへの活用を目指している。
事業パートナーのNTT Comは、技術面や制度運用の知見を活かし、子どもから高齢者まで利用できる具体的な提案を行った。
主な取り組みは、保育園の登降園管理、公共施設の利用カード化、健康増進のためのポイント付与サービスなど。これらは市民の行動変容を促し、行政のエビデンスにもとづく政策立案を支援する。
産官学が密に連携し、コストや納期の制約の中でも市民目線を重視。今回の前編では、そんなプロジェクトの発足から構想段階を振り返った。
※この要約は生成AIをもとに作成しました。
目次
――まず、今回の「SUKUMO マイナンバーカード市民カード化『宿毛ID』構想」事業がスタートした経緯を教えてください。
上村秀生副市長(以下、上村氏):きっかけの1つは、地方創生DXの促進を目的とした「デジタル田園都市国家構想交付金」の、「マイナンバーカード利用横展開事例創出型(通称:TYPE-X)」という、補助率100%で3億円の支援が受けられる交付金が、令和4年度補正予算限りの時限措置で創設されたことでした。
――全国への横展開モデルとなるカード利用の先行事例を支援する、というものですね。
上村氏:そうです。そのため、「マイナンバーカードの申請率が7割以上」という申請要件があったのですが、当市ではこれまで数年にわたってカードの普及に努めてきたこともあり、2022年5月1日時点で全国市町村の6位となる71.7%の方が取得をされていました。
ただ一方で、「持ちはしたけれど、マイナンバーカードで一体何ができるの?」という声も根強く、市としてはぜひこの機会を活用して、「持つ」から「使う」へとフェーズを進め、マイナンバーカードによるDX推進を図りたいと考えました。

――マイナンバーカードを「使う」ことで、どのような課題が解決できると考えられたのでしょうか。
上村氏:課題はいろいろとありましたが、具体的に解決すべきものを見据えて……という前に、そもそもマイナンバーカードを「持ち歩く」習慣がありません。まずは外に持ち歩いてもらえるように、マイナンバーカードを有効利用できるのはどのようなシーンか、子どもから高齢者まで、それぞれ考えるところからスタートしました。
例えば、保育園では、園児の登降園をマイナンバーカードで管理するアプリケーションを構想しました。ほとんどの業務をアナログで行っていた職員、また電話で登降園状況を確認していた保護者の方たちにとってもDXの効果を実感しやすく、小さなお子さんたちがマイナンバーカードに慣れ親しむ機会もできます。
市民全体へのアプローチとしても、すでに導入していた「書かない窓口システム」の利用率の向上や、市の提供するさまざまな施設の利用拡大につながるためのアイデアなどから考えていきました。



――ちなみに、こうした先進的な取り組みに対しては、もともと積極的な風土があったのでしょうか。
上村氏:そうですね。特にマイナンバーカードについては、全国の市町村に先駆けて普及振興を行っていました。ただ私たちのモチベーションとしては、地方の人口減少の問題は都市部より深刻で、今すぐに手をつけないと「近い将来、組織が回らなくなってしまう」という危機感を職員が持っていたところが大きいと思います。
――今回、構想を進めるにあたって事業パートナーを務めたNTT Comが、当構想の事業者公募に応募した狙いを教えてください。
渡邉博美(以下、渡邉):私たちの会社は、マイナンバー制度がスタートした当初より、マイナンバーカードおよび周辺システムの開発に携わってきました。今回、市民カード化のために導入したカードアプリケーション(AP)搭載システムも、関連システムの開発や運営を担っている地方公共団体情報システム機構(略称:J-LIS)のもとで弊社が手掛けたものです。そのため弊社には、マイナンバーカードに関する技術的な知見を持つメンバーが多く在籍しています。

しかし、具体的な利活用や制度運用という話になると、先ほど上村副市長の発言にもありましたが、危機感を持って対応されている自治体の方たちのほうが詳しいことが以前はよくあって、問い合わせや相談を受けても、支店や支社の担当者がすぐには対応できないケースも見受けられました。
そこで、マイナンバーカードを活用した自治体DXの支援において実績のある本社と、現場で対応するメンバーが連携することで体制強化を図り、デジタル技術を活用した地方の活性化や、行政サービスの効率化に、会社としてより一層貢献したいと考えていました。
平岡美希:私は高知支店の法人営業として、宿毛市の皆さんと以前よりさまざまな打ち合わせを重ねる中で、市が抱える課題や悩みについて伺っていました。自分たちがパートナーになれるかどうかも大事でしたが、市民カード化構想が実現することで、これまであちこちに点在していた課題が1つの線でつながって、少しずつ解決の方向に向かっていくことに期待を募らせていました。

――宿毛市は今回、どのような理由でNTT Comをパートナーに選んだのでしょうか。
上村氏:支社であるドコモビジネスソリューションズの方たちとは以前からつながりがあり、今回のプロジェクトでも支援を賜った高知大学次世代地域創造センターの岡村健志 准教授を含め3者で協働した前例などもあって、私たちが抱える課題感などもよく理解してもらっていました。
そんな中で今回はさらに、デジタル田園都市国家構想交付金の詳しい要綱が公表されてから申請までのスケジュールがかなりタイトだったこともあり、私たちの期待や要求に沿った対応をとってもらえる事業者というのは、他には考えられませんでした。
谷本裕子氏(以下、谷本氏):市としてもっとも実現したかったのが、「小さな子どもから高齢者まで、マイナンバーカードを利用できるシーンを提供する」というもので、その構想については、他の事業者の方たちにもお話ししました。ですが、「素晴らしいと思うけれど、うちでは難しい」と断られてしまうことがほとんどで、NTT Comさんでなければ、今回のような成果をあげることは難しかっただろうと感じています。

――なぜ、他の事業者では難しかったのでしょう。
渡邉:公的個人認証を用いてポータルサイトにログインしたり、本人確認に使ったり、といったことを得意とされている事業者は、弊社の他にもありますし、「書かない窓口」やスマートロックといったソリューションを提供できる事業者もたくさん存在します。ただ、市民カード化構想となると、何となく利用するシーンはイメージできたとしても、それを実現するための具体的な方法を提案できる事業者は限られていたのだと思います。
――具体的な方法とはどのようなものを指しているのでしょうか。
渡邉:技術仕様を正しく理解しているのはもちろんのこと、今回のケースであれば、J-LISに申し込みを行い、ICチップ内の空き領域にアプリケーションを搭載して、というような各手順においてポイントを押さえ、正しいプロセスを踏んでいかなくてはいけません。このあたりをすべて理解している事業者が、当時はほとんどいないのが実情でした。
それに加え、法制度を理解することもかなり大変です。マイナンバーカードは使用範囲が厳格に定められているので、「子どもから高齢者まで、すべての市民が恩恵を受けられる環境の整備を目指す」という宿毛市の方針や計画を、法的な観点も踏まえて迅速に整理できたのも、これまでの経験や積み上げてきた実績があってこそ、と自負しています。その上で、ドコモビジネスソリューションズ四国支社が宿毛市さんと良好な関係を構築できていたこともあって、今回こうしてパートナーに選定してもらえたのだと思います。
――それでは改めて、パートナー選定後の構想協議について話を伺います。今回の市民カード化構想の主だった取り組みについて、当初の狙いなどをお聞かせください。
中上大輔氏(以下、中上氏):市としての一番の狙いは、マイナンバーカードの利活用の拡大です。市民カード化を推進することで、まずは人々の、マイナンバーカードを持ち歩くことへの“忌避感”を取り除きたいと考えました。
上村副市長の説明にもあったように、保育園の登降園システムなどはまさにそうした狙いに最適で、登降園の際、園児本人がマイナンバーカードをリーダーにかざすことで、登降園の状況が保護者のスマートフォンでリアルタイムに確認できる仕組みの導入を検討しました。


――保護者には安心が、保育園の職員には事務作業の効率化が、そして子どもたちにはマイナンバーカードに毎日触れる習慣や経験がもたらされるわけですね。
中上氏:その通りです。同じく利活用の拡大というところでは、マイナンバーカード1枚で、「すくもいきいきサロン」など複数の公共施設の利用者カードを代替できるサービスも提供したいと考えました。
――行動変容をただ促すだけでなく、その経過を確認できる仕組みとして、データ活用プラットフォームサービスも構想されたと伺っています。
谷本氏:施設やイベントの利用履歴や参加履歴を蓄積し、そのデータを、市民も行政も確認したり活用したりできる仕組みをつくりたいと考えました。
当市でも昨年、高齢化率が40%を超え、健康寿命の延伸に向けた施策などに力を入れていますが、これまでは、分析データをもとに施策を立案したいと思ってもデータが存在しなかったり、あってもバラバラに存在していて統合するのが難しかったりと、結果的に経験や勘に頼らざるを得ないことが多くありました。
しかもそれだと、やり始めた施策の効果検証も困難で、成否の判断がつかず、やめられなくなってしまいます。このもどかしさを解消するためにも、マイナンバーカードを活用し、EBPM(エビデンス・ベースト・ポリシー・メイキング:証拠にもとづく政策立案)を実現することは、私たちたっての願いでした。
――リソースを割くべき効果的な施策を見極められることも、DXの効果ですね。デジタル化のメリットでいうと、宿毛IDの特徴のひとつである「ポイント付与サービス」には、どのような構想プロセスがあったのでしょうか。
有田聡氏:マイナンバーカードへのポイント付与は、健康増進のための行動など、市民に継続的な行動変容を促進するための施策として、導入検討を始めました。例えば、すくもいきいきサロンであれば、利用するたびにポイントを付与することで習慣化を促し、高齢者の健康維持につなげる、といったイメージですね。

私はあまりデジタルに強い人間ではないのですが、市民の中にもアナログな方はたくさんいます。その人たちがマイナンバーカードを使いたくなるにはどうすればいいか、という目線を常に意識しながら、「地域通貨をポイントとして付与するのがいいのではないか」「特に足を運んでもらいたい施設やイベントでは、ポイントの付与率を高くしたらいいのではないか」とアイデアを出し続けました。
上村氏:当初は開発期間を考慮して、今回は開発工程が複雑な地域通貨への変換は見送り、景品と交換するという案で申請を行ったのですが、採択後いざシステム開発をするとなった時に、「やっぱりそれだけでは弱いよね」という話も出てきました。私自身もそうですが、ポイントにあまり興味がない人もいるはずで、特に高齢の男性が、ポイントや景品を目当てに行動してくれるかどうかは疑問でした。
そこで新たに出てきたのが、未来投資型寄付というアイデア。参加型クラウドファンディングのように、たまったポイントを寄付することで、例えば、公園に遊具をつくるなどの政策を応援できれば、子どもたちの喜ぶ顔が見たくて行動してくれる人がいるのではないか、と考えました。

このように皆が当事者意識を持ち、高知大学の岡村准教授やNTT Comさんなど外部の人たちも巻き込んでギリギリまで議論を重ねたことで、多様な視点からアイデアが生まれたのも今回のプロジェクトの特徴だったと感じています。
岡西強:今年度必達の交付金事業ということもあり、コストと納期の部分でせめぎ合うところはありましたが、皆さんの、良いものをつくりたい、妥協せずに使えるシステムを構築したい、という思いは常に感じていました。

私たちとしても、具体的なサービスの要件定義を確定させる中で、追加要望の実現可否、また実現できた場合どういった実装イメージになるのかについて、「ただ要望通りに対応する」ということのないように努めました。市民の方たちが触ってみたいと思えるデザインはどんなものか、もっと利便性を向上させることができないか、など、主体性を持ってサービス内容を固めていったのです。
ただ、理想とコスト・納期がせめぎ合いながらも構想が詰められていく一方で、実際の開発に関しては、他にも越えなければならない技術的な問題があります。まず明らかになったのは、さまざまなアプリケーションが絡み合う本件は「標準タイプのカードAP」では対応が難しく、利便性とセキュリティを両立させるための障壁がかなり高い、ということです。当初は実現困難かと思われましたが、ある方法で解決への糸口を見つけることができました。
――産官学の密な連携から、マイナンバーカードの市民カード化構想がダイナミックに立ち上がる模様をお届けした当記事。前編に引き続き、後編では、構想の実現に向けて乗り越えなければならなかった技術面/運営面の壁や、その解決にあたってメンバーが工夫したこと、市民カードがもたらした市政の新しい展望など、宿毛IDが完成し市民に浸透していく過程を振り返っていきます。
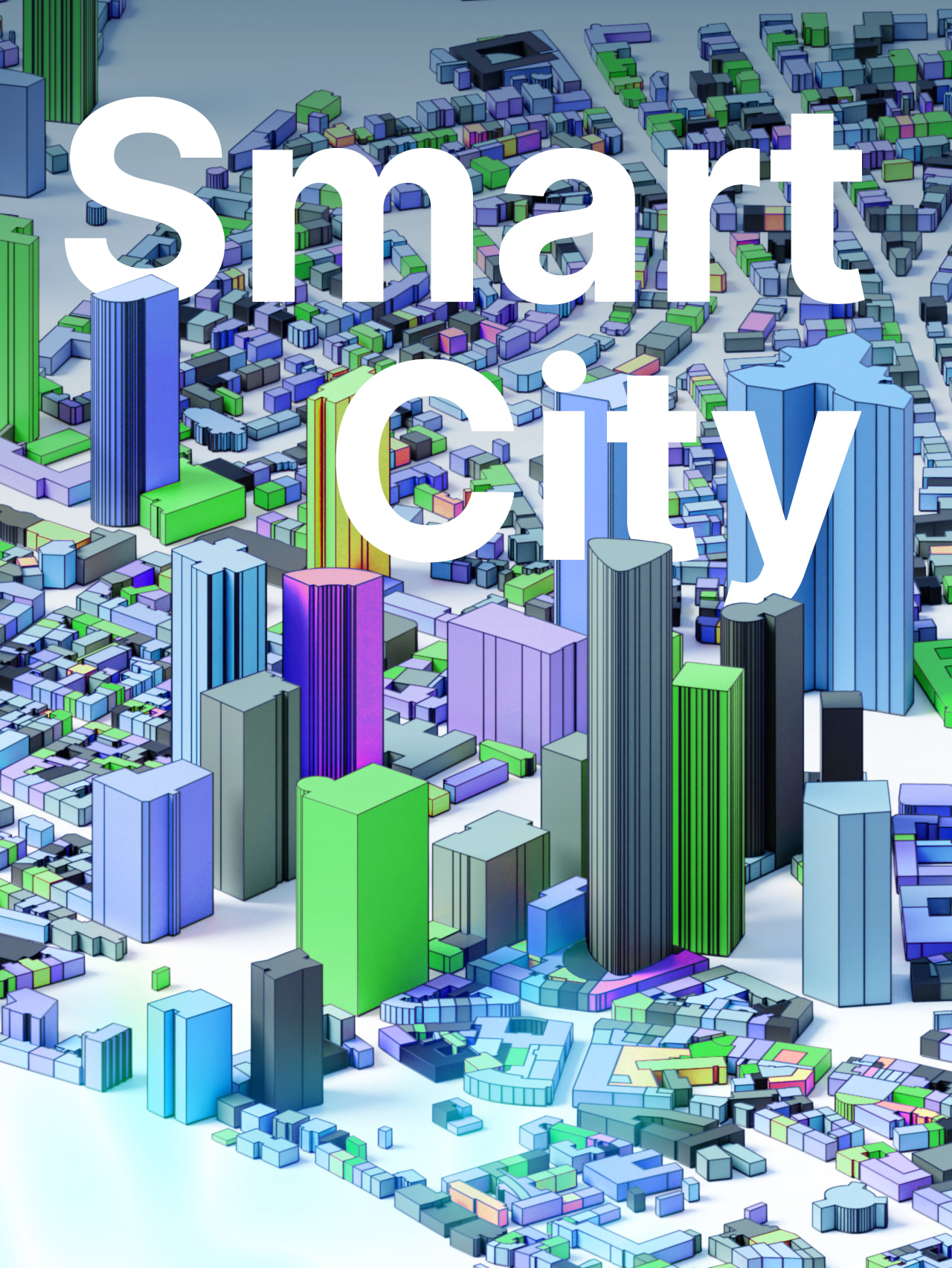
OPEN HUB
Theme
Smart City
#スマートシティ