
01
2025.07.18(Fri)
Carbon Neutrality
2025.08.20(Wed)
冷えるフィルム「SPACECOOL」とデジタル技術が描くSmart Surfaceの未来
目次
——太陽光が当たってもゼロエネルギーで冷やすことができるというSPACECOOLですが、どういった経緯で開発をされたのでしょうか?
末光真大代表取締役CEO(以下、末光氏):私自身は2012年に大阪ガス研究所に入社し、ずっと研究畑を歩んできました。その頃は、燃焼やエンジンの研究などが中心でしたが、高い温度で放出される光をコントロールできないかと、2013年に京都大学と共同で、光を自在に操るフォトニクス技術の研究開発を始めました。
当初はモノを温めるという観点で研究を進めていましたが、2017年に、モノを「冷やす」方向に転換して、放射冷却技術の研究にも着手。30以上の特許技術を取得した後、SPACECOOL株式会社を立ち上げました。
弊社のプロダクトは、この1枚のフィルムです。特長は、太陽光が当たってもゼロエネルギーで冷えるという点です。

——どのような仕組みで冷やしているのでしょうか?
末光氏:端的に言うと、太陽光を反射させるとともに、熱を効率的に宇宙空間に放出する仕組みで冷やしています。アウタースペース(宇宙空間)に熱を捨てるということで『SPACECOOL』と名づけました。身近にあるスペース(空間)を冷やすという意味でも分かりやすい名前になっていると思います。
中山千夏子(以下、中山):モノを温める研究をされていたとのことでしたが、冷やすという方向に応用できるものなのですか?
末光氏:「光」に注目しているからこそできた転換でした。光の領域で扱う温度域と波長を変えることで、温めたり、冷やしたりをコントロールできるのです。つまり、「温める」も「冷やす」も同じ技術シーズから生まれたと言えます。
「放射冷却」という言葉を天気予報などで聞いたことがありますよね。秋や冬に、地表面の温まった熱が赤外線として宇宙空間に放出されて地面が冷え、気温がぐっと下がる現象。SPACECOOLは、まさにこの仕組みを活用しています。
放射冷却は、雲がなくて星がきれいに見えるような夜に起こりますよね。熱を宇宙空間に放出する時に絶対に必要なのが、透明性の高い大気です。実は、赤外線には大気を通過しやすい「大気の窓」と呼ばれる波長帯があります。8〜13マイクロメーターの遠赤外線なのですが、この波長の光を選択的に放出できるようにすると、熱を効率的に宇宙空間に捨てることができます。同時に、太陽光を反射させて入熱を防ぐ機能も備えています。

鈴木与一(以下、鈴木):選択的に光を逃していく仕組みとは、どういう技術なのですか?
末光氏:分子振動を使っています。熱が加わると分子は振動するので、その振動エネルギーを光エネルギーに変えるのです。
熱は必ず、熱いところから冷たいところへと移動します。身の回りで最も冷たい場所と言えば「空」です。今日(取材は6月26日)の雲は、私の今までの経験からすると2℃から3℃くらい。よく晴れた夏の空であれば−5℃〜−10℃。秋や冬なら−60℃以下です。さらに、その上の宇宙空間ともなれば、常に−270℃という絶対零度に限りなく近い温度となります。じゃあ、そこに熱を捨てたらいいのではないかと考え、地表との温度差で熱を宇宙空間に放出させるように素材を開発しました。
——『SPACECOOL』はどういったところで活用されているのでしょうか?
末光氏:創業当初から注目していただいたのは屋外機器分野です。分電盤、携帯基地局の観測装置、太陽光パネルのパワーコンディショナーなどですね。これらの機器は発熱するのですが、雨風から保護するためにケースに格納されています。つまり、“夏にウインドブレーカーを着ている”ような状態と言えます。こうした装置は温度が上昇すると機器トラブルの原因となるため、温度上昇を防ぐSPACECOOLとの相性が非常に良いのです。
また最近、急速に広がっているのが建築分野です。防水シートやルーフシェードとして、すでに年間1万㎡を超える実績があります。東京都交通局におけるバス営業所では、防水シートとして600㎡に導入し、施設の光熱費が7.8%下がりました。世田谷区の小学校、ネッツトヨタ埼玉の店舗などにも導入いただいています。タイの自動車工場では、ルーフシェードとして利用してもらっています。
もう一つ、最近増えているのが室外機への導入です。特にデータセンターは省エネ性能を追求されていますので、熱に敏感です。東南アジアでも相当数が導入されています。
中山:『SPACECOOL』を導入した後の効果計測は、どのようにされているのですか?
末光氏:温度や消費電力を測定し、効果を算出しています。立命館大学の建築学の先生と連携した検証やシミュレーション測定も進めています。
——NTTドコモビジネスは、GHG排出量の見える化ツール、カーボンクレジット取引プラットフォームなど、カーボンニュートラルを支援するソリューションを提供しています。ぜひご紹介いただけますか?
鈴木:私と中山はスマートインダストリー推進室に所属しており、「カーボンニュートラル」「サーキュラーエコノミー」「ネイチャーポジティブ」といった課題に対応するソリューションの提供を通じて、さまざまな分野の企業をご支援しています。
例えば、GHG排出量可視化サービス『CO2MOS®(コスモス)』は、Scope1、2、3のGHG排出量分析、削減シミュレーション、サプライヤーとの連携、クレジット・証書管理、タスク管理などを実現します。
『SPACECOOL』の省エネ効果によってGHG排出量削減にどれくらいつながったかを『CO2MOS®』を使って可視化できれば、建設業界やネットエネルギーゼロを標榜するビルの管理・運営のニーズに対応していけそうですね。
ほかにも、住友林業と協業し、森林由来のカーボン・クレジットの創出・審査・流通を包括的に支援するプラットフォーム『森かち』を展開しています。また、実証段階ですが、サーキュラーエコノミーを支援するソリューションや、生物多様性を見える化するソリューションの技術開発にも取り組んでいます。

末光氏:GHG排出量算定可視化ツールとの連携は、今後必要になっていくと考えています。私たちは『SPACECOOL』を販売する際に、防水シートメーカーなどと連携しているのですが、そうしたパートナー企業も交えて、『SPACECOOL』の施工とその後のGHG排出削減効果の見える化や分析をセットにして販売できたら、バリューチェーンとしての広がりが生まれそうです。
また、カーボンクレジットも、省エネはポイントが付きづらいですが、取り組む効果を経済メリットとして感じてもらえますので、今後取り組んでいきたい領域です。
鈴木:まさにOPENHUBがめざしている「共創」の考え方ですね。『SPACECOOL』の用途は、屋外装置から建築物まで広がっているようですが、パートナー企業との連携で工夫されていることはありますか?
末光氏:SPACECOOLのような放射冷却素材を販売する競合の多くは「塗料」として商品化しているのですが、塗料だと施工が難しい場合も多いのです。そこで、私たちは既存のアセットに施工しやすい「フィルム」として開発をしました。施工しやすければ、パートナー企業にも積極的に販売してもらえると考えたのです。現在は、パートナー企業での施工技術の開発も進んでおり、より多くのお客さまに導入してもらえるようになりました。
もう一つのポイントは、ロンシール工業や日本ワイドクロスといった業界大手企業とパートナーシップを組み、そういった企業の商品として販売していることです。例えば、防水シートメーカーであるロンシール工業とは、同社が持つ全国200社もの施工体制を通じて、保証と施工もセットにした販売を行っています。
建築資材として販売してもらうには、さまざまな試験をクリアする必要があり手間と時間がかかります。ただ、一度通ってしまえば共創のメリットは非常に大きいと考えています。
鈴木:これから狙っていきたい業界や領域はありますか?
末光氏:グローバルですね。東南アジアでしっかりと広めていきたいですし、中東(サウジアラビア)でも現地企業との連携を進め、普及をめざしています。またヨーロッパは、カーボンニュートラルに対する意識が日本よりも格段に高いので、現地の商流をうまく使って広めていくことを考えています。
ただ、グローバルで販売していく上での最大のハードルは、効果測定や取得データの分析です。一件一件現地に見に行くことはなかなか難しいですし、アフターフォローが必要になるような複雑なものを導入するわけにもいきません。グローバルで利用できるIoTなどを使って、遠隔でデータを確認・分析できるようなシステムが必要だと感じています。
中山:お客さまと話していると、弊社のソリューションに対して、「可視化するのはいいけれど、お客さま要望/背景を踏まえて最適な削減策を提示してほしい」や「GHG排出量を削減した先にどう企業価値の向上につなげていくべきか」まで具体的な価値を提示しないと、納得してもらうのが難しいと感じることがあります。末光社長は、どのようにお客さまに価値を感じていただけたのでしょうか。

末光氏:『SPACECOOL』は、実際に触ってみると冷たいというのが分かります。直接触れて効果を体感してもらうことは重要だったと思います。
また、大阪ガス発のスタートアップ企業だったことも、初期に信頼を得られた一つの要因だと思います。特に日本では、「のれん」や「看板」が意識されやすい。何の後ろ楯もないスタートアップが、いきなり放射冷却素材を作りましたと言っても、信じてもらいにくいでしょう。その点、大阪ガスの看板があったことは信頼を得るという面で非常に助かりました。
カーブアウト型スタートアップは、経済産業省が発表しているガイダンスでも推奨されている形態です。対外的には大阪ガス発ということで信頼していただき、スタートアップとしてのスピード感も活かせる、いいとこ取りができる方法だと思います。
——今日は、共創の重要性や、グローバルでのビジネスチャンスのお話など、NTTドコモビジネスの取り組みと重なる部分も多くあったと思います。NTTドコモビジネスに期待したいことがありましたら、ぜひお聞かせください。
末光氏:サービスを広げていくためには、そのサービスを売ることに対する「意味づけ」が大事だと思います。意味づけをすると、共創するパートナーの商材のバリューアップにもつながり、より積極的に売ろうとするインセンティブも働いてサービスがさらに広がっていきます。
NTTドコモビジネスさまは幅広い分野のお客さまとのつながりをお持ちだと思いますし、OPEN HUBのような共創ビジネスの推進にも取り組まれています。さまざまな物の表面に着目しながら『SPACECOOL』を導入する意味づけを一緒に考えていけると、すごくいい連携ができるのではないかと思います。
鈴木:そうですね。私たちの強みは、精緻にデータを取って現状を見える化し、そのデータを利活用することです。GHG排出量を削減する技術を直接提供することはできませんが、データの利活用による価値を提供できます。GHG排出量削減技術を持った企業さまと強みをかけ合わせて連携できると、サービスを導入するメリットをお客さまに理解してもらいやすくなります。モノ×ITはすごく相性が良いですね。
中山:『SPACECOOL』の価値は、私が携わっている可視化ソリューションのその先を見据えられるという点で大きな意味づけになるものだと感じました。「表面」に着目した貴社と弊社のGXソリューションで、カーボンニュートラルに向けた面白いビジネスができるんじゃないかなと、今後がより一層楽しみになりました。NTTが有する約35万人の人材という強みや、企業としての信頼性・ブランド力は、スタートアップ企業の皆さまのビジネスを力強く後押しできるものと考えています。私たちスマートワールドビジネス部は共に新たな価値を創出していけるスタートアップ企業の皆さまとの協業を、心よりお待ちしています。

——光の研究から『SPACECOOL』が生まれたように、NTTも光をコントロールする技術などを活用して、高速大容量通信などを実現する「IOWN」を誕生させています。光って可能性が広がっていますね。
末光氏:私が所属している学会に、NTTの方もよくいらっしゃっています。光はさまざまな分野で活用されている技術です。光をコントロールする技術を応用し「世界に木陰の涼しさを」という私たちがめざすビジョンを実現させていきたいと思います。
■Sustainable Smart City Partner Program概要はこちら
https://digital-is-green.jp/program/forum04.html
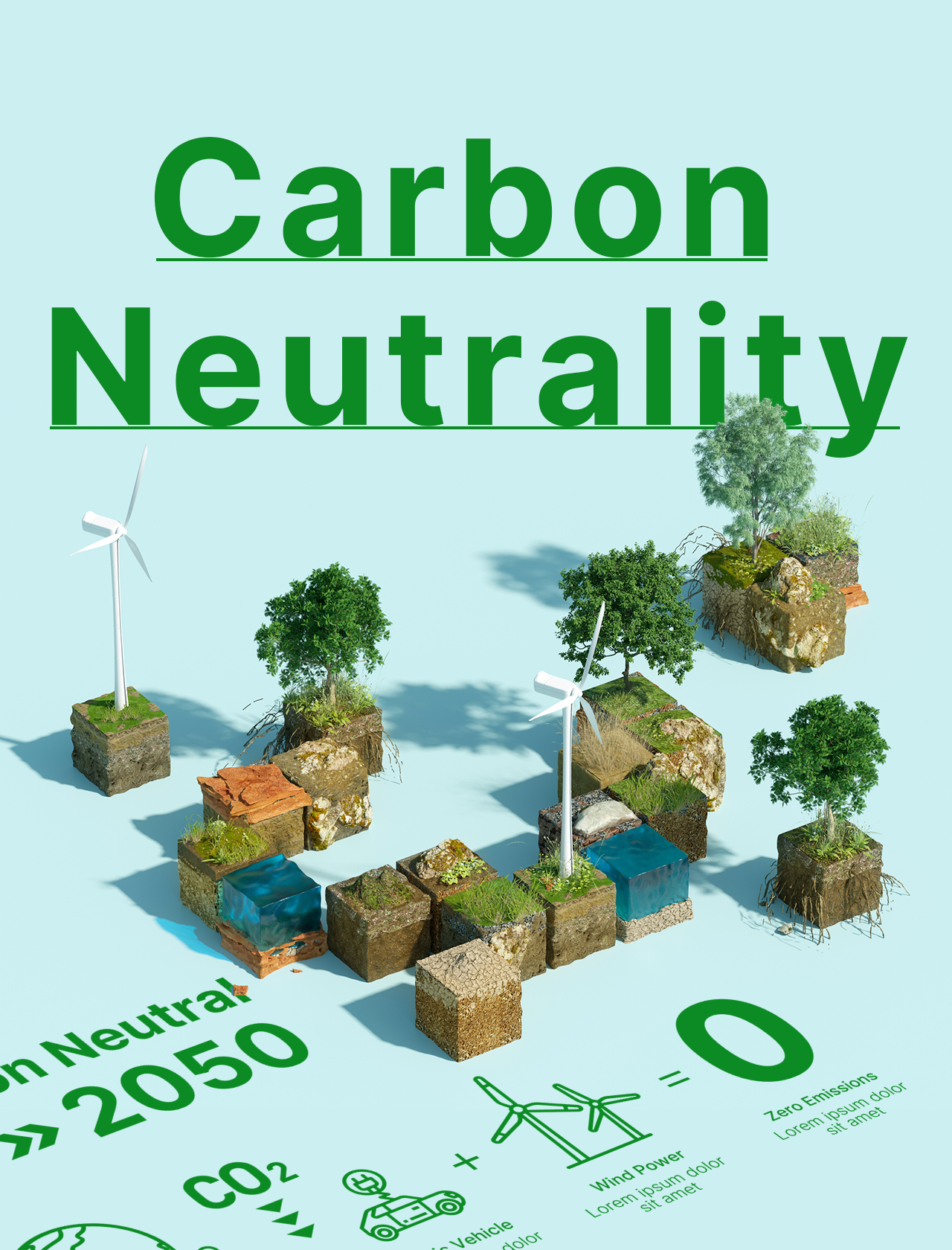
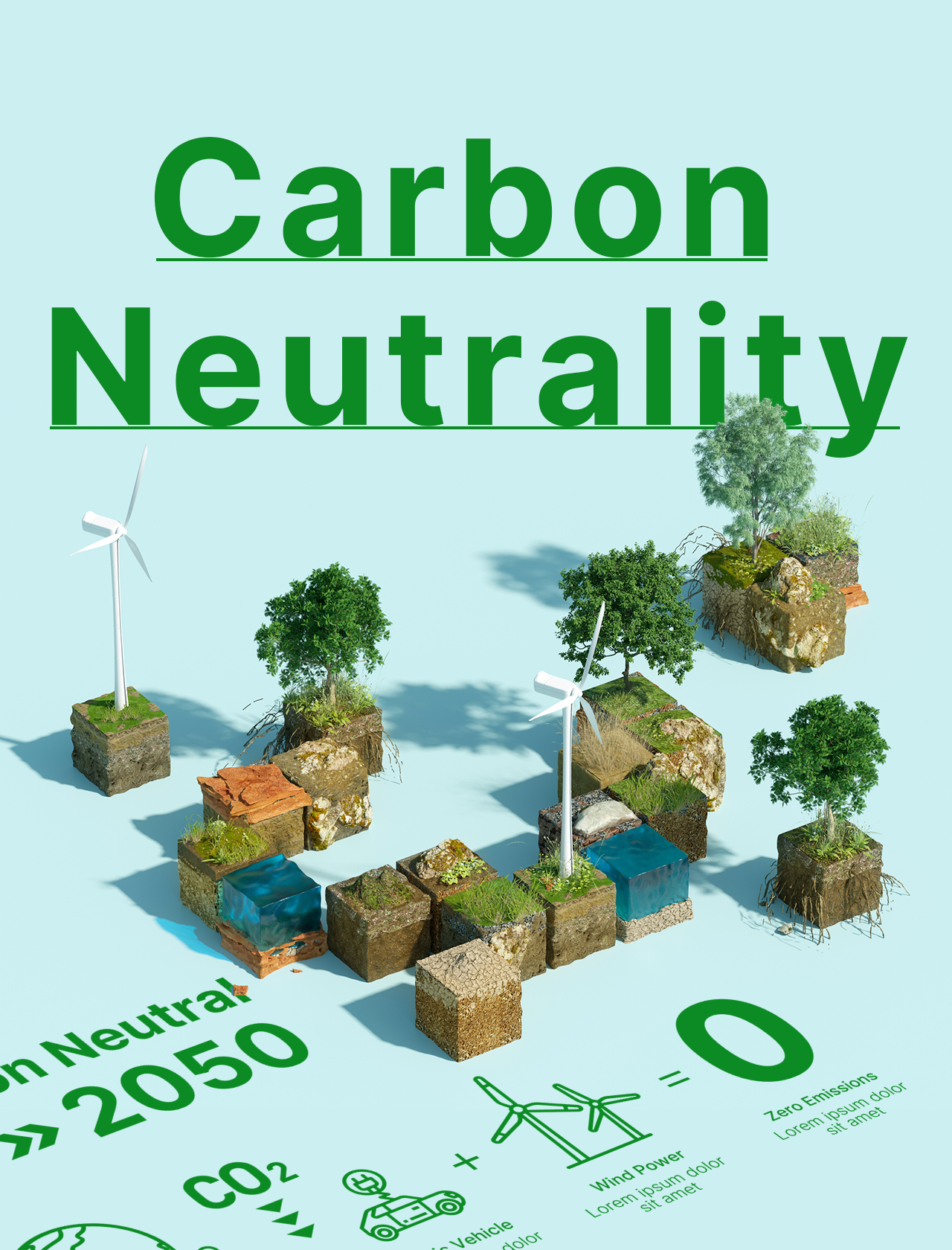
OPEN HUB
THEME
Carbon Neutrality
#脱炭素