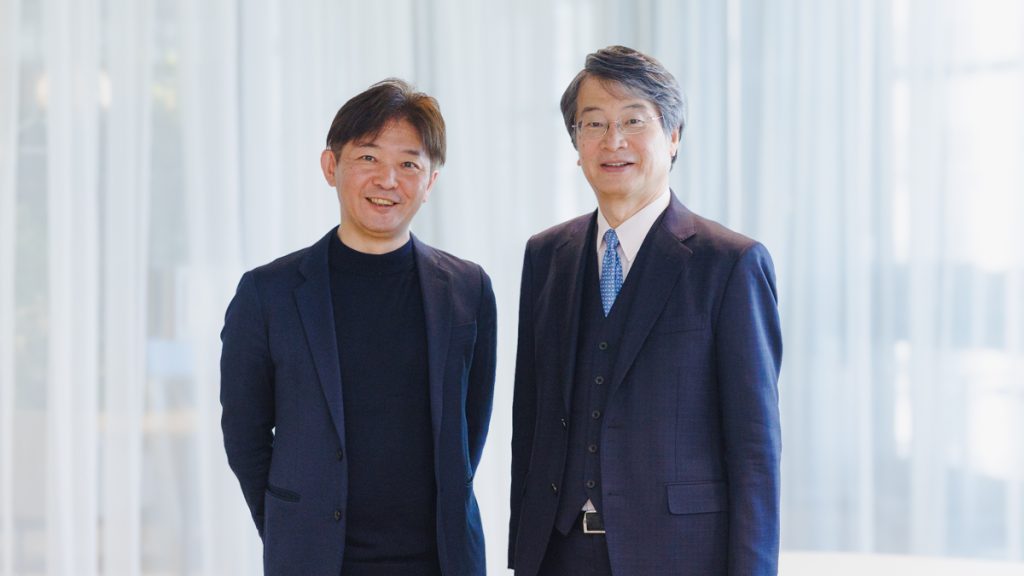
01
2025.05.16(Fri)
Co-Create the Future
2025.07.11(Fri)
この記事の要約
シンフォニーマーケティング代表の庭山一郎氏とNTTドコモビジネスの戸松正剛が、BtoBマーケティングの最新動向について対談しました。
世界では、重要顧客からの売上最大化を目指すABM(アカウント・ベースド・マーケティング)が主流になっています。
日本は世界から15年ほど遅れているものの、既存顧客との長期的な関係構築や名刺交換文化など、ABMで成功できる条件が備わっています。NTTドコモビジネスはABMの発展型であるABXに全社的に取り組み、多様な部門が連携して顧客にアプローチしています。
生成AI時代においては、AIが代替できない戦略立案やFace to Faceコミュニケーションの価値が高まりOne to Communityという新たなマーケティング手法も期待されています。
※この要約は生成AIをもとに作成しました。
目次
――BtoBマーケティングの戦略として、特定のターゲット顧客からの売上最大化を目指すABMが世界の潮流となる一方、日本ではまだ注目が高まりつつある状況にとどまっています。そもそもなぜABMが普及したのか、背景についてお聞かせください。
庭山一郎氏(以下、庭山氏):ABMには2つのルーツがあります。1つは、1990年代に提唱されたシェアの概念を市場占有率から個人の生涯価値での占有率に転換した考え方、LTV(Life Time Value)です。物の購入に例えるなら、ある地域での売上ではなく、一人の人間が一生の間に購入する車のシェアを競うという発想です。地域で見るならばマスメディアを使った大々的なプロモーションでシェア拡大を狙いますが、生涯占有率で考えるならば、「家族構成」「所得」などターゲット顧客の情報をもとにしたダイレクトコミュニケーションが必要です。このLTVをBtoBマーケティングに応用したのがABMと言われています。

――BtoC領域だけでなくBtoBでもLTVが重視されるようになったのですね。ABMのもう1つのルーツは何でしょうか。
庭山氏:ABMは、マーケターが生き残りをかけて試行錯誤したどり着いた新たなマーケティング戦略とも言えます。米国では、MQL(Marketing Qualified Lead)*1からSAL(Sales Accepted Lead)*2へ進める割合(アクセプト率)、つまりマーケティング部門が渡したリード(見込み顧客)を営業部門が受け入れてくれる割合によってマーケターの評価が左右されます。
ではどうすれば評価されるのか、マーケターが頭を悩ませた末に始めたのが、営業が優先的に追いたいと思う顧客に的を絞ってリードを育成するという手法であり、これによりアクセプト率が跳ね上がったのです。
営業が追いやすいのは、すでに関係構築ができている既存顧客です。新たに新規を開拓するよりも、既存顧客の案件化を目指したほうが効率が良いというわけです。米国では2010年代からこうした考え方をもとに成功事例が生まれ始め、自社にとって最も重要なターゲット顧客を絞り込むABMというマーケティング戦略が主流となっています。
*1 マーケティングによって創出されたリード(見込み客)のうち、購入意欲の高いと判断されたリード
*2 MQLの中で成約につながる可能性が高いと営業に判断されたリード
――庭山さんご自身はABMをどう定義付けていますか。
庭山氏:「特定の重要顧客と最良の関係を築くことで、強い顧客基盤を構築し、収益を最大化することを目的にした全社的なマーケティング戦略」をABMと定義しています。
2010年ごろにABMという言葉を初めて聞いた時は「また新しいバズワードが出てきた」という程度の受け止めでしたが、それからの数年間で耳にする回数が増え、圧倒的な成果を出したケーススタディをいくつも目にしたことで考えが変わり、以来ABMの研究を続けています。
――戸松さんはNTTドコモビジネスにおいてBtoBマーケティングを推進していますが、ABMとの出合いについてお聞かせください。
戸松正剛(以下、戸松):2008年ごろまで米国に留学しマーケティングとファイナンスを専攻していたのですが、当時はまだ聞いたことがなかったですね。ちょうど庭山さんと同じころに洋書を通じてABMという言葉に出合いました。「アカウント営業」という言葉は当たり前に使っていたのでABMと聞いてもあまり新鮮味を感じませんでしたが、「アカウント営業×マーケティング=ABM」だと気づいた時にこれはひょっとすると、と期待が膨らんだ記憶があります。

――従来のマーケティング戦略とABMは何が違うのでしょうか。
庭山氏:一言で言えば、ABMは成果の出方が尋常ではないということです。ターゲット顧客を1社(One to One)に絞るか、2~30社(One to Few)にするか、31社以上(One to Many)まで広げるか、やり方はさまざまですが、ターゲットを絞ることで顧客の今の状態や変化が見えやすくなるのです。
どの製品が売れているかいないのか、購買部門のキーパーソンは把握しているが研究開発部門とは接点がないなど、蓄積した顧客情報をフルに活用してターゲットアカウントと徹底的に向き合うことで新たなチャンスを見出し、マーケティングと営業が連携して圧倒的な成果を生み出すことができるのがABMの魅力です。
――NTTドコモビジネスではどのようにABMに取り組んでいますか。
戸松:前提として、ABMの発展型にあたるABXを重視しています。世界的に見るとABXの「X」には「Everything」「Transformation」「Index」「Experience」などさまざまな言葉が当てはまるとされますが、弊社では「Account Based Everything」と「Account Based Experience」という2つの文脈でABXという言葉を使っています。
弊社のビジネスにおいて最上段に掲げているのがCX(Customer Experience)の最大化です。これを実現するための戦略がABXであり、その担い手はマーケティングや営業だけに限りません。情報システムや人事などあらゆる部門と連携し会話しながら、一丸となってターゲットアカウントにアプローチするという点にこだわりを持っています。

――特徴的な取り組みについて教えてください。
戸松:独自のマーケティング戦略のもと多様なアプローチを行っていますが、その一環として、こちらのOPEN HUB Parkを事業共創の場と位置付け、さまざまな企業の方にお越しいただき新たなビジネスの可能性について議論を行っています。
また、OPEN HUBと弊社の人事部門が連動し、認定・育成を行っているのがCatalystです。「触媒」という意味を持つCatalystたちは現在1,000名以上が在籍し、個々の専門性や強みを活かして柔軟にチームを組み、顧客に合った最適な提案を実現しています。バトンリレーというよりはチームセリングで、「面」で顧客と向き合うといった感じでしょうか。
庭山さんの最新著書『法人営業は新規を追うな 重要顧客と最高の関係を築くABM』(日経BP)では、「BtoBはプロの世界です。(中略)顧客から相談される強い縦糸を、マーケティングの横糸で紡ぐことができれば顧客基盤は強くなります」と書かれていますが、まさにと膝を打ちました。ABMの定義を広く捉えれば、いろいろなアプローチができるのではと可能性を感じています。
――「日経クロストレンド BtoBマーケティング大賞2024」にて、NTTドコモビジネスは「ストラテジー部門賞」を受賞しました。庭山さんは2025年度も審査委員長を務められていますが、日本企業のBtoBマーケティングの現在地についてどう見ていますか。
庭山氏:いくつかの日本企業は世界にキャッチアップできていますが、日本全体で見れば、世界から15年遅れと言わざるを得ません。つまり、日本のトップを走る企業とそうでない企業との差が劇的に広がり続けている状況です。同じ業界や同じ規模の企業間でも驚くほどの差が生まれています。

――一方、著書では「日本のエンタープライズ企業にはABMで成果を出せる条件が備わっている」と書かれていますが、その理由は何でしょうか。
庭山氏:米国のマーケティング&セールスは、デマンドセンター、インサイドセールス、セールス、カスタマーサポートというプロセスが一般的ですが、日本のエンタープライズ企業の営業職は、セールスと言うよりカスタマーサポートと言ったほうが実情に合っているでしょう。何年、何十年と付き合いのある既存顧客に足しげく通い、良好な関係を築き、ゆるぎない信頼を獲得するというやり方ですね。そうしてでき上がった強固な営業基盤は、欧米企業がどれほど欲しいと思っても簡単に手に入れられるものではありません。
もう1つが、日本には名刺交換のカルチャーが根強く残っていることです。日々蓄積される膨大な名刺情報を適切に管理することは、ABMにおける地盤固めのようなもの。ターゲット企業のどの部門にどんな人が所属しているのか、キーパーソンは誰なのか、バイインググループ(購買の意思決定に関わる人々)のうち誰がどんな役割を担っているのか、データをもとにターゲット顧客の最新情報を追い続けることが受注への道のりとなるのです。こうした独自の文化や強みを活かせば、日本のエンタープライズ企業は世界のどの国よりもABMで成功できると考えています。
――生成AIの活用はマーケティング領域でも急速に広がっていますが、こうした動きをどのように見ていますか。
庭山氏:私が代表を務めるシンフォニーマーケティングでは、年に数回海外のカンファレンスに参加しているのですが、3年前に参加したB2B Marketing Exchangeというイベントで法人営業のメールを作成するAIのデモを見て心底驚いたのを覚えています。ところが今や「AIがメールを書く」と言っても誰も驚いたりはしませんよね。これからの時代は、情報収集を行うAIが顧客側のAIにアプローチし、AI同士が情報をやり取りするのが当たり前になるでしょう。
ではマーケターはどうしたらいいのかと言うと、今米国で起きているのが原点回帰です。クリエイティブやオペレーションはAIがやってくれるのだから、STP(Segmentation/Targeting/Positioning)といったマーケティングの基礎に立ち返り、自ら戦略を語れる人材になることに重きを置くようになっています。
戸松:生成AIによりこれまでのデジタルマーケティングの営みは完全に見直しを迫られるというのが個人的な見解です。だからこそ、生身の人間が出てくる数少ないタイミングをどう演出し、いかに顧客エンゲージメントを高めるかが重要になってくるのではないでしょうか。貴重なタイミングで確実にチャンスを捉えるには、人間の行動というものを改めて見つめ直す必要があると考えています。
BtoB領域はどうしてもCRMを軸に考える傾向が強いですが、先ほどお話が出たバイインググループのように、ターゲット顧客においてカギを握っている一人ひとりに対する洞察をBtoC並みに深めていかなければ受注につなげることは厳しくなっていくと見ています。
庭山氏:大変な時代ではありますが、リアルな場でのセミナー開催やネットワーキングなど、人間にしかできないことの重要性が増していますよね。マーケティングの設計が大きく変わっていきますが、Face to Faceのコミュニケーションの価値が高まるなど、決して良くないことばかりではないはずです。
戸松:おっしゃる通りだと思います。最近考えているのが、One to One、One to Few、One to Manyに続くABM手法の拡張として、One to Communityが生まれてくるのではないかということです。これまではターゲット顧客となる「企業」を単位としていたのが、これからは企業間に広がっている、人と人がリアルな接点を持つ「コミュニティー」がより大きな価値を持つのではないか、と。OPEN HUBにはさまざまな企業に所属する2万人のコミュニティー会員がいるのですが、こうしたつながりが生きてくる時代になると想像しています。
庭山氏:新たな時代のマーケティングがどう進化していくのか楽しみですね。BtoBマーケティングの領域で挑戦を続ける、日本企業の成長にさらなる期待を寄せています。



OPEN HUB
THEME
Co-Create the Future
#共創