
01
2025.07.18(Fri)
目次
はじめに、クリーンエネルギーの基礎知識を解説します。クリーンエネルギーと似ている用語との違いも理解しておきましょう。
●クリーンエネルギーとは?
クリーンエネルギーとは、温室効果ガスを排出しない(または排出量を抑える)エネルギーのことです。温室効果ガスは、大気を温めるガスのことで、「二酸化炭素(CO2)」「メタン」「一酸化二窒素」「フロン類」などの種類があります。なかでも二酸化炭素は、人間の活動にともなって排出され、地球温暖化に影響を与えています。
●クリーンエネルギーと再生可能エネルギーの違い
再生可能エネルギーとは、永続的に利用できるエネルギーのことです。エネルギー源が枯渇しないことが大きな特長となっています。それに対して、クリーンエネルギーには再生可能ではないエネルギー源も含まれる点が違いだといえるでしょう。また、再生可能エネルギーの中には、バイオマス発電のように温室効果ガスを排出するものも含まれます。
【再生可能エネルギーの定義】
・太陽光
・風力
・水力
・地熱
・太陽熱
・大気中の熱その他の自然界に存する熱
・バイオマス
【出典】経済産業省 資源エネルギー庁「なっとく!再生可能エネルギー」
●クリーンエネルギーとグリーンエネルギーの違い
グリーンエネルギーとは、再生可能エネルギーの中でも、温室効果ガスを排出しないエネルギーのことを指します。一般的には、バイオマス発電を除いた再生可能エネルギーがグリーンエネルギーに該当します。温室効果ガスを排出しない点はクリーンエネルギーと共通している一方で、永続的に利用可能である点が異なるといえるでしょう。
| クリーンエネルギー | 再生可能エネルギー | グリーンエネルギー | |
|---|---|---|---|
| 特長 | 温室効果ガスを排出しない(排出が少ない)エネルギー | 永続的に利用できるエネルギー | 永続的に利用可能で、かつ温室効果ガスを排出しないエネルギー |
| 環境負荷 | 環境負荷が少ない | 環境負荷がかかる場合もある | 環境負荷が少ない |
| 具体例 |
・太陽光発電 ・風力発電 ・水力発電 ・地熱発電 など ※温室効果ガスを排出しない水素ガス発電や原子力発電を含める考え方もある |
・太陽光発電 ・風力発電 ・水力発電 ・地熱発電 ・バイオマス発電 など |
・太陽光発電 ・風力発電 ・水力発電 ・地熱発電 など |
日本や世界が抱えるエネルギー問題の解決方法として、クリーンエネルギーが注目されています。ここでは、近年注目を集める理由をご紹介します。
●日本特有のエネルギー問題解決に役立つため
日本は国際社会の中でもエネルギー自給率が低い傾向にあり、エネルギーの大部分を海外に依存しているという課題を抱えています。東日本大震災以降は、エネルギー自給率がさらに低迷している状況です。こうした背景から、エネルギーの自給自足に向けて国内で生産可能なクリーンエネルギーが注目されています。2025年2月に閣議決定された第7次エネルギー基本計画では、脱炭素電源の拡大と系統整備に関して「2050年カーボンニュートラルに向けては、現状、電源構成の7割を占める火力発電の脱炭素電源への置き換えや、火力発電の脱炭素化を推進していく必要がある。」と結論づけられています。
【引用】経済産業省 資源エネルギー庁「エネルギー基本計画について 第7次エネルギー基本計画(令和7年2月)」
【出典】経済産業省 資源エネルギー庁「2023―日本が抱えているエネルギー問題(前編)」
●地球温暖化の防止につながるため
地球温暖化の原因となるのは、二酸化炭素をはじめとした温室効果ガスです。環境省が公表する資料によると、2022年度の日本の温室効果ガス排出量は約10億8,500万トンでした。なお、温室効果ガスの排出量が過去最高を記録した2013年度と比較すると、排出量は22.9%減少しています。今後も引き続き、化石燃料に頼ったエネルギー政策をクリーンエネルギーの普及へとシフトさせ、地球温暖化防止に取り組むことが重要です。
●パリ協定のモメンタムを維持するため
日本は国際社会の一員として、パリ協定のモメンタム(=国際的な意識の高まり)を維持し、取組みを続ける立場にあります。2015年に採択されたパリ協定では、世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べて2℃より十分低く保ち、1.5℃に抑える努力をするという目標が規定されました。化石燃料への依存を減らし、クリーンエネルギーの普及を促進する動きが世界的に活発になっています。
●SDGs(持続可能な開発目標)を達成するため
SDGsの目標7「エネルギーをみんなに そしてクリーンに」は、世界中の人々が安価かつ環境に配慮したエネルギーにアクセスするための目標です。現状、世界には電気やガスなどのエネルギーを使えない人々がいる一方で、化石燃料の消費が地球温暖化の原因となっています。エネルギーミックス(=多様なエネルギー源を組み合わせて利用すること)における再生可能エネルギーの割合を高めることが目標に掲げられています。
【目標7のターゲットの例】
・7.1 2030年までに、安価かつ信頼できる現代的エネルギーサービスへの普遍的アクセスを確保する。
・7.2 2030年までに、世界のエネルギーミックスにおける再生可能エネルギーの割合を大幅に拡大させる。
・7.3 2030年までに、世界全体のエネルギー効率の改善率を倍増させる。
【引用】一般社団法人 日本SDGs協会「SDGs(持続可能な開発目標)17のゴール その7」
ここでは、クリーンエネルギーの種類をご紹介します。各エネルギーの特長や仕組みを確認してみましょう。
●太陽光発電
太陽の光エネルギーを太陽電池によって電気に変える発電方法です。発電設備は住宅・学校・ビルの屋根など幅広い場所に設置でき、かつ蓄電池とも組み合わせられます。一方、一定の導入コストがかかり、日射量に発電量が左右されるのが注意点です。
●太陽熱利用
太陽の熱エネルギーを集熱器によって集めて利用する方法です。建物の屋根に設置した集熱器で、日中に熱エネルギーを貯めておき、給湯・暖房などに利用します。ただし、集熱器を設置するには屋根に一定の強度が求められます。
●風力発電
風の力でブレードを回転させて、その回転エネルギーを電気に変える方法です。数あるクリーンエネルギーの中でも比較的エネルギー変換効率が高い傾向にあります。ブレードの回転で騒音が発生するため、設置環境への配慮が不可欠です。
●水力発電
水が高い位置から低い位置に流れる力で水車を回転させて、その回転エネルギーを電気に変える方法です。クリーンエネルギーの中でエネルギー変換効率がもっとも高いとされています。一方、大規模なダムは建設に高額な費用がかかり、新設が難しい点が課題です。
●小水力発電
水力発電と同様の仕組みの、小規模な発電方法です。ダムによる水力発電とは異なり、川や用水路などの小規模な水の流れを利用して、天候に左右されずに安定的に発電が可能です。ただし、発電設備の設置には水利権が関わり、複雑な手続きが必要となります。
●地熱発電
地下深くにある高温の熱水や蒸気でタービンを回転させて、回転のエネルギーを電気に変える方法です。日本の豊富な地熱資源を活用し、安定的な発電が期待できます。その反面、開発から発電までにかかる時間とコストが高いのが難点です。
●地中熱利用
地表内部の地中熱を、ヒートポンプや熱交換器によって利用する方法です。地中熱は場所を問わずにどこでも利用でき、年間を通じて安定的に利用できるエネルギーとして知られています。一方、設備の導入コストの高さが課題となっています。
●雪氷利用
冬期の寒冷地で発生した雪や氷を保管し、冷熱が必要な夏期に利用する方法です。雪や氷の処分費用を抑えながら、冷房や農作物の冷蔵に活用できます。ただし、保管には大規模な貯蔵庫が必要で、運搬の過程で冷熱が損失しやすいのが注意点です。
【「水素ガス発電」や「原子力発電」はクリーンエネルギーに含まれる?】
前述した通り、クリーンエネルギーとは温室効果ガスを排出しない(排出が少ない)エネルギーのことを指します。温室効果ガスを排出しないという観点では、「水素ガス発電」や「原子力発電」をクリーンエネルギーに含める考え方もあります。その一方で、これらのエネルギーの利用には課題が多く、クリーンエネルギーに含めない考え方があることも押さえておきましょう。
たとえば、水素ガスを製造するには多くのエネルギーが使われ、その過程で温室効果ガスが発生する点に留意する必要があります。また、原子力発電では危険性の高い放射性物質の処理が必要で、万が一事故が起こると深刻な被害がもたらされるリスクが存在します。これらのエネルギーの安全性や環境への負荷については、技術的・社会的に解決すべき課題が多くあるのが現状です。
ビジネスにクリーンエネルギーを導入すると、民間企業にもさまざまなメリットがもたらされます。今後の導入へ向けて、改めてメリットを確認してみましょう。
●日本全体にとってのクリーンエネルギーのメリット
・日本のエネルギー自給率の向上
クリーンエネルギーは国内でも生産することが可能です。普及が進めば、エネルギーの生産・消費を実現し、エネルギー自給率の課題解決が期待できるでしょう。
・エネルギーの安定
クリーンエネルギーの中でも、太陽光や風力などの自然エネルギーを利用したものは、永続的に使い続けることが可能です。化石燃料とは異なり、枯渇する心配がありません。
・環境保全や気候変動の悪化の防止
クリーンエネルギーは、地球温暖化の原因となる温室効果ガスを排出しません。化石燃料への依存を減らすことで、環境保全や気候変動の悪化の防止につながります。
・健康の維持・向上
クリーンエネルギーが普及した結果、環境の改善が実現すると、人々の健康の維持・向上が期待できます。大気汚染や気候変動による健康への悪影響を避けられます。
・地域雇用や経済の活性化
クリーンエネルギーの導入にともない新たな仕事が必要となり、地域に雇用が発生します。また、インフラが整備され地域の経済活動の活性化にも寄与すると期待されています。
●企業にとってのクリーンエネルギーのメリット
・企業イメージの向上
企業がクリーンエネルギーの導入を推進し、それをアピールすると、環境意識の高い企業・ブランドとしての印象を与えられます。ESG投資(=環境・社会・ガバナンスを配慮した経営)の観点から自社の評価向上が期待できます。
・電気代の削減
オフィスの屋根や屋上に太陽光発電設備を設置すれば、自家発電により月々の光熱費を削減できる可能性があります。さらに、自社で使い切れない余った電気は制度を利用して売ることが可能です。
・災害時の対策
太陽光発電をはじめとしたクリーンエネルギーは、蓄電池と組み合わせることで自然災害や停電時の非常用電源として活用できます。緊急時の事業の継続に備えられるのはもちろん、電源の確保は従業員の安心にもつながるでしょう。
・競争優位性の確立
クリーンエネルギーの導入により、企業は自社製品・サービスの差別化を図り、顧客や優秀な人材から注目を集められる可能性があります。また、新たなビジネスの創出や柔軟性の向上など、経営面のメリットも期待できるでしょう。
クリーンエネルギーの導入にあたり、コストや発電量の面で課題が少なくありません。ここでは、クリーンエネルギー導入の主な課題を解説します。
●導入コストと発電コストの高さ
現状、国内ではクリーンエネルギーの導入・発電コストの高さが課題となっています。ただし、今後は技術の発展にともないコストが減少し、その他の発電方法と比較して競争力が高まる可能性があります。
●自然条件の不安定さ
自然エネルギーを利用して発電するクリーンエネルギーは、発電量が自然条件に左右されやすく、不安定になりやすいといえます。そのため、電力の需給バランスを保ったり、蓄電池を活用したりする対策が求められます。
●土地ごとの制約
クリーンエネルギーの発電設備を設置するにあたり、土地ごとの制約を受けるケースも少なくありません。たとえば地熱発電所は、発電が可能な自然環境に条件があるだけでなく、自然保全の観点から自然公園などへの設置に規制を受ける場合があります。
●認可手続きの複雑さ
クリーンエネルギーの発電設備を設置する際は、場合によっては認可手続きが必要で、事業開始に手間がかかります。たとえば大規模な太陽光発電設備を設置するケースでは、「事業計画認定」「林地開発許可申請」「市町村への申請」などの手続きが発生します。
●国の制度の不十分さ
現状、クリーンエネルギー導入へ向けた補助事業など、国によるさまざまな制度が用意されています。ただし、将来的な普及拡大を視野に入れるならば、今後さらなる制度の整備が求められるでしょう。
●スキルとノウハウの不足
クリーンエネルギーの事業は国内でまだ発展途上の段階にあります。専門分野のスキルを有する人材や、企業のクリーンエネルギー導入のノウハウが不足している状況です。今後のスキルやノウハウの向上が期待されています。
●社会的需要の難しさ
近年はクリーンエネルギーの認知が徐々に広がっているものの、既存のエネルギーに対して、新エネルギーの信頼性に疑問を抱いている人も少なくありません。また、発電設備の設置で生じる自然破壊や事故を懸念する声もあります。
●設備の廃棄・リサイクル問題
今後は、クリーンエネルギー導入後に老朽化した発電設備の廃棄やリサイクルについても考えていく必要があります。発電事業の終了後、事業者が適切に廃棄物の処理やリサイクルに取り組むことが重要です。
日本では高度経済成長期以降、石油を中心とした化石燃料に頼って発展してきた背景があります。その後、1970年代に発生したオイルショックを受けて、日本政府はエネルギーミックスへと方針をシフトさせました。
ここでは、近年の国内におけるエネルギーの現状を知るために、クリーンエネルギーの主な取組み事例をご紹介します。
●国(政府)の取り組み事例
・FIT制度・FIP制度
2012年に開始された「FIT制度(固定価格買取制度)」とは、クリーンエネルギーを含む再生可能エネルギーで発電した電気を、一定価格で一定期間買い取ることを、国が電力会社に義務付けた制度です。その際、電力会社が買い取る費用の一部を、電気の利用者から集めることで、国全体で再生可能エネルギーの導入を支える仕組みとなっています。
同じく2012年に開始された「FIP制度」とは、再生可能エネルギーの売電価格に対して、一定のプレミアム(補助額)を上乗せすることで再生可能エネルギー導入を促進する制度です。発電事業者は、電気を売った価格にプレミアムが上乗せされた合計分を、収入として受け取る仕組みとなっています。
【出典】経済産業省 資源エネルギー庁「FIT・FIP制度ガイドブック2024年度版」
・電力の小売全面自由化
2016年以降は、国の施策で電気の小売業への参入が全面自由化されています。これにより、一般家庭や企業は利用する電力会社や料金プランを自由に選択できるようになりました。電力会社間の競争が促され、料金の最適化やサービス向上が期待されています。
・RE100
「RE100」とは、事業の使用電力を100%再生可能エネルギーで賄うことをめざす国際的なイニシアティブです。国内外で多くの企業および公的機関が参加しています。国内では環境省が積極的に取組み、2020年度には「複数施設の電力契約を一本化してコスト削減を図る」「リバースオークション形式で最低価格を提示した小売電気事業者と契約する」といった施策が行われています。
【出典】環境省「気候変動時代に公的機関ができること~「再エネ100%」への挑戦~」
●NTTコミュニケーションズの取り組み事例
NTTコミュニケーションズは、2021年に環境エネルギービジョン「NTT Green Innovation toward 2040」を策定し、グリーントランスフォーメーション(GX)の分野でリーダーシップを発揮するフラッグシップ企業として取組みを進めています。具体的には、オフィスのCO2削減へ向けた「フレキシブル・ハイブリッドワーク」、温室効果ガスのデータを数値で可視化する「GHG排出可視化PoC」、データセンターを省エネ化する「データセンターのグリーン化」などの施策へ積極的に取組んでいる状況です。
なお、グリーントランスフォーメーション(GX)とは、脱炭素社会へ向けた取組みのことを指します。詳しくは以下の関連記事で解説するため、ぜひ併せてお読みください。
関連記事:「グリーントランスフォーメーションとは?概要と企業の取り組み事例」
ここまで、クリーンエネルギーが注目される理由や、クリーンエネルギーの種類、メリットや課題についてお伝えしました。企業がクリーンエネルギーを活用することで、自社やブランドのイメージ向上、電気代の削減、災害時の対策といったさまざまなメリットが期待できます。国際的なエネルギーの課題解決へ向けて、クリーンエネルギーの活用推進へ取り組んでみてはいかがでしょうか。
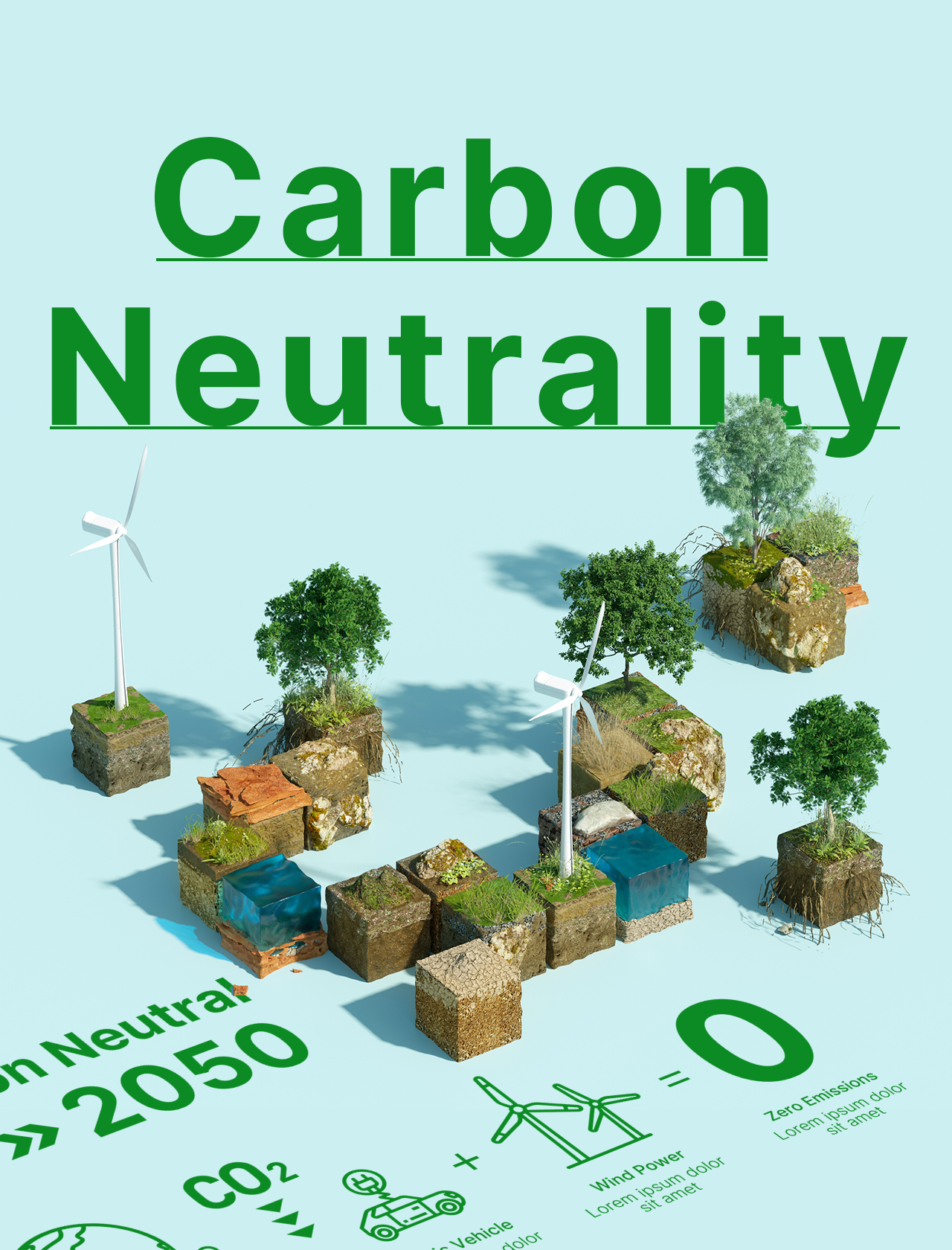
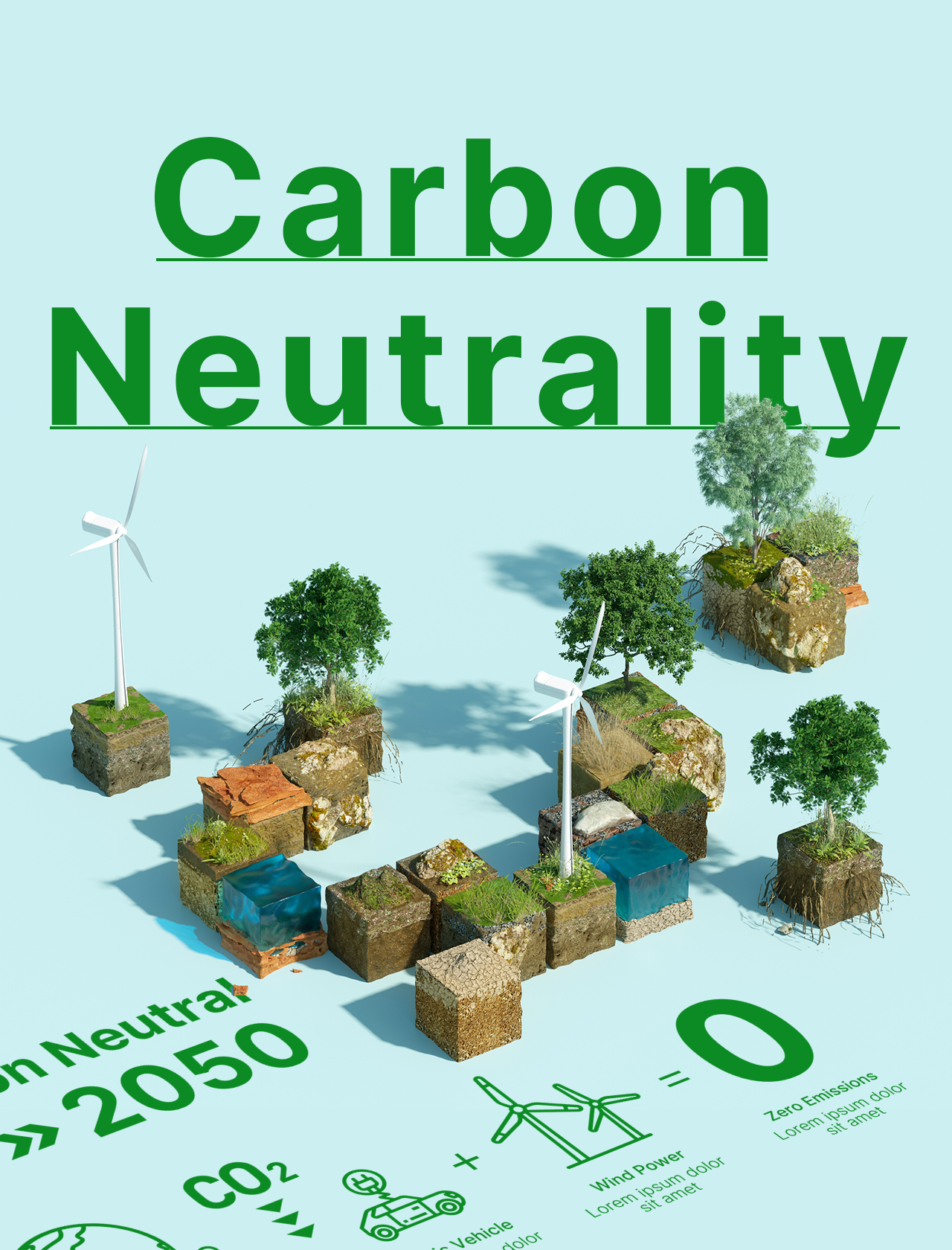
OPEN HUB
THEME
Carbon Neutrality
#脱炭素