
01
2025.07.09(Wed)
#70
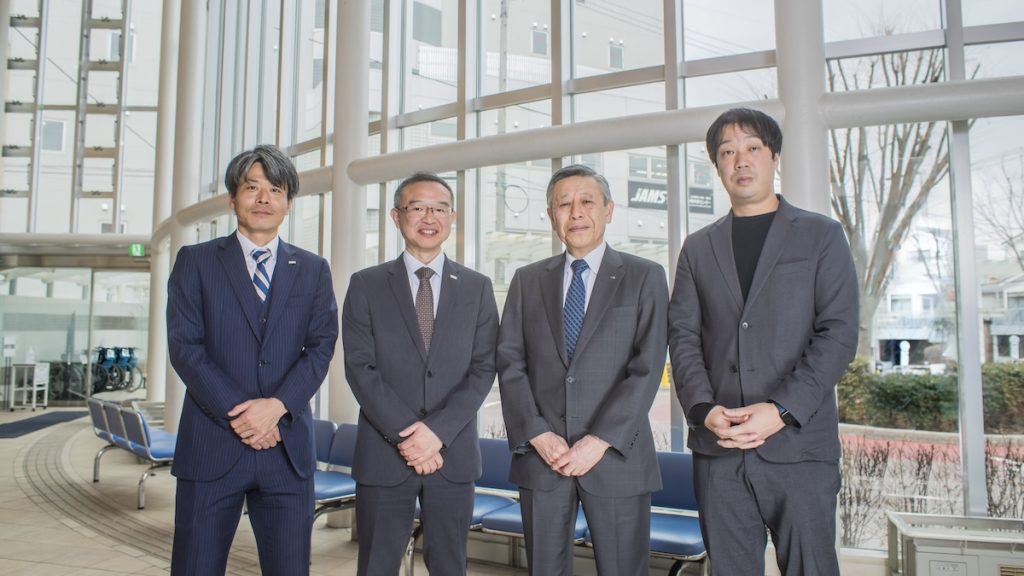
――中核病院として、松本市周辺地域の他の病院と連携し地域医療を支える仕組み(通称:松本モデル)の構築をはじめ、既存の枠にとらわれないサービスを提供している相澤病院ですが、どのような理念や構想のもとで取り組みを進めているのでしょうか?
相澤孝夫理事長(以下、相澤氏):医療機関は患者さんが来てくださって初めて価値を発揮することができるわけですから、患者さんが望んでいること、期待していることを軸に取り組みを進めています。その時に、医療と一括りにするのではなく、大きく「外来医療」「入院医療」「救急医療」「在宅医療」と分けることで具体的な課題が見えてくると考えています。
まず「外来」では急に体調が悪くなったり、心配事があったりした時に気軽に診てもらえるかかりつけ医が近くにいてほしいですよね。このような診療所は、できるだけ地域に分散しているべきです。一方、重い症状の場合は遠くても専門性の高い医療機関で診てもらいたい。ところが、地方でも都市でもかかりつけ医機能を発揮する医療機関が少なくなり、軽い症状の時でも、地方では遠くの医療機関へ行かざるを得ず、都市では大病院の外来に駆け込むしかないという状況が起きています。

また「入院医療」においては、働き手世代が減って狭心症や脳卒中も少なくなる一方、高齢者の増加に伴った病気が多くなっていますが、医療提供体制が追いついておらず、需要とのミスマッチが生まれています。「救急医療」では、救急を受け入れる病院がどんどん少なくなる中、本当に重症の患者さんを受け入れられなかったり、遠くの病院まで運ばれたりということが起きています。「在宅医療」でも、高齢者の集合住宅への医療が急増していますが、このような患者さんは医療だけでなく介護や生活支援がないと生活できません。
このような患者さんの多様なニーズ、地域の課題を一つの病院で解決していくことは難しいと気づいたのが、1998年頃です。医療機関がお互いの特徴と強みを活かし、情報を共有しながら連携して地域を守っていかなくてはいけないと考え、他病院との連携体制を構築してきました。
――そのような課題解決に、DXはどのような役割を果たしますか?
相澤氏:このような問題の根本的な解決には、医療提供体制そのものを変えていく必要がありますが、それにはどうしても時間がかかります。今の体制の中でもデジタル化することで仕事のやり方を変えていけば、少ない人数でも今まで以上のサービスを提供することができます。また患者さんの需要とのミスマッチも、情報共有によって医療機関同士の連携を高めることで解消を図ることができます。今、「医療DX」という言葉が叫ばれていますが、行政や企業が固定化したDXとして展開しても、病院ごとにオペレーションは異なるため、成果は限られます。本当に必要なのは、病院ごとのオペレーションに合わせた「病院DX」。医療行為だけでなく、病院単位で仕組みや働き方も含めて標準化できる部分を大胆にDXし、各病院がオペレーションを効率化するとともに病院間の連携も高めることで、地域の課題解決につなげていくことができるはずです。相澤病院が「病院DX」のロールモデルとしてDXの効果を実証し、全国へと広げていきたいと考えています。

OPEN HUB
Theme
Co-Create the Future
#共創