
01
2025.07.18(Fri)
目次
――NTT ドコモグループは、2030年までに陸と海の30%以上を健全な生態系として保全することを目標とする「30by30アライアンス」に参画しています。2022年にNTTドコモグループの法人事業会社として新たなスタートを切ったNTT Comでは、サステナビリティの推進にどのように取り組んでいますか?
サステナビリティ推進室長 田畑好崇(以下、田畑):NTT ComではNTTグループのサステナビリティ憲章を指針として、「社会」「環境」「人材」「ガバナンス」という4つの重点領域それぞれに、2から4つの重点活動項目を設定して取り組みを進めています。
環境に関しては、脱炭素社会と循環型社会の推進を重点活動項目としており、生物多様性の取り組みは、「生物多様性や生態系、森林保全の推進」「水資源の適切な管理」という2つを柱としています。
NTT Comは2022年にNTTドコモグループの法人事業会社として新たなスタートを切りました。それを機に、NTTドコモがICTを活用した生物多様性保全への取り組みの一環として行っていたサンゴの生態調査への協力を継承しています。企業のESGの取り組みには、「リスクの管理・低減」と「機会の創出・拡大」という両側面がありますが、本調査への協力は、その両面において意義があるものだと考えています。

――水中ドローンによるサンゴの調査に取り組むことになった経緯を教えてください。
NTT Com九州支社 永濱晋一郎(以下、永濱):私の所属する九州支社では沖縄地区の地域創生に向けて産学官連携の取り組みを進めています。その中で、観光地として有名な慶良間諸島国立公園もある座間味村のサンゴの調査をしようという話が出ていました。一方、私は、水中ドローンを使った牡蠣養殖やマグロ養殖場の点検プロジェクトを知り、サンゴ調査にも水中ドローンを活用できるだろうと考えました。その活用方法を座間味村の宮里哲村長や座間味地域のオセアナポートヴィレッジホテルの瀬長博康社長に提案をしたのが始まりです。
村長や地域企業から「産学官で進められたら面白いね」という反応をいただき、学術的なサンゴの生態調査と水中ドローンの組み合わせを検討していた時にたどり着いたのが、佐藤教授の研究でした。
佐藤矩行教授(以下、佐藤教授):私が所属するOISTには、ゲノム解析のシークエンサー(DNA解析装置)が揃っており、研究チームを立ち上げた2011年に、世界で初めてサンゴのゲノム解読に成功しました。こうしたゲノムの知識を活用して環境DNAという方法でサンゴの生態を解析できないかと考えました。海水にはサンゴが出す粘液が含まれているため、海水の表面から1リットルの水を採取し、そこに含まれるサンゴのゲノム塩基配列を解析することで、海水を取得した場所の海底にどんなサンゴが生息しているかが分かるのです。
しかし、この方法が使えるのは水深15メートル程度に生息するサンゴまで。ダイバーが潜れる深さにも限界があるため、水深が深い場所のサンゴの実態はほとんど調査できずにいました。この課題をどう乗り越えようかと研究チームで話していた時に、ちょうど永濱さんからお電話をいただいたのです。

――水深15メートル以上のところに生息するサンゴの分析を、水中ドローンでどのように実現したのでしょうか?
永濱:水深20から30メートル、最も深いところでは100メートル程度まで水中ドローンを潜らせて、水中で500ミリリットルの水を2つ採取します。それを佐藤教授が研究室に持ち帰って、シーケンサーを用いてDNA解析を行います。
NTT Com 5G&IoTサービス部 岡田修宏(以下、岡田):水中ドローンの製造メーカーと連携し、機体の改良にも取り組みました。環境DNA分析は、同じ場所で採取した水を使ってゲノム解析を複数回行い、データの信頼性を担保する必要があります。そのため、ゲノム解析を最低2回はできるように水1リットルを採取する必要がありますが、既製品の水中ドローンは500ミリリットルまでしか採取できません。そこで、製造メーカーに要望を伝え、サンゴの近くで水を1リットル採取できるように改良してもらいました。

佐藤教授:研究側の視点で少し補足しますと、沖縄の海は潮の流れがとても速いのです。流れの速い海中で水中ドローンを操縦し、狙った場所で位置を固定してサンプル(水)を採取するのは、相当高い操作技術が求められます。
――海中で水を採取する難しさは、どんなところにありますか?
岡田:空中ドローンは機体を目視しながら操縦することも可能ですが、水中ドローンの場合は目視ができず、さらにGPSも使えないため、スマホやタブレットなどのモニターを見ながら操縦しなければなりません。水中ドローンが今どこにいるのかは、経験と勘が頼り。私たちは、水中ドローンの協会独自資格を取得しており、あらゆる機種をさまざまな現場で運用してきた経験がありますので、場所に応じたオプション機能を最適にセットアップし調査に臨んでいます。

佐藤教授:調査を重ねるごとに環境DNAの採取方法の改良を重ね、今ではほぼ完璧な手法が確立できたと思っています。この過程で、NTT Comも水中ドローンの機体や操作技術に改良を重ねてくれました。いいデータを求めて「ドローンをもう少し右側に寄せて」などリクエストをするのですが、うまく操縦してくれるので本当に感謝しています。NTT Comメンバーのコンビネーションと技術は、世界トップだと思っています。調査では、水深100メートルのところに群がるサンゴも見つかりました。
――水中ドローンを用いた調査で、佐藤教授も驚くような新たな事実などは分かってきているのでしょうか?
佐藤教授:はい、来年には皆さんを驚かせるような発表ができる予定です。少し先出してお話しすると、サンゴのゲノム解析を始めた当初、沖縄に生息するサンゴは約40種類ほどだと考えられていました。しかし、日本全体では85属のサンゴがいると言われています。そこで、全国のサンゴ研究者からサンゴを送ってもらい、日本に生息するほぼすべて(83属)のサンゴDNAデータベースを作成し、環境DNA分析で得られたデータと照合しました。
すると、沖縄に生息するサンゴの種類は約40種類ではなく60種類以上いることが分かってきました。つまり、これまでの認識よりはるかに多様性に富んだサンゴの生態系が沖縄の海に広がっているということです。
――佐藤教授は、水中ドローンを使ってサンゴの生態を研究していく先に、どのようなことを目指しているのでしょうか?
佐藤教授:サンゴは水深によって生息する種類が変わってきます。光合成が必要な藻類(褐虫藻)と共生するハードコーラル(造礁サンゴ)は浅いところを中心に生息していますし、深いところにはソフトコーラルというグループが多く生息しています。ただ、ソフトコーラルは浅いところにも生息するなど、くわしい生態の解明には、さらなる研究が必要です。
例えば、沖縄県恩納村の海域では水深2メートルから40メートルまでサンゴが群生していますが、生息面積や種類、どのような種類のサンゴがグループを形成して面的に広がっているのか、そのつながりを解明し、サンゴの生態の全体像を捉えたいと思っています。
そしていずれは、サンゴに集まってくる魚類や甲殻類を含めたエコシステムのモデルを導き、サンゴが生物多様性に与える影響や、炭素吸収源としての価値がどれくらいあるのかを数値で示したいですね。
――NTT Comは佐藤教授との共同研究の他に、どのような活動をしているのですか?また、活動の目的についてもお聞かせください。
永濱:座間味村は観光地ですが、地元の子どもたちは自分たちの住む地域の良さや価値に触れる機会は少ない状況です。そこで、まずは地元の子どもたちに環境のすばらしさ、海のきれいさを理解してもらうため、子ども向けの環境学習を始めています。
ただ、環境学習には難しいイメージがあるようで、約200名の中高生などに行ったアンケートでは「面白くない」という回答が多くなっていました。
そこで、2024年3月5日、サンゴの日に佐藤教授にも協力してもらい、約30名の小学生に対し刷新したプログラムで環境学習を実施したのです。環境DNAを含んだ水をすくってもらいサンゴの種類を調べるプログラムや、サンゴの苗づくり、水中ドローンの操作などを体験した子どもたちから「とても楽しかった」という反応をもらい、これこそ、子どもたちが地元に誇りを持つきっかけになるのではないかという小さな手応えを感じています。
こうした活動を続けていくには、地域の企業や学校、自治体を巻き込み、持続可能な活動にしていくことが必要ですので、今、模索しているところです。

田畑:企業がサステナビリティに取り組む上での「リスクと機会」という大きなフレームで考えると、このサンゴ研究プロジェクトによりサンゴの生態やエコシステムが解明されれば、ブルーカーボンとしての価値が見えてくる可能性もある。つまり、企業や社会にとっての機会につながります。
機会をつかむまでには時間がかかりますから、できるだけ多くのステークホルダーと協力体制を築いていくことが重要になっていきます。
佐藤教授:研究者目線での話になってしまいますが、NTT Comとこの2〜3年で進めてきた共同研究の成果はとても大きく、膨大なデータを論文として報告できていないことに悩んでしまうほど、順調にデータが集まっています。こうした成果を公表していけば、世界からも注目を集め、サンゴ礁のエコシステム解明に向けた非常に大きな流れになっていくのではないかと思っています。
例えば、調査で得た膨大なデータをオープンデータとして公表することで、さらなる研究の広がりが期待できます。私たちの研究の現状では、サンゴのブルーカーボンとしての可能性を語ることはできませんが、海水中のCO2を計測できる技術などを用いて研究を進めれば、さまざまなことが明らかになっていくでしょう。このように、いろんな技術を持つ企業と研究者が連携することは、研究を進める上でも非常に有効です。こうした活動を引き続き進めていきたいと考えています。

永濱:私たちとしても、佐藤教授の研究と連携・協力していくことはもちろん、NTT Comが得意とするテクノロジー活用だけではなく、NTTグループの研究技術なども活用して地域課題やネイチャーポジティブに向けた課題へのサポートを続けていきます。活動を通じて、NTT Comを少しでも面白い会社と思ってくれる方が広がってくれたらうれしいです。
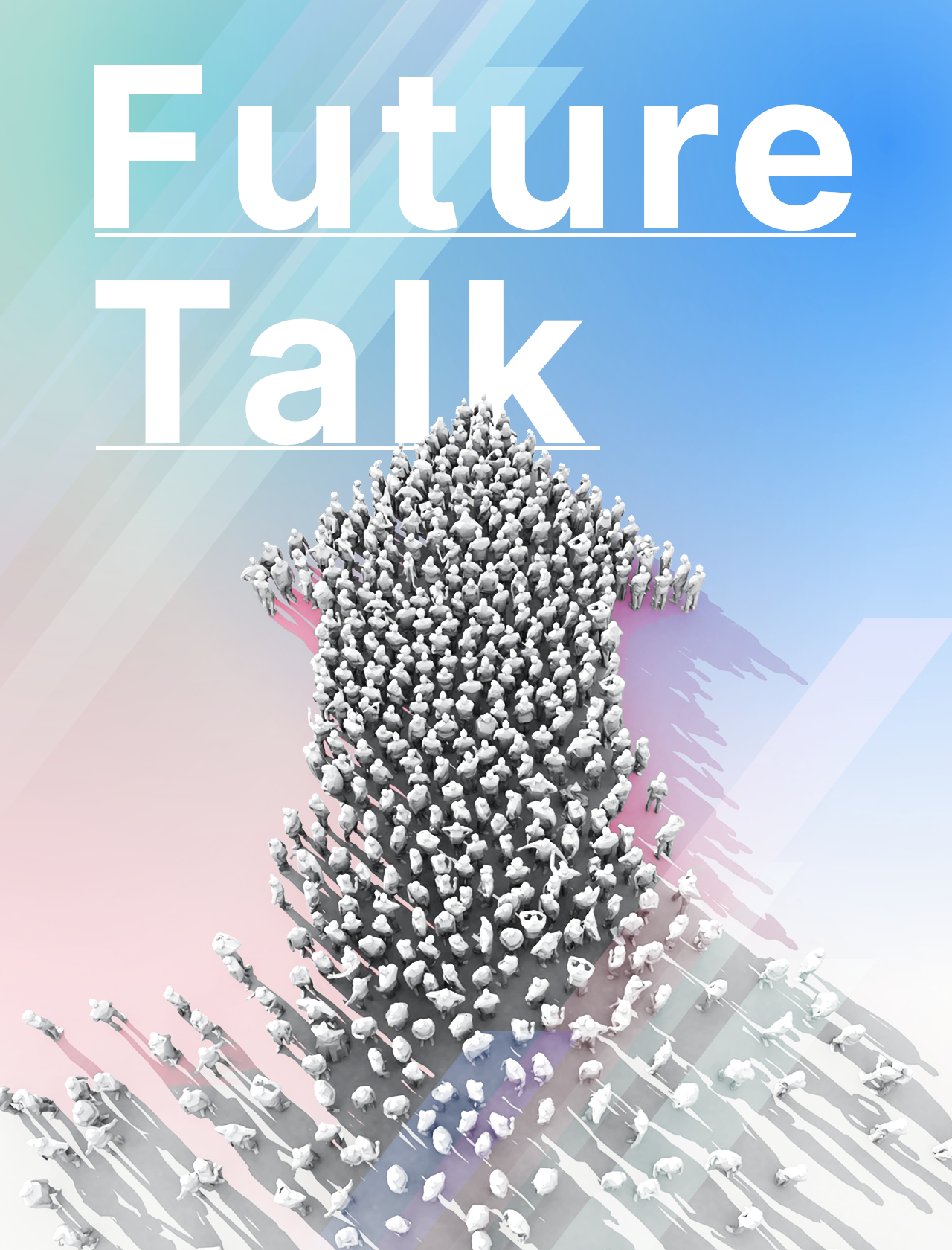
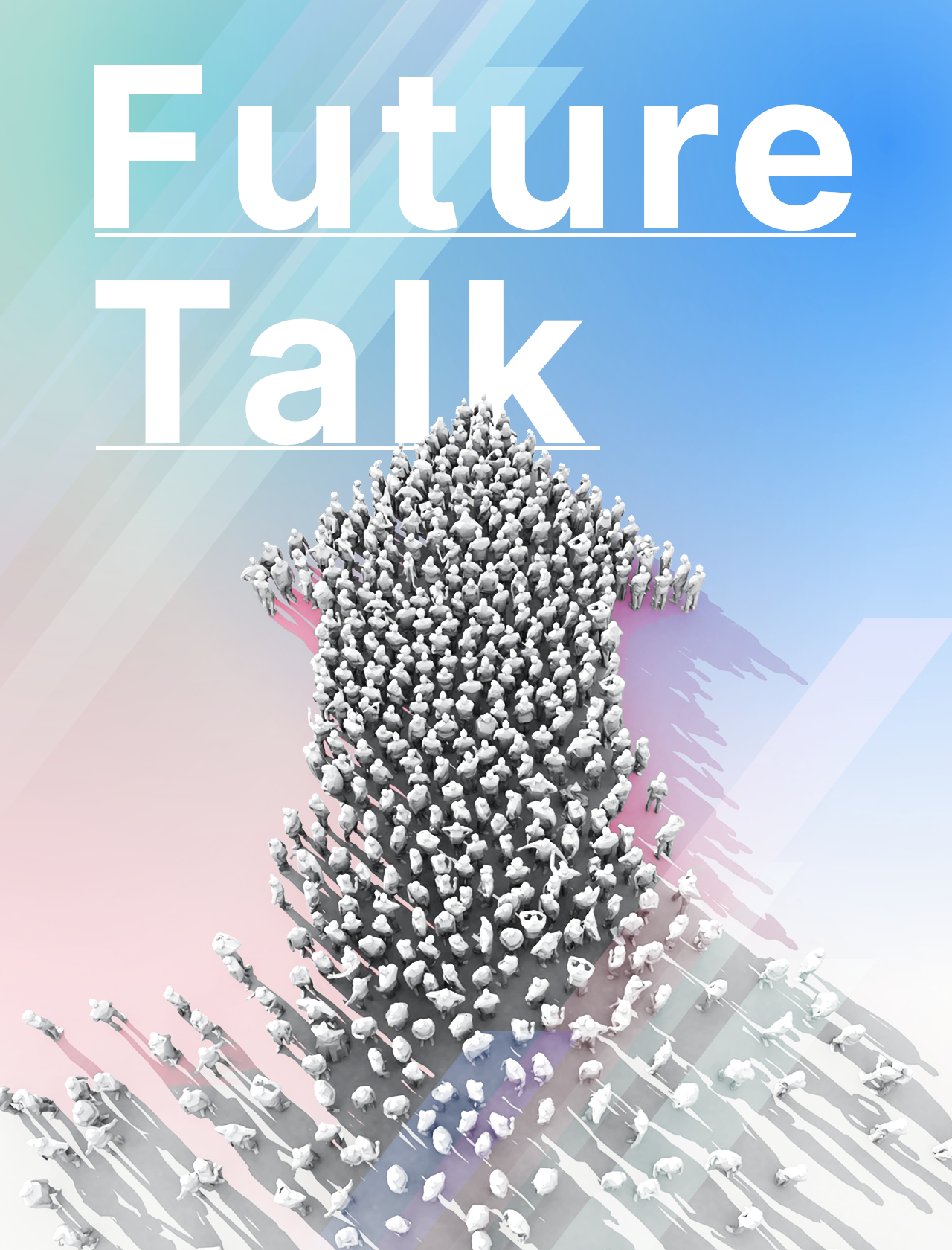
OPEN HUB
THEME
Future Talk
#専門家インタビュー