
01
2025.07.18(Fri)
目次
ー稲見さんはインタラクティブ技術やロボット工学などの研究を行われていると同時に、JINSとともにメガネ型ウェアラブル端末「JINS MEME」を開発したり、スポーツとテクノロジーを融合する「超人スポーツアカデミー」の設立に関わったりするなど、研究者の枠にとらわれない活動に取り組まれています。そうした「まだ誰も取り組んでいないこと」に挑戦するモチベーションは、どのようなところから生まれるのでしょうか?
稲見昌彦氏(以下、稲見氏):そもそも研究の領域においては、世界の誰もやっていないことでなければ、本当に新しい研究にはなりません。だから、社会の役に立つかどうかはわからないけれども、まだ誰もやっていないことをやるんです。

また、僕にとって研究は、一種の表現活動であり、コミュニケーションのツールです。今でこそペラペラ喋れるようになりましたが、昔は喋るのが非常に苦手でした。でも、面白いものをつくれば多くの人が私の考えに興味を持ってくれて話を聞いてくれる。そして、さまざまな分野で面白い活動をしている方々と対話することができる。
自分が面白いと思えること、みんなに面白いと思ってもらえることをやり続けていたい、自分も他の人の面白い話を聞きたい。そうやって取り組んできたことが、結果的に挑戦に見えたということだと思います。

川村真司氏(以下、川村氏):僕もクリエイターと研究者は似ているところがあると思っていて、クリエイターである以上、常に新しいものをつくっていたいんですよ。「なんでやったことのない研究をするんですか?」と研究者に聞いても、「誰もやっていないから」としか答えようがないように、クリエイターも誰もやっていない表現だからこそ、挑戦する。
ただ、難しいのは、新しいものが常にヒットするとは限らないということ。「早すぎた」ということが往々にしてある。僕のルーツは広告ですが、やっぱり広告って「広く告げる」べきものだと思うので、どうすれば新しい表現を生み出しつつ多くの人に愛してもらえるコンテンツがつくれるのか。そのバランスを常に考えながら、ギリギリのラインを攻めるようにしています。

稲見氏:「早すぎた」は研究でもありますね。私は「研究ワイン理論」と呼んでいるんですが、5年、10年寝かせなければいけない良いワインほど、最初は渋かったりするじゃないですか。シェフやソムリエのようなその筋の人はポテンシャルがわかるんだけれども、お客様に出すと「渋い」と捨てられてしまったりする。しかし、そういったものを地道に熟成させることで非常に価値の高いものができるわけですから、値上がりしないうちに価値を見極めて買うことができればそれが一番良いんです。
ー川村さんは2009年の時点で、ウェブカメラのリモート映像を組み合わせた、まさに現在を予見した先駆的なミュージックビデオ作品『日々の音色』など、テクノロジーを駆使した革新的なクリエイションを多数生み出されてきました。一方で、現在は木彫りパペットを用いたストップモーション時代劇『左』を手掛けています。アナログの手法を取り入れた理由は何でしょうか。

川村氏:僕が作品をつくるときは、それぞれの表現や体験、物語に求められている質感を大事にするようにしています。その上で、新しい表現手段として、デジタルかアナログかはあまり重要ではないと考えています。
『左』の場合は、「左甚五郎」という江戸時代の木彫職人の話だからこそ、コマ撮りで、木彫りで、やらなければいけないんです。ストップモーションの時代劇という誰も取り組んだことのないスタイルだからこそ、アナログの表現でもまだまだ彫られていない鉱脈があるということを提示したいという気持ちもあります。

CGを使ってストップモーション風の映像をつくることもできるでしょう。その方が費用対効果は高いですし、実際にそのような作品もあります。でも、僕としては、それではやはり失われるものがあると感じます。

稲見氏:ストップモーションという非常に手間のかかる手法自体に、私たちの認識できる価値が含まれていますよね。それは、これから到来するかもしれないメタバース時代における「価値」について捉え直すヒントにもなると思います。
奈良時代の税金に「租庸調」というものがありました。「租」はお米、「庸」は労役ですが、「調」は布。「なぜ布?」と思ったのですが、八丈島に行って黄八丈を見たときに腑に落ちました。布は人間の汗の結晶であり、人々の労働が集約された最も可搬性の高い価値だったのだと。その価値を当時の人たちがみんな信じていたから、税金として機能したと思うのです。

川村氏:なるほど。メタバースやそれに付随するNFTもそうですが、結局は「何を信じられるか」ということが物の価値を左右するんですよね。
ービジネスにおいては新たな分野への参入はそのタイミングが重要とされていますが、そうした視点からみて、お二人はメタバースが現在どのようなフェーズにあると思われますか。
川村氏:僕も、ちょうどそれを稲見さんに聞きたいと思っていたんです。メタバースのコンセプトが重要であることはわかりますし、「メタバースをやりたい」というご依頼をいただくことも多いんですが、ビジネスとして今がインベストすべきタイミングなのかというと、けっこう懐疑的なところがありまして……。
メタバースをやると言っても、スクラッチで開発するのか、clusterのようなプラットフォームを使うのか。本来は恒常的に続いていく生態系的なものであるべきだと思いますが、つくったあとの運用はどうするのか。そもそも本当にメタバースでやる必要があるのか、オープンワールドなゲームや、単なる3D化されたソーシャルネットワークと何が違うのか……まだいろいろと見えていない部分がありますね。

ーなるほど。稲見先生、「メタバースの時代」は本当に来るのでしょうか。
稲見氏:多少のブームの浮き沈みはあっても、メタバースが今後生活やビジネスのさまざまな場所で使われるようになっていくというトレンド自体は、消えることなく続いていくと思います。
1つのポイントは、個人が参入しやすくなったことです。実は1990年代に第一次のVRブームがあったのですが、当時HMD(ヘッドマウントディスプレイ)は数百万円、専用のコンピュータは数千万〜数億円と非常に高価で、NTTや松下電工(現パナソニック)のような大手メーカーと東京大学などいくつかの大学が持っているくらいでした。このようなフェーズでは、組織の方針次第で、突然ブームが消えてなくなることがあります。
しかし今は、ハードウェアの価格が十分に下がり、個人が容易にVRを体験したり、開発できたりするようになりました。コンピューターゲームという概念がなくならないように、メタバースも、一過性のブームとして終わらない、なくなりはしないところまで来ていると感じます。
ー今後メタバースが広く一般に普及していくために、何が必要だと思いますか?
稲見氏:「百聞百見は一験にしかず」という松下幸之助さんの言葉もありますが、HMDを使って体験することは絶対的に必要だと思います。
例えば、メタバースに関するあるサービスの発表会見を取材した記者たちの記事が、メタバースに「期待する」論調とそうでない論調とに分かれたことがあります。しかし、よくよく調べてみると「期待する」という論調の記事を書いた人はHMDを使ってメタバースを体験したことがあり、「期待しない」人はパソコンのディスプレイ上でしか体験したことがなかった、という話だったのです。
VRで体験しない限りその真価はわからないと思うので、ぜひVRで体験してから判断してもらいたいですね。体験した結果、VR酔いしてしまって、嫌いになっちゃう人もいるんですけど(笑)。

川村氏:ちなみに、僕はVR酔い専用の酔い止め薬の商品化を提案したことがあります(笑)。2015年くらいだったので、これも「新しすぎた」事例ですね。VR酔いもそうですし、「HMDが重い」「髪型が崩れる」など、改良すべき点はまだまだたくさんありますよね。
ただ、そうした苦労をしてでも体験してみたいと思えるようなコンテンツをつくるのはクリエイターの領域だと思うので、そこをなんとか探っていきたいですね。
ー稲見先生は、メタバースを「人間の能力を引き出す環境」と定義されていましたが、具体的にどのような人間の能力が引き出されていくのでしょうか。
稲見氏:一番わかりやすい事例は、「けん玉できた!VR」でしょう。これは、玉の動きをスローモーションにしたVR空間で5分間けん玉のトレーニングをすることで、体験者の9割近くが新しいけん玉の動きを習得することができたという事例があったのです。
私自身も非常に運動が苦手なのですが、運動が苦手な人にとって物理法則が支配する現実世界は、ゲームでいうところのハードモード。最初から失敗ばかりなので、「自分は向いていない」という判断になります。「失敗に学ぶ」と言いますが、失敗だけでは、人間もAIも闇雲な探索からなかなか抜け出せません。モチベーションの維持と成長のためには、適切な成功と失敗を繰り返す必要があります。
その点VR空間なら、物理法則を変えることで、イージーモードから練習できるようになります。物理法則の変え方にはいくつかあるのですが、そのうちの1つが「時間を遅くする」ことです。

ー適切な環境を設定することで人間の成長を加速できると。大きな可能性を感じますね。
稲見氏:また、身体的な能力だけでなく、想像力のような能力も、メタバースによって拡張されると考えています。
例えばデザイン思考において、「ユーザーを観察し、共感する」というプロセスがありますが、ここで意外なボトルネックになるのが観察力や想像力です。いかに適切な対象を選び、適切なユーザーモデルをつくれるかは、個人の能力に依存しています。
一方、メタバースを使えば、ユーザーの視点を直接体験することが可能になります。小学校で使うサービスをつくるのであれば、小学校の環境をVR空間につくり、小学生の視点で動いたり、遊んだりすることで、新たな課題やニーズを発見できるでしょう。これまでスキルのある人が「暗算」でやっていたことを、誰もが「筆算」できるようになるんです。
川村氏:ツールによって発想やクリエイティビティは変わると思っています。例えば、鉛筆を使っているときと、パソコンを使っているときと、粘土をこねているときでは考え方が大きく変わります。
メタバースでは、そうした発想のための環境が拡張され、しかも自分の望むように自由に変えられる。メタバースならではの新たな感覚や表現が生まれそうですよね。
稲見氏:そうですね。未来の川村さんのような方は、メタバース内でプロトタイピングをしたり、作品を発表したりするようになるのだろうと思います。

ーなるほど。物理法則や身体能力を超えた自由な活動が可能となるメタバースの世界では、「自分らしさ」が希薄になっていくような気もします。メタバース時代において、私たちはどこに個性やアイデンティティを見出せばよいのでしょうか。
稲見氏:好き、嫌い、喜怒哀楽といった自分の感情、情動でしょうか。「我思う、ゆえに我あり」という言葉がありますが、これからは「我感じる、ゆえに我あり」の時代になっていきます。
川村氏:自分なりの好きなものや、自分にしかわからない領域を表出することが価値になっていくということですね。
稲見氏:そうですね。他者を批判する必要はありませんが、心の中で「嫌い」という感情を持つことも、「好き」という感情を持つのと同じくらい重要だと思います。研究の世界においても、自分なりの「好き」「嫌い」の軸がなければ、良い研究はできません。「個性なんてない、でも自分の情動はある」ぐらいに思っておくと良いのではないでしょうか。
研究者とクリエイター。異なる立場ながら戦友のような雰囲気で話すお二人の間には、誰も踏み込んでいない新しい地平に踏み込むこと、または踏み込もうとする行動それ自体が、自分が本当に求めている景色に導いてくれるのだという確信が共有されているようでした。メタバースという今すべての人に開かれた地平に、いつ、どうやって飛び込むか。それは私たち自身が何を真に求めているのかを見つめることで、見えてくるのかもしれません。
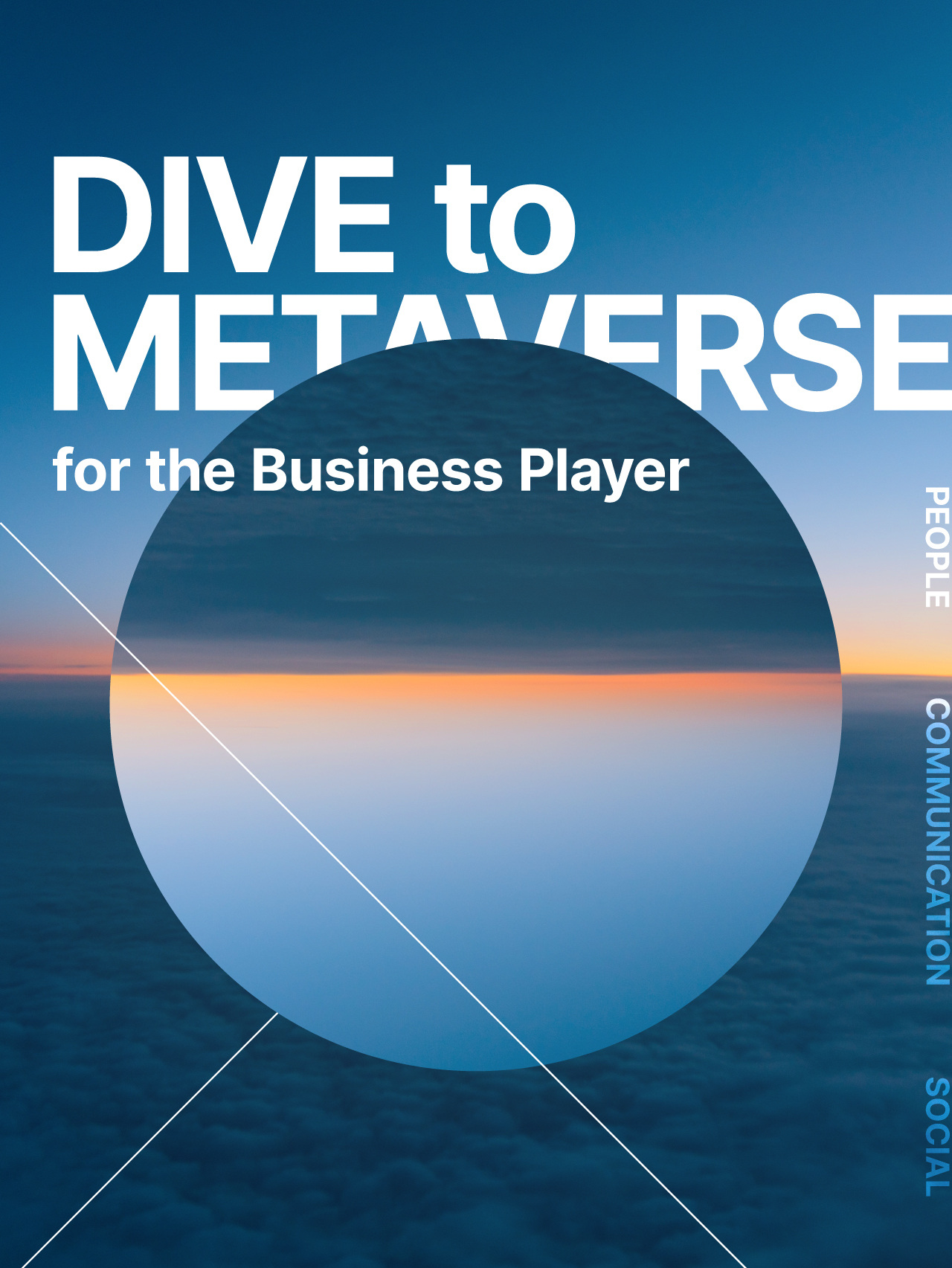
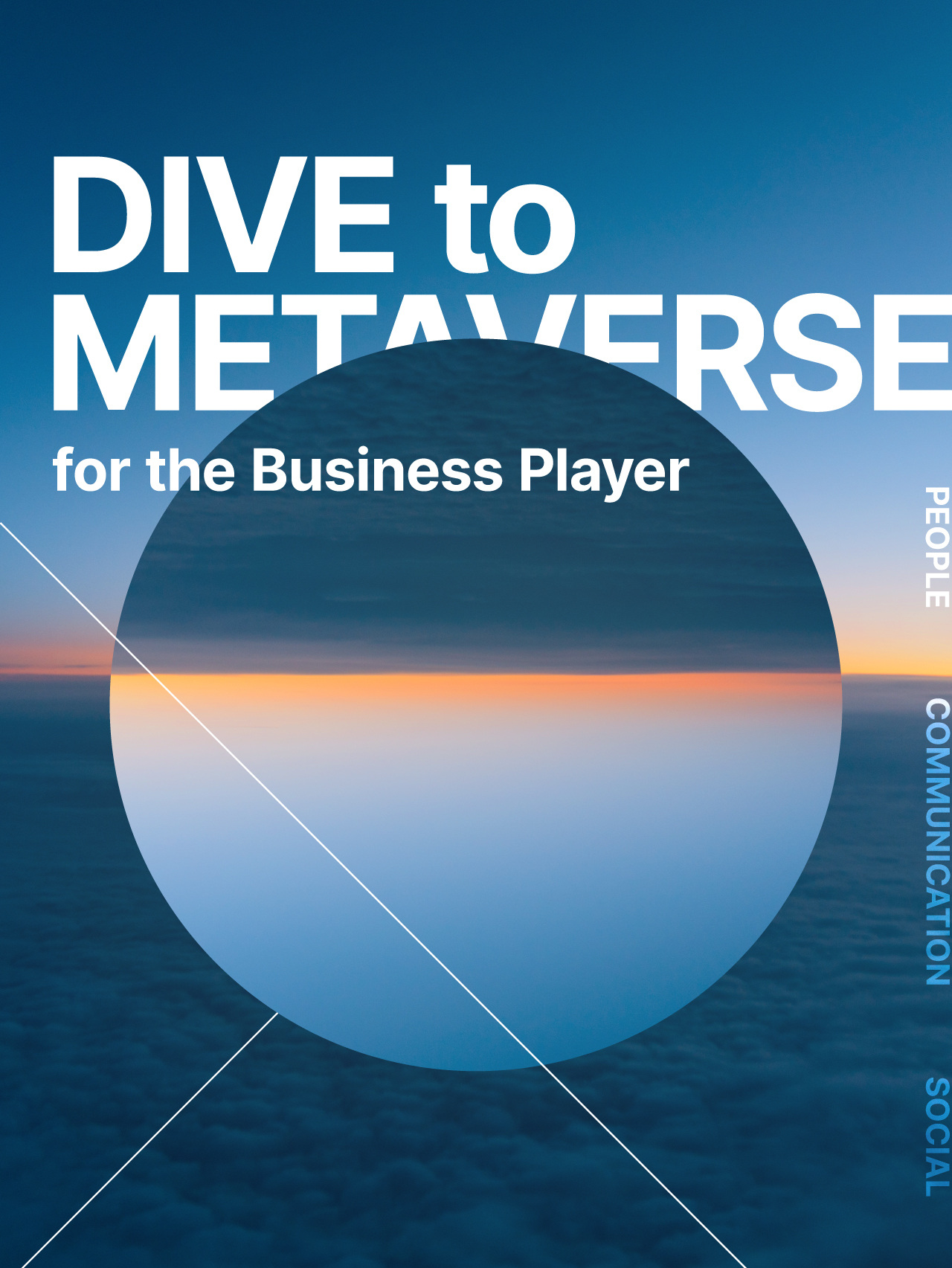
OPEN HUB
THEME
DIVE to METAVERSE
#メタバース