
01
2025.03.06(Thu)
目次
──現在、日本の防災を取り巻く状況についてお聞かせください。
片田:日本は長い年月をかけて防災・災害対策を強化してきました。1959年の伊勢湾台風を契機に「災害対策基本法」が制定され、国・県・市町村に「住民の生命と財産を守る責務」が明記されたからです。
これにより、国民にもいつしか「防災は行政がやるもの」という意識が定着したように思います。危険な場所に堤防を築くのも行政、ハザードマップをつくるのも行政、避難を呼びかけるのも行政、避難所を運営するのも行政。こうした構造が続いた結果、日本は「災害過保護」状態に陥ったといえるでしょう。つまり、いざという時に自分で判断し、行動するという機会が、災害に対しては失われてきたわけです。
島田:私にも思い当たるふしがあります。確かに防災に限らず、今は不確実な時代なので、いろいろな場面で自己判断が求められますよね。組織内でも社員一人ひとりが判断しなきゃいけない局面は多い。しかし、どうしても日本人はマニュアル依存になりがちです。
マニュアルに依存してしまうのは、おそらく学校教育の影響もあると思っています。子どもの頃から「正しい答えはこれです」と与えられて育つわけですから。そのせいか、海外の人に比べると日本人は自己判断の力が弱い印象を受けます。そう考えると、片田教授のおっしゃる日本人の災害過保護とマニュアル依存は、同じ構造にあるのかもしれません。

片田:防災の手法というのは、大きく分けると「行動指南型」と「状況通達型」の二つがあります。行動指南型防災というのは、行政が「避難してください」「海岸に近づかないでください」と具体的な指示を出し、それにもとづいて国民が動く防災です。日本の防災は基本的にこのスタイルを採用してきました
一方の状況通達型防災は、国民の主体性にもとづいています。行政の「川が氾濫危険水位に達しました」「避難所が開設されました」といった状況情報をもとに、国民一人ひとりが「それならすぐ避難しよう」とか「ここはしばらく様子を見よう」と、自ら判断して行動に移す防災です。これからの日本に必要なのは状況通達型防災なのだと考えています。
島田:最近はSNSなどでユーザー自らリサーチする動きも広がっていますよね。もちろん誤情報やデマも多いので、そのなかでどう取捨選択し、どう判断するかが問われます。結局、我々自身が情報への抵抗力を高め、自己判断力を鍛えていくフェーズに入っているように思います。
──国民が主体的に避難行動するというと “釜石の奇跡”が思い出されます。東日本大震災では、津波が東北沿岸に甚大な被害を及ぼしたにもかかわらず、岩手県釜石市内の小中学生のほとんどが無事でした。子どもたちの防災教育にあたったのが片田教授でしたね。
片田:釜石の子どもたちには、8年間にわたって「避難三原則」を指導してきました。一つ目は「想定にとらわれるな」です。もっと具体的に言うと「ハザードマップを信じるな」。もちろん、ハザードマップは非常に重要な資料です。けれども、現実の災害は地形や条件にかかわらず、思いもよらないかたちで起こり得る。「だからハザードマップを鵜呑みにするな」と伝えました。
二つ目は「最善を尽くせ」。災害が起こったら、自分にできることはただ一つ。最善を尽くすことです。子どもたちに「最善を尽くしても津波の方が大きかったら?」と聞かれたとき、私は「それは『死ぬ』ということだよ」と答えました。とても驚かれましたが、最善とは「これ以上はない」という行動を取ること。それ以上のことは受け入れるしかないのです。
そして三つ目は「率先避難者たれ」です。警報が出ているなか、自分だけ真っ先に避難するのはとても勇気のいることです。子どもたちにとってはクラスメイトから「弱虫だ」と思われかねないですからね。けれども、多くの人は「逃げない」のではなく「逃げる」という決断ができないだけなのです。その膠着状態を破り、最初の一歩を踏み出す避難者になることがどれほど重要か。自分が率先すれば、周囲も一気に逃げはじめる。その勇気が多くの命を救うのです。
三原則はどれも、子どもたちに「自分も防災の当事者」だと自覚させることが大きなテーマになっています。どう伝えれば「避難」という具体的な行動に結びつくのか。その意味で、当事者意識を高めるためのコミュニケーションデザインが非常に重要だと考えています。

──現在、生成AIがビジネスの現場に浸透しつつあります。今後は生成AIの技術を防災に活かすこともあるのでしょうか?
島田:可能性は十分にあると思います。例えば、災害が起こった際に状況を的確に判断して、避難行動を促すようなメッセージを発信するとか。それだけでも防災の実効性は高まるはずです。重要なのは、その情報を「必要な人に、必要なタイミングで」届けられるかどうか。そこにAIの力が加われば、大きな意義があると考えています。
片田:災害という現象が「不確実」なのであれば、それに対応する人間の行動もまた臨機応変で「不確実」であるべきです。そういった不確実性を正しく理解していただくための有効なツールとして、AI技術を活用できないかと考えています。
私も「津波災害総合シナリオ・シミュレータ」の開発に携わっていますが、一つのシミュレーション結果をお見せして「こうなります」と示すだけでは不十分です。本来であれば、諸条件を踏まえたうえであらゆる可能性を提示しなければならない。
「こうした事態もあり得る」「場合によってはこうなるかもしれない」といった複数のシナリオを並べ、最適な行動を判断するためのヒントを提供する。AIには、そうした役割を期待しています。
島田:そうですね。過去のデータだけをもとに予測モデルを構築すると、どうしても“シングルシナリオ”に陥りがちです。それでは災害の不確実性に十分に向き合えているとはいえません。だからこそ、リアルタイムの状況を捉える技術が重要になります。
私たちNTTドコモグループでも、2023年から「AIを活用した河川・ため池水位監視ソリューション」のトライアル提供を始めています。これは、物理的な水位計を設置する代わりに、現地のカメラ映像からAIが水位をリアルタイムに解析する技術です。映像上に仮想的な水位計を設定し、AIがその変化を監視することで、危険な水位に達した瞬間にアラートを自動で発信できます。
予測に加えて、災害の「リアリティ」を伝えることも大切です。近年は、現実の空間を仮想空間上に再現する「デジタルツイン」のような技術が進化しており、住居や街並みを三次元的に描き出すことも容易になっています。あるレベルの津波が迫った場合にどの程度の被害が想定されるのかを映像で示すこともできます。ちょっと怖い話ですが、自分や家族の分身をその空間に配置し、どのような状況に陥るかまで可視化できれば、危機感は格段に高まるはずです。
片田:ええ。AIやVR(仮想現実)といった技術は、防災訓練とも相性がよさそうです。例えば「水位があと1メートルで堤防を越える」と数値で伝えられても、なかなか現実味は湧きません。しかし、AIが生成した映像やVRで「堤防ギリギリまで濁流が迫り、激しい雨が降りつけている」という状況を再現すれば、現場の逼迫感をリアルに体感できる。そうした災害のリアリティを体験することが、より実践的な訓練につながるはずです。

──災害という不確実性の高い状況において、「人とAIの最適な関係」はどうあるべきだとお考えですか?
片田:生成AIは大きな可能性がありますが、社会全体としてはまだ受け入れるための地盤が整っていません。
繰り返しになりますが日本は災害過保護状態で、実際に被災した際に「ハザードマップが役に立たなかった、行政はどうしてくれるんだ」という責任追及に議論がすり替わってしまう。
こうした責任追及が生まれる構造は、生成AIを活用した防災においても避けては通れない課題になると感じています。
島田:すでに他業界では、似たような課題が顕在化しています。典型例がクルマの完全自動運転です。もしクルマが縁石に乗り上げたり、前のクルマに追突したりした場合は、ドライバーに責任が問われるものです。しかし、完全自動運転となるとそうはいきません。ドライバーに責任があるとは限らず、その結果「自動運転の開発企業が責任を負うべきなのではなのか」という議論に発展する。これでは企業側も二の足を踏んでしまいますよね。
さらに、「100%安全でなければ認められない」という社会的な空気も普及を阻んでいるように思います。しかし、現実には「100%の技術」などほとんど存在しません。この構造が変わらない限り、生成AIが真価を発揮するのは難しいでしょう。
片田:防災も生成AIも、根底に流れている課題は似ているようですね。
島田:そうですね。AIが防災の選択肢を提示すること自体は有効です。過去のデータから「徒歩では避難が難しいのでクルマを使いましょう」という判断材料を提示することも不可能ではありません。しかし、実際にはクルマを使うと、渋滞や土砂崩れといった想定外の事態が起こる可能性もあります。その際に「AIの指示に従った結果だ」という話になると、責任追及につながりかねません。
したがって、AIはあくまで「こういう選択肢がある」「それぞれにこうしたメリットとリスクがある」という情報を提示する役割にとどめるのが現実的です。最終的な決断はやはり使う人間に委ねるしかないと思います。

──最後に片田教授にお伺いします。防災分野において、NTTドコモビジネスに期待していることを教えてください。
片田:情報の受け手である国民のことをきちんと理解してほしいと思っています。技術やサービスを提供する側はどうしても「より正確で精緻な情報が望ましい」と考えがちですが、受け手の心構えや状況によっては同じ情報でも受け取られ方が大きく異なります。
「どこまで信用していいのかわからない」と懐疑的な人に向けた情報と、「万が一に備えて行動しよう」と思える人に向けた情報は異なる内容であるべきです。ですから、NTTドコモビジネス様には、国民や社会の状況を常にモニタリングし、それに応じたコミュニケーション設計に取り組んでいただきたいです。
島田:確かに、受け手のパーソナルな状況に意識を向けることで、より踏み込んだアプローチが可能になると感じます。家族構成や生活環境など、個々人の状況に応じた情報を提供することで、ただの警告ではなく、「自分ごと」として危険を実感できる。そこにAIの技術を上手く融合させることが新しい防災のかたちなのかもしれませんね。
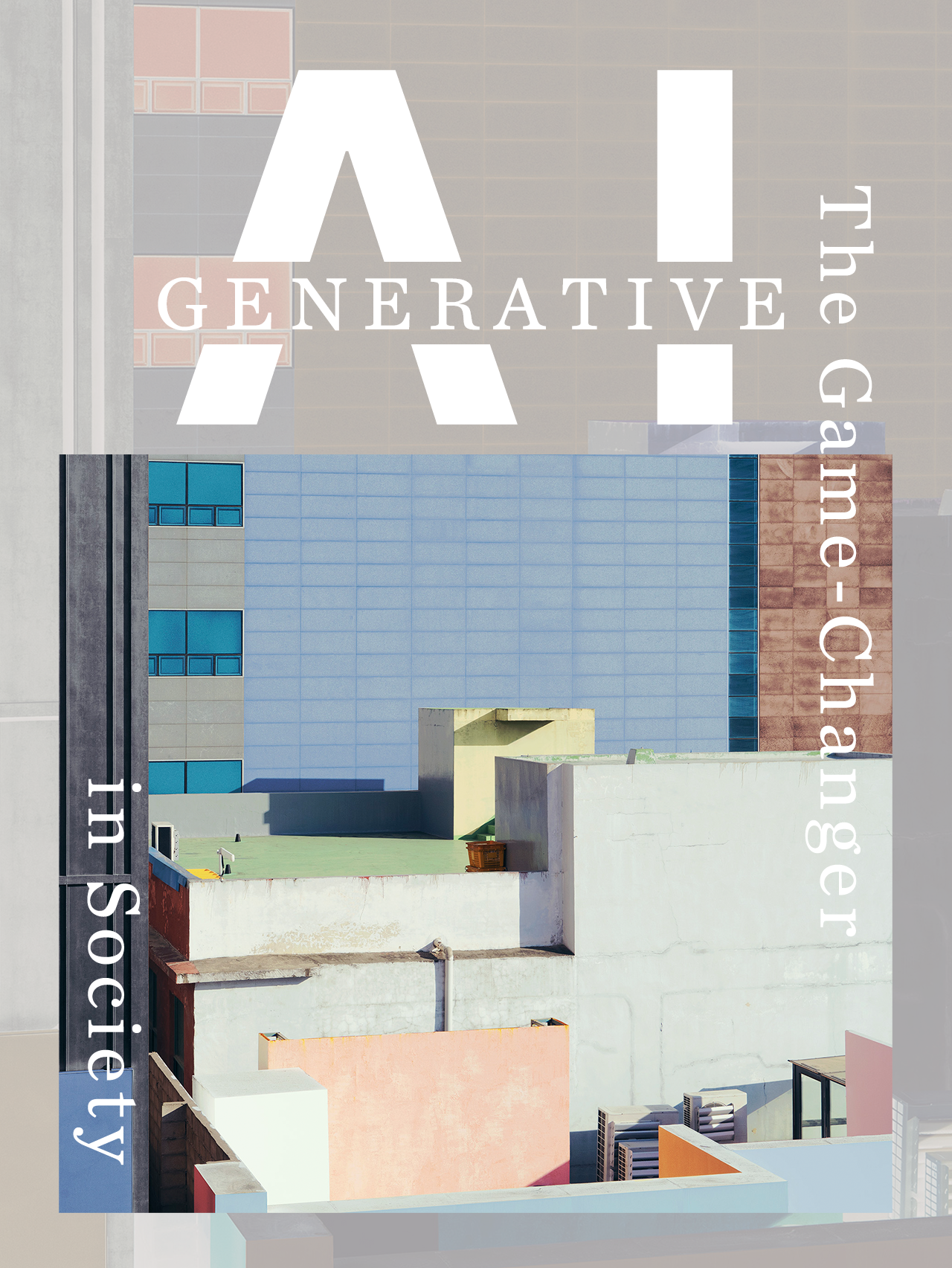
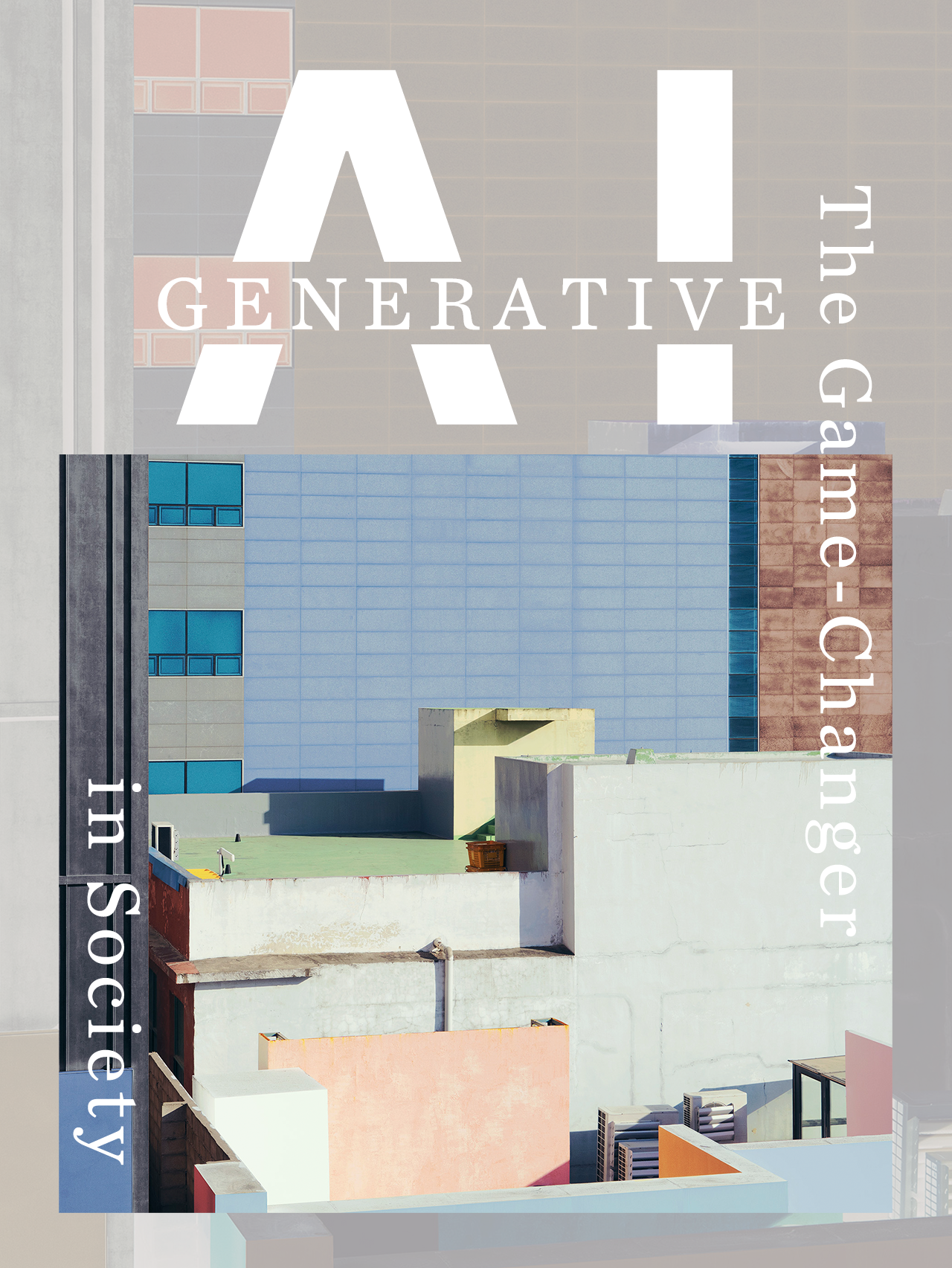
OPEN HUB
THEME
Generative AI: The Game-Changer in Society
#生成AI