
01
2025.03.06(Thu)
この記事の要約
日本企業の生成AI活用は欧米に比べ遅れており、導入済み企業は2〜4割にとどまる。背景には投資対効果への懸念や業務プロセス・データ基盤の未整備があり、現状は実証実験レベルにとどまる例が多い。一方で個人レベルの利用は広がり、全社的活用との乖離が顕著だ。さらに技術進化が目覚ましく、半年で状況が変わる「ゲームチェンジ・ラッシュ」への対応も課題となる。
大切なのはAIの仕組みを理解して進化を見通す力であり、AIを「脳」に見立て、手足や環境を整えることに大きな商機があると指摘される。雇用への影響も過渡期の産業変化と捉え、成果を得るにはデータのサイロ化解消やワークフロー再設計が不可欠で、現場理解・AI理解・権限の3要素が成功の鍵とされる。個人には「まず使いアウトプットを積み重ねる」姿勢が求められる。今後は労働力不足や製造業、IP産業など日本の課題や強みに根差した応用が有望で、海外展開も期待される。
※この要約は生成AIで作成しました。
目次
――『令和6年版 情報通信白書』の企業向けアンケートによると、日本企業で「生成AIを活用する方針を定めている」と回答した企業は42.7%だったそうです。一方、米国・ドイツ・中国企業の場合、同じ質問で約8割以上が「活用する方針を定めている」としており、大きな差があることが浮き彫りになりました。現在の日本企業において、生成AIの普及はどのような状況にあるとお考えでしょうか。
大野峻典氏(以下、大野氏):率直にいえば、やはり「普及が進んでいる」とはいえません。私たちAlgomaticでも、エンタープライズ向けにAIを事業の業務変革や組織づくりに組み込む支援をしていますが、実際はまだ「AIありきの新しいオペレーションを試している段階」で、しっかりと運用に乗っている企業は少ない印象です。
生成AIの技術進化は、確かにこの2〜3年で一気に進みました。とはいえ、すぐに「便利になったので、今日からAIを使ってください」とはいかない。というのも、AIを前提にすると業務フローそのものが変わり、新たにシステム導入や教育が必要になるためです。技術の進化に対してできることはまだたくさんあるけれど、やりきれてはいないな、というところですね。

ただ、これは時間の問題で、企業はやる気がないわけではありません。「生成AIを導入すべきかまだ迷っている」企業自体は多く、迷っている理由の大多数は「ROI(投資対効果)が見えない」というものです。今後1〜2年で各業界から成功事例が出てくるはずで、「この業界では、このように生成AIを導入して成果が出た」というケースが積み重なれば、ROIへの懸念も払拭され、普及は一気に進むと見ています。
――林さんはどうご覧になりますか?
林雅之(以下、林):先ほどの情報通信白書しかり、実際のデータを見ても、導入はまだこれからだと思います。先日発表された東京商工リサーチが公表した調査では、生成AIを導入している企業は全体の25.2%。大企業でも43%程度で、中小企業は23.4%にとどまるという状況にあることがわかりました。現状では、実証実験レベルの導入が中心で、全社的に本格運用されている例はまだ少ないと思います。
また、そういった段階でしばしばハードルとなるのが、「そもそもデータやシステムを標準化できておらず、まだ生成AIを効果的に導入できる段階に達していない」というケースです。私自身も以前、データマネジメントの仕事をしていましたが、企業内で組織のサイロ化が起きているケースも多く、データを集めて全社的なワークフローにフィットする形でAIを活用するのは、意外と難しいのです。大野さんが指摘しているように、業務プロセス自体を変えていく必要もあります。そのように全体から考えていかないと、やはりなかなか普及は進まないでしょう。

その一方で、個人的な業務タスクにおいては、誰もが意欲やスキルに応じて生成AIを活用できる状況にあり、部分的な業務効率化が進んでいます。アプリケーションのつくり方がわからなくても、自分で簡単なゲームをつくって遊んでみるという人も増えてきました。個人レベルでの局所的な活用が先行して進み、組織全体としての活用度合いとの乖離が深まりつつあるというのが、企業における生成AI活用のリアルな姿だと思います。
――全社的なAI活用を模索し始めた企業をさらに悩ませているのが、技術進化の驚くべきスピードです。ChatGPT o3リリースをきっかけに立案した当企画テーマも、取材時点ではもう陳腐化してしまうほどで、半年もたたずして基盤モデルの性能が飛躍的に向上し、「ビジネスモデルとして、どの時点での基盤モデル性能を前提とすべきか?」と迷う場面も出てきているかと思います。この進化サイクルの速さに対してどう向き合うべきでしょうか。
大野氏:大切なのは、技術への理解度を上げ、技術進化を見通すことです。AI技術はブラックボックスのように見えますが、理解を深めれば、その後に起こる技術革新を先読みしやすくなります。
o1で初めて搭載され、その後o3の公開で飛躍的な性能向上が大きな反響を呼んだ「Reasoningモデル(推論モデル)」ですが、実は以前から「複数ステップで思考させると、回答精度が格段に上がる」ことは理論的にわかっていました。仕組みを理解していれば驚きは小さくなりますし、次に何が来るのかもある程度読めるわけです。解像度を上げて理解する努力を諦めないことが、変化に翻弄されないひとつの方法です。
今の状況を俯瞰的に捉えると、現在はまさに「要素技術が生まれた瞬間」といえます。例えると、電気が発明され、そこから電化製品が次々と生まれたのと同じように、LLMという発明からさまざまな応用が広がっていく段階。まだ人類は「ここまでできる」とわかったばかりで、LLM開発におけるコスト削減や効率化など、技術の洗練に不可欠な周辺課題も解決されていません。だからこそ、今後も改良の余地は大きい。そうした前提に立って考えれば、進化のスピードに驚くことなく冷静に準備・対応できると思います。

林:おっしゃる通りですね。今後は大幅なコストダウンなどで普及のスピードもより上がっていくことが予見されますが、その上での展望として、企業はどのようなビジネス戦略を求められると思われますか?
大野氏:生成AIビジネスには大きく2つの立ち位置があります。「基盤モデルである“脳”そのものをつくる」こと、そして「その“脳”に手足や道具を与えて使いやすくする」ことの2つです。
AIは「純粋な脳みそ」のような存在で、検索やデータベースにアクセスさせる、業務マニュアルを読ませる、といった稼働環境さえ整えれば、AIの性能が向上するほど恩恵を受けられます。そこで私たちAlgomaticでは後者、つまり「AIが働きやすくなる環境を整える」ことに注力しています。
一方で、基盤モデルそのものをつくる道は非常に厳しい戦いになります。OpenAIやGoogleと直接競合することになるからです。もちろんそこに挑戦する方々を応援しますし、期待もしますが、私たちは「AIに手足を与える」立場で戦うのが合理的だと考えています。
林:なるほど。GPUの需要が急拡大し、データセンターの立地が追いついていない点なども踏まえると、サービス提供やアプリケーション開発だけでなく、AIを稼働させるためのインフラなどの「手足」においても、大きなビジネスチャンスがあるといえそうですね。我々も通信事業者としてネットワーク強化を求められていますし、インフラ領域も含めた「AIに手足を与える」ビジネスはこれから最盛期を迎えるでしょう。
また、今から基盤モデル開発競争の最前線を目指すのは確かに厳しいのですが、最近では文化的主権や安全保障確立の観点から自国内でのLLM開発を重視する「ソブリンAI」の動きも起こっており、NTTグループでも日本語特化の国産LLM「tsuzumi」の開発・提供や、一般に「ガードレール系」と呼ばれる、生成AIの入出力における安全性・信頼性・倫理性を確保するための制御ツール/サービス群の開発にも注力しています。
生成AIの技術理解に加えて、生成AIがもたらす新しい社会や文化のあり方などへの解像度を高めることも、今後ニーズが高まるビジネスを構想するヒントになるのではないでしょうか。
――ここからは、さらに踏み込んだテーマについてもお伺いしていければと思います。生成AIの大規模な開発投資やビジネス活用が進む一方で、その競争をリードするアメリカでは、雇用削減のためのレイオフや、エンジニア系新卒採用における就職氷河期の到来などのニュースも連日報じられ、“ねじれ”の顕在が見てとれます。根本的な疑問として伺いたいのですが、そもそも本当に生成AIビジネスで成果を上げられるのでしょうか。
大野氏:確かに、ビッグテックの株価がどんどん上昇しているのに、レイオフの頻発や就職氷河期が訪れるのは一見矛盾して見えます。ただ、AIの進化によって削減される仕事と、新たに創出される仕事とのバランスは基本的に変わらないはずです。
企業からすれば、コスト削減できた分の利益の再投資の先に新たな雇用も計画しているでしょうし、働き手はといえば、AIによって創出される新たな職業や、AIに代替されにくい領域にキャリアやスキルを寄せていく期間が必要です。今は産業の構造変化の過渡期にあり、新たな構造への適応に時間がかかっている、という見方をしています。
林:企業は採用・育成戦略やガバナンスなどにおいてもAI活用を前提に見直ししていかなければならないですし、これまで外注してきた業務のAI活用による内製化など、リソース配分やワークフローを変革する副作用としても、そういったニュースが増えている部分はあるでしょうね。
ですが裏を返せば、それは生成AIの効果を最大化するための仕組みが着々と構築されているということでもあります。先ほども述べましたが、ツールとして生成AIを導入するだけでは、個人が文章作成する程度で終わってしまい、ビジネスが拡大しません。生成AIで成果を上げるためには、部門を問わず、社員の誰もが業務の中で当たり前に生成AIを活用できる仕組みをつくることが大切です。
そのためには、社内にあるデータをしっかり集めて、使える形に整えなければなりませんが、多くの部門では、データを出したがらない傾向にあります。そこでデータのサイロ化を解消し、業務プロセスをAIに合わせて再設計する必要に迫られる。AIを前提とした業務改革を進めるには、そうした一定のコスト・時間的な負荷を要するアプローチも求められるはずです。

――大野さんの会社では、企業が生成AIを活用して生産性や売り上げを上げる支援も手掛けられていますが、どのような取り組みが必要だとお考えですか。
大野氏:林さんのおっしゃる通り、まずはワークフロー全体を再設計しなくてはなりません。例えばシステム開発も、生成AIによってコードを書く作業が楽になれば、AIから出てきたコードをもとに設計するなどプロセス自体が変わっていきます。マーケティングや営業のプロセスも、従来のようにインサイドセールスやフィールドセールスといった人間の分業モデルではなく、AIと人の分業を前提にした一気通貫のワークフローが考えられます。
そんなワークフロー再設計にあたり、重要なケイパビリティが3つあります。第1に現場の課題やオペレーションを理解していること、第2にAIの特性や得意領域を理解していること、最後にオペレーションを変えたり介入したりできる権限を持つことです。この3つが揃って初めて、AIを活用した業務改革は効果を発揮します。私たちのプロジェクトでは、ステークホルダーを巻き込みながら、この3つを同時に満たすように支援しています。従来のDXではなく、AIを前提にした業務改革「AX(AI Transformation)」ですね。
――それでは、企業から個々のビジネスパーソンにフォーカスして、生成AIのスキルについてはいかがでしょうか。ChatGPTなどが登場した当初は、いかにうまくAIに質問するか、プロンプト技術が注目されていました。しかし今は、むしろそういったスキルはAIの進化によって陳腐化してしまい、「AIをどう活用するか」という総合的なスキルをどう身につけるかが課題になっています。この点についてどうお考えでしょうか?
大野氏:人間の脳は、技術進化に応じて抽象化レベルを上げ「では、この技術をどのように使うか?」と切り替えて理解するものです。スマートフォンもどんどん進化していますが、その進化に合わせた使い方を自然に身につけていきますよね。加えて、仮に身につけたスキルがすぐに陳腐化してしまったとしても、使わないことによる機会損失を上回ることはないと考えています。
であるならば、まず根本的なマインドセットとして「いったん使ってみる」ことが非常に重要になってきます。問いを思いついたらその場でAIに投げてみる。上司や同僚に聞く前に、まずAIに質問してみる。それだけでも、かなりAIネイティブなスキルが身につくと思います。まず使う、アウトプットを繰り返す、そして目的意識を持つ。これが生成AIスキルを自然に身につけるためのプロセスですね。

林:私もアウトプットを習慣化することが一番大事だと思います。私自身、生成AIを活用して毎日ビジネスブログを書いているのですが、最初のうちはAIにどれだけ指示しても思うように記事が書けず、使用割合はせいぜい2割ぐらいでした。しかし最近では、モデルのアップデートによる恩恵もあって、7〜8割くらい自分のイメージ通りの記事を出力できるようになり、ひと月に50記事ほど書けるようになりました。
また、生成AIを使って英語や中国語、イタリア語など読めない言語の情報を翻訳して記事にすると新しい発見も生まれますし、海外の政府動向を記事にするなど、日本のメディアとの差別化にもつながりました。さらに生成AIを執筆の道具として使うだけでなく、自分の感性にフィットするグローバル・リサーチャーとしての活用法を見つけたことで、付加価値も生まれたのです。使い続けること、そしてアウトプットを積み重ねることが、自分なりの生成AIスキルセットを見つける鍵だと思います。
――グローバルというキーワードを踏まえてお伺いしますが、グローバル市場において日本企業は今後、生成AIをどう活用し、プレゼンスを確立していくべきでしょうか。
大野氏:日本固有の事情と、そうでない部分とを分けて考えることが必要だと思います。
まず日本特有ではない点からいうと、アプリケーションレイヤーはまだまだ全員に平等にチャンスがある領域です。基盤モデルの開発競争は、大企業や限られたプレーヤーしか参入できませんが、アプリケーションレイヤーではまさにインターネット黎明期のように、どんなサービスが広く使われるか誰にも読めない状況です。だからこそ多様なサービスが試され、その中から大きく成長するものが出てくるのだと思います。
一方で、日本特有の事情を活かした戦略は2つあります。1つは「労働力不足」という課題起点で、この課題を生成AIで解決するサービスは、その傾向が顕著な日本で成長する可能性も高いはずです。私たちAlgomaticが取り組む採用支援やアポイント獲得支援なども、生産性向上を軸にしています。
もう1つは産業起点で、日本がすでに強みを持つ製造業や、アニメ・マンガといったIPビジネスなどの領域に特化したAI活用では、よりクリティカルなイノベーション創出が可能であると見込んでいます。私たちも今後、製造業向けソリューションの開発を進めていく予定です。
――最後に、林さんはどうご覧になりますか。
林:私も大野さんのご意見に賛成です。特に業界や専門領域に特化した生成AIアプローチは、まだ十分に開拓されていません。製造業やコールセンターなど、多くの人手が必要な領域ではAIとの役割分担が有効ですし、それをパッケージ化して展開することが重要になるでしょう。
アメリカではホワイトハウスが「American AI Technology Stack」を発表し、インフラや半導体にとどまらず、製造業や医療などを産業ごとにパッケージ化し海外展開しようとしています。日本も同じように、課題先進国である強みを活かしつつ、国内に閉じるのではなく、海外市場に向けたビジネスモデルを考えるべきです。
生成AIビジネスは、飛躍的な翻訳の精度向上も相まって、グローバルに展開しやすい特性を持っています。だからこそ、日本発のソリューションが海外に広がり、逆に日本にフィードバックされるような循環も期待できると思いますし、そういったビジネスを共創/支援できるよう、今後も生成AIビジネスの輪を拡大していきたいですね。

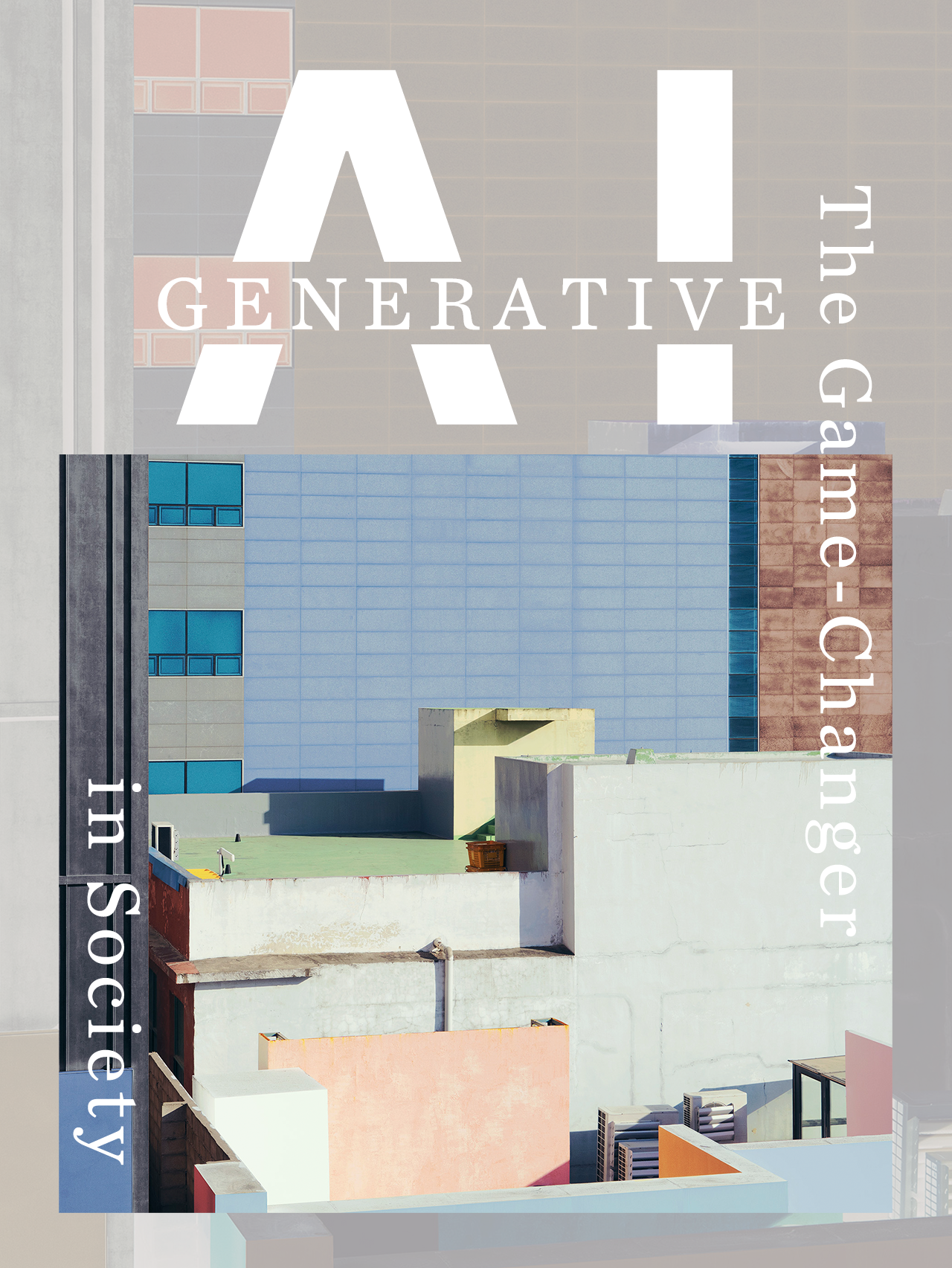
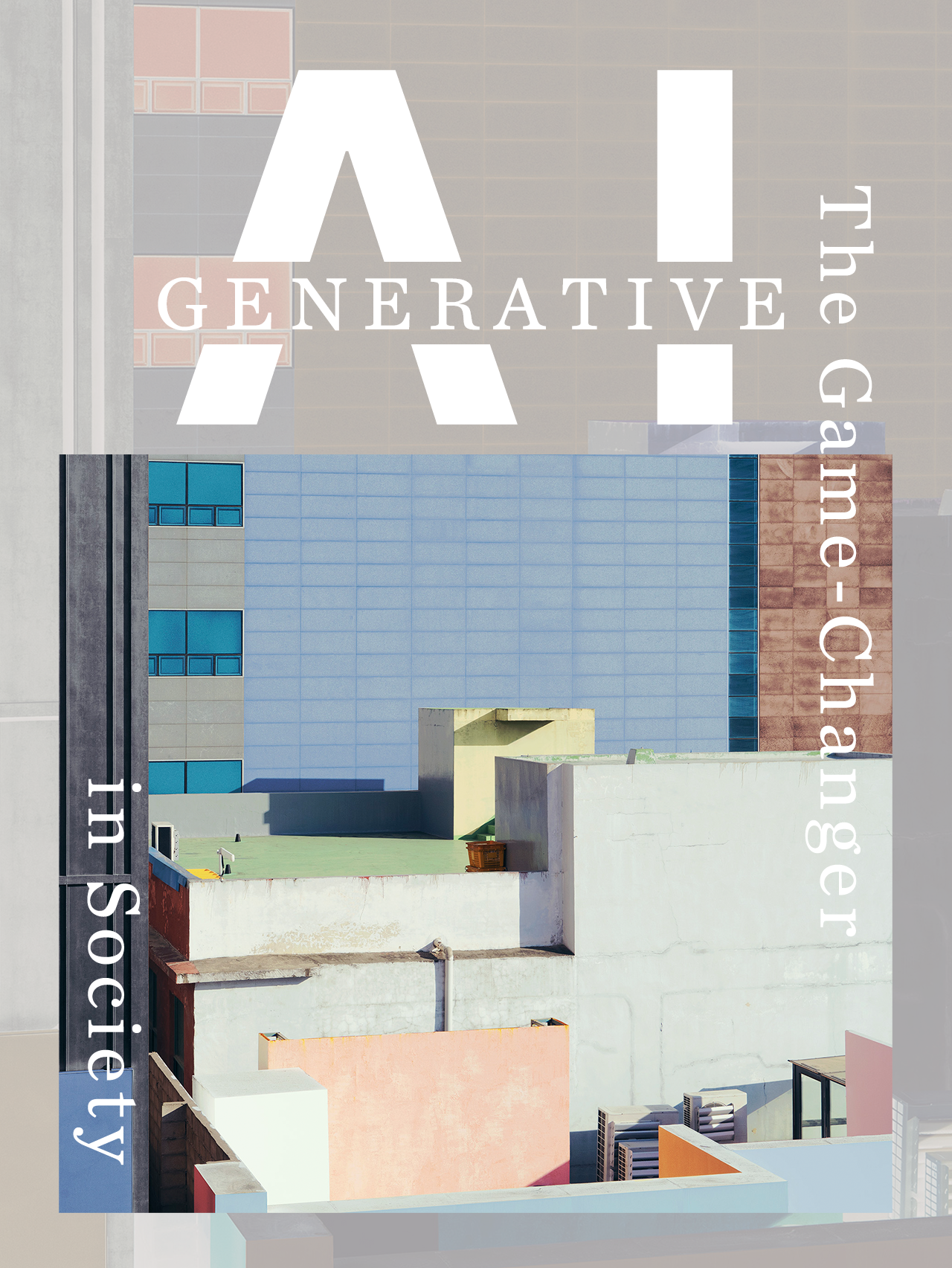
OPEN HUB
THEME
Generative AI: The Game-Changer in Society
#生成AI