
01
2025.07.18(Fri)
この記事の要約
日本の超高齢社会を背景に、認知症予防が重要視される中、理化学研究所の大武美保子氏とNTTドコモビジネスが「会話」を通じた認知機能の維持に注目。大武氏は会話支援手法「共想法」やAIロボット「ぼのちゃん」を開発し、社会実装を推進。NTTドコモビジネスは「脳の健康チェック」サービスを展開し、早期発見と企業の健康経営支援に取り組んでいる。日常的な会話を通じた予防の仕組みづくりが、持続可能な社会の鍵となると提言している。
目次
田畑氏(以下、省略)――本日はどうぞよろしくお願いします。まずは、大武先生をお迎えすることになった経緯からご紹介したいと思います。
NTTドコモグループは、2002年7月にNPO法人モバイル・コミュニケーション・ファンドを設立し、学術・福祉などの幅広い分野における情報通信関連の取り組みを20年以上にわたり支援してきました。毎年、優れた研究成果や論文などをドコモ・モバイル・サイエンス賞として表彰しています。2024年に選考委員特別賞を受賞した大武先生の研究「認知的健康につながるコミュニケーション支援技術の開発」は、認知症対策という点で弊社と共通の課題意識をお持ちでいらっしゃることから、ぜひ意見交換をさせてもらいたいと対談への参加をお願いしました。
大武先生は、会話と認知機能の関係性という心理的側面に着目され、加齢とともに低下しやすい認知機能を活用する会話支援手法「共想法」を独自に考案されています。また、AIロボットを使って生活に共想法を取り入れる技術を開発し、認知症予防に関心がある当事者の皆さんと利用評価を重ね、改良にも取り組まれています。こうした先生の活動と、NTTドコモビジネスが提供するDXソリューションを組み合わせることで、お客さまや、お客さまのサービスを利用する多くのエンドユーザーの皆さま、さらには、弊社の従業員やパートナーといったさまざまなステークホルダーと、サステナブルなデジタル社会の実現に貢献していけるのではないかと期待しています。

大武氏:ありがとうございます。私は理化学研究所の革新知能統合研究センターで認知行動支援技術チームのチームディレクターを務めており、高齢者の認知機能低下と認知症を予防するための認知行動支援技術を研究開発しています。一方で、「NPO法人ほのぼの研究所」も運営し、特に認知症予防をテーマに地域の高齢者の皆さんと当事者研究を進めています。私自身、研究者である前に自分も認知症の当事者になりうる一人として、超高齢社会と認知症に対する危機感を強く持っており、研究成果をいかに社会実装していくかということを常に考えています。
――日本は世界でもっとも高齢化が進んでいると言われますが、認知症の広がりというのはどのような状況なのでしょうか。
大武氏:認知症は今、日本だけでなく世界的に深刻な課題です。実は認知症のリスクファクターの中には「教育機会が少ない」ことも含まれており、低中所得国でも平均寿命の延びとともに認知症患者が急激に増加しています。
日本では2019年に認知症施策推進大綱が策定、2024年には共生社会の実現を推進するための認知症基本法が施行され、「共生」と「予防」を両輪とした取り組みが進められています。しかし、2040年には認知症もしくは軽度認知障害(MCI)*の人が1000万人を突破すると予想されており、誰もが当事者、当事者家族になり得る、まさに社会全体で取り組むべき課題と言えます。
* 軽度認知障害(MCI):日常生活に支障はなくても、認知機能の低下を感じている、同年代の人と比べて認知レベルが低下している状態のこと
――大武先生が、認知症予防のヒントとして「会話」に注目されているのはなぜなのですか?
大武氏:私が会話の効果に注目したきっかけは、祖母が認知症になった経験からでした。祖母の会話の繰り返しが極端になり、話していてもすぐに振り出しに戻るような状況になったのです。しかし、こちらが質問をしたり、写真を見せながら話したりすると、繰り返しの思考回路から外れて、今までと違う話が出てくることに気づきました。
生活行動の工夫によって脳内のさまざまな神経ネットワークを活用する生活をすると、神経細胞が一部死滅しても、代替の神経ネットワークがあることにより、認知機能が保たれて認知症になりにくいということは、多くの研究で明らかになっています。この仕組みに基づいて考えると、脳内のさまざまな神経ネットワークを活用する会話は、一言でまとめると、頭を使う会話です。一方的に自分の言いたいことを言って、相手の話を聞いていない場合は、脳が十分に働いていません。相手が発する音声を言葉に変換し、言葉から意味を取り出して、さらに、意味から相手の意図を推定する、という、丁寧に相手の話を聞く場合に行われる一連の処理をしていないからです。相手の言葉を受けて返す会話であること、自分から話す場合には、相手にどのように伝わるかを意識すること、つまり会話の質が重要なのです。
会話の質を変えることができれば、わざわざ脳をトレーニングする時間をつくらなくても、普段の会話を通じて脳の健康を保っていくことが可能になります。これを、「脳が長持ちする会話」と名付け、認知機能に与える効果を検証しています。

横山氏:普段の会話の中で脳の健康を保っていくという点は、私たちNTTドコモビジネスが目指している認知症対策にも通じます。「脳の健康チェック」は、「認知症で不安になる本人・家族・企業が少なくなる社会を目指す」をコンセプトに、日常の中で、まるで血圧や体重を計るように気軽に脳の健康を確認してほしいという思いで開発しました。
利用者が脳の健康チェックダイヤルに電話をかけて簡単な質問に答えると、発話時の音声の特徴やパターンをAIが解析して、利用者の認知機能の状態を把握し、わずか数分で認知機能のチェックが完了します。認知症の早期発見につながるサービスとして、企業や自治体にご利用いただいています。
大武氏:認知症は進行性の疾患ですから、早期に発見し、適切な治療を受けることが大切です。しかし、実際には物忘れなどの初期症状があっても、受診までには「本人が病院に行くほど深刻に受け止めていない」「家族が連れていこうとして断られる」「医師と対面するのが怖い」「病院に行くのを近所の人に見られたくない」など、いくつもの物理的・心理的障壁があります。その点、「脳の健康チェック」は、高齢者が操作しやすい電話を使って、自宅で簡単に認知機能をチェックできるので、とても良いサービスだと思います。
認知機能の評価は、他人との比較ではなく「今の自分と過去の自分を比べてどうなのか」という視点が大切です。定期的にチェックを受けることで、早期発見につながりますね。
横山氏:ありがとうございます。脳の健康チェックのような「認知機能の低下を早期発見する仕組み」と、大武先生が研究を進めている「認知症を予防する取り組み」の組み合わせは、今後重要なファクターになると感じています。実際に、事例も生まれています。兵庫県養父市で2025年6月からスタートした「ヘルスケアチェックサービス」です。
養父市では、地域に住んでいる独居の高齢者が家にこもってしまって出てこないなど、つながりの希薄化が起きており、こうした方々を要介護状態にしたくないという課題がありました。そこで、市が運用するパーソナルデータ連携基盤を活用し、認知機能の状態と生活環境の状況をチェック。その結果と個人の健康情報などを組み合わせてAI分析し、一人一人に適した社会参加やつどいの場の情報を提供する取り組みをスタートさせました。「脳の健康チェック」は、認知機能を把握するためのツールとして採用いただいています。高齢者自身が認知機能の変化に気づくきっかけを提供するとともに、個人ごとに適する社会参加を促すことで、認知症の予防にもつなげることができると考えています。
このように、私たちは「認知機能の低下を早期発見する仕組み」を提供してきましたが、これからはさらにそれを日常生活の中に溶け込ませていかなければいなりません。会話を通じて認知症を早期発見するだけでなく、こうしたコミュニケーションによって認知症の予防にもつなががっていく取り組みを、今後積極的に展開していきたいと考えています。

――大武先生が開発された「共想法」について、詳しく教えていただけますか?
大武氏:「共想法」は、2006年に認知機能を活用する会話を構造化し考案した会話支援手法です。数人で行うのですが、参加者は「最近、食べた物」や「最近、出かけたこと」などあらかじめ決めたテーマに沿って写真を持参します。共想法により、言葉を取り出すために必要な機能である言語流暢性が向上することを、ランダム化比較試験により検証しました。言語流暢性は、認知的柔軟性と言って、柔軟な思考プロセスを支える認知機能として知られています。脳が柔軟に働くようになると言えます。
例えば4人で行う場合、1人につき写真2枚、1枚につき1分ずつ合計8分間といったルールで、全員が写真について話題を提供するわけです。4人で写真2枚ずつですから、8つの話題が終わったところで、今度は質問の時間です。1人につき4分間(写真2枚分)、みんなでその人が話した内容について質問をします。準備をして話すこと、その後に「質問のシャワー」を浴びながら答えていく過程で、脳の認知機能を活用できるのです。
私が特に重要だと考えているのは、今、そして最近にフォーカスした内容であることです。体験や興味があることなど、現在進行形の話題を扱うことで、年齢や経歴に関係なく誰でも会話に参加することができます。記憶機能については、新しいことを覚える機能が、覚えたことを思い出す機能より先に衰えることが知られています。今や最近にフォーカスすることで、新しいことを覚える機能を使い、使わないことにより衰える確率を下げるのです。
横山氏:その会話というのは、活発なミーティングのようなものですね。ビジネスシーンでも「会議で発言をしたがらない人がいる」と聞くことがありますが、「健康にいいから喋りましょう」「認知機能を刺激していきましょう」とファシリテーションしたら、理想的な議論ができそうです。
――先生はほのぼの研究所での共想法の実践で、独自に開発されたAIロボットを活用されているそうですね。
大武氏:はい。私たちのチームで開発した会話支援ロボット「ぼのちゃん」に司会進行をしてもらっています。ぼのちゃんは、タイムキーパーを務めると同時に、参加者の会話量を測定。発言が少ない人には「いかがでしょうか」と促し、一方的に話す人がいる時は適切に止めたりもします。その名の通り、ほのぼのとした風貌をしているので注意をしても角が立ちにくく、場の雰囲気は朗らか。ぼのちゃんが司会進行をすることで、参加者が均等に会話に参加できます。共想法の体験会に参加された方から、「会社の会議に使いたい」という声をいただくこともよくあります。
――ビジネスの世界では、ファシリテータースキルは強く求められますので、共想法の手法を使ったビジネスパーソン向けの研修や、ソーシャルワーカー、派遣会社向けの資格制度としても広げていけそうですね。研究成果を社会に実装していくための取り組みというのは、進んでいるのでしょうか?
大武氏:はい、脳が長持ちするために必要な知識を身につけられる「長持ち脳検定」の開発に取り組んでいます。この検定の普及を通じて、日常生活の中で認知症予防につながる活動を無理なく実践する人を増やし、脳が長持ちする社会の実現に向けた一助としたいと考えています。
これまで認知症予防の研究を進める中で、70代を中心に延べ1万人以上の高齢者の方々と接してきました。そこで改めて気がついたのは、認知症には発症する確率を下げるための対応策があり、40代・50代のうちから取り組むことが重要だということです。
そもそも認知症とは「脳や身体の疾患を原因として、記憶や判断力などの障害が起こり、社会生活が送れなくなった状態」を指します。原因の約7割はアルツハイマー病などの神経変性疾患によるもの。約2割が脳血管障害、約1割がその他の疾患によるものです。このうちアルツハイマー病は、発症の20〜30年前から神経変性が始まるとされていますので、70代に発症する人の神経変性は、早くて40〜50代から始まることになります。
神経変性や脳血管障害の予防策として重要なのが運動と食事です。また、認知症を発症する程度に脳の神経細胞が死滅しても、脳内の神経細胞同士のつながりが保たれていると、認知機能を維持できる可能性が高いことも分かっています。こうした研究の成果を、より多くの方に知っていただき活用してもらいたいと思っています。
ただ、日本では健康でいることは当たり前という考え方があり、認知症の「予防」はビジネスになりにくいという課題も感じています。

横山氏:お客さまに対して、いかに自然な形で認知機能のチェックや予防ができるかは、ビジネス化を考える上で欠かせない視点です。実は、「脳の健康チェック」サービスの開発は、金融業界のお客さまからの相談もきっかけの1つでした。金融業界では、2030年に認知症患者の金融資産が215兆円になるという予測があり、高齢者への対応をどうするかが大きな課題です。利用者の認知機能が低下している恐れがある場合、サービス利用に関する意思決定が正しく行われたかどうかが曖昧になってしまうからです。
大武氏:かといって金融機関の方が、窓口で預金や投資を考えているお客さまに「認知機能のチェックを……」とは話しにくいですよね。
横山氏:まさに、そういうご相談をいただいており、金融業界のお客さまに「脳の健康チェック」の導入を提案しているところです。大武先生の共想法のお話を聞いていて、金融のお客さまを例にとると、生命保険業の営業の方が高齢のお客さまとコミュニケーションしながら生活の中での心配事や商品への要望を引き出していく会話には、脳の健康にいい効果があるかもしれないと思いました。
――社会実装という意味では、企業が健康経営の一環としてビジネスケアラーの支援に取り組むことも重要です。現状では、家庭での介護の担い手が女性になることも多く、女性活躍推進の観点でも問題があります。社員だけでなくその家族に対しても、早期発見や予防の仕組みを提供していくことについては、どう思われますか?
横山氏:今後そういったニーズは高まっていくのではないでしょうか。また、認知症対策の有無に関わらず、日頃の親子のコミュニケーションの中で、中高年世代の子どもが高齢世代の親のやりたいことを引き出すような会話を意識的に心がけていくのも、やるべきことかもしれませんね。
大武氏:まさにその通りです。例えば、旅行中にどちらのレストランにするかを親に決めてもらう、一緒に「推し活」をしてみる。そういったことで脳を活用できます。特に「推し活」は、外に出かけることで体力がつきますし、人との交流を前向きな気持ちで取り組めるすばらしい活動だと思います。
マイナスを防ぐ「予防」ではなく、日々の活動の中でプラスを増やしていくことが、結果的に「予防」につながっていく。そんな意識を持ちたいですね。
――日常の中に非日常に向けた対策を取り込んでいくことは、サステナビリティの観点でとても理にかなっています。遠隔でのコミュニケーションは私たちの生活に欠かせなくなっていますが、デジタルの活用についてはどのようにお考えでしょうか?
大武氏:コロナ禍中は、コミュニケーションが取りづらくなり、認知症が増えたとも言われています。ほのぼの研究所でも、オンラインでの共想法の実践に取り組んでいます。
その中で、気になっていることがあります。それは、インターネットで人と人はつながりましたが、本当に有効な情報がやり取りされているのかどうかという点です。これは企業の事業領域にも関わってくるかもしれませんが、人と人をつなぐ先にあるコミュニケーションの質にも踏み込んでいくべきではないでしょうか。情報の流通には、ものすごいエネルギーが使われています。人や社会にとってより良いコミュニケーションが生まれるようにすることが、真のサステナビリティには必要だと感じます。

――非常に共感できるご指摘です。NTTドコモビジネスは「産業・地域DXプラットフォーマー」として、安心・安全な通信を提供することはもちろんのこと、つないだ先にあるコミュニケーションの品質まで高められるようなデータ利活用を目指していきたいと思います。それでは最後に、今後の研究や事業展開について、お二人それぞれの展望をお聞かせいただけますでしょうか。
大武氏:基礎研究としては、会話の有効性をより体系的に捉えて明らかにしていくとともに、認知機能検査についても、脳波や生理信号などの微細な変化を捉えてより正確に把握できるようにしたいですね。
社会実装という点では、日常の生活と会話に工夫を加えることで認知症予防ができる世の中をめざしていきます。デジタルを活用しながら、40代・50代から、さらには全世代で取り組める対策を、より自然な形で実装できるように取り組んでいきます。
横山氏:NTTドコモビジネスは、金融、小売・通販、介護・医療といった領域とも深く関わっています。これらの領域では、安定的なサービス提供のため、エンドユーザーの認知機能の把握や認知症の早期発見・予防が非常に重要です。そうしたニーズに応えていけるよう、大武先生のような学識者と連携し「脳の健康チェック」の機能向上に取り組むとともに、お客さま企業と一緒に、エンドユーザーとのコミュニケーションを通じてどういった価値をご提供できるのかを意識しながら、プラットフォームをご提供していきたいと思います。
また、企業の健康経営につながるサービスも揃えていますので、福利厚生の仕組みも使いながら、従業員と家族をつなぎ支援していくことも考えていきたいです。
――私たちは誰もが認知症の当事者になる可能性があります。これは個人の問題ではなく、社会全体で取り組むべき課題です。企業、自治体、個人それぞれができることを考え、連携していくことで、認知症を恐れることなく、最後まで自分らしく生きることのできる社会を実現していきたいと思います。
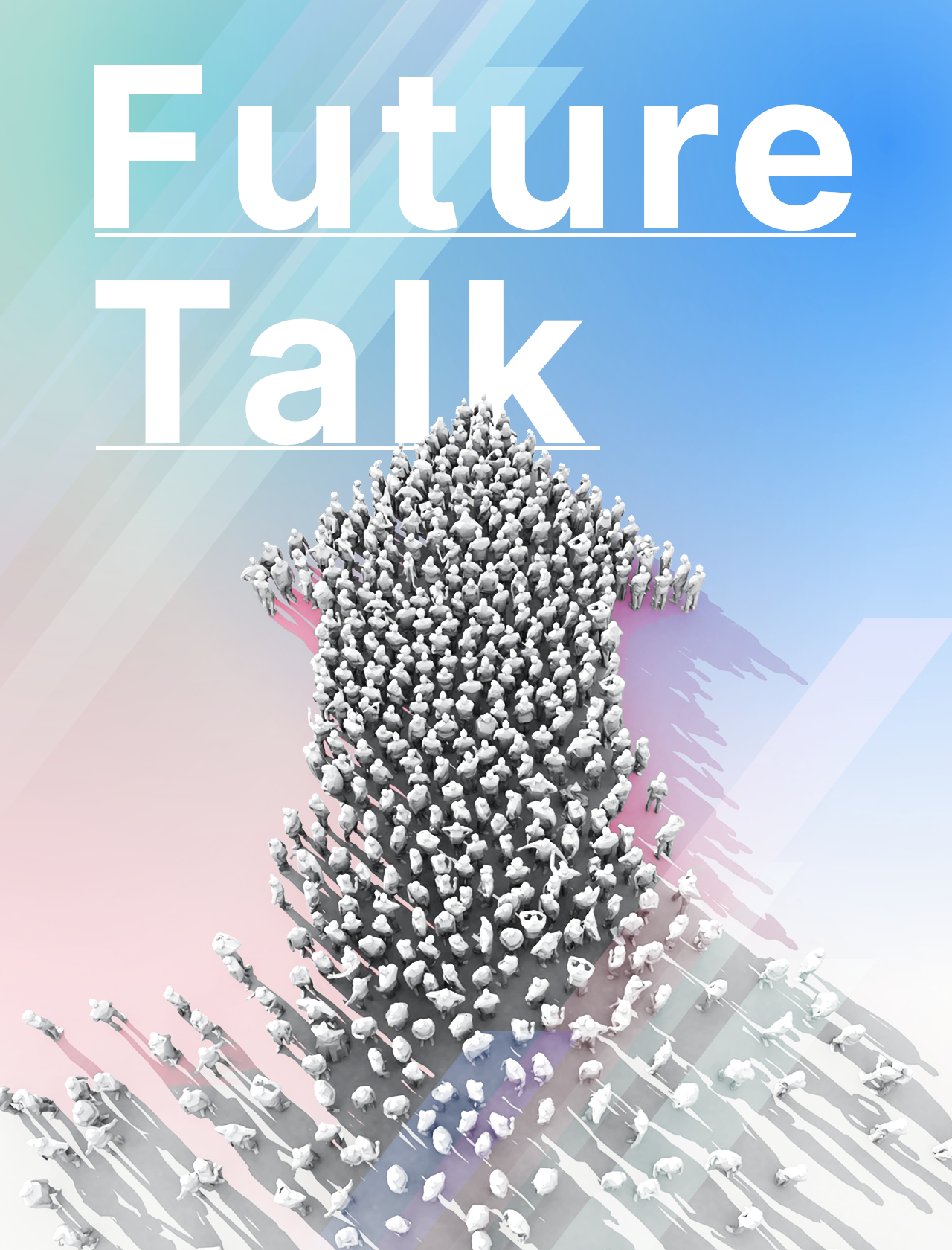
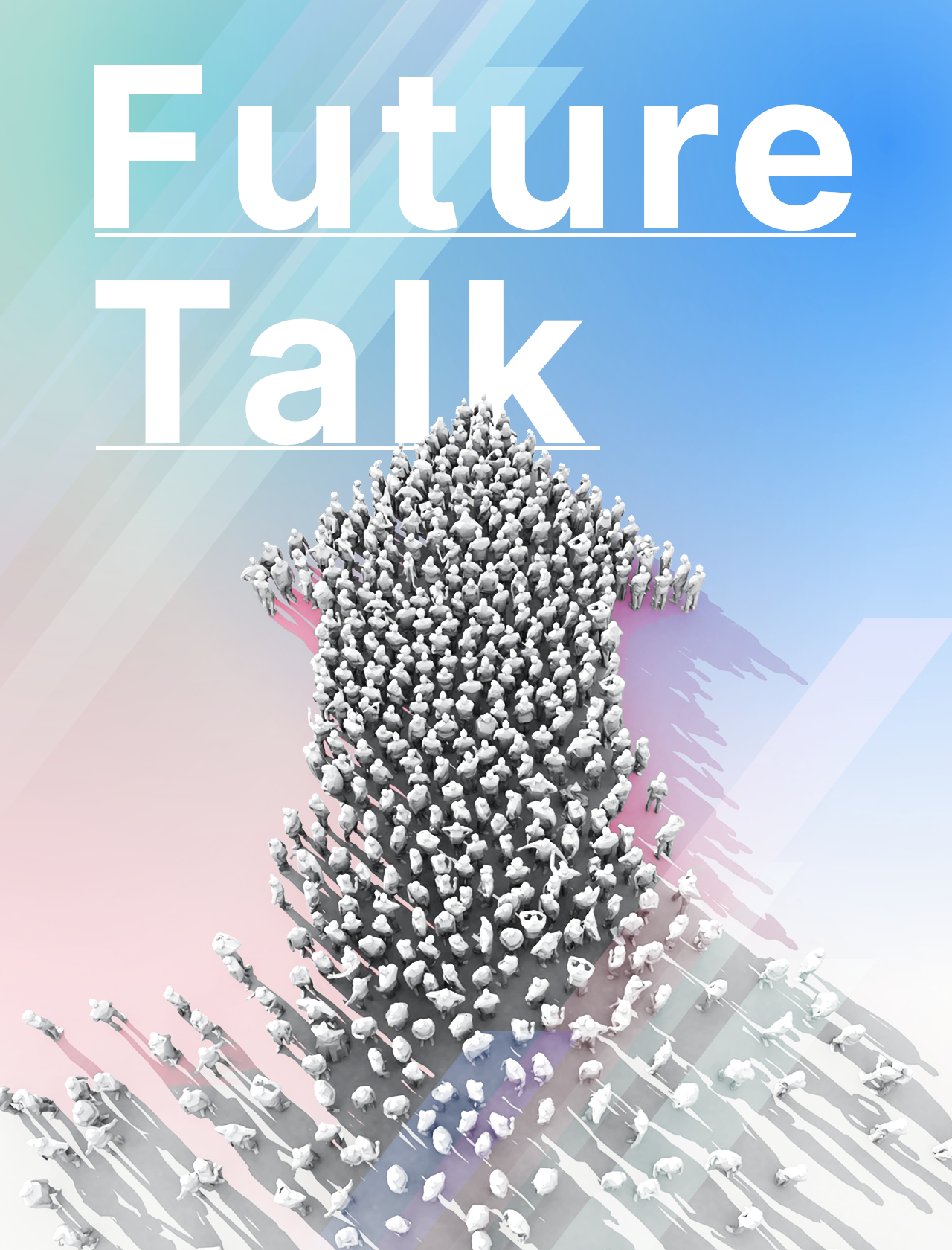
OPEN HUB
THEME
Future Talk
#専門家インタビュー