
01
2025.07.18(Fri)
Future Talk
2025.07.30(Wed)
目次
――まず、2018年に経済産業省が『DXレポート』を出した背景からお聞かせください。
DXレポートは、端的にいえば日本の経済界や産業界への警鐘です。2018年はIoTやAI技術によりビジネスモデルの変革が始まるタイミングで、グローバル市場では競争環境が激変。この流れに置いていかれると、日本の失われた30年が、40年、50年と長引く危機感がありました。そこで、日本全体の機会逸失を回避するため、企業のDX経営を国家レベルで推進していく意思を表明したのがDXレポートです。
DXレポートが指摘した本質は、経営全体の改革です。システム刷新だけに目を向けて表面的な改善を試みても、ゲームチェンジャーにはなれません。経営者は従来の経営を振り返り、システム刷新と経営改革を一体で考える重要性を理解しなくてはいけません。
――2018年のDXレポート発表から7年。企業のDXを取り巻く状況は変化しましたか。
2018年に公表されたDXレポートではレガシーシステムを抱える企業は約8割に上っていましたが、今回のレポートでは約6割に減少しており、着実に進展しています。しかし、その進捗は非常に緩やかです。こうしたレガシーシステムを最新の仕組みに置き換えるモダナイゼーションには、特にシステムの規模が大きい場合は通常3〜5年の期間を要します。しかも、必ずしも順調に進むとは限らず、途中で予期せぬ問題が発生してさらに期間が延びることも珍しくありません。
レガシーシステムの刷新が遅れている背景には、技術的・経営的な要因の両方が複雑に絡まっています。技術的な側面は、複雑化(肥大化)・老朽化・ブラックボックス化の3つの問題が主な要因です。まずは、既存のシステムに新しい機能を次々と追加していくことで、全体が複雑で巨大になり、管理が困難になってしまう。その結果、システムを構成するソフトウェアやハードウェアのサポートが終了したり、当初のシステムの開発担当者や運用担当者が退職などでいなくなったりして、古い技術の維持が難しくなり老朽化が進む。さらに、仕様書が不十分で失われている場合も多く、なぜその機能が動いているのか誰も説明できない状態、いわゆるブラックボックス化に陥ってしまうのです。

――経営的な要因についても教えてください。
まず最も大きな要因は経営者の意識にあります。システム刷新には多額の費用がかかり、一時的に利益が減少する可能性もあるため、自身の任期中にリスクを取りたがらない経営者は少なくありません。システムが稼働しておりビジネスも支障なく回っている状況では、差し迫った危機感が生まれにくく、結果としてレガシーシステムを使い続けてしまいます。多くの場合、大きなトラブルに直面して初めて、経営層が事の重大さに気づく。これがレガシーシステムの怖いところです。
欧米の経営者には、ビジネスとシステムを不可分のものと捉え、両者を一体でトランスフォームしていくマインドが根付いています。一方、日本の場合は、システムはあくまで業務のための道具と捉えられ、そこにかける費用は投資ではなくコストと見なされがちです。こうした意識の下に生まれたのが、システム構築を外注するSI(システムインテグレーション)ビジネスです。
――確かに、多くの企業では、システム開発は外注するのが一般的です。
システム構築をベンダーに委ねすぎることは、企業のITリテラシーを著しく低下させ、いわゆるベンダーロックインの状態に陥るリスクを高めます。また、ベンダーも、企業からの高度で多様な要求に対応するために、下請け構造の多層化、低利益率化、IT人材の専門領域への過度な固定化(いわゆるタコツボ化)といった課題を抱えるようになります。その結果、企業からIT人材が流出し、極端にベンダーに偏在する弊害が実際に生まれています。
しかし、企業にとっては「ベンダーに要求すればシステムを構築してもらえる」、ベンダーにとっても「安定して案件を受注できて一定の売上を確保できる」という、お互いに”ハッピー”な関係性から、このある種良くできた構造は形成されてきました。企業とベンダーとの強い依存状態を、私たちは『低位安定モデル』と呼び、深刻な問題として捉えています。なぜならば、外部環境の変化に対して極めて柔軟性に欠け、対応力が低下してしまうからです。
この構造から脱却するには、まず企業側が変わる必要があります。企業自身がITに対する理解とリテラシーを高め、自律的な判断と推進力を持つことが不可欠です。同時に、ベンダー側も適正な利益率と価値創出を実現できる市場構造へと変わっていく必要があります。
――このままレガシーシステムの刷新が進まなければ、どのようなリスクが顕在化してくるのでしょうか。
2020年以降、インフラ系システムの大規模障害が度々ニュースで取り上げられています。レガシーシステムが原因でビジネス変革が進まなければ、サービス提供に支障が出るだけでなく、企業の競争力も低下していきます。さらに、労働人口の減少をデジタル技術で補うこともできず、企業の屋台骨も揺らぐ可能性があります。また、レガシーシステムはセキュリティリスクも高く、万が一サイバー攻撃を受けた場合、一企業だけにとどまらず、サプライチェーン全体へ影響が波及する恐れがあります。場合によっては、企業の生命線を断たれる程の重大なリスクになり得ます。
――そうならないために、企業が取るべき対策について、改めて教えていただけますか。
企業が取り組むべきアクションとしては、『可視化』『標準化と内製化』『上流人材の育成・確保と技術開発』の3つが挙げられます。
最も重要なのは、1つ目の『可視化』です。これは、自社のIT資産を棚卸しして、見える化することで、自律的な自己診断を可能にする取り組みです。可視化によって明らかになったシステムの状況をもとに、「塩漬けにするシステム」「廃棄するシステム」「オンプレミスのままバージョンアップを続けるシステム」「クラウドに移行する、あるいは新しくクラウドネイティブで再構築するシステム」の4つのパターンに大まかに分類をします。こうした仕分けができて初めてIT投資の意思決定につなげることができます。
具体的には、自社のシステムの種類や数、構築時期、使用技術、規模などを一覧化し、仕様を整理してシステムの設計図として管理します。もし記録が残っていない場合は、新たに台帳を作成する必要があります。この台帳は、リフォームにおける設計図書と同様に、モダナイゼーションを担うベンダーにとっても非常に重要な手がかりとなります。

2つ目は、『標準化と内製化』です。まず標準化についてですが、日本ではこれまで、自社の業務に合わせてゼロからシステムを構築する、いわゆるオーダーメイド型に価値が置かれてきました。しかし、この方法では、生成AIなどの新しい技術が登場した際に、既存システムとの連携が難しくなります。企業独自の強みになる競争領域についてはシステムを作り込む一方で、バックオフィスなどの非競争領域については、標準的なシステムやSaaSを活用する、といったメリハリのある対応が重要です。
内製化とは、ベンダーへの100%依存から脱却することを指します。特に、企画やシステム要件定義といった上流工程は、自社のビジネスに精通した企業自らが行うべきです。その後の開発工程については、専門的なスキルを持つベンダーと協力しながら進めていく体制が望ましいです。こうした体制を敷いてガバナンスを利かせている企業は、モダナイゼーションも円滑に進められていることが統計的に分かっています。そもそも、すべてをベンダー任せにしてしまうと、自社に必要なシステムを理解できる人材が社内にいなくなり、適切な発注や交渉ができないだけでなく、完成したシステムの評価すら困難になります。
この内製化を実現するために不可欠なのが、3つ目の『上流人材の育成・確保と技術開発』です。既存のレガシーシステムを理解し、モダナイゼーションの先にある新たなシステムの姿を描きながら改善点を分析した上で、どのようなロードマップを策定すればプロジェクトを推進できるのかを明確に描ける、上流アーキテクトのスキルを持った人材が必要です。
上流人材に求められるのは、企業のシステムとビジネス内容の両方を深く理解した上での対応力です。企業の担当者はビジネスには詳しいものの、ITスキルが十分でない場合が多い。一方、ベンダーは技術には精通していますが、企業のビジネスの詳細までは把握していないことが少なくありません。だからこそ、ビジネスを理解した企業の担当者が、ベンダーの力を借りながらITリテラシーを高めて上流人材へと成長していくことが理想の形です。
また、ベンダーに多く在籍するIT人材を上流人材に育てていくことも重要です。プログラミングをはじめとしたIT関連業務の多くは、生成AIによって代替可能な領域が広がっています。そうした領域に携わっていた人材を、上流人材として再教育していくことは、今後ますます求められるでしょう。
――経済産業省は2020年に、企業のDX推進に向けた自主的な取り組みを促すため、経営層に求められる対応を『デジタルガバナンス・コード』として取りまとめました。2024年には、データ活用・連携やデジタル人材の育成・確保、サイバーセキュリティなどの時勢の変化に対応するため『デジタルガバナンス・コード3.0』へと改訂されましたが、その狙いについて教えていただいてよろしいですか。
デジタルガバナンス・コード3.0は、DXを経営課題として捉えてもらうためのガイドラインです。具体的には、自社のDXの進捗を機関投資家や社外株主などのステークホルダーにしっかりと説明をして、信頼関係を構築してもらうために『5つの柱』を定めています。
――『デジタルガバナンス・コード3.0』は、経営者の意識変革を促す施策と言えますが、現場レベルでモダナイゼーションを推進する施策についてはいかがでしょうか。
モダナイゼーションを推進するには、先ほどお話しした企業が取るべき3つのアクション『可視化』『標準化と内製化』『上流人材の育成・確保と技術開発』の実効性を確保することが重要です。この3つのアクションに対して、ITシステムやサイバーセキュリティ、データ連携などの観点から、より詳細に現状を自己診断できるチェックリストがあれば、企業はモダナイゼーションに取り組みやすくなるでしょう。また、自社のシステムの状態を一目で把握できるレーダーチャートのようなツールも有用です。経済産業省では、こうしたチェックリストやレーダーチャートを作成して、企業が自らITの健康診断を行える環境の整備を目指しています。

――上流人材の育成に関しても、何か施策を考えられているのですか。
デジタル人材育成用の新しいプラットフォームを官民共同で推進しています。まず、企業が自社のケイパビリティやスキルを分析し、モダナイゼーションやDX推進に必要な人材がどの分野で不足しているのかを把握します。それに対してベンダーは、企業に不足している人材を提供する。このマッチングをスムーズに行うためのプラットフォームです。
狙いはスキルの可視化です。必要とされる人材がどのようなスキルを持ち、どのようなキャリアを積めばより高度な専門人材になれるのか。こうした情報を登録し、企業とベンダーが同一のプラットフォーム上で管理できる仕組みをつくる予定です。また、スキルアップのための研修コンテンツを提供する企業などとも連携し、人材育成カリキュラムや資格取得支援サービスなども同じプラットフォーム上で展開する構想を描いています。
――経済産業省は東京証券取引所と共同で、DXに取り組む企業を『DX銘柄』としてピックアップしています。そのなかから、デジタル時代を先導する企業を『DXグランプリ』として選んでおり、2025年は、佐川急便の持ち株会社である『SGホールディングス』が選出されました。どういった点が評価されたのでしょうか。
SGホールディングスは早くから先進的な取り組みを進めており、2025年の崖を克服した企業です。2000年前後から段階的にメインフレームからの脱却を図り、オープン化を推進してきました。モダナイゼーションを成功させたことで、業務プロセスのデジタル化・標準化も段階的に進み、その結果、データに基づいた経営戦略の立案や意思決定が可能な仕組みを構築しています。グループのDX戦略には「オープン系のグループ共通IT基盤をベースに、同業他社やスタートアップ企業を含めた異業種との連携、IoT・AI・ロボティクス等のテクノロジーを活用することでさらなるDXを推進し、トータルロジスティクスをさらに進化させていく」と記されています。
加えて、サプライチェーン全体を見据えた取り組みも進んでいます。SGホールディングスと連携する協力会社を含め、予測や管理システムの最適化を図っています。こうした社内外のDXを経営トップダウンで推進している点が、大きな評価ポイントとなりました。
――SGホールディングスのような、業界をリードする企業のDXは、物流業界全体にどういった影響があるのでしょうか。
輸送・配送を行う物流は、小売や個人を含めると非常に多くのステークホルダーが関わっています。まさにサプライチェーンをつなぐ大動脈です。そのなかでも存在感のあるSGホールディングスがシステム変革を進めることは、社会的にも大きな影響をもたらします。デジタルプラットフォーム化は業界全体への波及効果があり、他の企業が追随する際の有力なベンチマークになるでしょう。

――OPEN HUBは、社会課題を解決して豊かで幸せになる未来を実現するための事業共創の実験場です。こうした共創活動は、企業のモダナイゼーションやDXにどういった効果をもたらすとお考えですか。
企業とベンダー、さらには業界の垣根を超えて企業同士がつながるコミュニティは非常に重要だと考えています。社会のニーズや課題を起点にして、各企業が他社の方針やマインドに直接触れることができる。こうした経験は、デジタル変革への意識を高めるきっかけとなり、経営層にとっても大きな刺激となる取り組みだと思います。
自分が知っているチャネルだけでは得られない情報は数多く存在します。そうした情報を提供できるのが、多様な顧客チャネルを持ち、さまざまなビジネス事例を実際に見聞きし、データ利活用プラットフォームなどを通じて企業を支援しているNTTドコモビジネスのような企業でしょう。多くの企業に新たな気づきを与え、新しい価値の実現に向けて伴走する、まさにハブとなる存在だと思います。生成AIの活用やデータ利活用の面でも企業を後押しできるのは大きな強みになると思います。
――『DXの現在地とレガシーシステム脱却に向けて』は、社会産業のDX、さらには日本経済の競争力強化につながっていく未来に向けて作ったレポートだと思います。最後に、未来への期待感をお聞かせください。
国が目指しているのは、日本の産業全体がデジタルによってより高い価値を創出することです。単なる業務効率化にとどまらず、サービスの質をさらに高め、顧客体験を向上させる。そして、最終的には新たな市場を創出するようなトランスフォーメーションを期待しています。
生成AIに続いて汎用AIなどが登場し、それらを搭載したロボティクスが本格化すれば、これまでとは異なる産業競争力が求められる時代が到来します。その時に大きくジャンプアップして崖を越えるためにも、レガシーシステムからの脱却は不可欠です。企業には、これを経営戦略の一環として積極的に推進していただきたいと思います。
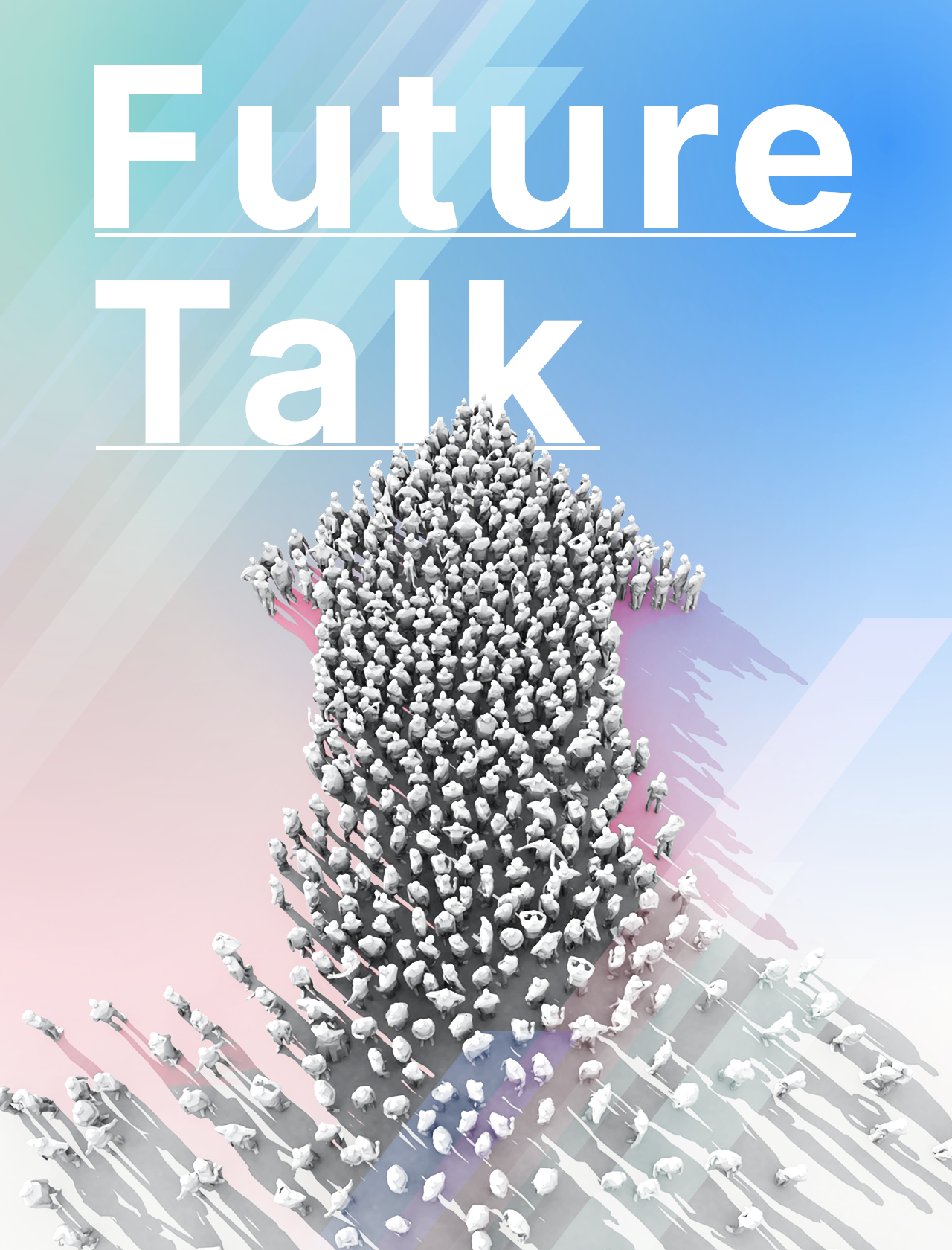
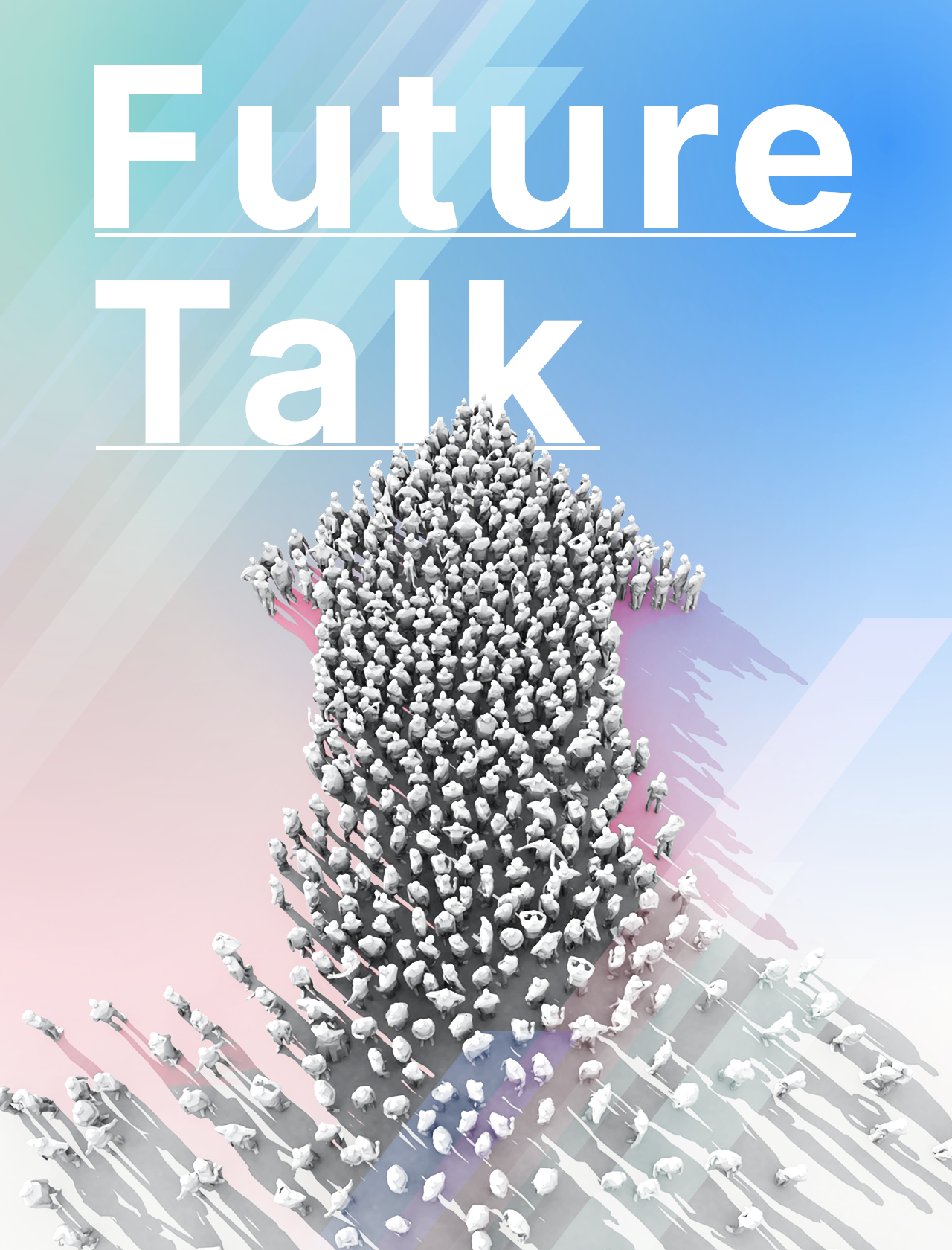
OPEN HUB
THEME
Future Talk
#専門家インタビュー