
01
2025.07.18(Fri)
目次
——近年、企業間でのデータ連携を促すデータスペースの構築が必要だと言われています。なぜ今、こうした仕組みが求められているのでしょうか。
越塚登氏(以下、越塚):いくつか理由はありますが、まずはインターネットやIoTデバイスの普及により、データが爆発的に増えたこと。そして、デジタル分野の競争力の源泉がデータのレイヤーになってきたことが挙げられます。
デジタル技術のトレンドは約20年周期で移り変わってきました。1960年代には大型計算機によって世界初のDXが実現され、1980年代になるとマイクロコンピューターが登場し、2000年代はインターネットの時代。そして、2020年頃からはデータとAIの時代になりました。
新しい時代にはその時代に適したプラットフォームが必要であり、データとAIの時代に必要な新しいプラットフォームがデータスペースなのです。
データスペースとは、企業や組織の垣根を越えてデータを安全に共有・活用するための仕組みのこと。必要なときに、必要なデータだけを、許可した相手とだけ共有することができます。データは自社で抱えるだけでなく、連携させることでネットワーク効果が働き、価値が増大しますから。

境野哲(以下、境野):地球規模の社会課題が出てきたこともデータスペースが求められる理由の1つです。環境問題や人権問題などを解決するためには、企業や産業、国の枠を超えて協力することが欠かせません。
このような社会課題を解決するには、必要な情報を社会の共有財産として、適切な範囲で関係者が活用できるようにする必要があります。例えば、CO2排出量は社会全体で把握していかなくてはなりません。従来のように企業がすべての情報を抱え込んで、自社だけで問題を解決するという時代ではなくなってきています。
——GXの文脈でデータスペースが果たす役割を教えてください。
越塚:GXとデータはとても相性が良いです。なぜかというと、CO2は見えないから。透明で手に持てないCO2の排出量を把握し、管理するためには、データが唯一の手がかりとなります。
製品の原料調達や製造、廃棄までの一連の流れにおけるカーボンフットプリントを測定するためには、サプライチェーンに関わる複数企業のデータ(Scope3)の連携が必須です。
境野:GXを実現するためには、地球上のあらゆる人、モノ、金、エネルギーなどの情報を把握しなければなりません。さらには現状把握だけでなく、100年後、200年後の地球をシミュレーションする必要もあります。これらの実現のためには、データスペースの存在が欠かせないのです。

——欧州では、「GAIA-X」「Catena-X」のようなデータスペースの国際的な枠組みが先行しています。この狙いや戦略をどう見ていますか。
越塚:「GAIA-X」「Catena-X」は、もとは製造業のDXを目指す「インダストリー4.0」の流れを汲んでおり、その中でもドイツの自動車業界が主導する「Catena-X」は、製造業全体をつなぐ「Manufacturing-X」の先行プロジェクトとして位置づけられています。
こうした動きの背景には、欧州が得意とする「ルールメイキングによる市場創出」という戦略があります。彼らはグリーン、データ、AIなどの分野で、まず世界に先駆けてレギュレーションを作る戦略をとります。その規制によって壁を築き、その内側を安全な市場、つまり先行者のいないブルーオーシャンとして定義し、欧州企業が先行者利益を得られるようにしているのです。
では、GXで重要な産業は鉄鋼やアパレルなど他にもあるのに、なぜ「Catena-X」は自動車なのか。自動車は欧州が強い分野だからです。自動車を含むモビリティ分野全体がCO2の全体排出量に占める割合は10%程度ですが、自分たちの強みである自動車産業に「グリーン」と「データ」という新しい武器を持ち込み、競争力をさらに強化しようとしているのです。これは非常に巧みな戦略です。

境野:以前、「Catena-X」のボードメンバーに「なぜこの取り組みを始めたのか」と聞いたところ、「今、アメリカのテスラや中国のBYDがイノベーションを起こしている。欧州の自動車産業は変わらなければ生き残れない。だから始めたんだ」と、強い危機感を語っていたのが印象的でした。
越塚:実は欧州の人たちは、過去にインターネットの主導権争いにおいて、満足のいく状況ではないと感じていると思います。だから、データスペースにおいてはなんとしてもイニシアチブを取りたいと思っているのです。
「Catena-X」に関して言えば、国際競争力を生み出すという点において、欧州と同じように自動車産業に強い日本もかなりの部分でメリットを共有できるのではないでしょうか。自動車産業において、欧州と日本はビジネス上のライバルも、課題も共通していますから。
——こうした大きな流れに、日本はどう向き合えばいいのでしょうか。
越塚:データスペースは、国と国が協力し合う「協調領域」のインフラであるべきです。ただ、データスペースの領域は陣取り合戦である部分も否めません。たとえば、データスペース自体は協調領域だとしても、もしデータスペースに関わる技術をある国が独占すれば、後にデータスペース上でビジネスを展開していく上では有利になります。
インターネット自体はインフラであり「協調領域」だけれど、その上のビジネスのレイヤーではいわゆるハイパースケーラーと呼ばれる企業群が覇権を握っていますよね。それらが生まれた背景にはインターネットがアメリカから始まったということが少なからず影響しているはずです。
データスペースも同じように、そのインフラの上で展開されるビジネスの覇権が、今後のその国の産業の国際競争力を左右するでしょう。そこは、日本企業にも頑張ってもらいたいところですよね。
境野:そうですね。私はデータスペース“サービス”を運用するところまでを海外に任せてしまったら、それは日本にとって大きなリスクになるのではないかと思います。
インターネットの基盤の上には、OCNやNiftyのような国内のインターネットサービス・プロバイダがいます。もしもそこが海外のプロバイダしか選択肢がなかったら、日本にインターネット産業は残っていなかったかもしれません。そこを海外に任せなかったからこそ、今国内にインターネット接続サービスを運用する知見が蓄えられているのだと思います。
データスペースはインフラであり、社会資本とも言うべき存在になる可能性があります。データスペースは日本の社会資本になり、国際的なデータ通信の基盤にもなり得ることを日本でも国家単位で認識して、いち早く企業はデータスペースの利用に着手するべきではないでしょうか。

──国際競争力とGXという両面において、データスペースの導入は待ったなしの状況だと思います。日本企業がデータスペースを活用するにあたって、どのような障壁があるのでしょうか。
越塚:少なくない企業が大事なデータを外部に出してはいけないという考えを持っています。確かにデータは無限にコピーできてしまうものですから、懸念していることはわかります。
ただ、それはテクノロジーによって解決できることです。昔は2つのデータを連携しようと思えば、同じマシンの中にそれらの2つのデータを入れるしかありませんでした。しかし、今は必要なときに必要なデータを必要な相手にだけ共有する技術があります。
境野:越塚先生のおっしゃった仕組みがまだ良く理解されていない印象を受けますね。データスペースを使うと機密情報がオープンになってしまうと勘違いしてしまっている。でも実際は、自分が許可した相手にしかデータは見えません。現在でも、機密保持契約に基づいて取引先に品質や性能に関する情報を見せていることもあるわけで、データスペースは、それと同じことをデジタルでも実現しようとしているだけです。
あとは、そもそもデータスペースを導入するにあたってのインフラが未整備だという点があると思います。例えば、なりすましを防ぐためにデータスペースで通信する相手の本人性を確認するトラスト基盤など、デジタル通信のインフラがまったく整備されていなくてはビジネスを展開することは難しい。それは道路がない国でビジネスをしようとするのと同じです。そのため、NTTドコモビジネスはその「道路づくり」をリードしていきたいと考えています。
——お二人は今、どのように「道路づくり」を進めているのでしょうか。
境野:具体的には、「Catena-X」で採用されている「データスペース・プロトコル」のような国際標準になりそうな仕組みをいち早く評価し、日本の企業がスムーズに接続できるような技術や環境を整える。そして、日本企業がすぐにでも普段利用しているネットワークサービスを使ってデータ連携を試せる「レディな状態」を提供することが、我々通信事業者の重要な役割だと考えています。
もちろん、欧州のデータスペースを敵視する必要はまったくありません。インターネットやスマートフォンの通信規格と同様、共通で使える便利なツールは積極的に利用して、国際的に相互接続・相互運用するべきです。そのうえで、日本企業がどのようにアプリケーションやサービスで差別化し、価値を生み出していくかが重要だと考えています。
越塚:一般社団法人データ社会推進協議会(DSA)が推進する「DATA-EX」は、日本でデータスペースを推進する動きを加速するために立ち上げた組織です。当初の目的の一つには、SIPのプロジェクトで得られた技術的な成果、「これを使えばデータスペースを構築できる」というシステムやコンポーネント、その方法論を社会に提供することがあります。
その立ち位置は今も変わっていません。「DATA-EX」が目指すのは、特定の業界のデータスペースを作ることではなく、さまざまな業界で生まれるであろう個々のデータスペースをつくったり、それらを連携させるための共通の技術や仕組みを提供しようとしています。

──日本のエンタープライズ企業に期待することがあれば、教えてください。
越塚:データスペースは、データの共有や流通のルール、ガバナンスなどを包含する概念ですが、最終的にデータをやり取りするのは各企業のエンタープライズシステムです。だからこそ、そのシステムを持つプレイヤーである企業がこの動きに参画することが極めて重要です。
今後はエンタープライズシステムを設計する際、ソフトウェアよりもデータの割合が物理的にどんどん増えていくはずです。重要なのは、「必要なときに、必要な人が、必要なだけ、ちゃんと連携できる」という仕組みを、自社の基本的な仕組みとして組み込むこと。そして、そこにAIをどう組み合わせるかを考え、新たなビジネスバリューを創出していただきたいと思います。
境野:インターネットの波に乗り遅れた企業が衰退してしまったのと同じことが、データスペースでも起こり得ます。データスペースを活用しないことで、生産性が上がらず競争力を失ってしまうかもしれません。また、GXの側面では、カーボンニュートラル達成への責任を果たすコンプライアンスの観点だけでなく、環境への意識が高い富裕層の優良なお客様から自社の製品やサービスが選ばれ続けるためのブランド戦略の観点でも、データスペースの活用は有益だと思います。
重要なのは、まず使ってみることです。インターネットがそうだったように、実際に使ってみないとその価値や活用法が分からない部分が多いんです。東京大学と協力して、データスペースの運用技術者を育てるテストベッドプロジェクトや、データスペースを活用した新しいビジネスアイディアを考えるワークショップなどを実施していきますので、企業の皆さまには我々と共に、データスペースを使ってどのような新しいビジネスができるかを一緒に考えていただきたいと思います。
関連資料はこちら
「企業間データ連携に向けたデータスペース概況と、NTTグループの取り組み」
https://smp.openhub.ntt.com/public/application/add/21681
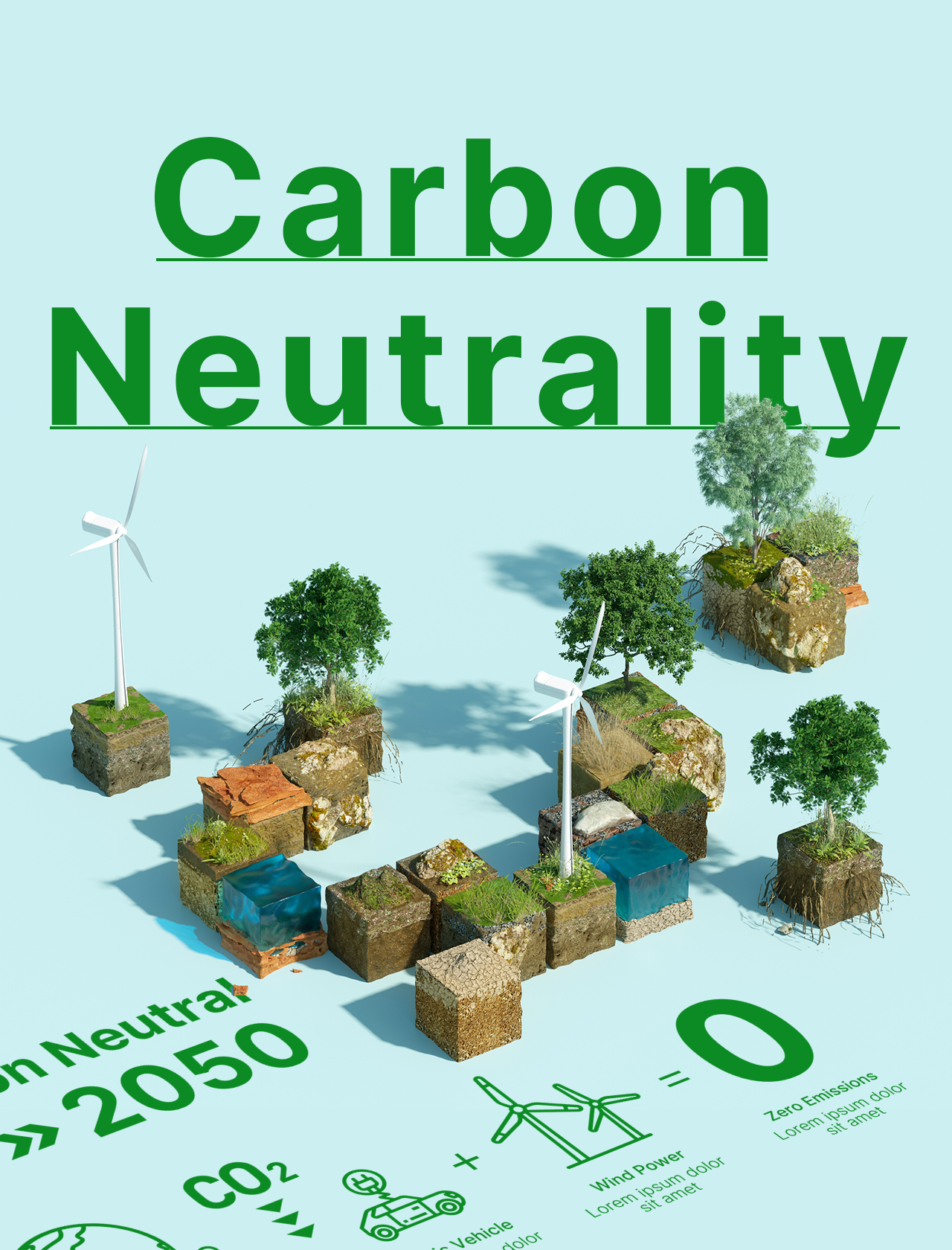
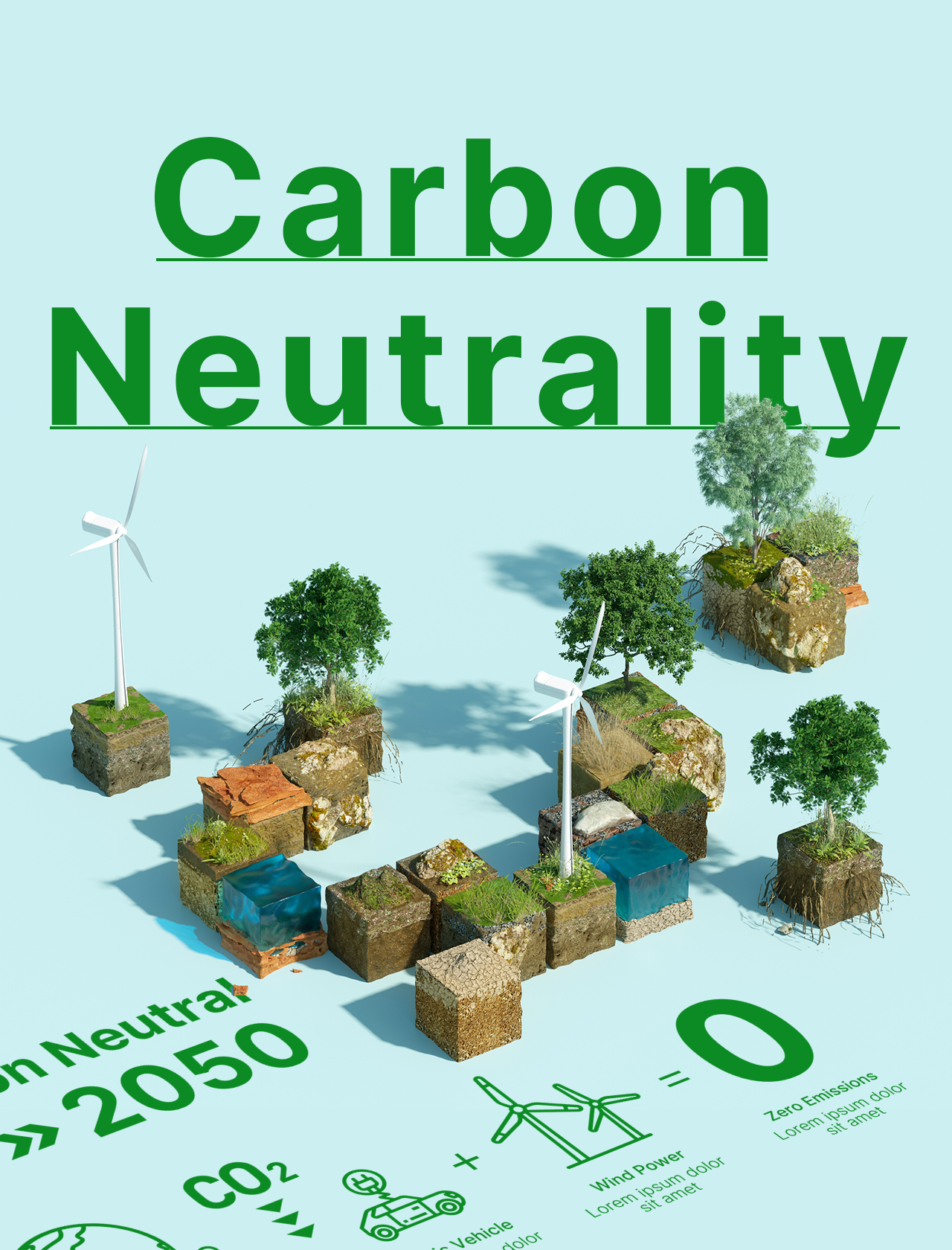
OPEN HUB
THEME
Carbon Neutrality
#脱炭素