
01
2025.07.18(Fri)
目次
都市OSとはどのような役割を持つものなのでしょうか。具体的な特徴や要件について見ていきましょう。
●都市OSとは?
都市OSは、都市サービスや都市間の連携を可能にする共通プラットフォームです。行政・物流・交通などの多岐にわたるサービスが都市OSに集約されることで、手続きや情報閲覧などをスムーズに行えるようになります。
都市OSは「スマートシティ」構想の発展とともに生まれました。内閣府もデータ連携基盤である都市OSの整備を推進しており、異なる事業者・自治体のサービスを統合し、都市の利便性向上をめざしています。
都市OSの導入において、事業者は主に技術開発やサービス提供を、自治体は導入・運用を担います。各々の役割は異なりますが、相互に連携して円滑なサービスの実現をめざすことが重要です。
●都市OSの要件
スマートシティとは、ICTなどの新技術を活用しながら都市の計画・整備・管理・運営を高度化し、効率化や快適性を向上させた都市・地域を指します。地域の抱える課題を解決し、新しい価値を創出できる持続可能性を備えている点が特徴です。
都市OSに期待される役割は、スマートシティの実現におけるシステム面での課題解決です。たとえば、AIによる交通渋滞の予測・緩和や、パーソナルデータの紐づけによるサービス連携など、さまざまな分野において都市OSの活用が進めば、都市全体の利便性が高まるでしょう。
また、都市OSには次の3つの要件があります。それぞれの概要は以下のとおりです。
・相互運用(つながる)
日本におけるスマートシティの実現を阻む課題の一つに、サービスの再利用や横展開の難しさがあります。各自治体や企業が独自のシステムを構築しているため互換性が低く、他の地域や組織と連携しにくいことが要因です。
上記の課題を解決し、都市内や都市間での相互運用を可能にするのが都市OSです。共通の機能や標準的なインターフェースを備えており、異なるシステム間の連携をスムーズに行えるようになります。
・データ流通(ながれる)
分野を超えたデータ利活用を促進するためには、地域内外のデータを円滑に仲介・連携させる仕組みが不可欠です。従来は産業や地域ごとに分かれてデータが蓄積されていたため、他のサービスとの共有が困難でした。都市OSによって、地理空間データ・パーソナルデータ・統計データなど、多種多様なデータを統合して効果的に活用できるようになります。
・拡張容易(機能を広げられる)
システムを持続しながらさらなる発展を求めるには、地域ごとの課題や将来像に応じた柔軟な拡張機能が必要とされます。従来のシステムではサービス間の連携が難しく、拡張にもコストがかかるという課題が見られました。都市OSによってシステムの規格が統一されると、必要な機能を効率的に拡張・更新できる仕組みが整います。
【参考】内閣府「スマートシティリファレンスアーキテクチャ ホワイトペーパー(日本語版)(移動ページ)」
近年では「EBPM(証拠に基づく政策立案)」も重視されており、統計データや実証研究などをもとにした政策の策定が推進されています。都市OSはデータ収集・分析・評価などにおいて、EBPMの助けとなるでしょう。ここでは、都市OSの主なメリットをご紹介します。
●サービス間の連携
都市OSの活用により、交通・医療・福祉などの異なるサービスがシームレスにつながります。住民の利便性が向上するのはもちろん、サービスの利用率を高めることにも有効です。
【例】
・交通系ICカードと医療サービスを連携させ、通院時の移動を支援
・公共施設予約システムと決済システムを統合し、手続きを簡略化
●都市間の連携
異なる自治体が共通の都市OSを導入することで、住民がどこにいても一貫したサービスを受けられます。単身赴任などで居住地と勤務地を行き来するような場合も便利です。
【例】
・複数都市で共通のシステムを導入し、引っ越しにおける行政手続きを円滑化
・異なる都市の交通データを統合し、効率的な広域公共交通網の設計に活用
●分野間の連携
防災や環境、交通などの異なる分野のデータを組み合わせることで、より効果的な都市運営が可能になります。さらに官民の枠を超えて連携すれば、都市の課題解決や発展につながるでしょう。
【例】
・行政のハザードマップと民間の道路通行データを統合し、災害時の迅速な避難ルートを提示
・ヘルスケアデータと地域サービスを連携させ、健康増進活動への参加状況に応じた特典を付与する仕組みを導入
都市OSの導入に際しては、以下のようにさまざまな課題が見られます。各項目の内容を踏まえたうえで検討を進めることが大切です。
●人材の確保や資金の調達が難しい
都市OSを取り入れてスマートシティを推進する際は、多大なコストが生じます。加えて、都市内外を横断してのデータ利活用を実現するために、専門的な人材を確保する必要もあります。人的資源や資金の問題は、特に中小規模の自治体には大きな問題となるでしょう。費用面のバランスを見ながら、段階的に導入を進めていくといった工夫が求められます。
●国や自治体のシステムと連携する必要がある
都市OSを機能させるには、国や自治体のシステムとの連携が不可欠です。しかし、自治体や省庁のネットワークは基幹系・LGWAN(総合行政ネットワーク)系・インターネット系の3つに分かれており、それぞれ異なる制約があります。LGWANは行政専用の閉鎖的なネットワークであり、地方公共団体や中央省庁などの通信網として活用されています。外部のインターネットとは直接接続されていないため、行政内部の情報を都市OSと連携させるには、LGWANからインターネット環境へデータ移行する必要があります。
また、一般的に、企業と自治体の連携には、先ほど述べたシステム面以外にもいくつかのハードルがあります。例えば、自治体が「求めること」および「その背景」と、企業の「技術でできること」の間には認識のギャップがあり、当初は互いに理解しづらいため、綿密な調整・すり合わせが必要になります。特に自治体のシステムは、法規制などによる複雑なセキュリティ対策が求められたり、補助金を受けるために納期がタイトになったり、突然の仕様変更が起こったりします。企業側は、地域理解を深めながら、自治体の要望に柔軟に対応して、信頼関係を結んでいくことが重要です。
●地域住民の合意を得る必要がある
スマートシティ化を進める中で避けられないのが、地域住民との合意形成です。これまでと異なる仕組みを取り入れる際は、住民からの反発を受けてしまうケースも珍しくありません。対話の機会を設け、意見交換を積極的に行いましょう。
現在は、さまざまな地方自治体において都市OSの導入が進められています。主な取組みの内容を確認してみましょう。
●福島県会津若松市
会津若松市は東日本大震災からの復興をきっかけとして、2013年からスマートシティ化を推進しています。「市民」「地域」「企業」の「三方良し」の実現をめざし、多岐にわたる分野でのICT活用を実現してきました。都市OS上では、行政手続きや地域通貨、商店街クーポンなど、さまざまなサービスを利用できます。
●静岡県浜松市
浜松市は2019年にデジタルファースト宣言を発表しました。行政・企業・市民が連携する官民共創の体制を構築し、さまざまな主体の参画によるスマートシティを推進してきました。データ連携基盤をSaaSとして導入し、市民の安全・安心の確保やボランティアマッチングなど、地域共助を促進する施策を展開しています。
●栃木県那須塩原市
那須塩原市は2022年に「那須塩原市DX推進戦略」を策定し、データ連携基盤を用いた行政サービスの向上に取り組んでいます。マイナンバーカード対応の共通IDを活用し、地域ポータル・電子母子手帳・地域通貨・観光パスポートなどの4種類のアプリを提供。データ活用を進め、新たな行政サービス開発にも対応できる体制を整えています。
●東京都狛江市
狛江市は福島県矢吹町と共同で都市OSを導入しました。三菱商事とNTTコミュニケーションズの支援を受け、小規模自治体向けのデータ連携基盤を構築。子育て支援を中心に、行政データや地域情報を連携させ、効率的なサービス提供を実現しています。
●岡山県西粟倉村
西粟倉村は地域創生の成功モデルとしても知られています。森林資源のデジタル活用や行政ポイントサービス、EVデータ連携などを推進し、都市OSを基盤に脱炭素・再生可能エネルギー施策とも連携しながら、持続可能な地域づくりを進めています。
関連記事:「2024年版国内スマートシティ事例 前編―5つの都市の事業モデルと都市OS―」
都市OSの導入は、都市の持続可能性を高めると同時に、ビジネスの新たな機会を生み出します。しかし、技術面・制度面・運用面の課題も多く、成功のためには適切な戦略とパートナーシップが欠かせません。
今後も日本各地の自治体において、都市OSの導入が進んでいくと考えられます。官民連携を強化し、データの利活用を促進することで、住民の利便性向上や行政サービスの効率化へつながっていくでしょう。ビジネスへの都市OSの活用を通じて、快適な都市環境を実現しましょう。
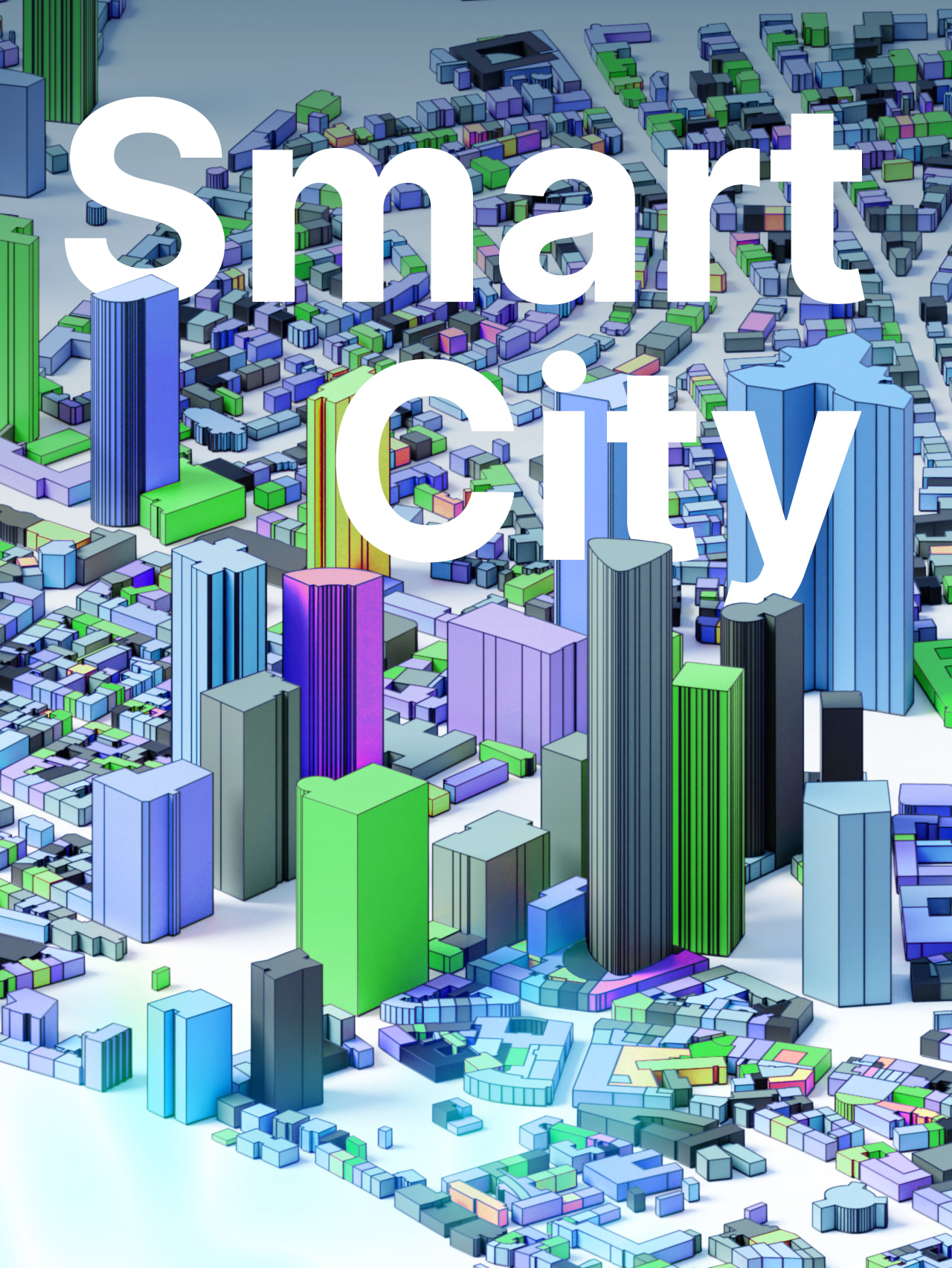
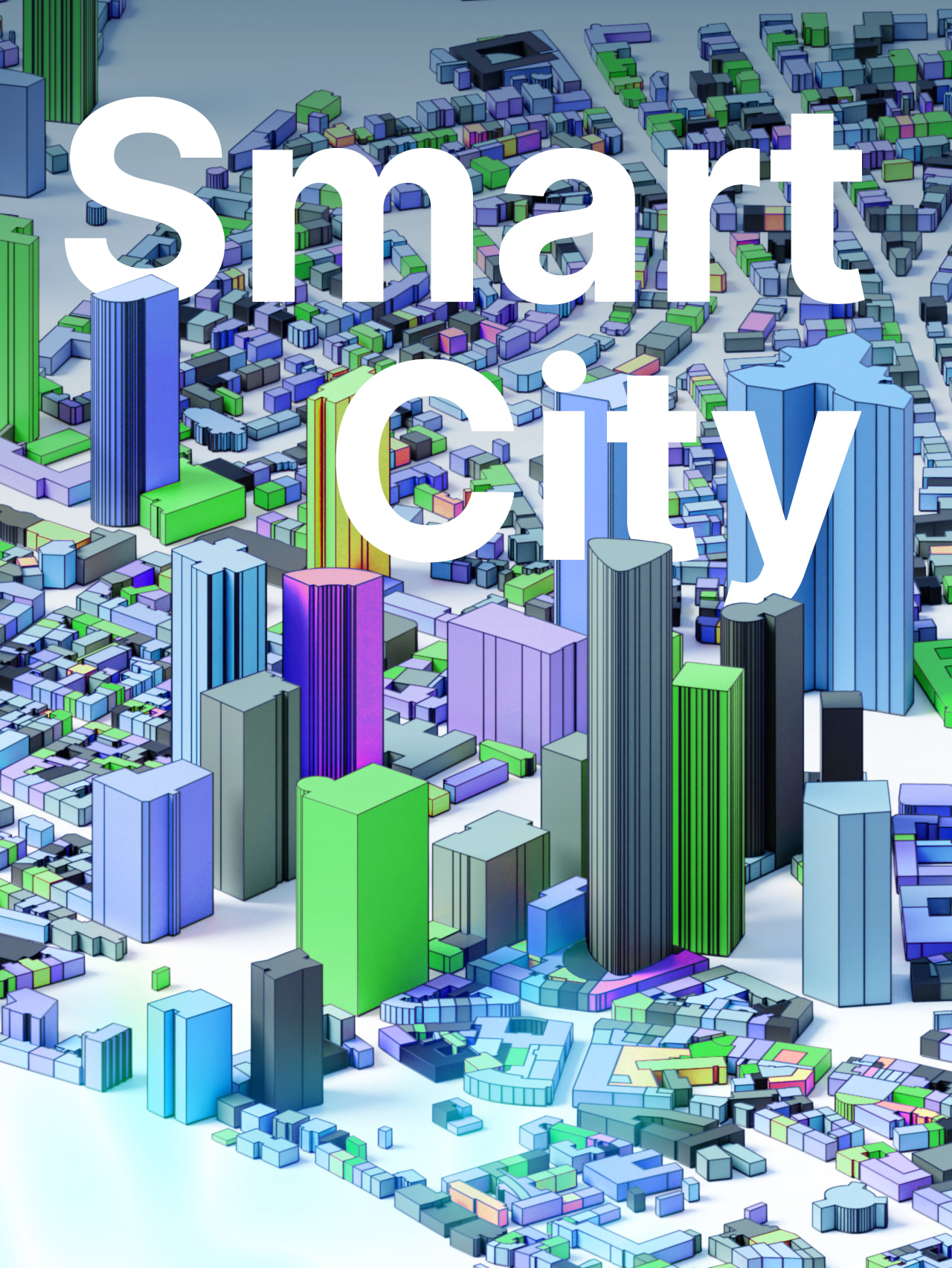
OPEN HUB
THEME
Smart City
#スマートシティ