
01
2025.07.18(Fri)
目次
はじめに、「再生可能エネルギー」に関する基礎知識をご紹介します。ビジネスシーンで注目が高まる持続可能なエネルギーについて、改めて基本から確認してみましょう。
●再生可能エネルギーとは?
再生可能エネルギーとは、自然の中にある永続的に利用できるエネルギーのことです。国内では、「エネルギー供給構造高度化法」によって再生可能エネルギーが定義されています。この法律で再生可能エネルギーとして定義されているのは、「太陽光」「風力」「水力」「地熱」「太陽熱」「大気中の熱、その他の自然界に存在する熱」「バイオマス」の7種類です。
【出典】経済産業省 資源エネルギー庁「なっとく!再生可能エネルギー」
●再生可能エネルギーの種類ごとの活用法
・太陽光発電
太陽の光エネルギーを太陽電池で受け取り、電気に変える発電方法です。事業用の大規模太陽光(メガソーラー)のほか、一般家庭では住宅用太陽光発電システムが活用されています。
・風力発電
風の力で風車を回して、回転運動を電気に変える発電方法です。事業用の風力発電所が開発される一方、近年は家庭向けの小型風力発電設備も登場しています。
・水力発電
高い位置にある水を低い位置に落として水車を回し、水車の回転運動を電気に変える発電方法です。山間にあるダムでせき止めた水を利用して発電が行われます。
・地熱発電
地下にある高温の蒸気や熱水を利用して、噴出する蒸気でタービンを回し、回転運動を電気に変える発電方法です。火山付近の地熱貯留層のある場所で発電が行われます。
・バイオマス
生物由来の「バイオマス燃料」を燃焼させ、タービンの回転を電気に変える発電方法です。バイオマス燃料は、家畜の排せつ物・食品廃棄物・汚水・間伐材などから作られます。
・太陽熱利用
太陽の熱を集めて温水や温風を作り、給湯や冷暖房に利用する方法です。病院やホテルなどのビルで用いられるほか、一般家庭では戸建住宅用太陽熱温水器も利用されています。
・雪氷熱利用
冬期に発生する雪や氷を保管し、夏期に冷気や冷水として利用する方法です。寒冷地では冬期に貯雪庫に雪を貯め、夏期に公共施設の冷房や農作物の冷蔵などに利用しています。
・温度差熱利用
海や河川などの水と大気との温度差を利用して、ヒートポンプや熱交換器で冷水・温水を作ります。一般家庭のヒートポンプ式電気給湯機でも用いられている技術です。
・その他の再生可能エネルギー
このほかにも、波のエネルギーを利用する「波力発電」、潮の満ち引きを利用する「潮力発電」、海上や湖面の風力を利用する「洋上風力発電」、地中と地上の温度差を利用する「地中熱利用」などが挙げられます。
●再生可能エネルギーとクリーンエネルギーの違い
「クリーンエネルギー」とは、環境負荷が少ないエネルギーのことです。温室効果ガスの排出が少ないエネルギーや、汚染物質の排出が少ないエネルギーが該当します。それに対して再生可能エネルギーは、永続的に利用できるエネルギーではあるものの、環境負荷が少ないとは限りません。たとえば、再生可能エネルギーの一つであるバイオマス発電は、燃焼により汚染物質を出す可能性があり、クリーンエネルギーと見なされない場合があります。
関連記事:「クリーンエネルギーとは?注目される理由と主な種類、メリットや課題は?」
日本国内では、再生可能エネルギーに関してどのような課題があり、どの程度普及が進んでいるのでしょうか。ここでは国内の現状をご紹介します。
●日本が抱えるエネルギー問題
日本の国土はエネルギー資源に乏しい環境にあります。現状はエネルギー供給の8割以上を化石燃料(石油・石炭・天然ガスなど)が占めており、海外からの輸入に依存している状況です。特に2011年に発生した東日本大震災以降、エネルギー自給率が低迷しています。経済産業省が公表する資料によると、2021年度の日本のエネルギー自給率は13.3%で、諸外国と比較して低い水準にあります。こうした火力発電への依存という課題に対して、近年は再生可能エネルギーを活用し、電源構成比における割合を増やす取り組みが始まっています。
●日本における再生可能エネルギーの導入の拡大状況
国内では、2012年7月に「FIT制度(固定価格買取制度)」が開始され、再生可能エネルギーの導入が大幅に増加しました。FIT制度とは、再生可能エネルギーで発電した電力の固定価格での買取を国が約束する制度のことです。なかでも太陽光発電の電源構成比は、2011年度の0.4%から2022年度の9.2%まで増加しました。一方、再生可能エネルギー全体では、2011年度の10.4%から2022年度の21.7%まで拡大しています。2030年度の目標値である36~38%を実現するには、さらなる再生可能エネルギーの導入拡大が求められます。
ここでは、再生可能エネルギーのメリット・デメリットを解説します。再生可能エネルギーの導入で期待できることや、注意点を確認してみましょう。
●再生可能エネルギーのメリット
・繰り返し利用できる
再生可能エネルギーの発電方法では、太陽光や風力などをエネルギー源とする仕組みのため、永続的に利用できます。資源に限りがある化石エネルギーのように、枯渇してしまう心配がありません。
・環境に優しい
再生可能エネルギーによる発電では、大気を温める効果(=温室効果)をもたらす「温室効果ガス」を排出しません。温室効果ガスには「二酸化炭素(CO2)」「メタン」「一酸化二窒素(亜酸化窒素)」などの種類があり、地球温暖化の原因となります。
・資源を輸入する必要がない
再生可能エネルギーを利用する際は、化石燃料のように産出国から資源を輸入する必要がありません。普及を促進することで、エネルギー資源の輸入依存から脱却し、日本のエネルギー自給率向上が期待できます。
・雇用創出効果がある
社会に再生可能エネルギーの普及が進むにつれて、世界的に関連分野の新たな雇用が生まれています。国内でも雇用創出効果がもたらされ、今後は再生可能エネルギーに関連する新規の仕事や職種が生まれる可能性があるでしょう。
●再生可能エネルギーのデメリット
・電力の安定供給が難しい
多くの再生可能エネルギーは、自然現象に左右されやすいため発電電力量を予測しにくく、安定供給が難しいのが難点です。たとえば、太陽光発電なら天候や日照時間、風力発電なら風量や風向きなど、気候により発電量が変動します。
・設置場所が限られる
国内の電力需要を賄うには、太陽光パネル・風車・水車といった大規模な再生可能エネルギーの発電設備が必要です。一方、日本は国土が狭いため新たな発電設備を設置するスペースに限りがあり、再生可能エネルギーの普及が進みにくくなっています。
最後に、国(政府)や企業の再生可能エネルギーへの取り組み事例をご紹介します。今後の取り組みへ向けて、ぜひ参考にしてみてください。
●JPEA太陽光発電推進センター
2024年には「令和6年度予算 需要家主導型太陽光発電導入支援事業」が実施されました。これは、需要家主導型による太陽光発電設備の新たな導入モデルを支援する国(政府)の事業です。カーボンニュートラルの推進に向けて、経済産業省 資源エネルギー庁の主導のもとで、一般社団法人太陽光発電協会(JPEA)が実施しています。需要家に電気を供給する目的で、新たに太陽光発電設備を設置・所有する発電事業者が補助対象となり、費用の補助を受けられます。
【出典】JPEA太陽光発電推進センター(JP-PC)「令和6年度予算 需要家主導型太陽光発電導入支援事業」
●セブン&アイ・ホールディングス
民間企業では、セブン&アイ・ホールディングスとNTTコミュニケーションズによる共創事業が実施されました。セブン&アイ・ホールディングスでは、2019年5月にグループの環境宣言「GREEN CHALLENGE 2050」を策定しています。そこでは、取り組むべき課題の一環として「グループ各店の店舗運営に関わるCO2排出量を実質ゼロにする」が目標に掲げられました。セブン&アイ・ホールディングスとNTTコミュニケーションズは、両グループの協業により、再生可能エネルギーを活用したCO2排出量の削減に取り組んでいる状況です。
参考:「セブン&アイグループが実現した、100%再生可能エネルギーの利用」
ここまで、再生可能エネルギーの基礎知識や、日本の現状、取り組み事例などを解説しました。近年、世界的な課題となっている気候変動を受けて、国内の民間企業でも脱炭素化へ向けて地球温暖化対策の取り組みが始まっています。ご紹介した事例を参考に、事業での再生可能エネルギーの活用を検討してはいかがでしょうか。
※¹【出典】環境省
「温室効果ガス排出・吸収量等の算定と報告 世界のエネルギー起源CO2排出量」
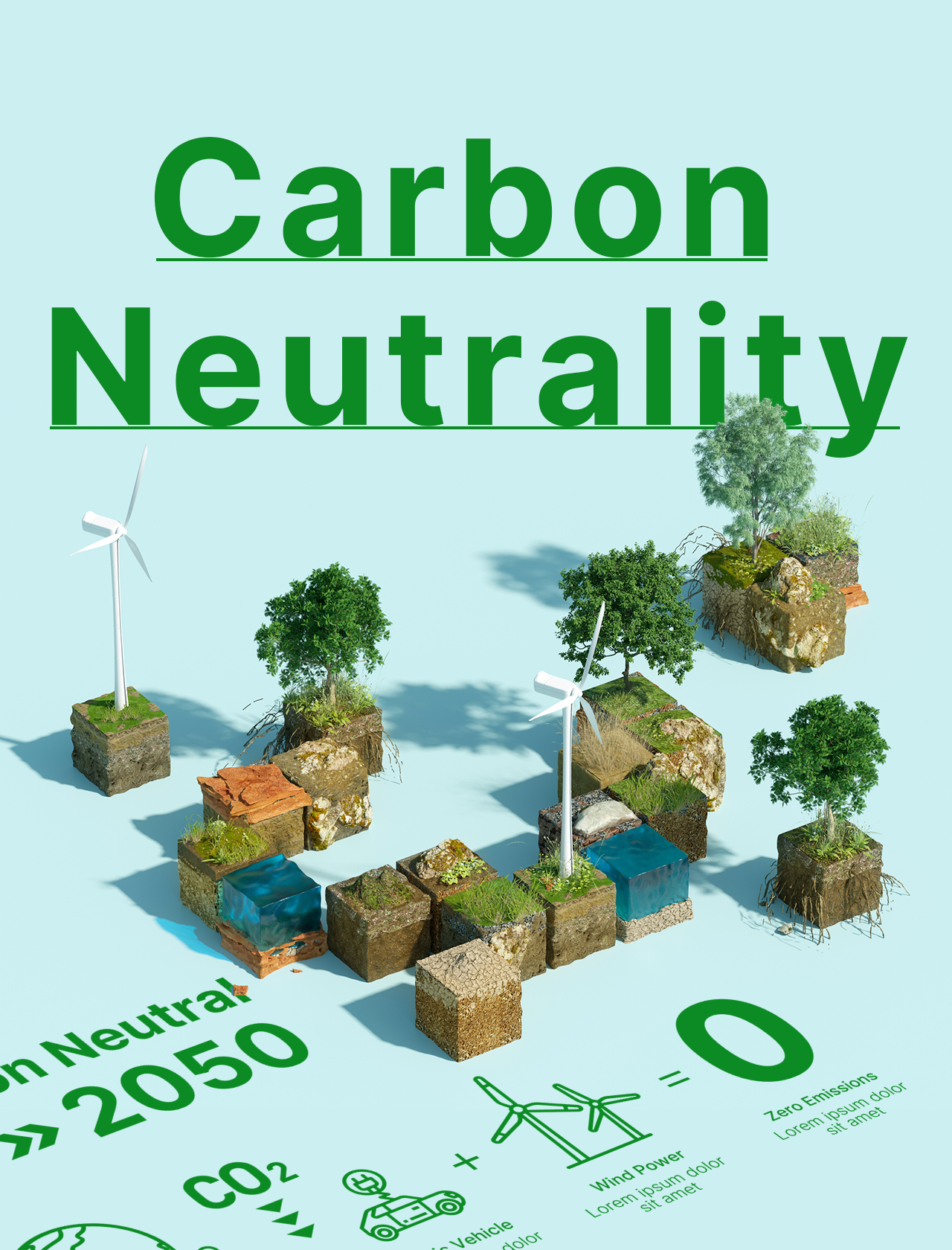
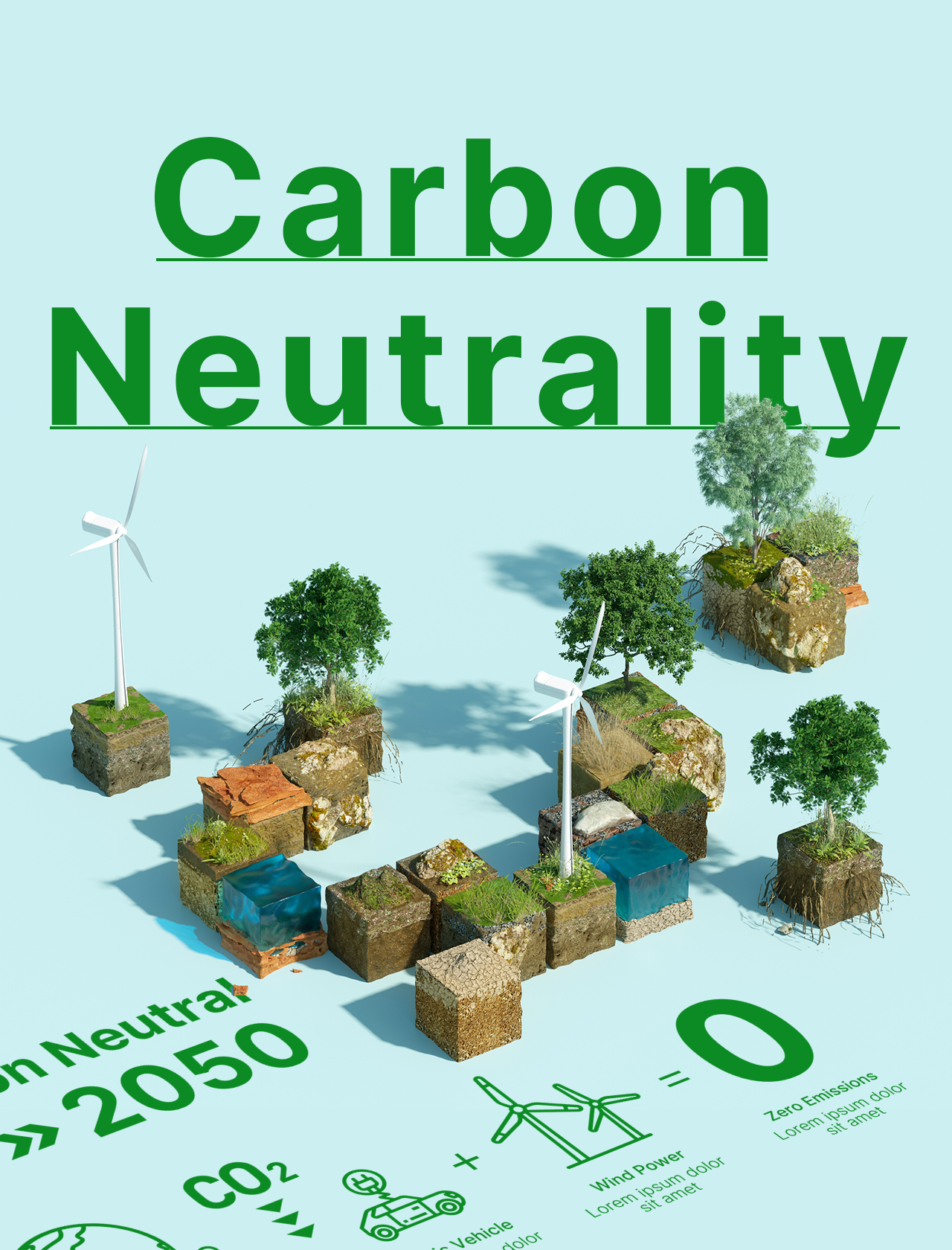
OPEN HUB
THEME
Carbon Neutrality
#脱炭素