
01
2025.07.18(Fri)
目次
——5人に1人が後期高齢者となる2025年問題をはじめ、多くの企業で人手不足が深刻化しています。こうした課題に対し、生成AIはどのような可能性があると感じていますか。
中山 浩太郎氏(以下、中山):生成AIは雇用を奪うという見方がある一方で、人手不足に悩む企業の救世主になりうる技術です。
やらなければいけない業務はたくさんあるのに、対応できる人材が不足している。こうした業務と人材のギャップが生まれている場面に生成AIを活用することで、労働力不足の解決が期待できると思います。

北川 公士(以下、北川):同感です。ただし、現状では生成AIは人の労働力を完全に代替するレベルには達しておらず、まずは生産性を高めるという観点で活用するべきでしょう。
人手不足の解消という観点では、生成AIが広まる中で人材に求められるスキルも変わるため、生成AIの活用を前提とした社員のリスキリングも必要でしょう。
——生成AIの活用によってどのような業務が大きく変わる可能性がありますか。
中山:近年業務効率化の流れで導入が進んできたツールにRPAがあります。しかし、RPAはあらかじめルールを設定したうえで定型的な特定の作業を自動化するのに対して、生成AIは前提となるルールを定めずとも柔軟に非常に幅広いタスクに取り組むことができます。この点はかなりの違いがあります。
特に生成AIを活用するインパクトが大きいのは、ITが人間とのコンタクトポイントになっていた領域です。たとえば、営業、マーケティング、PR、顧客対応など、テキストでやりとりする情報量が多い業務に生成AIを導入すると非常に有効だと思います。
たとえば、今まで顧客対応を実施する中で、1人のオペレーターが数名の顧客しか対応できなかったのが、生成AIを活用することで数十人を同時に対応できるようになります。また、PRやマーケティングの領域でも、月1本だった情報発信を数十本に増やすことが可能です。
つまり、生成AIを活用することで生産できるケタが1つ増えるのです。

北川:生成AIがカバーできる業務範囲は幅広いですが、現時点で活用しやすいのは、受付業務やコールセンターなど一定のルールがあるオペレーショナルな業務です。
一方、今後は膨大なデータを扱う専門家の業務支援でも生成AIの活用は広がっていくでしょう。例えば、開発者向けのプログラムコード作成支援などは、すでに一般的になってきておりますし、生成AIを使って法務に関する業務を支援するサービスなども増えてきています。
——今後は生成AIの活用を前提とした組織づくりが必要になると思いますが、生成AIと人、どのように役割分担して、組織を設計するといいのでしょうか。
中山:生成AIは膨大な知識をもとにいろいろなタスクを処理することができますが、さまざまな状況を複合的に把握して状況判断をすることはまだ苦手です。生成された回答が浅かったり、間違えたりすることも正直多い。
膨大なデータや知識が必要となる細かいタスクは生成AIに任せて、大局的な視点を持って判断する部分を人が担うという業務の仕方が今後は定着していくと考えています。
一方、組織の仕組み自体はそこまで大きく変わらないと思います。生成AIによって生産性は1が10になるくらいに大きく飛躍しますが、それぞれの業務の役割や意思決定の仕組みは従来通りでよいでしょう。
北川:私も同意見です。ただし、生産性向上によって生まれた余力をより創造的な業務やR&Dにシフトさせていくことは必要です。たとえば、ある業務で10%の生産性向上が実現できれば、その分のリソースを新規事業開発などに割くことで企業価値の向上につなげることができます。
単純な作業は生成AIでカバーし、新規事業の立ち上げや強化などAIができないコア業務に人材を振りわけていくことが、企業の競争力強化につながっていくと思います。

——多くの企業が生成AIの導入を進めていますが、企業が直面しやすい課題はありますか。
中山:最大のボトルネックは人材です。AI技術について適切な知見を持ち、「何ができて、何ができないか」を理解している人材が不足しています。上場企業では「AIゼネラリスト」と呼べる人材が社内にいることがありますが、多くの企業ではまだまだ不足しているのが現状です。IPAの調査によると、日本のAI人材は諸外国と比較して圧倒的に少ない。
そのため、生成AIというキーワードだけが1人歩きしてしまい、導入するだけであらゆる業務が劇的に変わるような印象がもたれてしまっているケースもあります。高度なAI技術者の育成を進めると同時に、一般社員から経営層まで含めた組織全体でAIリテラシーを高める教育を進めることが大切です。
北川:生成AIを「魔法の箱」のように捉えている方もいますよね。実際、私も登場した当初はそう感じました。しかし、当然ですが、できることとできないことがあります。
生成AIを導入するにあたってまず考えなければいけないのは、「何をしたいのか」「何が課題なのか」を明確にすることです。「生成AIを導入したい」という漠然とした要望では効果的な活用は難しいでしょう。具体的な課題が明確になれば、必要なデータや最適なモデルの選定に進むことができます。
また、日本企業特有の保守的な姿勢が生成AI導入の課題となるケースもあります。
たとえば、LLMを用いたFAQシステムで6〜7割の精度が出たとします。この精度、どう思いますか?AIの知見がある人材なら「6〜7割の精度がでれば十分」と考えます。しかし、保守的な企業だと「9割以上の精度がないと使えない」という声が出てくることがあります。
欧米や中国の企業は、ある程度の精度があれば導入して改善しながら進めていくことが一般的です。しかし、日本の製造業などでは品質へのこだわりが強いことの裏返しで、間違いを許容できないカルチャーを持つ企業も多い。精度の高さを求めるあまりに、生成AIの活用にブレーキがかかってしまうケースがあるのです。
中山:そもそも人間でも間違えることがあるのに、生成AIに100%の精度を求めることがおかしいですよね。ウォータフォール型ではなくアジャイル型で、トライ&エラーを繰り返しながら最適化していくべきです。

——生成AIの活用について企業からは具体的にどのような相談が寄せられていますか。
中山:少し前は「生成AIで何かしたい」といった漠然とした相談が多かったですが、最近は「LLMでこういう課題を解決したい」という具体的な相談が増えて来ました。
また、NABLASへの依頼で増えているのがフェイク検知です。生成AIでつくられたコンテンツで個人・企業が不利益を被るケースが増えているため、なんとかそれを見破りたいというニーズが高まっているのです。
NABLASでは現在フェイクを検知するソリューションを展開しており、すでに複数の企業や団体で活用されています。
フェイク検知技術は、従来人間では対応できなかった課題を解決し、訴訟リスクを抑えるだけでなく数億円規模の損失を防ぐ可能性もあります。訴訟知的財産保護の観点からも、今後はフェイク検知の技術はますます高まっていくはず。生産性の向上だけに留まらない生成AIの新しい価値として、評価していく必要があると考えています。
北川:NTTコミュニケーションズでは、CX(カスタマーエクスペリエンス)、EX(従業員エクスペリエンス)、CRX(サイバーレジリエンストランスフォーメーション)という3つの軸で生成AI関連のソリューションを展開しています。
特に相談が多いのが、コンタクトセンターでの生成AIの活用です。たとえば、オペレーターの会話をリアルタイムでテキスト化し、適切な対応マニュアルを提示するシステムを導入することで、経験の浅いオペレーターでも質の高い対応が可能になります。
また、企業内データを活用したRAGの導入もニーズが高まっていますし、セキュリティ分野ではAIアドバイザーを開発し、システムの脆弱性診断などにも活用を始めています。
これまでは業務にどのように生成AIを溶け込ませるかを課題とする企業が多かったですが、今後はROIも重視されていくでしょう。その時、目の前の結果だけを見て「投資コストを回収できない」と判断するのか、3年後を見据えて「コストを投じる価値がある」と判断するか。
生成AIは導入してすぐに精度が出るものではなく、使いながら改善していくものなので、中長期的な視点で価値を評価する必要があります。

——生成AIの進化はどこまできているのでしょうか。最先端の事例を教えてください。また、企業の生成AI活用は今後どのように広がっていくと思いますか。
北川: 2025年1月に開催された「CES2025」ではAIエージェントの実用化が近づいていると感じました。単なる人の代替ではなく、より自律的な判断や行動ができる存在へと進化していくと思います。
たとえば製造業では生成AIによるロボット制御の研究も進んでおり、「やって」と指示するだけで適切な動作を判断・実行できるようになる日も近いでしょう。
中山:今まではテキストや画像生成など、コンピューター上で人間をサポートする形だったのが、今後3〜5年で実世界の中で人間とインタラクションしながら幅広いタスクに取り組めるようになっていくと思います。
また、最近では画像や言語、音声などさまざまなデータタイプを1つのモデルで統合的に扱うマルチモーダル技術が進展しています。これにより、画像を見てテキストを生成したり、テキストから画像を生成したりすることが可能になりました。この技術がさらに進めば生成AIへのインプットがより簡単になりますし、高度な判断や実世界のインタラクションにもつながります。
北川: 生成AIの進化はものすごく早いため、今言っていることや注目されているテクノロジーが1年後には古くなっているかもしれません。また、日本ではまだ大きな危機感を感じないかもしれませんが、アメリカや中国などは生成AIをはじめとした先進的な取り組みにどんどんトライしています。
国内でも人手不足が深刻化していく中、生成AIは私たちの働き方や組織のあり方を大きく変えていく可能性を秘めています。生成AIの活用は選択肢ではなく、企業の成長と生き残りをかけた不可欠な取り組みとなっていくはずです。
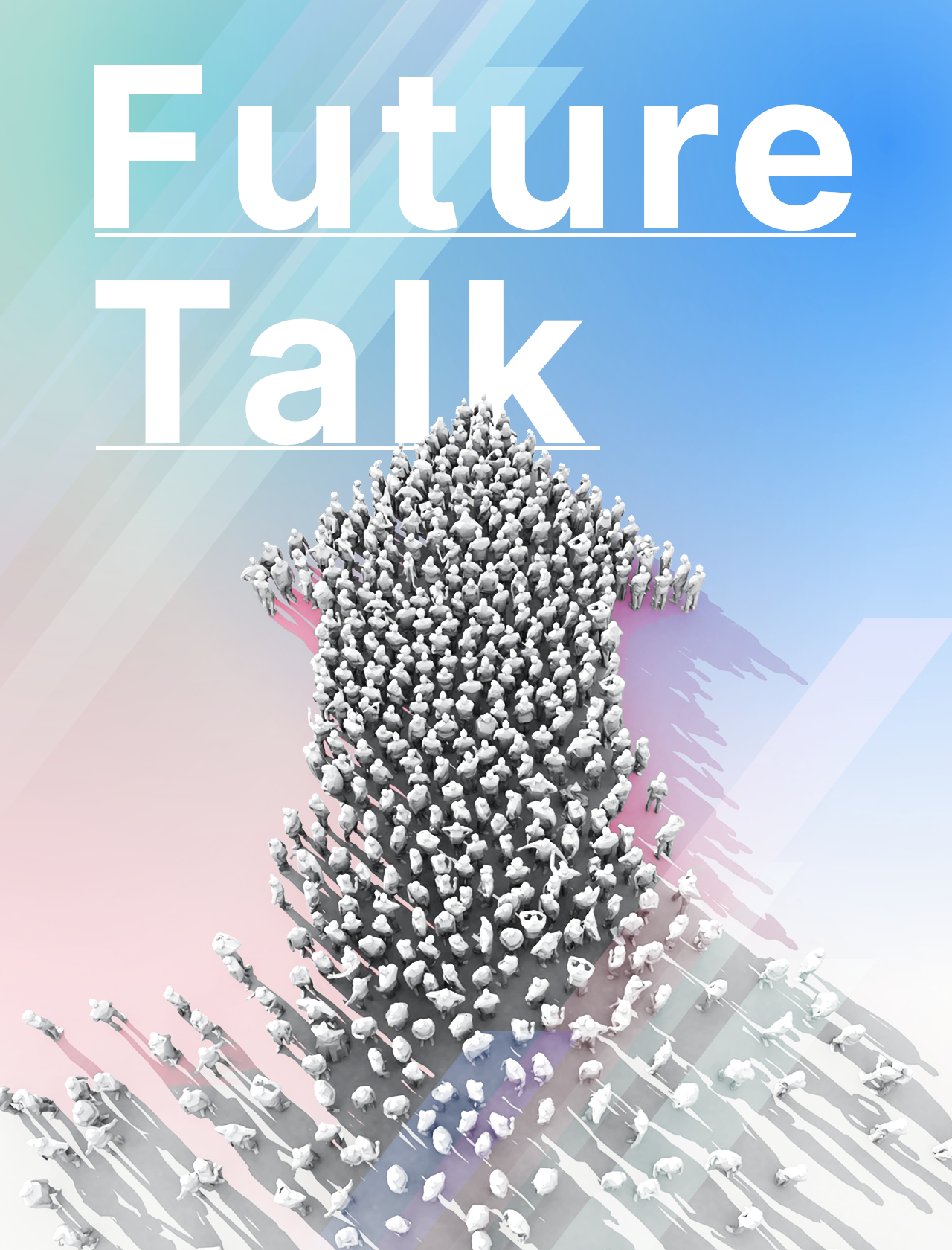
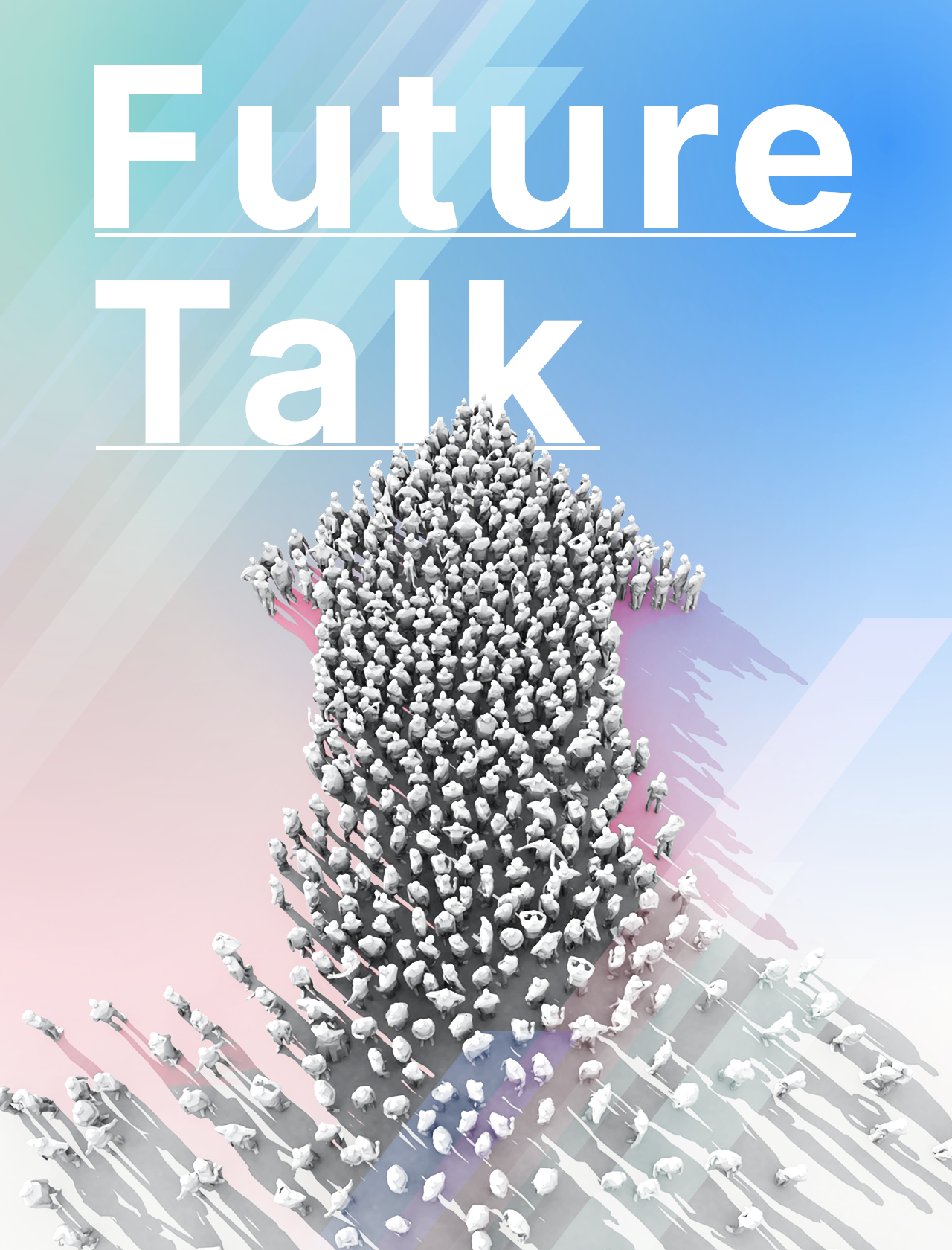
OPEN HUB
THEME
Future Talk
#専門家インタビュー