
01
2025.07.18(Fri)
この記事の要約
環境省と企業のサステナ担当者が参加したイベントの内容をレポートします。第1部では環境省の島田智寛氏が「デコ活」について講演し、2030年までに家庭のCO2排出量を66%削減する目標と、官民連携による行動変容の重要性を説明。第2部ではNTTコミュニケーションズが実施する「ONE TEAM CHALLENGE」の取り組みを紹介します。ONE TEAM CHALLENGEには約1000名の従業員が参加し、身近なエコアクションの実践とCO2削減量の可視化により、環境意識の向上を実現しました。第3部ではONE TEAM CHALLENGE参加企業によるクロストークを実施。トランスコスモス、ネットワンシステムズ、三井住友銀行の担当者が、従業員の意識改革や行動変容に向けた課題と取り組みを共有しました。各社とも「自分ごと化」「共感」「見える化」を重視し、継続的な活動を推進していくとしています。
※この要約は生成AIをもとに作成しました
目次
2050年カーボンニュートラルおよび2030年度削減目標の実現に向け、環境省が推進する「デコ活(脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動)」。環境省 脱炭素ライフスタイル推進室長でデコ活応援隊長を務める島田智寛氏は「国民一人ひとりの脱炭素型ライフスタイルへの転換」をテーマに掲げるデコ活が生まれた背景について次のように説明します。
「脱炭素の実現に向けて、衣食住、職場、移動、買い物などあらゆるシーンでCO2削減に取り組むことにより、家庭におけるCO2排出量を2030年までに2013年度比で66%削減する必要があります。
しかし、『脱炭素』という言葉の認知が広まる一方で、『何をしたらよいか分からない』と具体的な行動に結びついていないのが現状です。これに対し私たちは大きな危機感を持っており、現状を変えていくためにさまざまな施策を展開しています」

その1つが「デコ活アクション」の発信。「電気も省エネ 断熱住宅」「こだわる楽しさ エコグッズ」「感謝の心 食べ残しゼロ」「つながるオフィス テレワーク」などのスローガンを掲げ、アクションを呼びかけています。
また、国、企業、自治体、団体、消費者と一体となって脱炭素を進めるべく発足したのが「デコ活応援団」です。これは1000以上の企業、300以上の自治体などをはじめ1900を超える参画者で構成された官民連携協議会で、垣根を超えた情報共有、意見交換の場として機能しています。
環境省では、このコミュニティーによって企業同士や企業×自治体などのマッチング、脱炭素につながる情報発信、補助金による取り組み支援を促進。官民連携により活動を展開し、デコ活の機運を高め、行動変容やライフスタイル転換を後押ししていくことが狙いです。
補助金の採択にはさまざまな企業や自治体が選ばれており、NTT Comが開催している「ONE TEAM CHALLENGE」もその1つです。企業や消費者を巻き込んだデコ活の広がりについて、島田氏は次のように展望を語りました。
「脱炭素は『言うは易く行うは難し』です。そんな中、異業種の企業が一体となって従業員の脱炭素活動を促し、アクションの効果を見える化して発信するONE TEAM CHALLENGEは画期的なプロジェクトであり、今後もこうした取り組みへの支援を強化していきたいと考えています。
例えば、企業目線では従業員の皆さんが脱炭素に自然と取り組める環境や風土をつくっていくことで、一人ひとりのライフスタイルの転換や定着を促すことができるでしょう。また企業から消費者に対して、製品やサービスを通じて『脱炭素な暮らしをしましょう』というメッセージを発信していただくことも重要です。
さらに消費者目線で考えれば、旅行やスポーツといったイベントにおいて、脱炭素につながる行動が自然とできるような仕掛けがあれば意識の変化が生まれやすく、その後の日常生活での行動変容につながることも期待できます。官民連携で力を合わせれば、社会全体により多くの変革を起こせるはずです。デコ活は2022年にスタートしたばかりですが、試行錯誤を重ねながら横断的な取り組みを加速していきたいと考えます」

2023年にスタートしたONE TEAM CHALLENGEは、日常生活やビジネスシーンでできるエコアクションを選んで実践すると、その行動によってどれだけCO2が削減されたのかが数値化され、アプリ上で確認することができる仕組みです。
2024年のONE TEAM CHALLENGEには、多様な業界の企業が参加し、約1000名の従業員がエコアクションに取り組みました。その結果、約3万回のエコアクションにより14トン近くのCO2削減を達成。また、蓄積したエコアクションのデータを分析した結果、行動変容を実現するための4つのヒントが見えてきたといいます。第2部のプレゼンテーションを担当したNTT Comの宮田吉朗は次のように解説しました。
「1つ目は、身近で実行しやすく勤務中でもできるエコアクションを多く用意すること。2023年のエコアクションは10種類ほどでしたが、2024年は「出社」「在宅」「休日」などのシーンに合わせて20種類以上のエコアクションを用意したところ、『環境にやさしい行動に取り組めた』という従業員が65%から79%に増えました。
2つ目は、数値の推移で成長や貢献を実感できること。CO2削減量の数値化やフィードバックの仕組みが、環境行動を継続させるモチベーションにつながっています。
3つ目は、多面的な評価をすること。エコアクションの「実施回数」と「CO2削減量」は必ずしも連動しておらず、実施回数は上位にランクインしているユーザーがCO2削減量はランク外というケースもあり、複数の観点から評価ができる仕組みが有効だといえます。
4つ目は、情報を届けること。『環境配慮製品に気付いたときは購入する』『環境問題については受動的に情報を得ている』という従業員が半数を占めていることから、情報の届け方を改善することで行動変容につなげられると考えられます」

また、ONE TEAM CHALLENGEの2年間にわたる活動を通して、環境への意識や行動をより広く浸透させるためのポイントは、一人ではなく周りを巻き込むこと。自分ごととして実行しやすいアクションを伝えて、成果や貢献度合いを共有し合う環境をつくることが重要だと来場者に語りかけました。
第3部では、2024年のONE TEAM CHALLENGE参加企業から、トランスコスモスの菅岳大氏、ネットワンシステムズの和田智之氏、三井住友銀行の清水倫氏を迎え、脱炭素社会の実現に向けた従業員の意識・行動改革について意見を交わしました。
「従業員の意識・行動改革は大変重要ですが、弊社はお客さまの業務代行やWebサービスの提供がメインであり、業務と脱炭素が結びつきづらいという課題があります」と語る菅氏は、その対策として従業員が環境活動などに参加できるソーシャルグッド活動制度の導入を検討していると明かしました。
和田氏は「情報インフラ構築やICT利活用を実現するノウハウの提供を行っており、ONE TEAM CHALLENGEへの参加は変革のきっかけになると期待しています。脱炭素の目的を本質的に理解することは出発点であり、従業員一人ひとりの関心を高め、行動につなげてもらうことが重要だと感じています」と述べます。
銀行業界からの視点として、清水氏は「従業員の意識・行動改革は銀行業においても極めて重要です。銀行におけるScope3の大層は融資先のお客さまによるCO2排出量であり、従業員一人ひとりが当事者意識を持ってお客さまと真剣に対話すること、これを積み重ねていかねばScope3のネットゼロは実現できない」と指摘しました。



社内浸透における課題について、和田氏は「ビジネスモデル上、事業成長に伴いCO2排出量も増えていくジレンマはある」としながらも、定期的に開催するサステナビリティデーでの啓発活動、GXトレンド勉強会、カーボンニュートラル入門コースの開設など、社内外に向けた取り組みを通じて企業姿勢を示すとともに、従業員の理解促進を行っています。
清水氏からは「お客さまとの対話において脱炭素がテーマに上がるフロント業務の従業員のみならず、ミドルバック業務に携わる従業員も含めた意識醸成、良き取り組みをたたえ合うカルチャーの醸成が重要」との見解が示されました。約7万人の従業員を抱えるトランスコスモスでは、「ISO 14001(※)の環境マネジメントシステムなどを活用することで、拠点ごとに自発的に脱炭素活動を行う文化が醸成されつつあります。ONE TEAM CHALLENGEは複数の拠点で実施しているのですが、結果が見えることにより互いに競争心が生まれ、アクションを活発化する良い刺激になっています」と菅氏は説明します。
※ ISO 14001:環境マネジメントシステムに関する国際規格。社会経済的ニーズとバランスをとりながら、環境を保護し、変化する環境状態に対応するための組織の枠組みを示しています

今後の展望について、清水氏は「一隅を照らす、これすなわち国宝なり」という仏教僧の最澄の言葉を引用し、「業務や部署にかかわらず、脱炭素に真摯(しんし)に取り組む従業員の頑張りにもっと光を当てたい」と語り、全社に発信し、皆でたたえ合うカルチャー醸成へのチャレンジに意欲を示しました。
菅氏は「ITサービス企業にもできる環境貢献活動として、沖縄県での従業員参加型の植樹活動や、企業版ふるさと納税を活用した大分県の森林J-クレジット創出事業などを支援しています」と述べ、今後もこうした制度を活用するとともに、従業員が積極的に参加できるような環境を整えていく意向を示しました。
最後に和田氏は、「従業員に向けて脱炭素の重要性を引き続き発信していくとともに、新たに策定する中期経営計画では、脱炭素に向けたKPIとして単なる数値目標ではなく、お客さまと弊社の双方にとってのメリットを考えた上で目標を設定したい」と述べ、社内外に目を向けて今後も脱炭素活動を加速させていく決意を示しました。
環境省とONE TEAM CHALLENGE参加企業の活動から見えてきたのは、「自分ごと化」や「共感」「見える化」といったキーワードの重要性。従業員一人ひとりが主体的に取り組める環境づくりと、官民が連携した継続的な活動によって、2030年の目標達成、そして2050年のカーボンニュートラル実現への歩みを着実に進めていくことが期待されます。


【イベントアーカイブのお知らせ】
本イベントの動画は、以下のバナーよりご視聴いただけます。
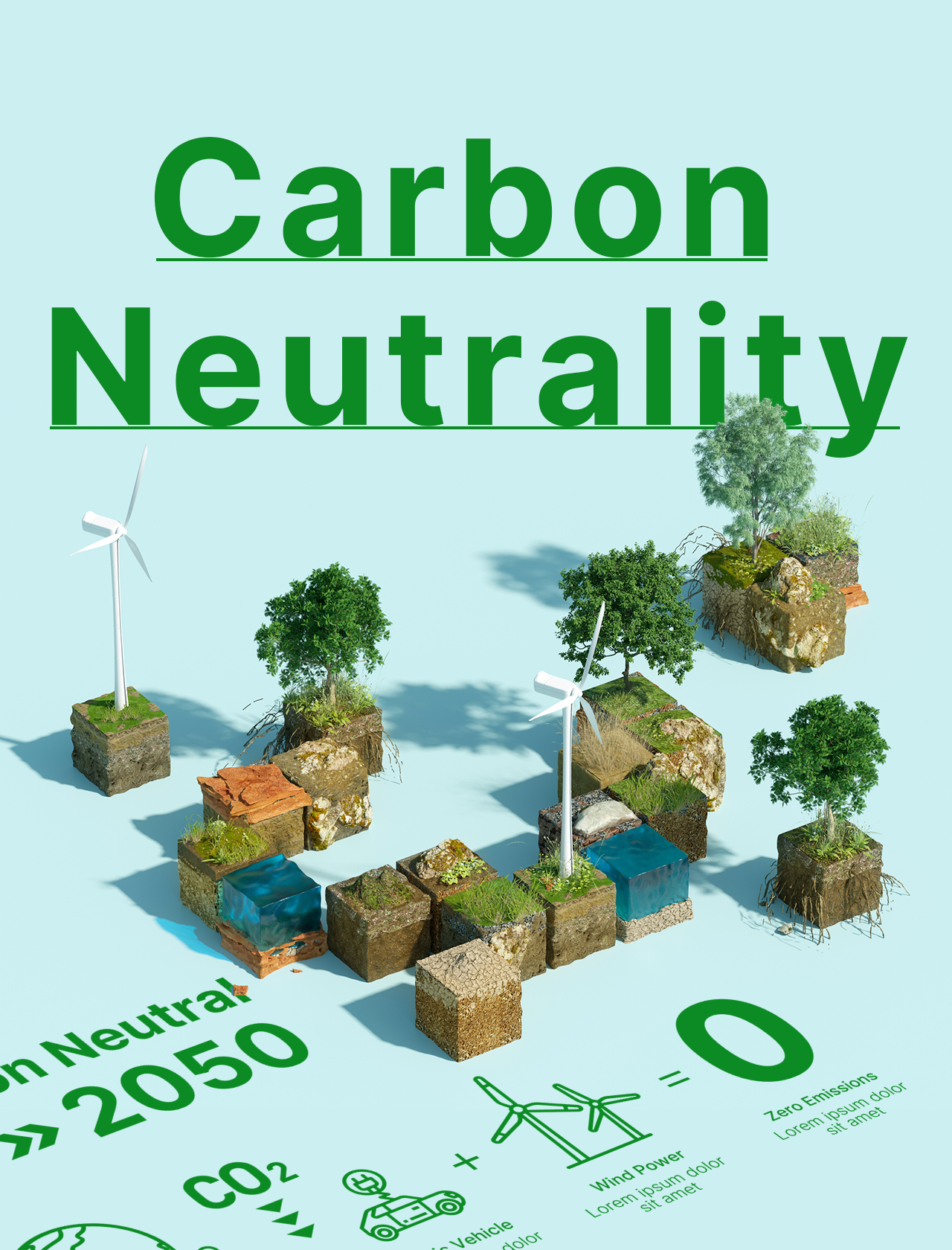
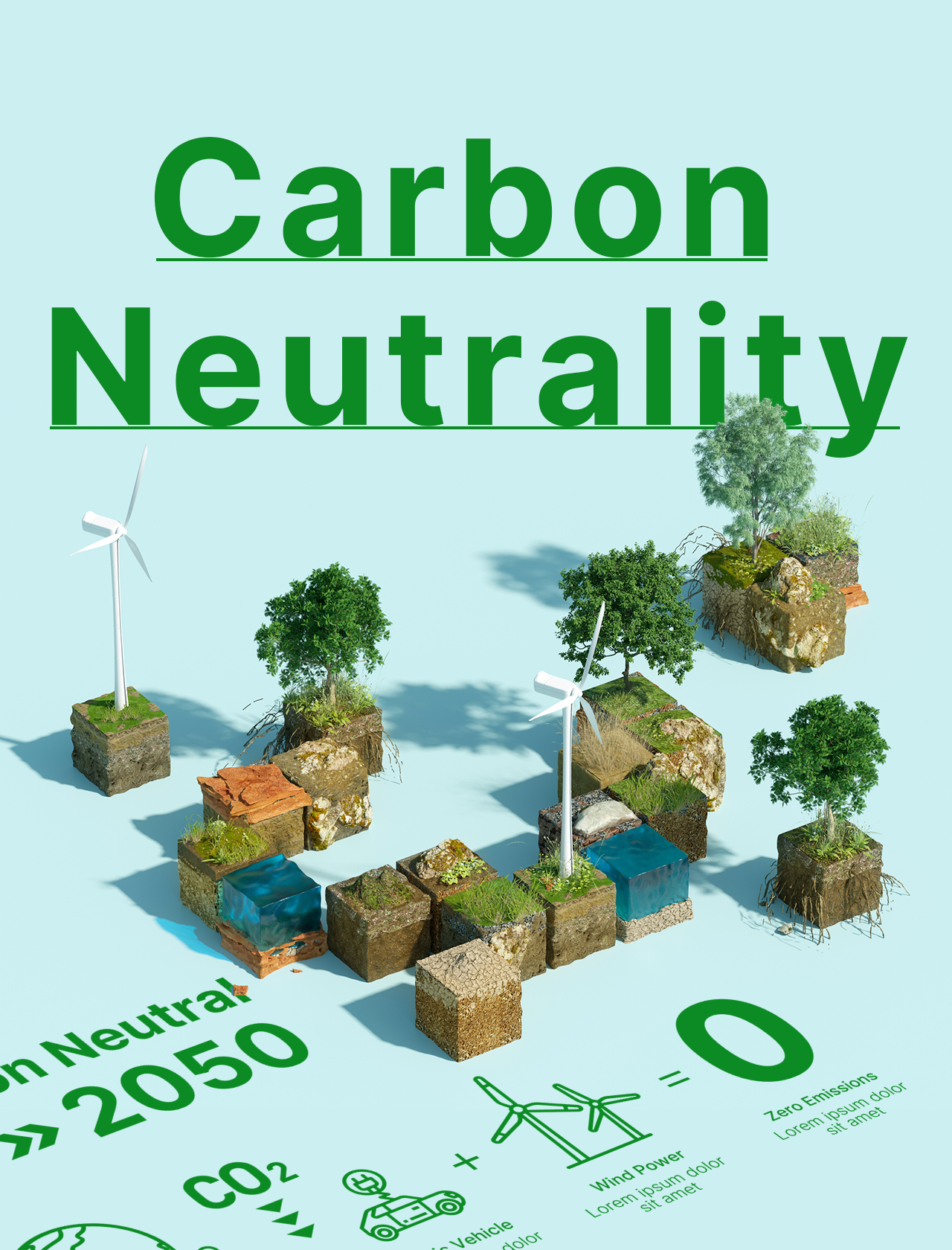
OPEN HUB
THEME
Carbon Neutrality
#脱炭素