
01
2025.03.06(Thu)
目次
――今回、飯豊町でゼロカーボン日本酒をつくるプロジェクトが発足した経緯についてお聞かせください。
城戸氏:飯豊町では人口減少が進んでいますが、年間約13億円のエネルギー代金を町外の電力会社に支払っていて、その半分ほどが電気代です。これを地産地消で賄えるようになれば、6〜7億円を地域振興などに活用できるという発想のもと、一昨年くらい前から脱炭素化を通じた循環型社会づくりへの機運が高まっています。環境省の脱炭素先行地域という事業へのチャレンジを始め、第6回の応募で採択されました。バイオマス発電など、いろいろな施策を企画書に入れる中で、「お酒もあるよね」という話になり、ゼロカーボンのお米をつくり、山形らしい日本酒によって地域のブランドを高めるというアイデアを盛り込んだところ、高い評価を得ることができました。

小野氏:ゼロカーボンのお米というのは、地域の畜産から出てくる肥料を使って田んぼをつくり、さらにその田んぼでメタンガスの排出も削減できる手法でつくられるお米のことです。この手法については農林水産省が、夏に田んぼの水を抜いてヒビが入るまで乾かす「中干し」期間を直近2年間の平均より7日間延長することで、メタンガスの排出を抑制することを、温室効果ガスの排出削減活動として認証し、カーボンクレジットとして市場で売買もできる「J-クレジット」の制度をスタートさせました。これによって、地域でさらに価値を循環させることができるのですが、認証を受ける方法がわかりませんでした。そんな時、NTTドコモビジネスさんが、「J-クレジット」認証のサポートをしていると聞き、私の大学の後輩を通じて藤田さんを紹介いただきました。
藤田:NTTドコモビジネスではこれまで約200の生産者さんに、「J-クレジット」の認証サポートを行ってきた実績があります。カーボンクレジットの推進を通じて、一次生産者さんと地域おこしの活動を連結させ、地域の価値創出、また若者の農業への関心を高めることにも貢献したいと思っています。
飯豊町のプロジェクトでは、生産者である沖のカモメさんから田んぼの写真や位置情報などを送っていただき、それを私たちが認証機関へ通せるように整え、デジタル化して送信する認証サポートを担っています。これによって、沖のカモメさんにはクレジットの売却益という価値を還元できます。一方、このお米を使って日本酒をつくる若乃井酒造さんは、製造工程においてなるべく再生可能エネルギーを使っていきますが、ボイラーや重油も使わざるを得ず、そのままでゼロカーボンの日本酒を名乗ることはできません。そこで、沖のカモメさんの取り組みによって発行されたカーボンクレジットを購入することでオフセットし、環境に配慮したゼロカーボン日本酒という訴求力の高い新酒を発表することができるというのが、プロジェクト全体のスキームになっています。

――米生産者である沖のカモメさん、日本酒を製造する若乃井酒造さんが参画することとなった経緯についてもお聞かせください
武田氏:私も小野さんと同じく飯豊町の地域おこし協力隊に参加し、農業担当としての研修先という形で沖のカモメでの米づくりをしています。小野さんとは以前からゼロカーボンという枠組みで何かやりたいと話していました。今回のプロジェクトにおいては、「J-クレジット」の認定条件となる中干し期間の延長に加えて、稲を刈った後に出た藁を秋にすき込んで耕す「秋耕」にも取り組み、メタンガスの排出抑制を徹底していきましたが、これにより以前は休んでいた期間に時間と手間と燃料をかけて作業をすることになります。「環境にいい」というだけの理由では難しい取り組みですが、農家としても収入が上がることになれば、若い人も農業が職業の選択肢に入ってきて後継問題の解消につながるかもしれません。
またせっかく環境にいいお米をつくっても、農協や大手のスーパーに他のお米と変わらない値段で出荷しては意味がないと思っています。地元の若乃井酒造さんに使っていただき、“ゼロカーボン“という付加価値をつけた商品を出すことで新しい層が日本酒に興味を持ってくれるとか、それによって若乃井酒造さんの利益にも還元できるといった循環が生まれるといいなと思っています。

大沼氏:地産地消でゼロカーボンの日本酒をつくりたいというお話をいただき、うちは地域で唯一の酒造メーカーですから、お断りする理由はありませんでしたね。実際、米を選定する時に、沖のカモメさんでは酒米はつくっていませんでしたが、地元のブランドである「つや姫」がありました。もともと、つや姫で日本酒をつくってみたいという思いはありましたし、地産地消という観点からもぴったりのお米です。
SDGsというワードからは、多くの人が無駄を出さないというイメージを連想しますよね。だからお米自体をあまり削らず、町内産のお米で、山形の工法によるお酒造りに挑もうと構想しました。またうちの会社は、お酒を通じた人の縁を大事にしていますから、プロジェクトとして1つの商品をつくる時につながる縁の考え方にはすごく共感しましたし、ゼロカーボンという取り組みを広める観点からも意義を感じました。
ゼロカーボンやSDGsといった言葉だけでは伝わらないコンセプトが、新しい日本酒を通じてひとつのストーリーとして語られた時に、全く違う説得力を持ち始めますよね。「J-クレジット」は設備に大きなコストをかけられない企業でも取り組める活動ですし、うちもまだ設備導入はせず、製造工程でも重油を使っていますが、こういうプロジェクトをきっかけに将来的な設備導入を検討するきっかけになるかもしれないとも思っています。
――実際に、ゼロカーボン日本酒をつくる中で、ご苦労された点はありますか?
武田氏:中干しの延長に関しては、米の質が落ちないように、天候や田んぼの状態を見ながら進めなくてはいけません。今のところ、中干し時期に雨が降ったこともあり、米づくりに影響は出ていませんが、あまりにも干ばつがひどければ、カーボンクレジットを諦めて水を入れざるを得ないという判断を迫られるかもしれません。周りの農家さんに聞くと、中干しをするとヒビが入るのは当たり前で、それによってメタンガスの発生が抑えられるのですが、あまりに割れすぎると根っこが切れてしまうという影響は起こり得ると考えています。
藤田:実際に、中干し延長の実施による影響はさまざまで、収量が減少する可能性も指摘されている一方、むしろお米の品質が向上するケースも見られます。生産方法を変えることで「J-クレジット」の認定を受けられるメリットと同時に、収量や作物の品質に与える影響も踏まえた上で、生産者さん自身が田んぼの状況を見ながら臨機応変にご対応いただくことが重要です。取り組み自体は私たちから強制するものではなく、途中で中断される場合もご判断は生産者さんに任せており、それによるペナルティなどもありません。
武田氏:今回のプロジェクトにおいては、うちが中干しをやめて「J-クレジット」が発行できなかった時に、若乃井酒造さんに渡すクレジットがなくなると、ゼロカーボン日本酒を謳えなくなってしまうので、その時にどうクレジットを確保するのかも、今後の課題ですね。NTTドコモビジネスさんに調達いただくという方法もあるのかもしれません。
――5月10日、飯豊町の道の駅で新酒発表会が開催されました。ゼロカーボン日本酒の反響はいかがでしたでしょうか?
大沼氏:地元のお客さんが多かったので、いつも飲んでいる日本酒と何が違うのかという興味を持っていただけました。感想としては、飲みやすいという声が多かったので、あまり日本酒を飲まない若い方でも手に取りやすい味なのかもしれません。
精⽶歩合70%のお酒としては、一般的な価格より1000円ほど高くなっていますから、地元の多くの方が関わっているというストーリーを含めて、環境にも興味のある意識の高い層がメインのターゲットになっていくと思います。

城戸氏:そういったストーリーを語る上でも、ネーミングにはこだわり、みんなで50案くらい出して議論していきましたね。30年後、温室効果ガスの排出量が実質ゼロのつくり方が当たり前になっている、人の縁がつながって永遠にお酒が造られ、いつまでも酔えるという願いを込めて「永遠酔(とわよい)」と名付けました。
大沼氏:そうですね、デザイナーさんにも思いを伝えて、すごくいいラベルをつくっていただきましたし、ネーミングも最終的にはデザイナーさんが考えてくださったものでした。また、反響という意味では、地元の新聞にも取り上げられ、酒屋さんから「うちでも扱えますか?」という連絡は多くいただきました。大量に生産するというよりは、興味を持ち、共感していただける方に、いつまでも楽しんでいただけるようなブランドになればいいと思っています。

――今後、このプロジェクトはどのように発展させていきたいとお考えでしょうか?
小野氏:日本も世界も脱炭素に舵を切る中で、私たちも飯豊町の脱炭素化に取り組み、住民の方に説明する機会も多いのですが、大沼さんも仰っていた通り脱炭素やゼロカーボンと言われてもピンとこないという人も少なくありません。今回のプロジェクトで初めてひとつの商品ができたので、私たちの活動の表す象徴としても大事にし、続けていくとともに取り組みを広げていけたらと思っています。

城戸氏:昨日も大沼さんと打ち合わせをしていて、来年もゼロカーボンの日本酒をつくりましょうという話になりました。いろんな人が関わってできているお酒で、NTTドコモビジネスさんとも「J-クレジット」をきっかけにつながることができたので、この縁をさらに広げ、名前の通り永遠に続くプロジェクトに育てていきたいと思っています。
藤田:NTTドコモビジネスとしては、「J-クレジット」の取り組みを通じて、脱炭素社会の実現につなげたいという思いがあります。生産者の方とともにこのような環境価値を作り上げていく上で、今後はデジタル技術を活用していくことも重要です。しかし、その方法として「J-クレジット」の申請のために必要な情報をセンサーで自動的に収集するとなると、生産者さんに導入コストなどの負担がかかることにもなります。衛星の写真など、既存の汎用的な技術を活用することで、生産者さんにとって負担とならない取り組みを実現し、日本全国へと広げていきたいと考えています。
武田氏:中干しした時にちゃんと水を止めたかどうか、今は真夏に田んぼを歩きながらスマホで約400枚を撮影しているので、申請のための情報収集も大変なところはあります。画像は衛星写真やドローンで自動的に収集してもらえたり、メタンガスやCO2の排出抑制がセンサーで自動判別できたりするとありがたいですね。NTTドコモビジネスさんには、今後はその辺も期待したいと思います。
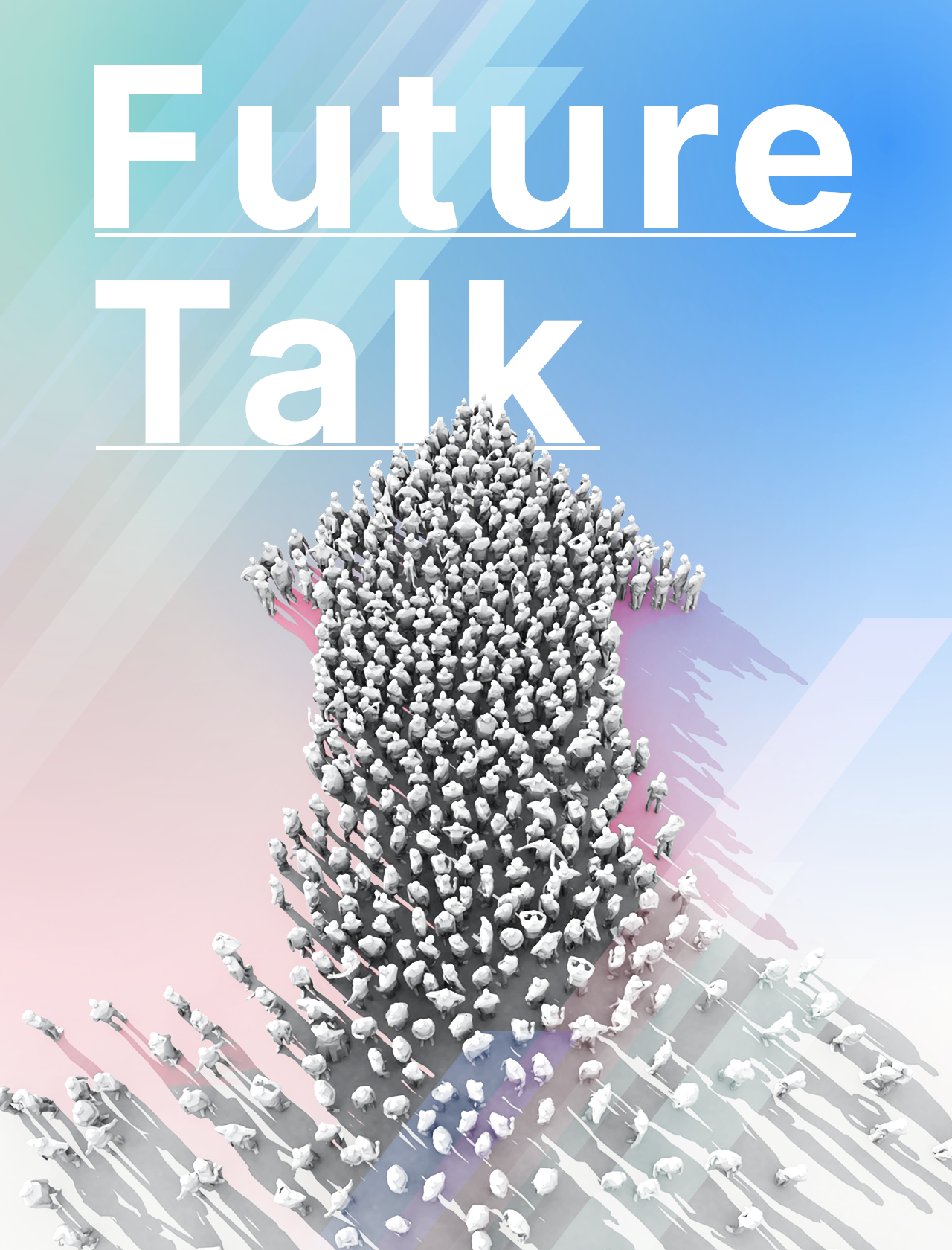
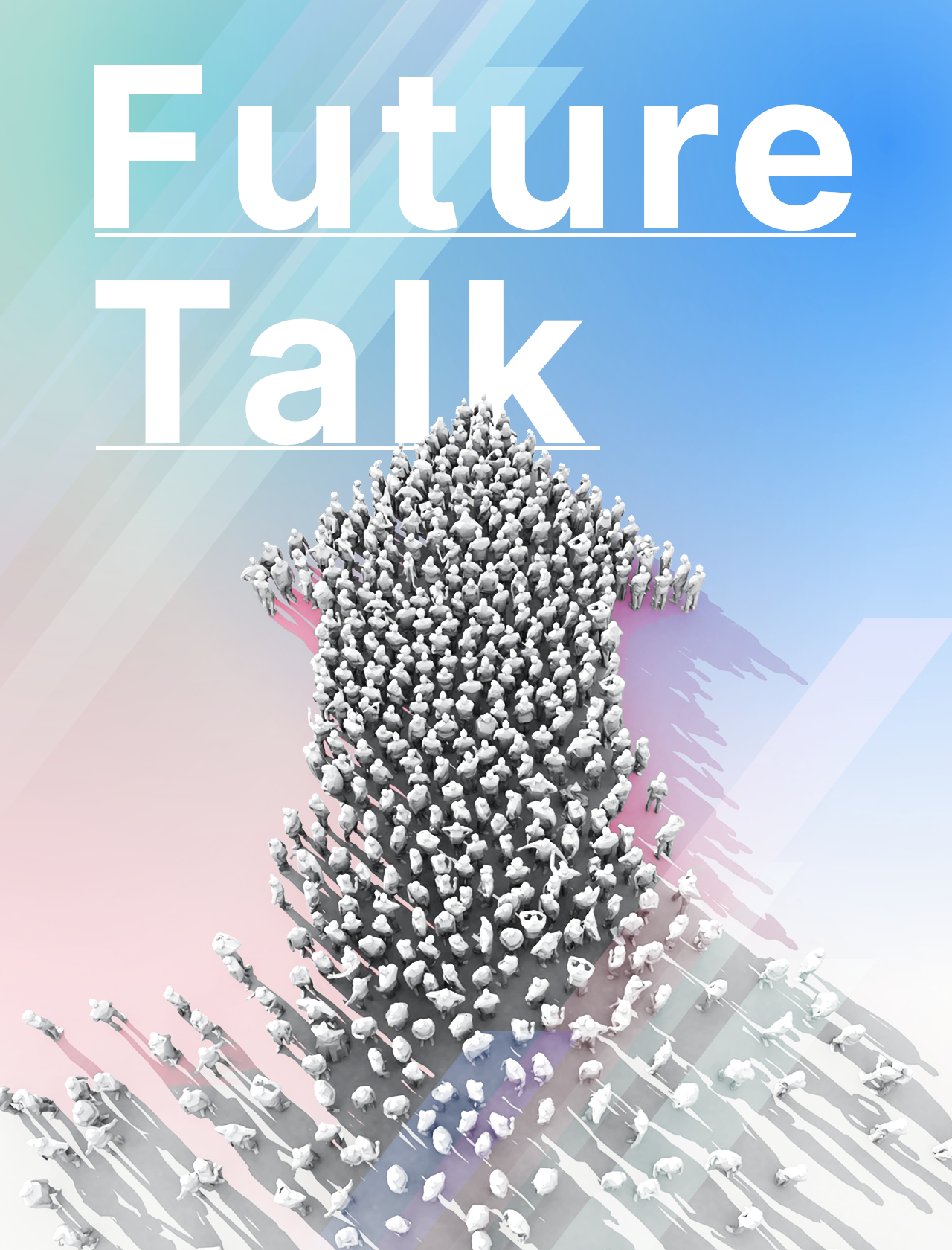
OPEN HUB
THEME
Future Talk
#専門家インタビュー