
01
2025.07.18(Fri)
この記事の要約
連載「Creator's Voice」の第10回ゲストは京都大学教授の出口康夫氏です。AI時代における哲学の役割と、AIと人間の関係性について語っています。
出口氏は、AIの研究開発は「人間とは何か」を問い直す行為だと指摘します。AIを単なる機械ではなく、ある程度の自立性を持つ存在として捉えています。
教育現場でのAI活用については、人間の創造性や独創性がより重要になると予測しています。ビジネスでは、AIコンサルタントやケア領域での活用が進むと見ています。
AIと人間の関係性について、欧米の「主人/奴隷モデル」に対し、日本的な「共冒険者」「親友」としての捉え方を提示します。多様なモデルの共存が重要だと主張しています。今後のAI開発では、開発者もユーザーも明確な価値観を持つことが求められるとします。その軸となる「直感」は、他者との共同作業を通じて磨かれるといいます。
多様化する社会で前進するには、「われわれとしての自己」「共冒険者」という概念が重要になると締めくくっています。
※この要約は生成AIをもとに作成しました。
目次
渡邉史貴(以下、渡邉):まずは、近現代西洋哲学や分析アジア哲学を専門とされてきた出口先生が、AIというテーマに関心を持たれたきっかけについて教えていただけますか。
出口康夫氏(以下、出口氏):2019年にNTTの研究者の方より、「個人のデジタルな分身をつくる」デジタルツインに関する共同研究のお声がけをいただいたことが、大きなきっかけでした。
NTTの研究者の方々は、共同研究にあたって、「わたし」とデジタルツインの関係性をきちんと整理しておきたいという問題意識をお持ちでした。
個人のデジタルツインをつくるということは、「わたし」のコピーをつくること、「わたし」を複数化することを意味します。では、そもそも「わたし」をコピーすることは可能なのか? オリジナルとコピーとは、どのような関係にあるのか?「わたし」をコピーすることは許されるのか? デジタルツインの開発は、このような問題を避けて通れません。これらの問題は、結局のところ、「人間とは何か」「わたしとは何か」といった根源的な問題を改めて問い直すことにつながっていきます。デジタルツインが引き起こしかねない社会的ないしは倫理的な問題を事前に回避するためにも、このような根源的な、哲学的なレベルから概念整理をしたいという理由で、共同研究の申し込みをいただきました。
渡邉:産業側からの要請が先にあったわけですね。その後2023年には、NTTと共同で京都哲学研究所という研究機関を設立されていますが、こちらはどのような活動をされているのでしょうか。
出口氏:京都哲学研究所では、「社会に向けて具体的な価値を提案する」というスタイルの哲学研究を行っています。
20世紀が「科学技術と経済の世紀」だったとすれば、21世紀は「価値の世紀」です。科学技術の進展と経済的繁栄が必ずしも人々のウェルビーイングや世界の平和に直結しないことが明らかとなった今日、改めて「本当の幸せとは何か」、「目指すべき価値とは何か」が問われているからです。
一方、哲学とは価値を提案する学問です。それも、「これこそが正しい」という唯一、絶対の真理の押し売りではなく、1つの可能なオプションを追加することで、結果として価値の選択肢の幅を増やしていくようなスタイルの提案です。社会が1つの価値観で染まるのではなく、多様な価値観が多様な方法で共存しているような社会や個人のあり方を実現する。そのために具体的な価値を提案していくことが、京都哲学研究所のミッションなのです。
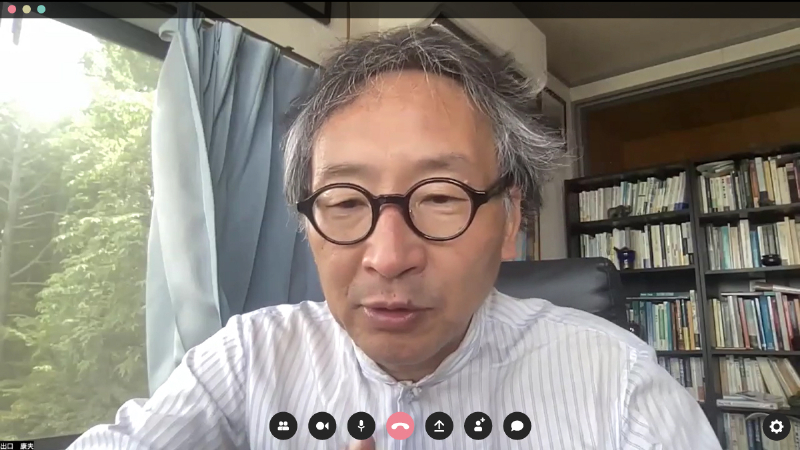
渡邉:画一的な正解が用意されていない時代だからこそ、哲学が求められているというわけですね。そうしたなかで出口先生は「われわれとしての自己」「WEターン」という概念を提唱されていますが、これらについて簡単に教えていただけますか。
出口氏:「WEターン」の出発点は、単独行為不可能性、すなわち「一人では何もできない」という根源的な「できなさ」の認定です。このような認定にもとづいて、行為の主体は個人である「私(I)」から、「わたし」をその一員とする「われわれ(WE)」へとシフトさせるのが、行為者のWEターンです。ここで言う「われわれ」とは、人間や動物などの自然物に加えて、AIやロボットなどの人工物や歴史上の出来事といった多種多様の「エージェント」からなるマルチエージェントシステムです。さらに「自己」を行為者と見なせば、「私としての自己(Self-as-I)」から「われわれとしての自己(Self-as-WE)」への自己のWEターンも導かれます。結果として、「わたし」は常に「われわれ」の一員として捉えられることになります。このような「WEターン」は「人間とAIのあるべき関係」を考える1つの起点になる考えでもあります。
渡邉:『AI親友論』では、「できなさ」こそが人間の価値なのであって、たとえAIによって機能的に凌駕(りょうが)されたとしても、尊厳やかけがえのなさが失われることはないという、AI脅威論への出口先生独自の反論が展開されており大変興味深かったです。AIについては技術的、社会的文脈において語られることが多いなか、哲学の視点からAIを語るという出口先生の試みは非常にユニークだと感じます。
出口氏:そもそも人工知能(AI)の研究のモチベーションの1つは、一貫して、「人間とは、人間の知性とは何か」を知りたい、という人間に関する問いにあったのではないでしょうか。実際、ロボット工学やAIの研究者には、哲学に興味を持っておられる方が多いように感じます。
「人間とは何か」というのは哲学的な問いそのものですので、哲学の営みとAIやロボットの研究開発には重なる部分があると思います。
渡邉:「AI/ロボットとは何か」という問いは、「人間とは何か」という問いの裏返しでもあると。出口先生ご自身は「AI」をどのように定義されていらっしゃるのでしょうか。
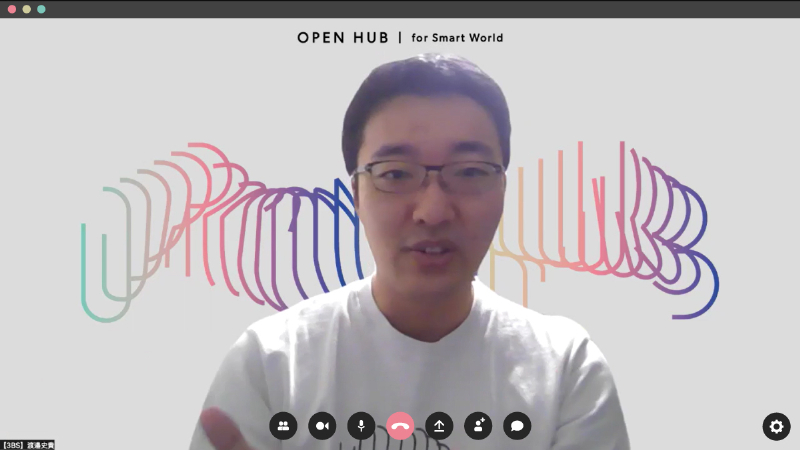
出口氏:AI は1つの定義で捉えることは難しい概念だと思います。むしろ、さまざまな概念のクラスターが乱雑に散らばりつつ重なり合っている点こそが、「AI」の特徴だと思います。そのなかでも重要な指標の1つが、「自律性」です。
AIは単に人間の指示に自動的に従う機械ではありません。ある一定以上の自律性、自律的な思考ないしは、一見「思考」しているように思われる動作を行う能力を持つことで、単なる計算機ではなく、「人工知能」と呼ばれるのです。とはいえ、ここでの「自律性」も多義的な概念です。そこで『AI親友論』では、AIをその自律性の度合いと種類に応じて5つのバージョンに分類しました。
渡邉:ChatGPTのような生成AIの登場と普及により、AIに関する議論が新たなステージに突入したような印象がありますが、出口先生は昨今のAIの研究開発と活用の動向をどのように見ていらっしゃいますか。
出口氏:去年から今年にかけて、生成AIは研究や教育の現場にも大きなインパクトを与えました。いまは少し落ち着いてきてはいますが、レポートや試験で生成AIが不正利用されるのではないかと危惧する向きもありました。
生成AIはパワフルなツールで、調べものをして文章にする作業はほぼ自動的にやってくれます。非常に便利ではありますが、これまで人間がやっていたことを丸ごと外注していいのかという疑問が湧いてくるのは当然のことだと思います。
ただ、教育の現場においてAIはもはや、使わざるをえないというか、禁止することはほとんど不可能だと感じています。「使っちゃダメ」と言っても、どうせみんなこっそり使いますから。したがって今後は、AIの特性や限界を理解した上で、AIと人間の差分に注目することが重要だと考えています。
現在の生成AIには、原理的な制約があります。膨大なデータをインプットし、統計的にもっとも確率の高い文字列をアウトプットするという仕組みを持つため、平均的で当たり前の内容しか書けない、データにないことは書けないのです。
そしてこの限界こそが、人間の創造性や独創性の価値を逆照射する可能性があります。教育の現場でも、「AIはこう書きました。では、あなたはどう書きますか?」といった問いかけが増えていくでしょう。平均的な秀才的回答以上の何かが求められる点で、問いの難易度が上がると言えるかもしれませんが、同時に、AIとは異なる人間のあり方や能力に再び焦点があたり、それらを見つめ直すきっかけになりうるのではないかと思います。
渡邉:教育現場においては、人間の個性や創造性がますます重要なキーワードとなりそうですね。一方、ビジネスにおけるAIの活用については、どのように見ていらっしゃいますか。
出口氏:ビジネスの現場においても、AIの活用はますます進んでいくでしょう。例えば、私が共同研究をしているあるコンサルティング会社では、すでにAIコンサルタントが活躍しつつあります。私もデモを見せていただいたのですが、企業のデータをインプットすると、プレゼンテーション用のスライドが瞬時に生成されるのには驚きました。新人のコンサルタントが1週間かけてつくる資料が、ほんの数秒のうちに出力される。人間の仕事をAIに代替させるケースは、今後ますます増えていくでしょう。
また、別の研究所では、子育てや高齢者の介護に従事するAI搭載ロボットの開発も進められています。こうしたケアを行うAIで重要なのは、単なる機械的な対応ではなく、人間らしい対話や感情のやりとりができることであり、それらをAIに装備させることに、ビジネスの1つの方向性があるのでしょう。このような流れは私の提唱する「共冒険者としてのAI」や「親友としてのAI」といったAIのあり方にも重なります。
渡邉:NTTが開発・提供しているLLM「tsuzumi」には、ユーザーの声のトーンから、ユーザーが大人であるのか子どもであるのか、喜んでいるのか落ち込んでいるのかといった情報を判別し、それぞれの状況に合った応答をする機能があります。単なるデータのアウトプットにとどまらない、柔軟性をもたらすような技術も、今後のAI開発において重要になっていくのでしょうか。
出口氏:そうですね。AIにおける「マルチモダリティ(複数の感覚様式)」の進化は、AIとの対話がより人間味のあるものに近づいていく上で必要不可欠な要素でしょう。現在のChatGPTのような生成AIにおいては、主にテキストベースのコミュニケーションが主流ですが、今後は声のトーンや抑揚、話すスピードなど、より多様な要素や次元が加わっていくと思います。
渡邉:AIやロボットの開発および普及において、グローバルな潮流は無視できません。特に、AIやロボットを「共冒険者」や「親友」として捉えようとする視点は、昔から『ドラえもん』や『鉄腕アトム』のようなコンテンツが親しまれてきた日本ならでは価値観であるとする見方もあります。AIと人間の関係性について、各国の文化の間でどのような違いがあるのでしょうか。
出口氏:特にEU圏では、人間とロボット・AIの関係を「主人/奴隷モデル」で捉える傾向が根強く残っています。実際に人間とAIの関係性が、そのようなモデルにのっとって法制化(※)されつつあります。
「主人/奴隷モデル」では、AIやロボットを仲間や親友として扱うことは許されません。AIをコーチや教師として扱ったり、先ほど申し上げたような子育てや介護におけるガーディアンロボットとして活用することも、否定される可能性があります。たとえ便利であったとしても、そうしたAIの利用は人間の自律性や自由や尊厳を損なうものであり、倫理的に許されないとされるためです。少なくとも、EUの公的資金を使ってそのようなAIを開発したり購入することが、規制されていく可能性もあると思います。
※EUのAIに関する法規制:EUでは2024年5月21日、生成AIを含む包括的なAIの規制である「欧州(EU)AI規制法」が成立。
渡邉:つまり、今後はAIやロボットの開発において、文化間で摩擦が起きる可能性があるということですね。
出口氏:そうです。しかし興味深いのは、ヨーロッパのロボット工学者たちの直感や考えが、必ずしもEUの法律の方向性と一致しているわけではないということです。インタビューをしてみると、彼らは「奴隷をつくっているつもりはない」と口をそろえて言います。人間とAIやロボットのあるべき関係としては、より平等で、相補的な関係が志向されているようなのです。つまり、ヨーロッパにおける法思想と開発思想の間にも一種の摩擦が見られるのです。また、『ドラえもん』や『鉄腕アトム』のようなコンテンツのファンが世界中にいることも、「共冒険者」や「親友」としてのAIという発想が、ある程度の普遍性を持ちうることの証左とも言えるでしょう。
京都哲学研究所の話ともつながりますが、このような状況下において私たちがいますべきことは、ある特定のモデルを「良い/悪い」と決めつけることではなく、さまざまな可能性を開いておくことだと考えています。人間とAIの関係性について、多様なモデル、多様な選択肢を提供し、それぞれに対して人間観にもとづいた理論的な裏付けを行う。そうすることで、AIやロボット開発の多様性を担保できるのではないかと思います。
渡邉:今後、AIの研究開発はどのように発展していくべきだとお考えですか。
出口氏:ますます多様化と多層化が進むと思いますし、そうなるべきだと考えています。繰り返しになりますが、1つの価値観や関係性のモデルだけが支配的になるのではなく、さまざまな価値観やモデルが共存する社会こそが理想的なあり方なのです。
20世紀は、ヨーロッパやアメリカの価値観がグローバル・デファクト・スタンダードとされていました。しかし21世紀、特にその後半では、世界はますます多様化していくでしょう。このことは、「グローバル・サウス」という言葉が国際政治における新たなパワーとして語られ出していることにも表れています。
このような流れにおいて、人間とAIの関係性に関するモデルも、より多様化するのではないかと思います。
渡邉:AIは今後ますます身近な存在になっていくものと思われますが、そうした時代において、開発者とユーザーにはそれぞれどのような姿勢が求められるのでしょうか。
出口氏:開発者側には、人間とは何か、また人間とAIとの望ましい関係とは何かについて明確なビジョンを持つことが求められると思います。先ほども申し上げた通り、今後はグローバルな開発環境において文化摩擦が起きることも予想されますので、そうした状況において右往左往しないためにも、一貫した研究の方向性を保持することは重要です。そのためには、「何が良くて、何が悪いのか」を判断するための明確なモデルや価値観を持つ必要があります。
ユーザー側も同様に、AIの使用に関する価値基準を持つことが重要です。あらゆるAIの使用が「良い」とは限らないので、「良い使用」と「悪い使用」を判断するための軸が必要になるのです。
渡邉:まさに、美学的な価値判断、哲学がますます求められてくるということですね。しかし、どうすればそうした自分なりの軸を持つことができるのでしょうか。
出口氏:「軸を持つ」というのは、「自分なりの直感を持つ」ことなのではないかと考えています。そして、自分なりの直感とは、安全な場所にいて一人で考えているだけでは磨かれません。チームでの仕事や子育てなど、失敗のリスクを伴う他者との共同作業において、さまざまな判断を迫られるなかで磨かれていくものです。
そうした「共冒険者」との関わりのなかで磨かれた直感を言語化することで、自分なりの軸を持つことができると考えています。
渡邉:なるほど、多様化する社会において自分たちの進むべき方向を見失わないためにも、「われわれとしての自己」「共冒険者」といった価値観が重要になってくるのですね。出口先生、今日は貴重なお話をお聞かせいただきまして、どうもありがとうございました。
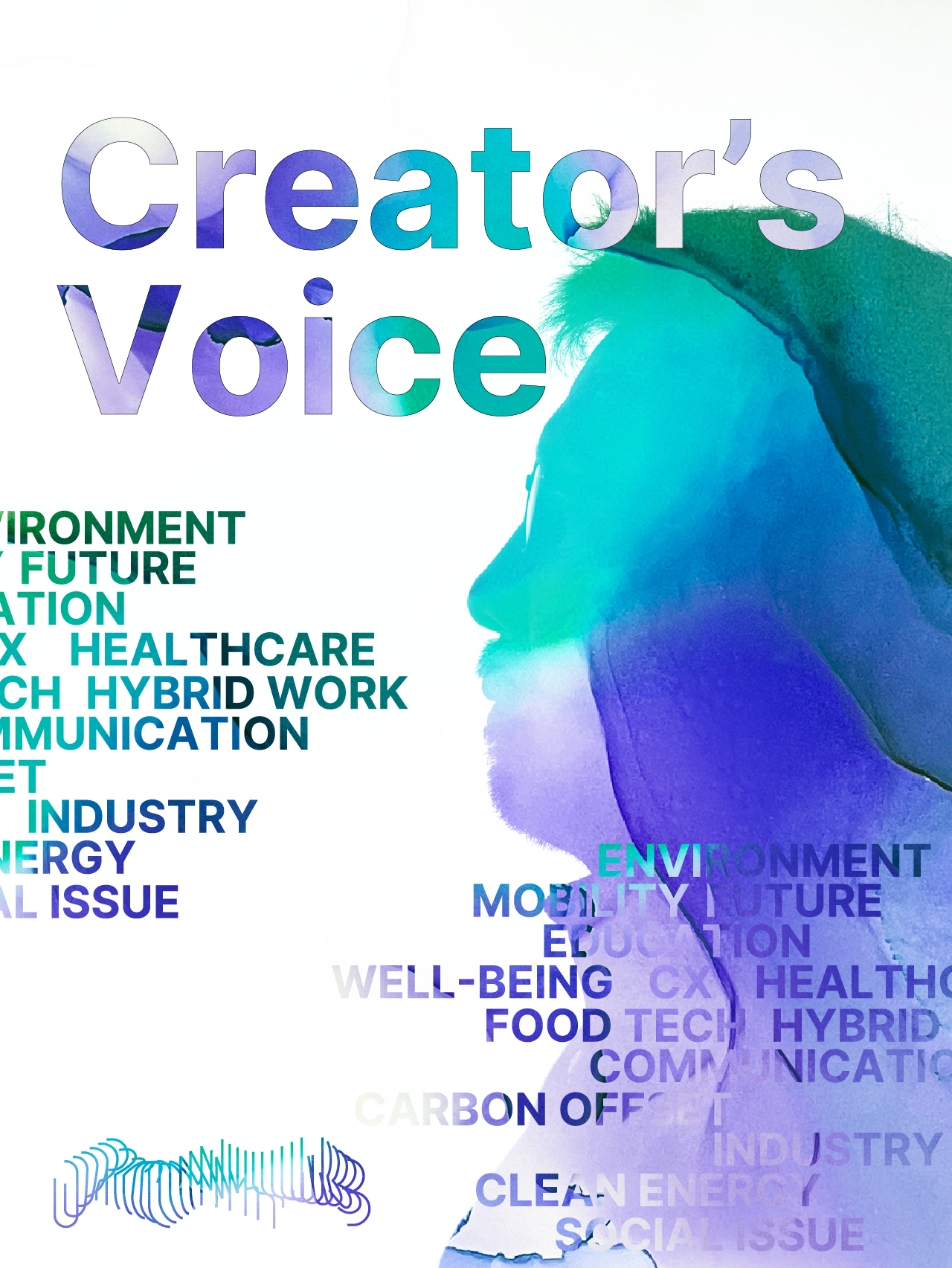
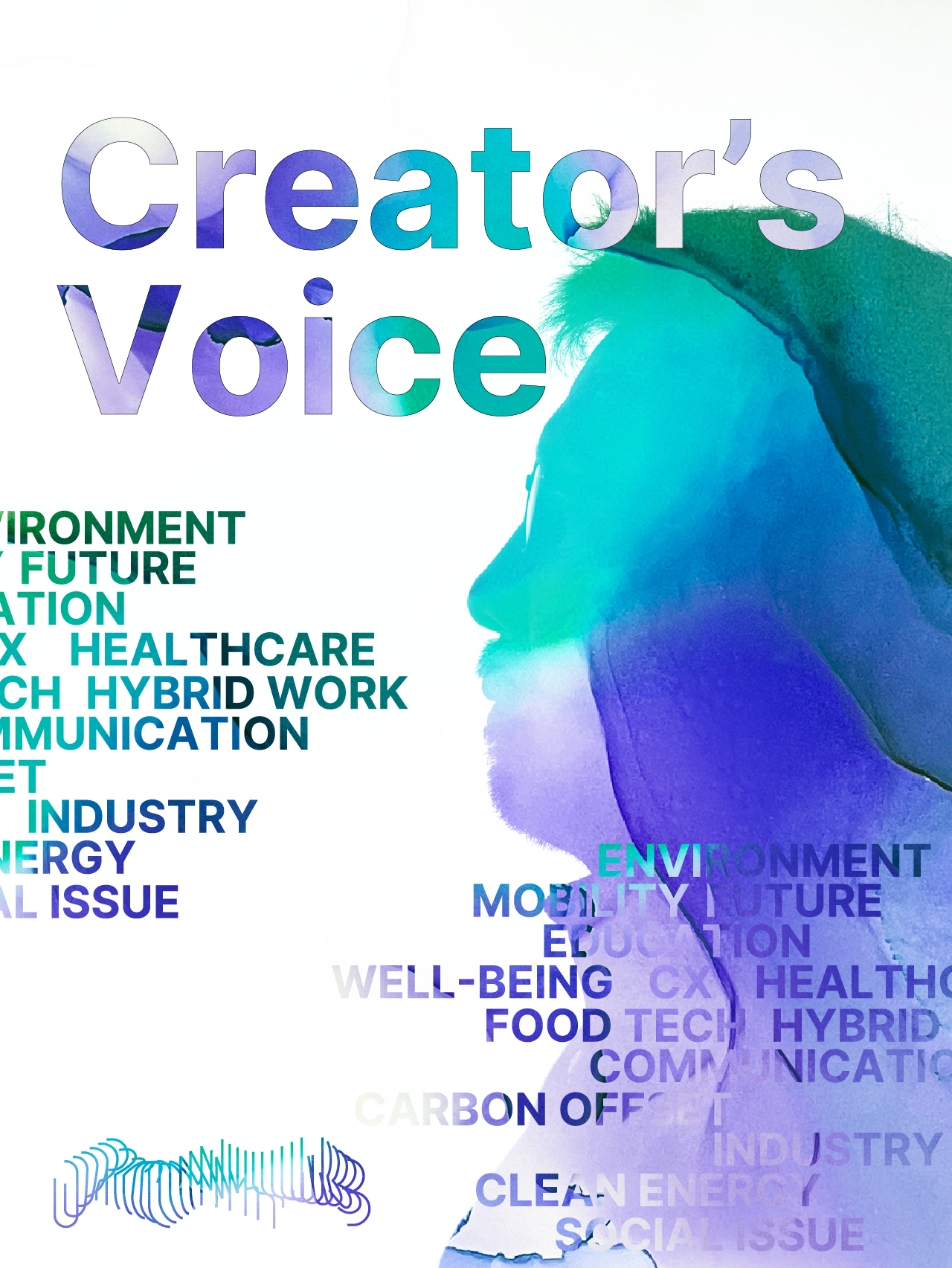
OPEN HUB
THEME
Creator’s Voice
#クリエイターインタビュー